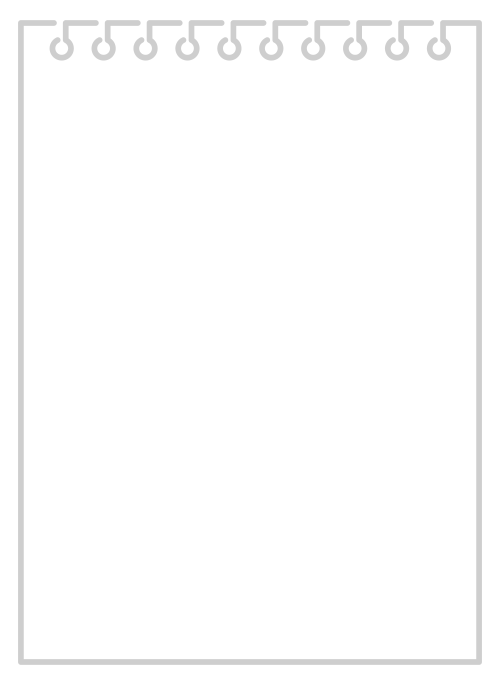「三瀬くんってなんだか不思議な人だね」
クスクス笑いながらそう聞けば、三瀬くんは柔らかい笑みを浮かべた。
「星子さんも」
三瀬くんの指先が私の手の甲に触れた。子供のようなスタンプを撫でて大人の瞳で私を射ぬく。
「不思議な人ですよ」
それはいったいどのへんがどのように?と問いただすことはできないまま手の熱が離れた。何事もなかったように三瀬くんがパソコンに向き直る。
私をなぐさめるためだろうか。褒めてもらわないと前に進めなかったという彼の言葉が脳内でまわる。
後輩になぐさめられてしまったという劣等感より今は優っているものがあった。
もっと、三瀬くんを知りたい。
その端正な横顔を眺めながらそんなことを思ってしまう。
ーーーまあ、案の定そんなことを思っていればバチは当たるようで。
「川北さんって、三瀬くんの教育係だからってベタベタしすぎじゃない?」
上司に頼まれた資料をとりに資料室に向かったところで聞こえてきたのは女たちのそんな声である。
戸を開ける手がとまる。
ここで私が「いやー、その通りです失礼いたしました!!」とへこへこ出てこようものならどんな雰囲気になるのだろうか。
そんな想像をした。笑えなかった。
「この前なんて川北さんが営業の資料忘れて、三瀬くんがカバーしたって」
「うわー、浮ついてるからそんなミスすんのよ。てかそれも三瀬くんの気を引くためにわざとやったんじゃない?」
「それで部長にこっぴどく怒られてんのざまあないわ」
ーーーねー、本当ね、ざまあないわ。
わざとじゃないし、気を引こうなんて思っていないけれど、事実ミスをして怒られて三瀬くんからかばってもらった。
「そもそも川北さんってなんか仕事できないわけじゃないけど、何考えてるか分かんないのよ。同期で飲みにいこって時も絶対来ないでしょあの人」
「付き合いとか考えられないんじゃないの。昔から友達いないからそういうの分かんないとか?」
「うわーぽいわ!学生の時とか教室の隅でひとりでなんか縮こまってる感じある!」
失敬な、友達くらい、
友達くらい、いたような。
あれ、いたっけ。
上っ面の愛想笑いの仮面を貼り付けて一緒にいるような友達はいたけれど。
口をへの字に曲げて過去の記憶を遡る。
ああ、おそらくランドセルを背負っている時に出会った彼だけだったかもしれない。
そんなことをふと思う。なぜ今、こんなことを思い出したんだろうか。
もう消えかかっている手の甲のスタンプを視界に入れた。
ーーー『次は、星子の番!』
「星子さん?」
名前を呼ばれ、ぱっと顔を上げる。
彼は戸の前でかたまる私を不思議そうに首を傾げて見つめた。
「どうしました?中入らないんですか?」
「あー、えっと」
タイミング悪く資料室の扉が開いた。
同期の女2人が笑いながら出てきたが、私を視界に入れた瞬間その顔を引き攣らせた。