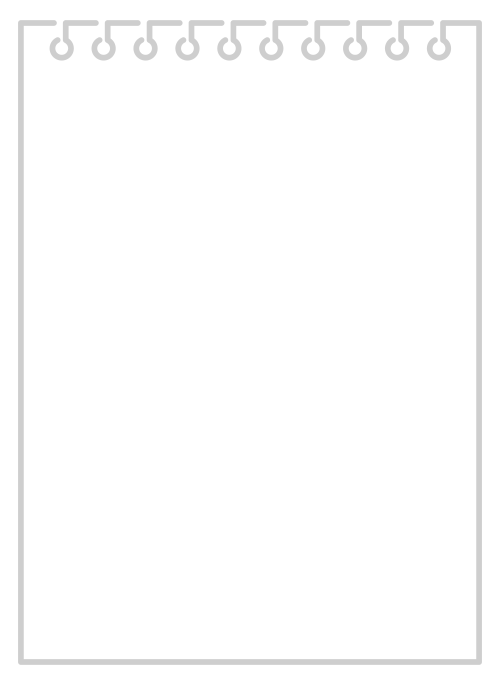「ほい」
何も気づかないふりをして俺は彼の腕に新しい痣が付けられていないか確認するようになった。
彼の手の甲におしたそれ。あわよくば彼が暴力から解放されますようにと願いながら。
手の甲にスタンプを押す際、反対の手で軽く彼の服の袖をめくる。
タバコを押し付けられたような『あと』があった。思わず声が出そうになるがぐっと堪える。
「これ、本当に嬉しいのか」
「嬉しいですよ、帰っても消えないのでこれみて頑張ろうって思えます」
帰って、何を頑張っているんだ。
そうきいても、彼ははぐらかすのだろうか。
俺はただ確認をしているだけだ。救うなんて誓ったのに、過去のトラウマを引きずってなかなか前に進めない。
そんな心配をよそに二瀬はスキップをしながらノートを手にとった。楽しげに口笛をふいてそれをパラパラとめくる。
二瀬は、この空き教室の空間では感情をあらわにするようになった。
「げっ、ペリクの仮面の下イケメンだって、先生。
一気に物語がチープになったと思いませんか」
「あはは、そうだな」
「魔法の薬『レホメディ』」を奪い合うところは面白かったのに、またイケメンだのなんだの言い始めたな〜、星子はおそらくキラキラプリンセス物語にしたいのかな」
机の上に仰向けに寝そべり、饒舌にそういった二瀬。
いつしか、おそらくこの物語の丸っこい字の方の『川北星子』を呼び捨てしながら物語の続きを少しずつ読んでは感想をこぼしている。
俺はそれを時々相槌をうちながらきいていた。
この時間を彼なりに素を出せる場として楽しんでくれているのならよかった。
手の甲につけられた『よく頑張りました』のスタンプを眺めてそう思う。
「リンデル姫はいいですよね」
ノートを胸においた二瀬がその大きな瞳を俺に向ける。
「なんでだ?」
「自由奔放じゃないですか、新しいイケメンがきたらちょっと揺らいで恋して、殺されそうになったらちゃんと『助けて』って言える。そんで手を差し伸べてくれる人が必ずいる」
『助けて』か。簡単な言葉なのにそれは人を巻き込む合図となることが分かっているから言えない。
今にも切れそうな細い細い『愛』を手繰り寄せるようにしてあの子は最後までそれを言わなかったんだ。
「二瀬がそれをのぞんでいるから、そう思うんじゃないか」
「…どういうことですか」
「誰かに『助けて』って言いたい、とか」
二瀬はむくりと起き上がった。
そして少し瞳を泳がせたあと、机からおりて俺にノートを押しつけた。
「…言えてたら苦労しないです」
「っ、二瀬」
「じゃ、帰りますね。また明日」
無表情に戻った二瀬が早口でそう言って教室を出ていく。
たらりと変な汗がつたった。
大丈夫だよな、『また明日』って言ったし。
彼を追いかけて、またあの時と同じようになったら?憎しみの瞳を向けられたら?
感情のままつっぱしってはダメだ。
もう誰の心も殺さないように。
俺は何度も何度も走らない言い訳を考えた。