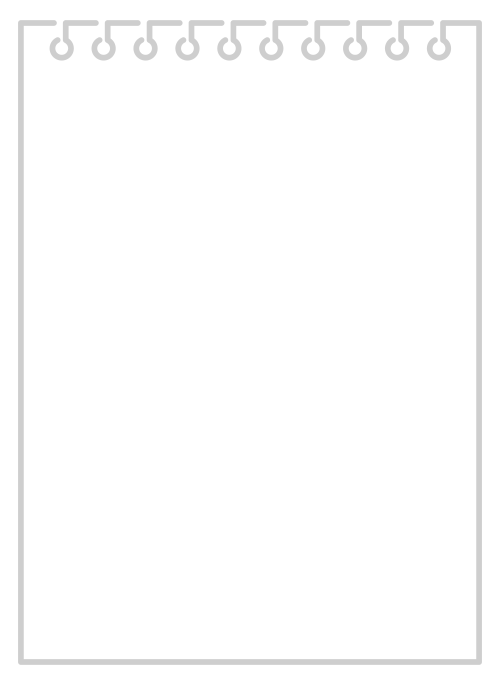俺は職員室と教室、どちらでもない解放された場をもとめた。
年々子供が減っていることもあり、空き教室が増えていく。
時には掃除をしないとすぐに埃が溜まってしまうので、放課後に掃除をしてきますともっともらしいことを言い放ったものの手に掃除道具が握られることもなく、空き教室の角の椅子へと腰を下ろした。
「ちっせーな」
あまりの小ささにそんな言葉をもらしながら、机の中へと手を入れた。
中は少し涼しく感じて、小学生の頃空の机の中によく手を入れていたことを思い出した。
「ん?」
手を中で上下に動かしていれば、下に何かがあたる。
取り出してみると1冊のノートであった。
「スターこくものがたり?」
表紙に書いてある時をそのままたどたどしく声に出す。そのすぐ下には『川北星子』と名前が書かれていた。
自分は聞いたことのない生徒であったが、おそらく在籍生か空き教室にあるということは卒業生のものだろうか。
ぱらぱらとそれをめくっていけば、表紙の通り物語が綴られているようだ。
よくこんな黒歴史みたいな産物を残していけたものだと小さく笑う。
と、
「長谷川先生」
教室の戸があいて、顔を覗かせたのは二瀬だった。
驚きのあまり席を立つと椅子が倒れた。
そこに大きな音が響いて、二瀬の肩が揺れる。
「ああ、ごめん」
椅子を立たせれば、二瀬がこちらに歩いてきた。
その瞳に憎しみはこもっていない。だからといって喜びや楽しみの瞳でもなかった。この子は感情を表に出すことがないのだと改めて思う。
腕の痣のことをきいても彼の言葉の裏を読み取れる自信がない。二瀬に限ったことではなかった、俺はあの時から何も進めてなんていない。
「それ、なんですか」
「え?」
二瀬が指をさした先には机の上にある1冊のノート。
俺は苦笑いしながらそれを持ち上げた。
「おそらく忘れ物だ」
「面白そう、見てみたいです」
表紙を見た二瀬がそう言って手を差し出す。対象物はなんであれ二瀬が何かを求めているのが珍しく思い、俺はそれを彼に渡した。
見ず知らずの生徒が書いた物語を読むのには少し抵抗はあったものの自分も好奇心に耐えられず、彼の横からそれをのぞき込む。
「途中途中で字体と物語の雰囲気が変わってますね、2人で書いたんですかね」
「そうだろうな」
しばらく読んでいると、二瀬が息をふっともらした。
二瀬の方に顔を向けるとクスクスと笑っている。
二瀬が、笑っている。
「なんでワンドとリンデル姫がいい雰囲気になったらアイマイが必ず邪魔しにくるんですかね」
「この、アイマイという集団のリーダー、ペリクがワンドに嫉妬しているんじゃないか」
「なんで?」
「そりゃあ、その、好きだからだろ」
生徒にそういう話をするのは多少なりとも憚られるが。
「誰が誰を?」
「ペリクがリンデル姫を」
「ふーん」
と、口を軽く尖らせて返事をした二瀬が1枚紙を捲る。こんなに表情豊かなのははじめてみた。
教室の中から一歩外に出れば案外彼も子供なのかもしれない いや、彼はれっきとした子供だ。守られるべき存在である。
「嫉妬してるにしても、そういう感情じゃない気もします」
「どういうことだ?」
「アイマイのやつらは幸せじゃないからスター国を侵略しにきたんでしょ?
お金持ちで何不自由なく暮らすスター国の姫と何の苦労もなしに顔だけでのしあがってくるワンドにたいして、その幸せさに嫉妬してると思います。
俺たちはこんなに不幸なのにって」
正直子供が書いたものにそんな深い意味が込められているようには思えなかったが俺は「そういう考え方もあるな」と全肯定で頷く。
物語の捉え方なんて人それぞれだ。その人自身の境遇やその時の気持ちによって読み解かれる部分も変わってくるのだろう。
ーー俺たちはこんなに不幸なのにって。
二瀬が言ったそれが脳内でもう一度再生される。
「先生」
「なんだ」
「このノートにはスタンプ押してあげないんですか」
「どういう意味だ」
首を傾げた俺に、二瀬は指先でノートの端に何かを描いた。
「ほら、クマがいて『よく頑張りました』ってやつ」
二瀬の指先がクマを描いていることが分かって俺は思わず吹き出してしまった。
「見ず知らずの生徒のノート、しかも読んだら怒られそうなものにさすがに押せないよ」
「俺、あれ結構嬉しいですけどね」
二瀬はそう言った。
何気ない言葉だったけれど純粋に嬉しかった。
気持ちのこもっていた過去とは違い、それはいつしか義務でしかなくて、唯一何も考えなくていい時間で、無心で行なっていたと今更ながら気づいた。
それが急に恥ずかしくなる。そっか、嬉しいんだ。よかった。
「先生、あのスタンプ今持ってないんですか?」
「あ、ああ今は持ってない。このノートにはつけないぞ、持ち主に返すつもりだ」
「このノートじゃなくて、俺にスタンプ押してください」
「え?」
「…俺、毎日頑張ってますから」
小さな二瀬の声。俺は自然と頷いてしまった。
そしてこんなことを思ってしまう。
ーーあの呑気に笑っているクマのスタンプが、彼を救ってくれるかもしれない、と。
違う、かもではなく、俺はあれを利用して彼を救うんだ。
「明日でいいのでお願いします。それとそのノートまだ持ち主に返さないでください。最後まで読んでないので」
「分かった」
「では、また明日」
彼はそう言って、ノートを俺に預けたあと教室を出て行った。