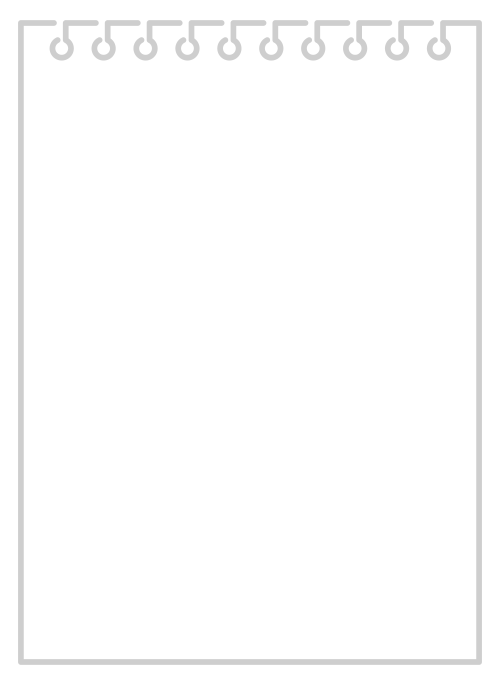ガシャン、と教室中に音が響き渡って我にかえる。
「せんせー!二瀬くんが転びましたー!」
顔を上げれば、地面には倒れている男子生徒とその先に見事に床に散らばっている給食。
俺は慌てて立ち上がる。
「大丈夫か、二瀬」
二瀬に問いかけてかけよれば、無言で頷き体を起き上がらせた。
「こいつ転けた時も無表情だったぜ!ロボットなんじゃねえの!」
二瀬が転んだすぐそばの席の男子生徒がそう言う。
俺は彼を睨みつけた。
「そういうことを言うのは間違っているとは思わないか?」
「はあ?」
俺は子供からこういう憎しみで溢れた瞳でみられるのが嫌いになった。
先生という肩書きがある限りそれは拭えないものだというのも知っている だから俺は目を背けたくて仕方がない。
「まさかわざと転ばせたんじゃないだろうな」
「ちげーし!なあみんな!こいつ勝手に転んだよな!」
声の大きなものに同調する。いつの世代になってもそれは変わらないことだ。
周りの生徒たちがこくりこくりと頷いていた。
「それが本当だとしても、お前のすぐそばで転んだんだぞ、ロボットだのなんだの言う前に片づけを手伝いなさい」
「はあ?なんで俺がこいつを手伝わないといけないんだよ!」
気に食わないことがあると癇癪をおこして物にあたる。机が揺れて給食の皿の中からおかずがこぼれ出た。
俺は彼を立たせようと手を伸ばしたが、後ろから裾を引っ張られて動きを止めた。
「…先生、大丈夫です。1人で片付けられます」
小さく、消えていきそうな声が聞こえた。
二瀬は裾から手を離し、黙々と床に散らばったものを片付けだす。
「ほらみろ!1人でやるってよ!みんな先に給食食べてよーぜ!」
もう彼を叱責する気は失せ、俺は二瀬と一緒に床を片付け始めた。
「怪我してないか、二瀬」
「…はい」
二瀬は無口な男子生徒だ。
そして常に無表情であまり感情が分からない。
前髪で隠れてしまってはいるが目は大きく、顔つきは整っていた。美少年とはこういう子のことを言うのだろうと思う。
こぼれたおかずを丁寧にお皿に戻して、少し先にある唐揚げに手を伸ばした。
「あ、先生がとるよ」
「…大丈夫です」
伸ばした手。裾が少し上がって、白い腕が見えた。
「っ!」
ーーー見なければよかった。
そう思った。
何度も何度も思い出してしまういくつもの痣。
助けたいという空回った正義感。
憎しみを増幅させた瞳。
行動に出すな、もう、誰も傷つけてはならない。
「…先生、どうかしましたか」
「あ、っ、だ、大丈夫」
俺は二瀬から視線を外して、崩れた給食がのったおぼんを持ち上げる。
「今日は給食の余りはないか?」
「今日全部空っぽです!」
「そうか、先生のもわけるが何人か二瀬に給食のおかずをわけてやってくれ!」
そういうと、何人かが動き始めた。俺は自らの給食を二瀬にわけようと教卓の隣にある自分の机へと向かおうとするが、二瀬が俺の裾をクイクイと引っ張った。
「ん?どうした二瀬」
「…いりません」
「え?」
「お腹空いてないのでいりません」
二瀬は俺をまっすぐ見つめてそう言う。
「いや」と声を発したがそれを上回る声がすぐそばから聞こえてくる。
「おい!二瀬給食いらねーってよ!わけなくていいぞ!」
その声により、何人かの動きが止まる。
本当にこいつは。
クラスのヒエラルキーのトップに立ったつもりにいるだろうがお前は所詮この小さな世界の中でしか上に立てない。社会に出てみればそれがよく分かるはずだ。
と。でかかった暴言をごくりと飲み込んだ。
「二瀬、先生のをあげるからちゃんと食え」
蘇る過去の『悪夢』というなの現実。俺は今、目を背けることが正解なんだろうか。
あの時のように彼の腕をつかみ、問いただすことが正解なのか。
あの時、三橋が勇気を持って俺に現実をつきつけなければどうなっていたんだろうか。
あの子は、どんな人生を歩んでいたんだろうか。
「いりません。本当にお腹空いてないので。
先生のもらっちゃったら絶対に全部食べきらないといけないじゃないですか
偽善って時に人を苦しめるんですよ」
小学校5年生とは思えないその口調に俺は少し困惑すると同時に、俺の迷いに一気に壁を作るかのような物言いだと思った。考えすぎだろうか。
静かに教室を出ていった二瀬を俺は追いかけることもできない。込み上げてくる感情の処理の仕方が分からず立ち尽くすことしかできなかった。
偽善は、時に人を苦しめる。
その通りだと思った。