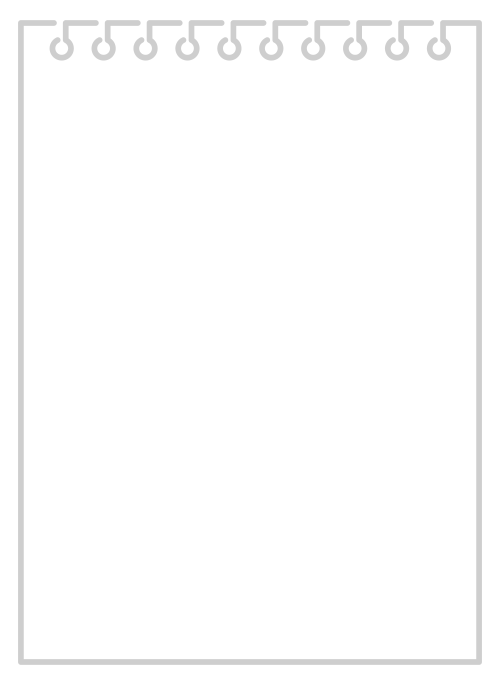僕は星子と過ごした空き教室に向かった。
そして星子がいつも座っていた机の中にノートを入れる。
「星子、好きだよ」
誰にも聞かれることのないその言葉が静寂の中にぽつりとこぼれた。
そして僕は学校を出る。
もしかしたら今日が最後になるのかもしれない。
後悔がないといったら嘘になるけれど、星子と出会えたこと、好きになったこと、この初恋をずっと胸に居座らせながら生きていくんだろうなと漠然と思った。
僕はろくな大人にならないのだから、それくらい美しいものをもっていたってバチはあたらないだろう。
僕はいつもなら帰りたくなくて少し寄り道する川を横目に通り過ぎて、学校より窮屈で息苦しい家へと向かった。
「ただいま」
憂鬱な玄関の扉をあける。
一番最初に視界に入ったのは僕をみて顔をしかめた母だ。おそらく兄が帰ってきたと思ったのだろう。僕は母の横を通り過ぎて自分の部屋へと向かおうと階段へすすんだが、目に入った光景に足を止めた。
「あんたの部屋、もうないよ」
僕の部屋の中にあったものが、階段に散乱している。
背中に母の冷たい声が刺さった。
父からもらった古い本や、おもちゃ、言ってしまえばあったって役に立たないものだ。
だけど、いよいよ僕の居場所はなくなったのだと『現実』を突きつけられたような感覚。
母はお前はいらないと改めて伝えたくてこんなことをしたのだと思う。
ぎゅっと拳を握る。
「はやくそれ片付けて、さっさと出ていってね。卒業式なんて待たなくていいから」
母は冷たくそう言うと、リビングへと戻っていく。
僕は床に散らばったガラクタたちを手で拾う。
悪党集団アイマイは、自らの存在を知らしめるためにスター国でひと暴れする。
僕はつらいことがあると、星子とのえがく物語の続きを考えてしまうのがクセになっていた。
アイマイのボス、ペリクはワンドと対峙する時にどんなことを思っているのだろうか。
父からもらった戦隊ものに出てくる怪獣を拾い上げようと手を伸ばした時、
「ただいま〜、って、なんだよこれきったねえな」
兄が帰ってきて、階段に散らばっているそれを足で蹴飛ばした。
いとも簡単に怪獣は床を転がった。
何かがぷつんと、切れた気がした。
瞳から一滴だけ涙がこぼれた。
これは、こいつらにたいしての涙ではない。
僕が存在意義をとなえることで星子とは2度と会えなくなり、スター国物語を2人で語り合うこともなくなることへの嘆きの涙だ。
僕は父からもらった1番分厚い本を拾い上げて兄に向かってそれを思いきり投げた。
「ってえな!!なにすんだよ!」
本は兄の後頭部にあたった。
鬼の形相でこちらを振り向いた兄。こわくない、こわくない!
星子がいじめっこを殴る前、「いけ」と思ったように、もう1人の自分が叫んでいた。
『いけ!』
僕は腹の底から声を荒げながら、兄にあらゆるものをぶつけていった。
いつか、星子に言った言葉を思い出した。
なぜ、アイマイはスター国で暴れるのか。
僕は、とくに深いことも考えずに言った。
好きだから、
僕だけをみてほしいから、スター国でひと暴れしてるってだけ。
ーーーおそらく、心にとどめた本音だった。
僕は、はじめて声が枯れるくらい泣き喚いて、暴れた。
ーーーー「ーーリクさん」
肩を強めにゆすられて、薄く目を開ける。
背中には着ていたシャツが肌にへばりつくくらい汗をかいていた。
「ペリクさん、こんなところで寝たらだめですよ」
苦笑いの目の前の金髪がそう言った。
俺はゆっくりと起き上がる。
「なんかうなされてましたけど、嫌な夢でもみてたんすか」
そう問われ、俺は首を横にふった。
テーブルの上には色とりどりの星が散らばっていた。
ーーーーろくな大人にならなかったな。
改めてそう思う。
「嫌な夢じゃない」
「え?」
俺は、手の甲の『あと』を見つめて笑った。