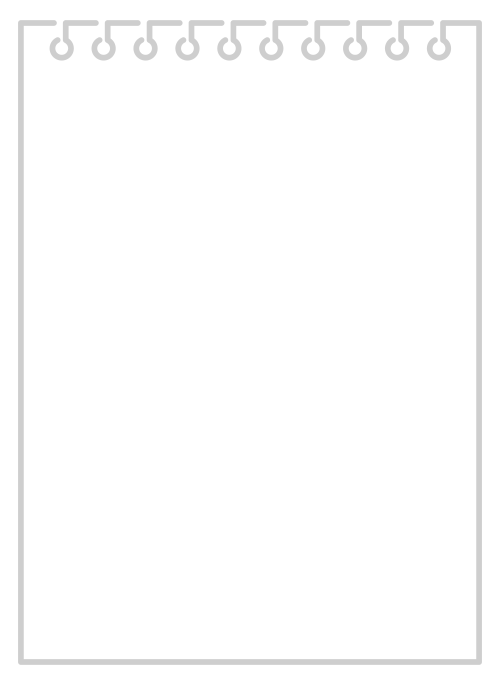「なんじゃこりゃ」
星子は案の定、僕の書いた物語の続きを読んで顔をしかめた。
くくくっと小さく喉を鳴らせば、星子は僕の方をみて「お前の仕業か」と言うようにノートの角を僕の額にあてる。
「幸せなプリンセス物語に何してくれてるのよ」
星子は、勝手に物語を読まれたことより僕によって話を捻じ曲げられたことにご立腹の様子だった。
「ありがちなのは面白くないと思って」
「だからってこれはないでしょっ」
幸せなスター国に、身分差の恋なんて非にならない災難が降りかかる。
「なんでいきなり悪い奴が国を侵略しにきてんのよ!そんな過激な話じゃないのこれは!」
「その侵略してきたやつらの名前を迷ってんだよなあ、なんかいい案ない?」
「話聞いてる!?」
頬を膨らませた星子。最近こういうやりとりを星子としていなかったため僕は怒らせてしまった焦りよりも星子が僕に感情を向けていることがなにより嬉しかった。
「どうせだったらリレー形式で物語書いていこうよ」
「はあ?」
「1人で書くより、2人で書く方が刺激的で楽しそうだろ」
僕の提案に星子は、好奇心を抑え込むように顔を歪ませた。そしてちらりと教室で固まって話をしている女の子の集団へと瞳を向ける。
星子の視線を追うように、僕もそちらに目を向けた。
1人の女の子がこちらをみていた。
そして目があって、あからさまにそらされる。
小さな舌打ちをして、星子の方へと顔を戻した。
「星子」
「なに?」と僕の方を見た星子。その小さな手を掴んだ。
咄嗟にひっこめようとした星子の手を離さないようにぎゅっと握って、僕は黒いペンを筆箱から取り出した。
「な、なにしてるの?」
「スター国の証」
我ながら子供じみていて、幼稚で、バカらしいとは思ったけれど星子とのつながりをこれ以上切らせたくなかった。
星子の手の甲に黒いペンで星のマークを描く。
「うへぇ、川﨑くん星描くの下手くそだあ」
「うるせえな」
少し歪になった星のうえをぺちっと叩けば、星子は小さく笑って僕の手からペンを奪った。
そして僕の手を掴む。
「星子も描いてあげる」
「っ、」
星子は自分のことを「星子」という。親にいい加減自分のことを名前でいうのはやめなさいと叱られたらしく最近は「わたし」と言っていたが、ふとした時に自らのことを「星子」と言う。かわいい。
「物語のリレーいいけど、教室でそのこと話すのはやめよう」
「なんで?」
「わたしが川﨑くんと仲良くすると嫌って思う子もいるの」
「なんで?」
「いいから。ほら、休憩時間とかに隣の空き教室で話そうよ」
「なんで?」
「貴方はなんで星人ですか?」
別にいいじゃん。他のやつらのことなんて考えなくて。もうすぐ卒業じゃん。
という言葉は飲み込んだ。そうだ、何もかも関係がなくなってしまうのは僕だけであって、星子はこれから先ああいう卑怯な奴らとも付き合っていかないといけない。
「分かった、休憩時間は隣の空き教室で話そう」
手の甲に描かれた僕と星子だけの証と、ノートに綴られる僕たちだけの物語。
考えただけで気持ちがふわふわした。