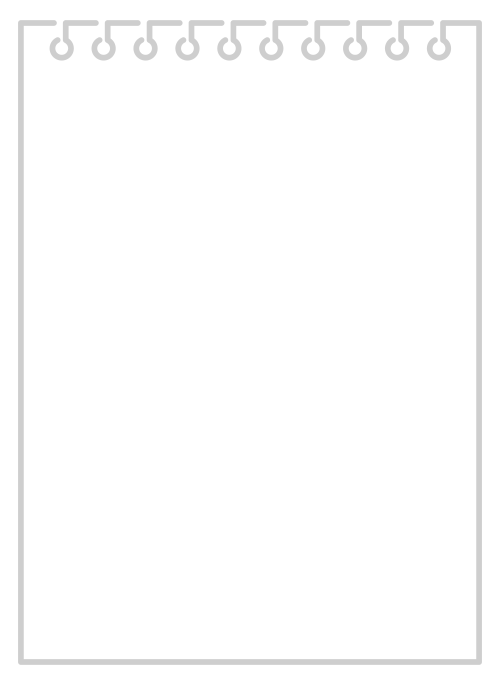「ふう、」
まだ店内は盛り上がっている。
さすがに耐えられなくなった私は「お手洗い」と嘘をついて一度外に出た。
このまま帰りたいけれど、かばんは中に取り残されたままだ。
少し酔いがまわって眩暈がした。
思わずしゃがみ込む。
「…帰りたい」
空気中に吐き出された本音。誰にも聞かれることなく消えていく。
後ろの戸がガラリとあいた音がしたけれど、一度座ってしまうとなかなか立ち上がれない。
「星子さん」
顔をあげると、三瀬くんがいた。
「大丈夫ですか?」
力なく、首を横に振る。
「かばん、持ってきたんで帰りましょう。送りますから」
救世主だ!
にへらと笑った私に、三瀬くんは小さなため息をついて私に手を差し伸べた。
いつもなら「大丈夫!」と自らで立つけれど、今日は甘えたい気分だった。
彼の手に触れる。冷たくて気持ちがいい。
そのまま手は離れず、私はなぜか片想いをしている後輩と手を繋いで歩いている。
現実か夢か分からなかった。
「ふらふらしないでください、危ないから」
「大丈夫、大丈夫」
「おんぶ、しましょうか」
「手、つなぐだけで充分」
繋がれている手を振りながらそういうと、三瀬くんは「そうですか」と笑った。
しばらく少し冷たい夜風により頬の熱が少しずつ冷めていくのを感じながら私は緩い足取りで彼と歩く。
「星子さんって、隠し事とかあります?」
「なに、急に」
「気になって」
それは私が彼のことを好きになっている、ということを理解しているよという彼なりの警告なのか分からなかった。
え、好きになったらやっぱりダメ?
「そっちこそ、隠し事、なんかあるんじゃないの?」
足を止めて、彼を見上げる。
「っ、」
初めて、彼の少しの動揺がみえた。
そして考え込むように瞳を揺らして、何かを言いかけたあと、いつもの笑顔を私に向ける。
「星子さんってたぶん何も考えずに言葉を発してるでしょ」
「どういう意味よ」
「何か裏があるんじゃないかって勘ぐる方がアホらしくなってきた」
「はい?」
「もういいや、はやく帰りましょう」
私の手を引っ張って再び歩き出した三瀬くん。
首を傾げながら私は彼についていく。
しばらく歩いて、私の家の前まで着いた時、彼が繋がれた手を離そうとする。
「っ、あのさ、」
ぎゅ、と掴んだ。
まだ、離れたくない。
「お、お茶でも、のんでく?」
酔っている。それはもうふらふらに。
シラフだったらこんなテンプレみたいな誘い方できない。
「何言ってるんですか、はやく中入ってください」とか「結構です」とか爽やかな笑顔で拒否られると思った。
ーーーーが、
「はい、お茶、飲んでいきます」
さらりと、そんなことを言われるもんだから一気にからだの熱が上昇した。