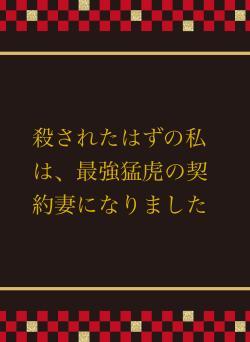翌朝の早い段階で、朱璃は執務室を訪ねた。
そして伯蓮に、後宮行きの許可をもらう。
表向きは伯蓮の侍女として、後宮の視察をするためとしている。
しかし本当の理由は、伯蓮が可愛がっていたあやかし“流”の捜索のためである。
「それでは朱璃。よろしく頼む」
「はい。日没までにはこちらに戻ってくるよう心がけます。ところで伯蓮様」
椅子に腰掛ける伯蓮の顔色を窺いながら、朱璃が心配そうに尋ねてきた。
「風邪はひいていませんか?」
その問いかけに、伯蓮の心臓をがドキリと跳ねた。
背後には侍従の関韋が控えている。夜中に蒼山宮を抜け出したことが知られると厄介だったから。
「……し、心配ない……」
「良かったです。では行って参ります!」
笑顔を咲かせて、朱璃は元気よく退室していった。
その背中を少し不安げに見送った伯蓮は、ふうと息を吐く。
今日から朱璃は、流の捜索のために毎日後宮へと足を運ぶことになる。
朝から日没まで、一日がかりで後宮内をくまなく探してくれる予定だ。
その間、この蒼山宮内で朱璃の姿を見かけることがないと思うと、伯蓮は寂しさを覚えた。
すると哀愁漂う背後に、関韋が質問を投げかけた。
「風邪を引くようなことでもしたのですか?」
「っ⁉︎ ……何もしていない」
やはり朱璃の言葉が気になった感の良い関韋が、意味深な目で見てくる。
何もないと答えたはずの伯蓮に、更なる質問で追い詰めようとした。
「ではなぜ朱璃殿は、伯蓮様の体調を気遣われたのですか」
「は、鼻声にでも聞こえたのだろう」
狼狽えることなく鼻を啜ってみせ、これで関韋からの質問は終了したと思っていた。
しかし、伯蓮が蒼山宮にやってきて七年。侍従を務める関韋はそう簡単には騙せなかった。
「では伯蓮様。夜中とはいえ、あまり二人きりで出かけるのは良ろしくないかと」
「っっ関……おまえっ⁉︎」
「あらぬ噂を立てられるやもしれませんので、念のためお気をつけください」
たとえば、この国の皇太子は後宮にいる妃のもとに通わず、お気に入りの侍女をそばに置いている――とか。
夜中に二人きりで散歩へ出かけるほど、皇太子は侍女を溺愛している――などなど。
考えられる噂の例を、関韋は無表情で淡々と口に出していく。
以前から心が読みにくく、今のが忠告なのか冷やかしなのか判断がつかない。
それよりも、聞き慣れない単語を聞いて伯蓮が狼狽えた。
「お気に入り? 溺、愛……⁉︎」
朱璃に接する自分は他者にそう映るのかと驚愕し、伯蓮は頬から耳にかけて真っ赤にした。
七年そばで仕えていた関韋も、主人のそういう姿を見たことがなくて少し驚く。
同時に皇太子とはいえ、やはり伯蓮も年頃の青年であるということを改めて認識した。
だからこそ、その気持ちを大切にしていけるよう、関韋は物申す。
「その存在は、時に伯蓮様の弱みにもなります。ですから絶対に、周囲に悟られてはなりません」
「関韋……」
伯蓮が大切に思う朱璃を、政に利用しよう企む者が出てくるかもしれない。
何か問題に巻き込まれ、危険な目に遭うかもしれない。
その可能性を指摘すると、同じことを考えていた伯蓮にもしっかりと真意が届いていた。
真剣な顔で一点を見つめ、何かを考える伯蓮。
(関韋の言う通り、朱璃のためにも深く関わってはいけない……)
今回の朱璃の後宮行きは、距離を置くのに良い時機だったのかもしれない。
伯蓮はそう納得した。
*
後宮に到着した朱璃は、早速目撃情報があった食堂を目指した。
しかし“視察”という名目で来ているため、それとなく勤務中の雰囲気を醸し出しながら歩く。
すると、様子を見に来た三々が颯爽と飛んできて、朱璃の頭に乗った。
「今日から本格的に捜索開始か?」
「三々おはよう! まずは食堂から少しずつ北に向かって探す予定」
「お前のことだから先に貂々に会いに行くと思っていたぞ」
朱璃と貂々の関係性を知っていた三々が、意外そうに声をかけた。
集会にこなかった貂々のことは朱璃も気になっていたが、きっといつもの場所で昼寝をしているだろう。
近くを通りかかってからでも遅くないと思っていた朱璃は、微笑みながら返答する。
「まずは捜索して、日没間際に貂々に挨拶して帰るよ」
「早く流を見つけてやらないとな。って俺はこのあと街の広場で大道芸を見に行くんだけど」
流の捜索に協力的な三々だが、本日は王宮外の娯楽で忙しいらしい。
あやかしの暮らしぶりについては、未だにわからないことが多い。
けれど、自由気ままに昼寝したり遊びに行ったりする貂々や三々を見て、羨ましいと思った。
「私も、大道芸見たいなぁ……」
「なんだ? 朱璃、王宮出たいのか?」
「っえ……?」
何気なく問われて、朱璃はすぐに答えが出てこなかった。
生活苦で増えていく実家の借金。それを返済するため、朱璃は下女として後宮入りした。
ただ、ここでの暮らしは衣食住が揃っており、苦だとは思っていない。
借金を完済したら両親から知らせが届き、任期を終えたら王宮を出る予定でいる。
それは、貂々、三々や星。他のあやかしたちとも会えなくなることを意味していた。
さらには、あやかしに会えなくなることだけを悲観しているのではないと、朱璃が自覚する。
(……伯蓮様にも、会えなくなるんだ)
一度王宮を出たら、おそらく二度と会うことはない。
初めてできた、あやかし好きの仲間。
けれど、伯蓮はこの国の次期皇帝であり、王宮の中で生きる高貴な方。
今こうしてそばで侍女をしていることが、どれほどの奇跡なのかと思い知らされる。
考え込んで動きが止まった朱璃を、三々が気にして空気を変えた。
「まあ明日は手伝ってやるからよ、じゃあな」
「うん。楽しんできてね」
太陽目掛けて空高く飛んでいった三々を見送り、朱璃は眩しさから目を細めた。
たとえ王宮を出たとしても、三々のように飛んでいつでも遊びに来ることができたら良いのに――。
そんなことを考えながら、朱璃は捜索を再開した。
*
西日が王宮全体を照らしはじめた頃、コソコソと華応宮の中庭に姿を現した朱璃。
「貂々ー、来たよー」
木に向かって小声で話しかけるが、反応はない。
貂々は人の言葉を話さないから、返事がないのはいつものこと。
ただ存在を示したくて、朱璃は徐々に近づいていく。
木の上に視線を向け、そこでようやく貂々が不在だと知った。
「あれ?」
尚華が入内したのと同時期に、この中庭の木の上で貂々と出会った。
あれからずっと定位置で寝ていることが多かった貂々は、ここ最近よく動き回る。
少し席を外しているだけで、待っていればすぐに戻ってくるだろう。
そう思った朱璃は、その場に座って本日の一人反省会をはじめた。
(結局、食堂とその周辺の建物に、流はいなかったなぁ……)
“視察”なので建物内への侵入も許可が下りていたが、それでも流の姿は発見できず。
たまたま見かけたあやかしたちに尋ねてみても、流を見た者はいなかった。
こうなったら、後宮内の全ての建物を順番に確認していくしかない。
それは途方もない作戦だけれど、流を心配する伯蓮を思い、早く見つけたい一心だった。
(お優しい伯蓮様のため、私ならできる!)
自らを鼓舞した朱璃が、明日も頑張ろうと気合を入れる。
しかし、一向に貂々は帰ってこなくて、今日はもう諦めて帰ろうと立ち上がった時。
渡り廊下を歩いていた侍女が、朱璃の存在に気づいて声を上げた。
「あ、あの時の下女!」
驚いて肩を震わせた朱璃が振り向くと、その侍女は眉根を寄せてジリジリと近づいてくる。
「あんた、尚華様の初夜をよくも邪魔してくれたわね……!」
「あ、あの時は、本当に……」
ごめんなさいと言うより前に、侍女の手が朱璃の肩に掴み掛かかろうと距離を詰めてきた。
明らかに喧嘩腰な尚華の侍女だけど、下手に朱璃が刃向かえば何を言われるかわからない。
何より自分が問題を起こせば、主人の伯蓮にも責任が問われてしまう。
それだけは嫌だと考えて、侍女に触れられそうな一瞬に体を捻ってかわした。
「あ、待ちなさいー!」
(ひぇぇごめんなさーい!)
朱璃は逃げるように走り出して、侍女の制止も聞か図にひたすら前だけを見ていた。
*
「申し訳ございません尚華様、逃してしまいました……」
「あの下女、よくも恐れずにまた現れたわね」
報告を受けた尚華は、朱色の鮮やかな牀の上でくつろいでいた。
お気に入りの香を焚き、茶を嗜みながら呆れ顔を浮かべる。
初夜を妨害してきた翌日も、中庭にいたという目撃情報があった。
あの時はすぐに駆けつけたけれど、朱璃の姿は確認できず。
しかし、こうも侍女が見かけているとなると、何か目的があってあの中庭に出没するのか。
頭の中でぐるぐると考えていた時、尚華の顔が歪んでいく。
「わたくしを嘲笑いにきているのかしら……」
皇太子の妃だというのに、二度も初夜を見送られた、かわいそうな尚華。
憔悴している姿でも見てやろうと、隠れて何度もやってくる。
そんな曲がった考え方をすればするほど、恨みの念が高まっていく。
「次見かけたら下女に声はかけず、すぐ私に報告しなさい」
「え? は、はい……」
「あの下女が何度も中庭にくるなら、それを利用して油断させるのよ」
尚華に指示された侍女は、拱手しながら頭を下げて部屋を出ていく。
すると、尚華と二人きりになった初老の侍女が、何かを差し出してきた。
「お父上様からの文です」
「……父上から?」
尚華の父、すなわち宰相を務める、胡豪子からの文が届いていた。
嫌な顔をした尚華は、初老の侍女から文を受け取ると乱暴に開いていく。
そこには、昨日豪子のもとに伯蓮が謝罪にきたこと。
そして、例の下女に特別な感情はないという報告が書かれていた。
尚華はたまらず、嘲笑うような声を出す。
「はは! 父上も甘いわね。伯蓮様の言葉を真に受けたのかしら?」
「男は皆、色恋には鈍感な生き物ですから……」
初老の侍女が、微笑みながら尚華の意見に賛同する。
仮に、伯蓮が本気でそう思いながら豪子に話したとしても、あの夜現場にいた尚華にはわかっていた。
二度目の初夜を妨害した朱璃への心遣い、話し方、微笑みが、尚華を前にしている時とは違う。
あの時の伯蓮は、確実に心を許しているような柔らかい雰囲気を纏っていた。
思い出すと再び血圧が上昇しそうになり、そばにあった茶を飲み干して深呼吸する。
しかし、文には続きが書かれてあり、尚華がゆっくりと目で追っていく。
「……なっ、これは……」
口元を隠すほど驚く尚華が、目を見開いたまま初老の侍女に視線を向ける。
すると初老の侍女は、胸元から鶸色の小さな巾着袋を取り出した。
そして妖しく、にんまりと口角を上げて話す。
「尚華様。伯蓮様を手に入れられるのも、もうすぐですよ」
豪子の策略、そして謎の巾着袋。
尚華はこの時初めて、父親の豪子を心の底から恐ろしいと思った。