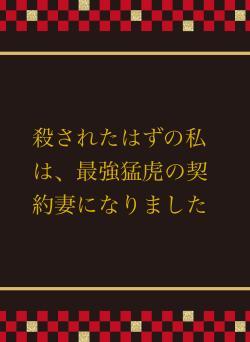「……伯蓮様」
朱璃は意を決して、伯蓮の名前を呼ぶ。
今抱えている想いが溢れたまま胸がいっぱいで苦しい。それを吐き出したかった。
「わ……私、多分。恋を、しています」
初めて明かされた朱璃の胸中に、伯蓮も驚きを隠せずに目を見張った。
振り絞るように出した声と、耳まで真っ赤にした朱璃の様子に、伯蓮の期待が高まる。
「その方の幸せを願い、その方を想うと胸が激しく脈打つのは、恋、なんですよね?」
伯蓮の心臓の鼓動を聞かされたことがある朱璃が、確かめるように尋ねた。
恋をすると生じる異変は、すでに朱璃の身にも起こっていた。
ただ、朱璃には伯蓮以外にもそう思える存在があった。
「そのもふもふに触れると、こう、心臓がきゅーんとして……」
「…………ん? もふもふ?」
様子のおかしい会話になってきて、伯蓮が怪訝な表情を浮かべる。
朱璃は両頬を包み込んで陶酔しており、体をクネクネさせていた。
そしてついに宣言される。
「伯蓮様とあやかしたちに、恋をしているみたいなんです!」
「…………ん……?」
朱璃との相思相愛が確立されて、超絶嬉しいはずの伯蓮が無表情になる。
どうやら伯蓮に向けられる朱璃の想いは、あやかしに向けられるものと同格らしい。
その新事実に、周りにいた三々、そして流と星が一斉に朱璃を凝視して空気が凍る。
すると皆を代表して、眠っていたはずの貂々が呆れたため息を漏らし説教をはじめた。
「朱璃」
「わ、貂々。起きてたの?」
突然目を開けて話しはじめた貂々に驚く朱璃は、先ほどの問題発言を問題と思ってない様子だった。
肝心なところで間違う朱璃に、貂々はわかりやすく恋とは何かを解説する。
「お前は人間だ」
「わ、わかってるよ……」
「ならば恋をする相手は当然人間。あやかしが好きなのは結構だが、その好きは“恋”とは違う」
断言された朱璃は、雷を受けたような衝撃に打ちひしがれていた。
あやかしを想う気持ちと、伯蓮を想う気持ちが同じだと考えてみたら、朱璃の中で気持ちが軽くなった。
一国の皇太子に恋をしたなんて認めたら、報われない恋に苦しむだけの未来が待っているから。
ただし、その考えを貂々は逃げだと悟った。
すると、徐々に表情がこわばってきた朱璃が、とうとう観念したように本音を漏らしはじめた。
「……だって、私なんかが伯蓮様をお慕いするなんて、そんなのダメに決まってる……」
両手で顔を隠しながら、朱璃は今すぐ部屋を逃げ出したいと思った。
伯蓮の気持ちに気付きながらも誤魔化して、自分の気持ちにも嘘をつく。
その理由が朱璃の言葉から読み取れて、伯蓮は臓器をもぎ取られるような痛みを感じた。
朱璃の立場を思えば当然ともいえる、身分の差。
苦しむ朱璃を慰めたくて、伯蓮はそっと席を立つ。
そして朱璃の席まで歩み寄ると、その場に跪いて優しい声をかけた。
「私には勿体無いほどに、朱璃は素敵な女性だ」
「そ、そんなはずありません。私は国境近い郷の貧しい家の出で――」
「違うんだ朱璃……私を見て」
顔を隠したまま首を横に振るので、伯蓮は朱璃の名をそっと呼んだ。
すると、顔を覆っていたは両手を下ろした朱璃の、今にも泣き出しそうな顔が露わになった。
その潤んだ瞳も、震える唇も。
今の伯蓮にとっては褒美になるほどに、愛おしい姿がそこにある。
「私が朱璃を想う気持ちはもう止めようがない。同じように朱璃も想ってくれているなら、嬉しい」
「っ……伯蓮様……」
「それだけで、私はとても幸せだ」
家柄も身分も負い目に感じることなく、朱璃には自分の気持ちに正直でいてほしい。
そう思い、伯蓮が朱璃に微笑みかけると、朱璃の瞳から涙が溢れ出る。
「っ……伯蓮様を、お慕いしたままでも、いいのですか……?」
「私が許す。私は朱璃に想われたいし、こうして触れたいのだから……」
声を震わせながら歓喜する朱璃の涙を、伯蓮が指先で優しく拭う。
すると瞬きした朱璃が、潤んだ瞳で伯蓮を見つめてきた。
そんなふうに見られては居ても立っても居られなくなる。
跪いていた伯蓮は、感情のままにそっと顔を近づけていく。
互いの心が通った直後、その喜びを分かち合うためにも唇を重ねたい思うのは当然のこと。
しかしそう思っていたのは伯蓮だけで、鼻先が触れそうな地点で朱璃の顔が後退りした。
「ハッ、ごごごめんなさい! お顔が近くにあって心臓がもたないので、つい!」
「…………つい、か」
必死に言い訳をする朱璃だが、伯蓮は活力を失った目をしたまま動かない。
悪気があったわけではないと理解しつつも、ようやく迎えた口付けの機会を拒まれたことに変わりはない。
今にも灰になって風に飛ばされそうな伯蓮の背後で、三々と貂々がコソコソと会話する。
「うわ、皇太子が拒否られてんぞ」
「私の子孫として非常に恥ずかしいな」
「今の空気感でイケると思った伯蓮、憐れ」
「驕りが過ぎた」
全くコソコソできていない二匹の容赦ない言葉の数々が、しっかりと伯蓮の耳にも届いていた。
羞恥と鬱憤で肩を震わせながら立ち上がった伯蓮は、二匹に近づいていく。
そして窓を開け放ち、二匹の首根っこを掴んでペッと追い出した。
ここは三階。つまり二階部分の琉璃瓦上に置かれた貂々と三々は、互いの顔を見合わせて少しだけ反省会をす開く。
「からかいすぎた?」
「皇太子といえど、まだまだ青いな」
一方、窓を閉めた伯蓮は、言葉が話せるあやかしも考えものだなとため息をついた。
ただ、不機嫌を隠しきれなかった自分の未熟さも痛感して、少し反省の色を見せる。
たかが口付けを断られたくらいで。と悔恨の念にかられていると、背後から声をかけられた。
「伯蓮様、そのまま後ろを向いていてくださいっ」
「朱璃……?」
動きを制限された伯蓮は、窓の方を向いたまま朱璃に何かあったのかと不安になる。
しかし、その思考は背中に伝わってきた温もりによって、すぐに解除された。
慣れないなりに、後ろからそっと抱きついてきた朱璃の気持ちが、伯蓮の心を大きな衝撃を与える。
「さ、先ほどはすみませんでした……。い、今は、これが限界で……」
「……いや、朱璃は悪くない。私が急に……」
「違うんです。伯蓮様は、その……」
言いながら伯蓮の体を抱く腕の力が、ぎゅっと強くなる。
言葉はぎこちなくても、その行動は朱璃の今の気持ちの表れだ。
だから伯蓮は、振り向いて抱きしめ返したい衝動を必死に抑え、続く言葉を待った。
「……伯蓮様は私に、“初めて”をくれるんです……」
蓮の香りを初めて近くに感じたあの日。綺麗な手を差し伸べながら初めて会話したあの瞬間。
思いがけない胸の高鳴りを覚えて、思い返せばこれが恋の始まりだったようにも思う。
そして初めて笑顔を見せてくれた時、初めて抱き抱えてくれた時。
激しく波立つ鼓動を抑えられなくて、眠れない夜を初めて経験した。
「これが、恋をするってことなんですね。伯蓮様……」
感情を揺さぶられて、それがたまらなく嬉しくてもどかしい。
それが伯蓮と同じ気持ちだということが、朱璃にとってまた喜びに変わる。
そう思うと離れ難い朱璃だったが、さすがの伯蓮も我慢の限界を訪れようとしていた。
「……っ朱璃、飲み直そう」
背後から抱きつく細い腕に手を添えて、伯蓮は空気を変える一言を伝える。
朱璃は明るく返事をして、二人は席に座り直した。
「この杏仁豆腐も是非食べてほしい。私の大好物だ」
「伯蓮様のおすすめですね! いただきます!」
再度果酒を注いで乾杯し、楽しそうに会話を弾ませる。
架子牀の隅から一部始終を見ていた流と星は、二人の笑顔にホッと胸を撫で下ろす。
そして衾の上で欠伸を漏らし、寄り添いながら入眠した。
閉め出されてしまった三々は外から部屋を覗き込み、その様子を貂々に実況する。
「貂々、伯蓮が耐えたぞぉぉ!」
「……はあ、私たちは一体何を見せられているのだ……」
「まあいいじゃん。始まったばかりの二人なんだから見守ってやろうぜ」
呆れた顔をする貂々を励ます三々は、楽しそうに笑みを浮かべる。
未来ある皇太子が宿命に抗い、しきたりを変えようと奮闘した。
健気で鈍感な侍女が、初めての恋に胸を躍らせている。
歴史的瞬間に立ち会えたことを良しとして、夜空を見上げた二匹のあやかし。
その背中は、まるで二人の保護者のようだった。
***
朝日が昇ると共に、本日の業務が始まる侍従の関韋。
伯蓮の私室までやってきて、いつものように起床刻を知らせようとしている。
しかし本日は、扉前で腕を組み暫し考える。
(……大丈夫、だろうな……?)
昨夜の宴会は、どうしても朱璃と二人でお祝いをしたいという伯蓮の頼みだった。
ここ最近の伯蓮の心労を考えて、今回のみと承知することにした関韋。
しかし、一応二人は年頃の男女なわけでそれなりに危惧していた。
(あんなことやこんなことまでは許可していませんからね、伯蓮様……)
そう念じ「失礼いたします」と声をかけ、いざ私室の扉を開ける。
しんと静まり返った室内を進むと、円卓の上には空の皿や筒杯が置かれたまま。
しかし二人の姿は確認できず、関韋は部屋中に視線を配った。
すると、架子牀の衾の上に大きな影が存在していることに気づく。
その正体は、衣服を纏ったまま並んで寝転がっている朱璃と伯蓮。
小さな寝息を立てて、寄り添いながら眠っていた。
(……な、なんだこの、純真な二人は……!)
その光景は関韋には眩しさを覚えるほどに、清らかな空気を放っていた。
そして自分の想像していたものが、いかに汚い大人の発想だったかを突きつけられて猛省した。
二人とも無防備な状態で眠り、その手はそっと繋がれているのが確認できる。
関韋は強い衝撃を受けて、ぐっと眉間を押さえた。そして――。
「……尊い」
つい口を滑らせて出た言葉と共に、二人に畏敬の念を抱く侍従。
もう少しだけこのままでいさせてあげようと、気を利かせて静かに部屋をあとにする。
パタンと閉じられた微かな扉の音に、伯蓮の瞼がピクリと動いた。
「……ん……朝か……」
寝ぼけた意識の中で、昨夜のことを思い出す。
まるで遊び疲れた子供のように、二人揃って寝てしまった。
すると片手に温もりを感じて、伯蓮が起き上がる。
隣に眠る朱璃と、いつの間にか手を繋いでいたのだ。
「……無意識の中でも、朱璃を求めてしまうのだな」
それはもう仕方のないことだと諦めた伯蓮は、繋がれた手をキュッと優しく握る。
朱璃の寝顔を愛おしそうに見つめ、幸せを噛み締めていた。
今なら昨夜拒まれた口付けが容易にできる。
そんな邪念を一瞬抱いたものの、尚華との嫌な出来事を思い出してすぐに振り払われた。
こうして手を繋いだまま、朱璃と朝を迎えられる日がまた訪れることを、伯蓮は密かに願う。