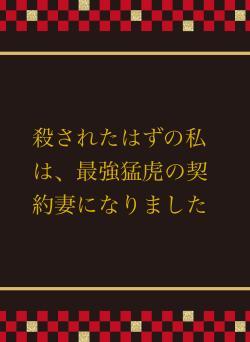扉を壊してしまった書庫から、三人とあやかし一匹が退室した。
伯蓮に抱き抱えられる朱璃は、その腕の中で大人しくしてする。
ただ、ずっと緊張していて体は強張り、表情が引き攣っていた。
そんな二人の後ろをついて歩くのは、実は人間の言葉が話せることが判明した貂々。
それと、流星に願いを届けて今だけ人間の姿をしている流。
書庫を出て広い空間に出た時、一つあくびをした流がふと見つけた。
広間の中心にある大きな物体。
伯蓮と同じ背丈ほどのそれは、大幕が掛けられていて中身が不明。
「なんだあれ、確認してみよっと」
「流、勝手に――!」
伯蓮の制止も聞かず、好奇心いっぱいの笑みを浮かべた流が幕を掴む。
美しい妃や異国の女神の彫刻などを期待して、丈夫な幕を思い切り引っ張った。
すると突如現れたのは、仏座に佇んでいる男性の塑像。
鮮やかに着色されて傷んだ様子もなく、凛々しく整った顔と優しい口元がよくわかる。
冕服を着用しているところを見ると、この塑像が皇帝だと誰もが理解した。
全てが粘土で造られていると思いきや、頭には本物の冕冠を被る。
おそらく、この皇帝が愛用していた実物なのだろう。
初めて見る塑像に、別人ではあるけれど伯蓮にとてもよく似ていると朱璃が思っていた。
それを伝えようと顔を上げた時、伯蓮本人は言葉を失い瞠目している。
「……伯蓮様?」
「あ、すまない。少し驚いてしまった」
「立派な塑像ですね。どなたかご存知なのですか?」
何気なく朱璃が問うと、伯蓮は何か考えるように視線を落とした。
一つ瞬きをしたのち、思いあたる人物の名を口にする。
「……第十代皇帝、鄧鮑泉様だ」
鄧王朝、第十代皇帝。今から二百年も前に生きていた皇帝陛下の塑像だった。
由緒ある歴史的塑像に、朱璃は心から感動して瞳を輝かせている。
「こんなにお美しい方だったんですね!」
「そうだな。私も肖像画と記録書で読んだだけだったが――」
その時、今まで沈黙していた貂々が、伯蓮の話を遮って批判的なことを話しはじめた。
「政治に関心がなく全て臣下任せ。酒と女遊びにうつつを抜かしていた暗君だ」
「え、そうだったの⁉︎」
貂々の言葉に、朱璃は衝撃を受けたように声を上げる。
塑像から滲み出る端正な顔立ちや優しい雰囲気に、勝手に名君だと思い込んでいたから。
「おかげで子孫繁栄には役立ったが、世子を決めることなく死んだ」
そのため、余計な派閥を生み兄弟たちで歪み合い宮中の雰囲気は最悪。
臣下たちは裏で悪行を働き、国の財政を危機に陥れた。
朱璃にもわかりやすく説明する貂々は、怒りと悲しみに満ちた表情で鮑泉の塑像を睨む。
こんなに感情を表に出す貂々を見るのは、初夜妨害の日以来。
朱璃が少し不思議に思っていると、同じように考えていた伯蓮が不意に問いかけた。
「貂々、なぜそんなに詳しいのだ?」
「……暇な時に王宮の歴史書を読んでいただけだ」
「しかし、それはあくまで後世に残された王宮都合の評価だ」
貂々の話に納得していないような表情で、伯蓮が鮑泉の塑像に視線を向ける。
「私が知る鄧鮑泉という皇帝の素性は、その侍従が残した極秘手記が基だ」
「……侍従……?」
今まで冷静だった貂々が、明らかに動揺して目を見張った。
そのような手記の存在は、今まで聞いたことがなかったから。
伯蓮だけがその手記を手にしていた理由は一つ。
まだ後宮で暮らしていた幼い頃に、一匹のあやかしが咥えていたのが、古びた手記。
その価値を知っていた伯蓮は、こっそりと大切に保管していた。
そして、手記の内容を知りたそうにする貂々のために、伯蓮は自分が知る鮑泉という人物の生涯を語りはじめた。
***
今から二百年前、鮑泉が第十代皇帝となる以前の出来事。
十八歳の皇太子だった鮑泉には、密かに想いを寄せる姚羌という同い年の侍女がいた。
やがて二人は身分差を超えて慕い合う仲となり、ついに鮑泉は姚羌を妃にしたいと実父に願い出る。
そこで皇帝になったばかりの父は、ある条件を出してきた。
『宰相の娘を妃として迎え、のちの皇后とすること』
『皇后とは皇太子の母です。まだ世継ぎもなく、私の即位もいつになるか不明だというのに……』
そもそも、宰相の娘との間に子ができるかもわからない。
鮑泉は、今からそのような条件を提示するなど無意味だと思った。それでも皇帝は意見を覆さない。
『代々、皇后は家柄が求められる。お前も知っているだろう』
『ですが姚羌はとても誠実で深慮深く――』
鮑泉が反論しようとすると、皇帝は嘲笑って冷ややかな視線を向けてきた。
『フン、農民の出の皇后など聞いたことがない。お前は鄧王朝の歴史に傷を作るつもりか』
『……父上……』
我が父ながら、皇帝になった途端に冷酷な人間になってしまったと鮑泉は絶句する。
胸焼けのような吐き気を覚えながらも、握りしめた拳をどうすることもできずに、ただただ耐えた。
政略結婚という条件を強いられた鮑泉は、姚羌を皇后として臣下や国民に認めてもらえる未来はないと悟る。
*
そのことを包み隠さず姚羌に説明した鮑泉は、自分の非力さを痛感して何度も謝った。
しかし姚羌は、鮑泉のそばにいられるなら妾で充分だとして、入内を決意する。
こうして、渋々皇帝の条件を飲んだ鮑泉は、やがて姚羌を貴妃の位を与える。
のちに宰相の娘を皇后候補として迎えたものの、娘の宮に赴くことはせず。
鮑泉は姚羌の宮ばかりに通い、寵愛し続けた。
そんな生活を三月送った頃、宰相の娘が体調を崩して寝込んでしまったという知らせがやってくる。
鮑泉が見舞いに向かうと、娘は豪華な架子牀で横たわっていた。
顔色は青白く、確かに具合がよくないように見受けられて鮑泉も心配する。
すると突然、宰相の娘がとんでもないことを言い出した。
『……姚羌妃との食事の際に、毒を盛られました』
娘を診察した医官が、少量の毒による体調不良だと診断したらしい。
しかし、そんなことをいったい誰が……と鮑泉が考えた時。
『姚羌妃しかいませんわ』
娘は眉根を寄せながら、姚羌の犯行だと言い切った。
姚羌の人柄も優しさも知っている鮑泉は、彼女が他人に毒を盛るとは信じ難く、誤解だと否定する。
『姚羌がそんなことをするはずない。何かの間違いだ』
『わたくしに恨みを持つ者は、この後宮内に姚羌妃だけです』
『証拠もないのに何を――』
流石の鮑泉も苛立ちと焦りを覚えはじめた時、娘は小さな巾着袋を翳した。
そして、ひどく傷ついたような表情で証言する。
『先ほど、姚羌妃の部屋から発見されたと報告を受けました』
『それは……』
『毒です。今頃、姚羌妃は捕えられ尋問中でしょう』
全ての証拠が出揃えば、皇帝も黙っているわけにはいかない。
何かの間違いで、姚羌が何者かに罪をなすりつけられた可能性もあるのに。
充分な再調査も行わないまま、鮑泉の訴えも虚しく、姚羌は牢に閉じ込められてしまった。
それだけにとどまらず、姚羌に心酔している鮑泉が証拠隠滅に加担することを考え、二人の面会禁止。
以降、鮑泉は毎日毎日、皇帝と宰相を相手に抗議し続けた。
『姚羌はそんなことをする人間ではない! 他に犯人がいるはずです!』
謁見の間に、鮑泉の激情をはらんだ声が響き渡った。
それを皇帝は軽くあしらうように、頬杖をついて対応する。
『お前はあの性悪女に騙されているのだ。地位欲しさに宰相の娘に毒を盛るとは』
『その毒の出所を調べてください! それと姚羌の部屋の出入りをした者を――』
『くどいぞ鮑泉! 次期皇帝となるお前がこのようなことで冷静さを失っては国は滅びるぞ!』
どの口が言っているのかと反論したい鮑泉が、グッと言葉を飲み込んだ。
実の父とはいえ皇帝に刃向かえば処罰される。
姚羌を救ってやれるのは自分だけだと察し、鮑泉は耐えに耐えた。
*
姚羌が捕らえられて、二月が経ってしまった。
新たな証拠や証言をする者は見つからず、姚羌の疑いは晴れないまま。
独り牢獄で過ごす姚羌を思うと、鮑泉は毎日胸に槍が刺さったような苦痛を抱いていた。
唯一、姚羌の様子を知ることができる方法が、面会した侍従の報告。
信頼できる侍従に頼み、自分の代わりに姚羌の面会をお願いしていた。
日に日に顔色が悪くなる姚羌は、ついに嘔吐を繰り返すようになり、寝込むほど衰弱していると報告された。
精神的にも肉体的にも限界。
このままでは姚羌の命が危ないと感じた鮑泉は、一か八かで宰相の娘の宮を訪問した。
自分の力ではどうすることもできない。だから恥を承知で、姚羌を救ってほしいと娘に頭を下げて懇願する。
すると、返ってきた言葉は――。
『姚羌妃を国外追放してくださるなら、許して差し上げます』
『……後宮だけでなく、国を去れというのか』
『殺されかけたわたくしは、一生会いたくありませんので』
例外は認めないというような目で、鮑泉をじっと見つめる娘。
今の皇帝は宰相の言いなり。
そんな独裁的宰相の娘が、皇太子である鮑泉を脅すような言葉を選んで言い放つ。
強気な態度と駆け引き上手は、父を宰相に持つだけあって非常に用意周到で腹立たしい。
ただ、悩んでいる猶予も選択肢もない。
鮑泉は血の味がするほどに歯を食いしばって、娘の条件を受け入れた。
貴妃の位を剥奪し、国外追放することで姚羌はこの世のどこかで生きていける。
この手で幸せにしてやれないことを悔やみながらも、今の自分では皇帝どころか宰相にも勝てない。
己の無力さと無能を痛感して、鮑泉は姚羌との永遠の別れを覚悟した。
その翌日。牢獄から監視部屋に移送された姚羌は、充分な食事と暖かい衣を用意される。
同時に国外追放の命が知らされると、静かに目を閉じ頷いたと風の噂で聞いた。
姚羌の体調が回復して間も無く、自らの足で後宮を去ったことを、鮑泉は後日聞かされる。
結局最後まで、姚羌に会うことは叶わなかった。
しかし、面会を禁止されていた鮑泉は、姚羌のためにあるものを用意していた。
後宮を出たあと、生活に困らないための金子。
そして謝罪の言葉と、いつまでも愛していると綴った文。
それらをまとめた小包を、後宮を出る直前の姚羌に渡してほしい。
この後宮で一番信頼している侍従にそれを託していた。
『あの小包は、姚羌様にお渡ししております』
『そうか。感謝する……』
強い西日に照らされる私室で、侍従からの報告を受けた鮑泉。
西の空を眺めたまま、しばらく動けずにいた。
何も考えたくない、何も知りたくない。
そんな心の声が聞こえた気がした侍従は、静かに鮑泉の部屋を退室した。
そのため、この時の鮑泉が人知れず涙を流していたという事実は、侍従の手記には記されていない。
***
「……とても悲しいお話です」
二百年前の鮑泉と姚羌の悲恋を知って、朱璃が頬を涙で濡らしていた。
伯蓮が知っている鮑泉は、決して暗君ではない。
もしそうだとしても、その責任は国にあると言いたかった。
「鮑泉様は最も愛する人との別れを経験し、次第に生きる気力を失っていったのだ」
「そうなりますよ、鮑泉様も姚羌様もかわいそうです」
毒を盛られた娘の、誰も信用できない不安な気持ちも理解できる。
しかし、姚羌が無実を訴えているのに、一方的に処罰されることに朱璃は納得できなかった。
そして伯蓮は、今の自分と同じ立場の鮑泉の状況を、よく理解していた。
「結局、皇太子といえど政の駒。利益の駒に利用される無力な人間なのだ」
「伯蓮様……」
「だからこそ鮑泉様は、皇帝に即位できれば力を得られると思っていた」
その一年後、皇帝が病に倒れたまま再起不能となり、鮑泉は第十代皇帝陛下となる。
これで鮑泉は、皇帝の父に縛られることがなくなると思い、朱璃が安堵した。
「しかし、即位後の侍従の手記には……」
突然、躊躇するような素振りをみせた伯蓮に、朱璃も首を傾げてしまう。
すると、言いにくそうにする伯蓮の代わりに貂々が語り出した。
「鮑泉が皇帝となったことで、宰相の娘は念願の皇后の座に就いた」
「え?」
「娘は子を産んだのだ。鮑泉の世子となりうる男児を……」
それを聞いて、朱璃はなんとも言えない悔しさと儚さが込み上げてきた。
手記を読んで事実を知っていた伯蓮も、納得できないように眉根を寄せる。
そして貂々は、さらに吐き気を催すほどの真実を話した。
「即位を祝して宴が催された。そこでついに、皇后が鮑泉に耳打ちしたのだ」
「な、何を……?」
恐怖心を煽られた朱璃が、身を縮こませた。
「“最初から毒など盛られていない”、“自作自演した甲斐があった”――と」
無事に皇后となった宰相の娘は、ついに種明かしをしてきたと貂々が説明した。
衝撃を受けた朱璃は、今まで感じたことのないような憤りを覚えて瞳を潤ませる。
ただ伯蓮だけは不思議そうに貂々を見つめ、少しの間沈黙した。
そして自身が手記で読んだ、真実を知った後の鮑泉の様子を語る。
「宴の翌日。鮑泉様は国外追放となった姚羌様を呼び戻すため、侍従に捜索を依頼したと書かれてあった」
「そうですよね。皇后様の自白で姚羌様が濡れ衣だったと判明しましたから!」
やはり姚羌は毒なんて盛っていない。それがわかって朱璃が笑顔を咲かせた。
隣国を捜索して一年。侍従はようやく邑のはずれで、姚羌を見つけることになる。
しかし、その時の事が書かれた手記の一文を思い出して、伯蓮は胸が締め付けられる感覚に陥った。
初めて手記を読んだ当時十歳の頃は、そこまでの感情は湧かなかった。
それは幼かっただけでなく、そのような経験がなく想像が難しかったから。
けれど今なら、鮑泉の想いも侍従の気持ちも痛いほど理解できる。
今だからこそ、沸き立つ感情が伯蓮の中にあった。
「手記には、“姚羌様のそばには立つのを覚えたばかりの幼な子と、薪を抱えた温厚そうな男の姿があった”――と」
「え……」
鄧北国を追放されてから、二年が経過していた。
その間に新たな家族ができていた姚羌は、変わらず美しく、とても幸せそうに笑っていたらしい。
鮑泉のために姚羌を探し当てた侍従も、声をかけられないほどの雰囲気。
もう一度、姚羌を後宮に迎え入れたいと考えていた鮑泉。
その想いを知りながら、侍従は姚羌に気づかれないようにその場を立ち去ることにした。
侍従だけが味わった苦悩と葛藤が、懺悔のように書かれていたと伯蓮は話す。
王宮に戻った侍従は、鮑泉に事実を伝えようか迷った。
しかし、全てを知りたいと本人が望んだため、目撃したままを包み隠さず報告する。
姚羌が新たな家族と過ごしていたことを知った鮑泉は、ただただ悲しげに笑ったという。
「それからの鮑泉様は、政は宰相の思うままに運ばせ、毎晩酒を飲むようになった」
自暴自棄となった鮑泉に対して、侍従はどうやって救うことができるのかわからなかった。
鮑泉は、後宮への入内を希望する者を皆快く迎え入れていく。
寂しさを埋めるように、たくさんの妃の宮に通ったという記録もあった。
酒に溺れ女に溺れた、歴代皇帝の中で暗君と呼ばれる鮑泉。
その真相は、語り継がれることのなかった悲しき恋の物語が隠されていた。
「しかし酒の飲み過ぎが祟ったのか、鮑泉様は四十代の若さで……」
「そうでしたか。どうかあちらの世界では、穏やかに過ごせていると良いですね」
悔しさを滲ませる伯蓮を見た朱璃は、鮑泉に思いを馳せて微笑んだ。
その優しい心に、伯蓮も自然と表情が柔らかくなっていく。
「鮑泉様は、ただ一人の女性をずっと愛し続けたかった、心優しいお方なのだ」
言いながら目を閉じ、伯蓮が祈りを捧げる。
朱璃もそれに倣って、塑像に向かい手を合わせた。
二人の姿を横目に、貂々も黙って鮑泉の塑像を見上げる。
幕で覆われ忘れ去られていた塑像が今、少しだけ微笑んだように見えた。
「さあ、そろそろ廟を出ようか。流は幕を元通りに」
「わかってるよ。しっかし皇帝ってなんだか孤独なんだなー」
流が塑像に幕を掛け直しながら、他人事のように言い放つ。
その言葉を耳にした伯蓮は、眉を下げて悲しげに微笑んだ。
皇帝も皇太子も、生まれた時から将来が約束されている者は、たくさんの臣下と従者を従えていても孤独だ。
だからこそ、その宿命にある伯蓮は古いしきたりや因習を変えていきたいと考える。
鮑泉の経験した悲劇を繰り返さないように。もっと自由に誰かを想いながら生きられるように。
そう考えた時、真っ先に朱璃の笑顔が脳内を支配して、伯蓮は微かに頬を赤く染めた。