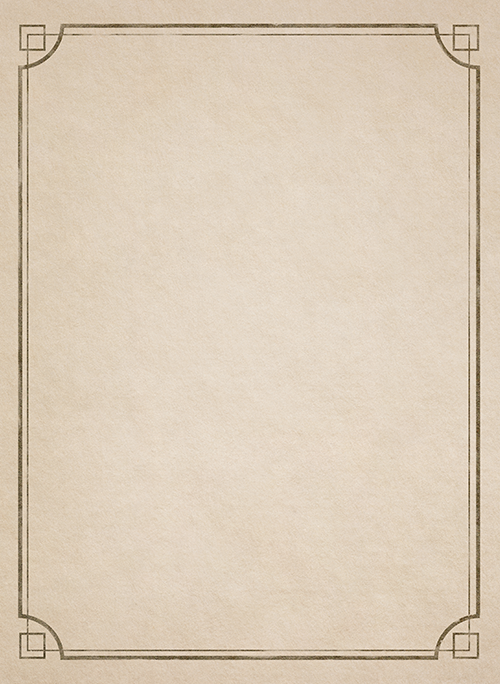「理由も聞かされずに何かをするのは嫌いなんだ」
渉がそう言うと、諦めたようにあかりはぽつりと呟いた。
「呉屋くんって、すごく優しい性格してるじゃない」
「僕が? 優しい?」
渉はすっかり力を抜いていた背中と腰を、元の位置まで引き上げた。油断していたところに急に「優しい」と言われて驚いたのだ。
「去年のクラスで、呉屋くんの友達が喧嘩したことあったでしょ? 覚えてる?」
「覚えてるよ、数少ない友達だからね。池原と、屋宜のことでしょ?」
「ええ、そうよ。あの時、クラスの中で二人を本気で心配してたの、呉屋くんだけだったじゃない。自分から話をしに行って、最後には仲直りまでさせたのを見て、私思ったの。呉屋くんって、相手が真剣な気持ちの時には同じくらいの気持ちで応えてくれるんだってね。自分ごととして受け止められるって、結構素敵なことじゃない?」
「仲直りなんて立派なものじゃないよ。話を聞いてストレスを発散させただけ。あの二人に何かあったら、僕の生活に直接関わるんだから心配にもなるよ」
「あなたって、意外と自己肯定感低いのね」
「僕はそういう人間なんだ。今のところ変えるつもりもない」
渉はあかりに笑って見せた。彼の笑みには、自虐的なものが含まれていた。
「でも、あなたは自分で思ってるよりずっと素敵な人だと思うな。少なくとも、私の目にはそう見える」
「何かの錯覚かもしれない」
「でも私って勘が鋭い方なの。その私が言ってるんだから、間違い無い。だからもっと自信持ってよ」
と、あかりが言った。そして渉がしたように、白い歯を見せて笑った。
空には雲が重くのしかかっているのだが、彼女が笑った瞬間にそこだけ陽がさしたような感覚があった。
眩しい笑顔とはこのことか、と渉は思った。そして言った。
「相談、乗るよ」
「本当に?」
「うん。ただ、事件解決のために僕にも何かさせて欲しい。どうせなら、石嶺さんの家族が偽物かどうかちゃんと確認しよう。そのための方法を、これから一緒に考えよう」
渉がそう言うと、あかりはもう一度笑った。それから「ありがとう!」と大きな声で礼を言った。
「今日の呉屋くん、いつもより酷い顔をしてたから正直不安だったんだ。話しかけていいのかってね。でも、おかげでなんとかなりそう」
「いつもより酷い顔……。普段の僕って顔が酷いの?」
「うん。死んだ魚の目ってやつ。でも今日は、砂浜に流れ着いたクジラ
渉がそう言うと、諦めたようにあかりはぽつりと呟いた。
「呉屋くんって、すごく優しい性格してるじゃない」
「僕が? 優しい?」
渉はすっかり力を抜いていた背中と腰を、元の位置まで引き上げた。油断していたところに急に「優しい」と言われて驚いたのだ。
「去年のクラスで、呉屋くんの友達が喧嘩したことあったでしょ? 覚えてる?」
「覚えてるよ、数少ない友達だからね。池原と、屋宜のことでしょ?」
「ええ、そうよ。あの時、クラスの中で二人を本気で心配してたの、呉屋くんだけだったじゃない。自分から話をしに行って、最後には仲直りまでさせたのを見て、私思ったの。呉屋くんって、相手が真剣な気持ちの時には同じくらいの気持ちで応えてくれるんだってね。自分ごととして受け止められるって、結構素敵なことじゃない?」
「仲直りなんて立派なものじゃないよ。話を聞いてストレスを発散させただけ。あの二人に何かあったら、僕の生活に直接関わるんだから心配にもなるよ」
「あなたって、意外と自己肯定感低いのね」
「僕はそういう人間なんだ。今のところ変えるつもりもない」
渉はあかりに笑って見せた。彼の笑みには、自虐的なものが含まれていた。
「でも、あなたは自分で思ってるよりずっと素敵な人だと思うな。少なくとも、私の目にはそう見える」
「何かの錯覚かもしれない」
「でも私って勘が鋭い方なの。その私が言ってるんだから、間違い無い。だからもっと自信持ってよ」
と、あかりが言った。そして渉がしたように、白い歯を見せて笑った。
空には雲が重くのしかかっているのだが、彼女が笑った瞬間にそこだけ陽がさしたような感覚があった。
眩しい笑顔とはこのことか、と渉は思った。そして言った。
「相談、乗るよ」
「本当に?」
「うん。ただ、事件解決のために僕にも何かさせて欲しい。どうせなら、石嶺さんの家族が偽物かどうかちゃんと確認しよう。そのための方法を、これから一緒に考えよう」
渉がそう言うと、あかりはもう一度笑った。それから「ありがとう!」と大きな声で礼を言った。
「今日の呉屋くん、いつもより酷い顔をしてたから正直不安だったんだ。話しかけていいのかってね。でも、おかげでなんとかなりそう」
「いつもより酷い顔……。普段の僕って顔が酷いの?」
「うん。死んだ魚の目ってやつ。でも今日は、砂浜に流れ着いたクジラ