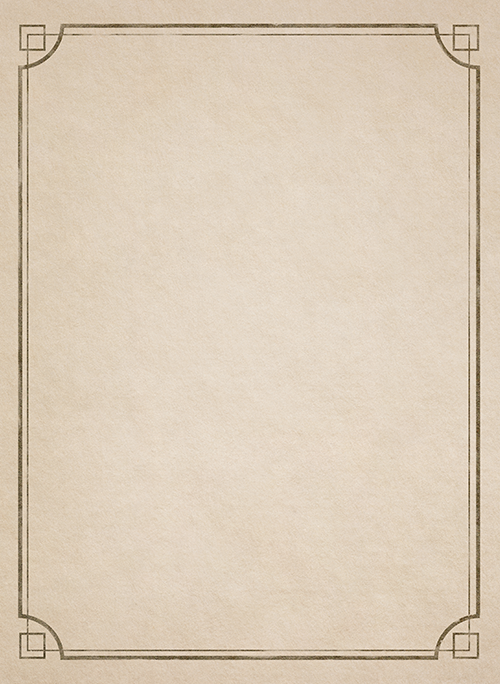ただ、イタズラにしては嘘の相談話の内容が不可思議すぎる。
普通、渉のような男子を騙すのにこんな話題をこしらえる必要もないはずなのだ。
とりあえず彼は思い切って踏み込まず、ジャブを打つことに決めた。
「その前に、訊きたいことがあるんだ」
「なに?」
あかりはきょとんとした。まさか質問で返されるとは想像していなかったのだろう。
「どうして、僕にこの相談をしたの? 石嶺さんは友達がたくさんいるし、先生たちともかなり仲が良い。何より、こうして二人きりで話す機会だってこれまでなかったんだ。それなのに、どうして僕でなくてはいけなかったんだろう」
渉とあかりは、去年も教室が同じであった。一年三組に所属していた。
だが二年生が終わりかけているこの頃になっても、口を聞いたことがない。
厳密には授業のグループワークの際会話をした覚えがあるものの、至って事務的なものだった。
だから渉は、疑問を感じないわけにはいかないのだ。
「それは、単純な理由よ。こんな話をしたら、変に思われるじゃない。友達に話しても、先生に話しても、最悪妙な噂が流れて終了。悩みを解決するどころか、むしろ増やしちゃう。でも呉屋くん相手なら、そう言うこともないでしょ?」
肘を机の上に置いて、手のひらで顎を支えながらあかりは言った。彼女の顔には、嫌な笑顔が張り付けられていた。
「つまり、僕にならどう思われたって構わないってことね。どんな噂を流されても、痛くも痒くもない」
渉はあからさまに椅子の上で脱力してみせた。肩を下げて、浅く腰掛けた。
少し慌てた様子で、あかりは言った。
「嘘よ、嘘。冗談に決まってるじゃない」
「冗談には思えなかったけどね。僕みたいなのは石嶺さんたちより『下』にいる人間だから、都合よく利用してやろうって魂胆なんでしょ? そういう顔してた」
「本当に、違うの! ちょっとお笑いの要素を入れて、雰囲気を中和しようと思っただけ! ほら、なんだかさっきから気まずい空気流れてるじゃない? だからこう、和ませようと……」
「本当に?」
渉が訊くと、あかりは何度も力強く首を縦に振った。本気で焦っているように見える。
「冗談だって言うなら、本当の理由聞かせてよ。なんで僕だったの?」
「どうしても、言わなきゃだめ?」
普通、渉のような男子を騙すのにこんな話題をこしらえる必要もないはずなのだ。
とりあえず彼は思い切って踏み込まず、ジャブを打つことに決めた。
「その前に、訊きたいことがあるんだ」
「なに?」
あかりはきょとんとした。まさか質問で返されるとは想像していなかったのだろう。
「どうして、僕にこの相談をしたの? 石嶺さんは友達がたくさんいるし、先生たちともかなり仲が良い。何より、こうして二人きりで話す機会だってこれまでなかったんだ。それなのに、どうして僕でなくてはいけなかったんだろう」
渉とあかりは、去年も教室が同じであった。一年三組に所属していた。
だが二年生が終わりかけているこの頃になっても、口を聞いたことがない。
厳密には授業のグループワークの際会話をした覚えがあるものの、至って事務的なものだった。
だから渉は、疑問を感じないわけにはいかないのだ。
「それは、単純な理由よ。こんな話をしたら、変に思われるじゃない。友達に話しても、先生に話しても、最悪妙な噂が流れて終了。悩みを解決するどころか、むしろ増やしちゃう。でも呉屋くん相手なら、そう言うこともないでしょ?」
肘を机の上に置いて、手のひらで顎を支えながらあかりは言った。彼女の顔には、嫌な笑顔が張り付けられていた。
「つまり、僕にならどう思われたって構わないってことね。どんな噂を流されても、痛くも痒くもない」
渉はあからさまに椅子の上で脱力してみせた。肩を下げて、浅く腰掛けた。
少し慌てた様子で、あかりは言った。
「嘘よ、嘘。冗談に決まってるじゃない」
「冗談には思えなかったけどね。僕みたいなのは石嶺さんたちより『下』にいる人間だから、都合よく利用してやろうって魂胆なんでしょ? そういう顔してた」
「本当に、違うの! ちょっとお笑いの要素を入れて、雰囲気を中和しようと思っただけ! ほら、なんだかさっきから気まずい空気流れてるじゃない? だからこう、和ませようと……」
「本当に?」
渉が訊くと、あかりは何度も力強く首を縦に振った。本気で焦っているように見える。
「冗談だって言うなら、本当の理由聞かせてよ。なんで僕だったの?」
「どうしても、言わなきゃだめ?」