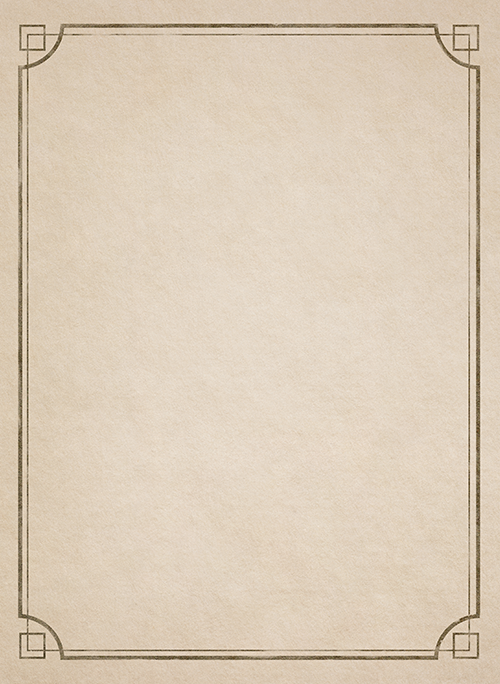「その旅行って、いつの話?」
「帰ってきたのが、二週間くらい前だった、ような気がする」
どうやら彼女も曖昧に記憶しているらしい。しかし裏を返せば、それだけの間奇妙な違和感は続いているということだ。
「はっきりと日付は覚えていないんだけど、とにかく、旅行から帰ってきた日には言葉遣いが変になってた。最初は、旅行が楽しくて浮かれているんだろうなって思ってた。でも、いつになっても元に戻らなくて。それでよく観察してみたら、他にもいろんなところが前とは違ってた。気のせいだって言い聞かせてきたけど、明らかに違うのよ。だから、呉屋くんに話を聞いてもらおうって考えたの。呉屋くんは私の話、どう思う?」
渉は「どう思うと言われても」と呟いて、こめかみに人差し指を置いた。
「僕は石嶺さんのご両親とは会ったことがない。顔も見たことないから、全部想像の中の話になってしまう。正直に言えば、僕にできることは何もないんじゃないかな」
「何かしてほしいわけじゃないのよ。ただ話を聞いて、どう思ったのか聞かせてほしいの」
「ただ僕の感想が欲しいんだ」
「そういうこと」
渉はもう一度額に人差し指を押し当てた。そして「うーん……」と唸った。
出し抜けに持ち込まれたこの話は、彼にとってわからない点が多すぎる。
何より渉が気に掛かったのは、石嶺あかりという人物が彼に相談を持ちかけたことそのものだった。
彼女は本来、何かを怖がったりする性格ではないはずだ。
教室の中ではいつも、仲間の女子たちと談笑して盛り上がっている。他人の席に無断で腰掛けることだってあるような、いわば『イケイケグループ』の中にいる花の女子高生なのだ。
渉はその手の人種があまり好きではない。しかし目立つことは目立つので、毎日その存在感に圧倒されていた。
そのあかりが友人も連れず、たった一人で渉に会いにきたのだ。貴重な放課後の時間を使って。
イタズラの可能性も考慮して、図書室に来るまでの道中何度も背後を振り返ったが、仲間らしき生徒の影はなかった。
ならばあかりは、本気でこの相談をしているのだろうか。
簡単にそのようだと結論づけるのは早計な気もするが、かといってイタズラと断定できる材料もない。
渉は額に指を当てたままうーん、ともう一度唸った。
これがもしイタズラだったなら、真剣に相談に乗る必要性はどこにもない。
「帰ってきたのが、二週間くらい前だった、ような気がする」
どうやら彼女も曖昧に記憶しているらしい。しかし裏を返せば、それだけの間奇妙な違和感は続いているということだ。
「はっきりと日付は覚えていないんだけど、とにかく、旅行から帰ってきた日には言葉遣いが変になってた。最初は、旅行が楽しくて浮かれているんだろうなって思ってた。でも、いつになっても元に戻らなくて。それでよく観察してみたら、他にもいろんなところが前とは違ってた。気のせいだって言い聞かせてきたけど、明らかに違うのよ。だから、呉屋くんに話を聞いてもらおうって考えたの。呉屋くんは私の話、どう思う?」
渉は「どう思うと言われても」と呟いて、こめかみに人差し指を置いた。
「僕は石嶺さんのご両親とは会ったことがない。顔も見たことないから、全部想像の中の話になってしまう。正直に言えば、僕にできることは何もないんじゃないかな」
「何かしてほしいわけじゃないのよ。ただ話を聞いて、どう思ったのか聞かせてほしいの」
「ただ僕の感想が欲しいんだ」
「そういうこと」
渉はもう一度額に人差し指を押し当てた。そして「うーん……」と唸った。
出し抜けに持ち込まれたこの話は、彼にとってわからない点が多すぎる。
何より渉が気に掛かったのは、石嶺あかりという人物が彼に相談を持ちかけたことそのものだった。
彼女は本来、何かを怖がったりする性格ではないはずだ。
教室の中ではいつも、仲間の女子たちと談笑して盛り上がっている。他人の席に無断で腰掛けることだってあるような、いわば『イケイケグループ』の中にいる花の女子高生なのだ。
渉はその手の人種があまり好きではない。しかし目立つことは目立つので、毎日その存在感に圧倒されていた。
そのあかりが友人も連れず、たった一人で渉に会いにきたのだ。貴重な放課後の時間を使って。
イタズラの可能性も考慮して、図書室に来るまでの道中何度も背後を振り返ったが、仲間らしき生徒の影はなかった。
ならばあかりは、本気でこの相談をしているのだろうか。
簡単にそのようだと結論づけるのは早計な気もするが、かといってイタズラと断定できる材料もない。
渉は額に指を当てたままうーん、ともう一度唸った。
これがもしイタズラだったなら、真剣に相談に乗る必要性はどこにもない。