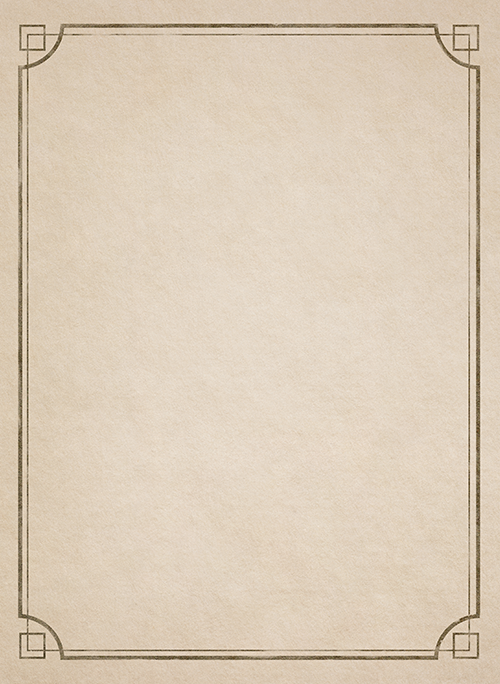思った。
窓の外の景色を一瞥してから、あかりは深呼吸し、そしてこう言った。
「実はね、私の両親が偽物かもしれないの」
彼女の声は震え、弱々しいものだった。何かに怯えているのか、それとも強い不安を感じているのか。
さっきまでのぶっきらぼうな態度とは打って変わった声の響き方に、渉は戸惑う。それと同時に、話してくれた内容の突拍子のなさに困惑した。
彼は直前まで、「好きです。付き合ってください」などと言われて所謂『本命のチョコレート』を渡されるのだとばかり考えていた。自分のような人が何故、と疑問がないではなかったが、シチュエーションのせいで疑いにくくなっていたのだ。
ところが現実としてあるのは、クラスメイトから家族について相談されるというもの。脳の処理が追いつかないと言っても、誰も咎めたりはしないだろう。
故に、彼は反応が遅れた。
言葉のキャッチボールに空白が生まれた。その空白は、沈黙という形をとって二人を包んだ。
お互いに何も言わない時間が一〇秒、二〇秒と続き、痺れを切らしたようにあかりが口を開いた。
「何か言ってよ!」
ぶっきらぼうな口調が元に戻っていた。
「ごめん、なんていうか、想像の斜め上だったから。どう返すのが正解なのかちょっとわかんなくて」
渉は、この日三度目となる謝罪を行った。そして続けた。
「石嶺さんの家族について相談する、ということなんだよね?」
あかりは直前に見せた怯えるような眼差しで、渉を見た。それから一度頷いた。
「ええ。私のお母さんとお父さんが、偽物に思えるのよ」
「それは、どういう意味なの?」
「言葉通りの意味、といってもそれだけじゃわからないわよね。つまり私が言いたいのは、見た目はお父さんとお母さんで間違いないけれど、いつもと様子が違うっていうことよ」
「様子が違う?」
と、渉は言った。具体的にどのように違うのかを尋ねるニュアンスが込められていた。
「たとえば、前とは話し方が少し変わったの。お父さんは乱暴な言葉遣いをすることが増えたし、逆にお母さんは敬語を使うことが目につくようになった。その他にも、色や食べ物の好み、寝る時間とかお風呂に入るタイミングとか、いろんなところが変わってしまってるの。でも、顔とか声とか、身長とかは少しも変わってない。私が気づく限りでは、外
窓の外の景色を一瞥してから、あかりは深呼吸し、そしてこう言った。
「実はね、私の両親が偽物かもしれないの」
彼女の声は震え、弱々しいものだった。何かに怯えているのか、それとも強い不安を感じているのか。
さっきまでのぶっきらぼうな態度とは打って変わった声の響き方に、渉は戸惑う。それと同時に、話してくれた内容の突拍子のなさに困惑した。
彼は直前まで、「好きです。付き合ってください」などと言われて所謂『本命のチョコレート』を渡されるのだとばかり考えていた。自分のような人が何故、と疑問がないではなかったが、シチュエーションのせいで疑いにくくなっていたのだ。
ところが現実としてあるのは、クラスメイトから家族について相談されるというもの。脳の処理が追いつかないと言っても、誰も咎めたりはしないだろう。
故に、彼は反応が遅れた。
言葉のキャッチボールに空白が生まれた。その空白は、沈黙という形をとって二人を包んだ。
お互いに何も言わない時間が一〇秒、二〇秒と続き、痺れを切らしたようにあかりが口を開いた。
「何か言ってよ!」
ぶっきらぼうな口調が元に戻っていた。
「ごめん、なんていうか、想像の斜め上だったから。どう返すのが正解なのかちょっとわかんなくて」
渉は、この日三度目となる謝罪を行った。そして続けた。
「石嶺さんの家族について相談する、ということなんだよね?」
あかりは直前に見せた怯えるような眼差しで、渉を見た。それから一度頷いた。
「ええ。私のお母さんとお父さんが、偽物に思えるのよ」
「それは、どういう意味なの?」
「言葉通りの意味、といってもそれだけじゃわからないわよね。つまり私が言いたいのは、見た目はお父さんとお母さんで間違いないけれど、いつもと様子が違うっていうことよ」
「様子が違う?」
と、渉は言った。具体的にどのように違うのかを尋ねるニュアンスが込められていた。
「たとえば、前とは話し方が少し変わったの。お父さんは乱暴な言葉遣いをすることが増えたし、逆にお母さんは敬語を使うことが目につくようになった。その他にも、色や食べ物の好み、寝る時間とかお風呂に入るタイミングとか、いろんなところが変わってしまってるの。でも、顔とか声とか、身長とかは少しも変わってない。私が気づく限りでは、外