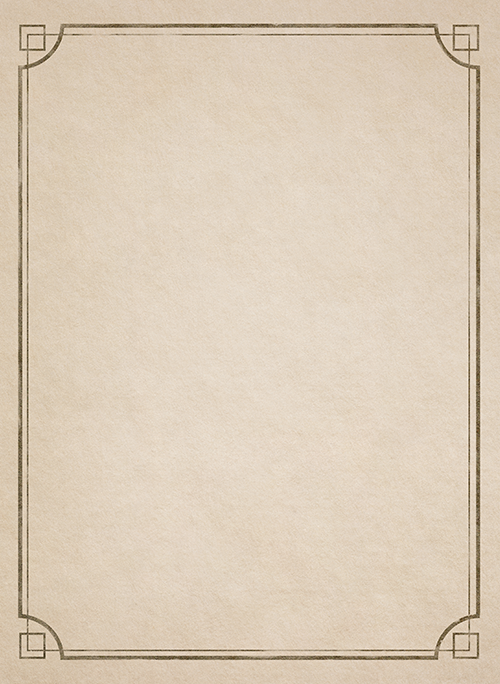もしかすると、もしかするかもしれない。
否が応でも、ピンク色の妄想が膨らんでいった。
どこか人気のない場所を知らないか、とあかりに訊かれて、渉は図書室をあげた。図書委員とか、司書の先生も本日は留守にしているはずだと伝えた。
「どうしてそんなこと知ってるの」
「本が好きなんだ。ほぼ毎日通ってて、図書委員とか担当の先生のスケジュールとかもある程度聞いてる」
「あそこの人たちと仲が良いんだ」
「結構良いと思う」
果たして、図書室には図書委員の生徒も、司書の先生もいなかった。他に利用している生徒もおらず、放課後の喧騒から隔絶された空間となっていた。
閉めた窓の向こうから部活生の元気のある掛け声が聞こえることを別にすれば、音を立てるものは一つもない。
まるでここだけが、人々から忘れ去られたかのようだった。
渉とあかりの二人は、窓際に置かれた四人掛けの席に腰を下ろした。そこは本来なら、読書や調べ物で活用されるべきものだった。
この場合においては、違う使い道を見出された。
「それで、話って何?」
やや緊張しながら渉が訊いた。これまでの人生を振り返ってみても、そんなフレーズを口に出した経験は一度も無い。彼にとってはドラマや漫画の中だけの言葉だった。
それが今、自分でも驚くくらいごく自然なものとして発することができた。青春の扉をノックした瞬間だと、彼は確信した。
「それがね、とっても言い難いことなの」
と、あかりが言った。
「全部を話そうとすると、とっても難しいの。始まりから終わりまでをきっちり説明しようとしたら、なんていうか、順番が入れ違ったりしそうで。糸が絡まってるような感じがするというか」
「だ、大丈夫だよ。落ち着いて話してみて。話してみたら、意外とうまくできたりするものだよ」
「そうよね。じゃあ、話すわ」
あかりがそこで言葉を切った。次に口にするべき言葉を慎重に選んでいる気配があった。
渉は唾を飲んだ。静かな図書室の中では、その音さえあかりの耳まで届いていそうだった。
緊張した渉の向かいに座るあかりが、自分の膝に目を落とした。
彼女の視線の先では、二つの手が互いの指をもじもじと絡み合わせていた。直接確認したわけではないが、連動する腕の動きを見た限りではそのようになっているはずだ。
彼女の落ち着かない心境が指先の動きとなって表れたのだ、と渉は
否が応でも、ピンク色の妄想が膨らんでいった。
どこか人気のない場所を知らないか、とあかりに訊かれて、渉は図書室をあげた。図書委員とか、司書の先生も本日は留守にしているはずだと伝えた。
「どうしてそんなこと知ってるの」
「本が好きなんだ。ほぼ毎日通ってて、図書委員とか担当の先生のスケジュールとかもある程度聞いてる」
「あそこの人たちと仲が良いんだ」
「結構良いと思う」
果たして、図書室には図書委員の生徒も、司書の先生もいなかった。他に利用している生徒もおらず、放課後の喧騒から隔絶された空間となっていた。
閉めた窓の向こうから部活生の元気のある掛け声が聞こえることを別にすれば、音を立てるものは一つもない。
まるでここだけが、人々から忘れ去られたかのようだった。
渉とあかりの二人は、窓際に置かれた四人掛けの席に腰を下ろした。そこは本来なら、読書や調べ物で活用されるべきものだった。
この場合においては、違う使い道を見出された。
「それで、話って何?」
やや緊張しながら渉が訊いた。これまでの人生を振り返ってみても、そんなフレーズを口に出した経験は一度も無い。彼にとってはドラマや漫画の中だけの言葉だった。
それが今、自分でも驚くくらいごく自然なものとして発することができた。青春の扉をノックした瞬間だと、彼は確信した。
「それがね、とっても言い難いことなの」
と、あかりが言った。
「全部を話そうとすると、とっても難しいの。始まりから終わりまでをきっちり説明しようとしたら、なんていうか、順番が入れ違ったりしそうで。糸が絡まってるような感じがするというか」
「だ、大丈夫だよ。落ち着いて話してみて。話してみたら、意外とうまくできたりするものだよ」
「そうよね。じゃあ、話すわ」
あかりがそこで言葉を切った。次に口にするべき言葉を慎重に選んでいる気配があった。
渉は唾を飲んだ。静かな図書室の中では、その音さえあかりの耳まで届いていそうだった。
緊張した渉の向かいに座るあかりが、自分の膝に目を落とした。
彼女の視線の先では、二つの手が互いの指をもじもじと絡み合わせていた。直接確認したわけではないが、連動する腕の動きを見た限りではそのようになっているはずだ。
彼女の落ち着かない心境が指先の動きとなって表れたのだ、と渉は