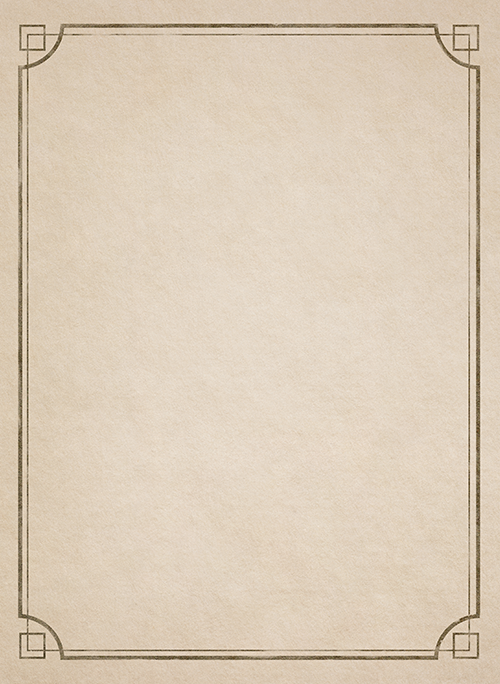どんな顔をしているのか、見てみようじゃないか。
練った作戦通りに、渉はトイレに入った。すぐ後ろで「あっ」と女子が声を漏らしたが、気がつかないふりをした。
個室には入らず、鏡の前にも立たず、渉は入ってすぐの場所で立ち止まり、後ろを向いた。きっと、『呉屋さん』の背中を追いかける女子が通り過ぎていくだろう。
そんな想像をしながら回れ右をすると、予想外なことに女子生徒と目が合った。
そんなバカな、と彼は思った。ここは女人禁制の男子用便所の入口だ。普通なら、女性は決して近寄ったりしない場所のはずなのだ。
あるいは自分か、目の前の女子生徒のどちらかが入るところを間違えたのかもしれない。慌てて渉は首を回し、トイレ内の構造を確認した。男子のために作られた小便器が並んでいる。見間違えるはずはない。
ということは、女子生徒が間違えた側なのだろうか。それとも、女装をした男子なのだろうか。
渉はもう一度、立ち塞がる女子を見た。突然の事態でわからなかったのだが、よく見ると目の前にいるのは同じクラスの生徒だった。
茶色がかった髪の毛が特徴的な人物だった。地毛なのか、染めたのかは知らない。髪の長さは肩に届くくらいのもので、よく手入れが行き届いているように見える。
制服を程よく着崩している様子から、身なり指導をあまり恐れていないような人であることも窺えた。
彼女の名は、石嶺あかりといった。
「石嶺さん……? ここは男子トイレ、だよ……?」
とりあえず彼は言ってみた。
「わかるわよ、そのくらい」
と、あかりはぶっきらぼうに言った。
「どれだけ呼んでも反応してくれないから、出てくるところを捕まえてやろうと思ったの。そしたら急に振り向くんだもの、びっくりしたわ」
「ごめんなさい。まさか僕のことだと思わなくて……」
「トイレに立てこもって様子を伺おうとしたんだ」
渉はごめんさい、と、もう一度謝った。
「まあ、いいわ。それよりも、呉屋くんに聞いてほしい話があるの。これから予定ある?」
「今日は何もないよ」
「じゃあ、場所を変えましょう。少なくともトイレの入り口で話すようなことじゃないから」
そう言って、彼女はどこかに向かって歩き出した。渉はその後を追った。
話を聞いてほしい、とあかりは口にした。いったいどんな話だろうかと渉は考えてみた。日付のことを含めて考えるのなら、内容はいくらか限定される。それは、今日の彼が密かに期待していた類のものだ。
練った作戦通りに、渉はトイレに入った。すぐ後ろで「あっ」と女子が声を漏らしたが、気がつかないふりをした。
個室には入らず、鏡の前にも立たず、渉は入ってすぐの場所で立ち止まり、後ろを向いた。きっと、『呉屋さん』の背中を追いかける女子が通り過ぎていくだろう。
そんな想像をしながら回れ右をすると、予想外なことに女子生徒と目が合った。
そんなバカな、と彼は思った。ここは女人禁制の男子用便所の入口だ。普通なら、女性は決して近寄ったりしない場所のはずなのだ。
あるいは自分か、目の前の女子生徒のどちらかが入るところを間違えたのかもしれない。慌てて渉は首を回し、トイレ内の構造を確認した。男子のために作られた小便器が並んでいる。見間違えるはずはない。
ということは、女子生徒が間違えた側なのだろうか。それとも、女装をした男子なのだろうか。
渉はもう一度、立ち塞がる女子を見た。突然の事態でわからなかったのだが、よく見ると目の前にいるのは同じクラスの生徒だった。
茶色がかった髪の毛が特徴的な人物だった。地毛なのか、染めたのかは知らない。髪の長さは肩に届くくらいのもので、よく手入れが行き届いているように見える。
制服を程よく着崩している様子から、身なり指導をあまり恐れていないような人であることも窺えた。
彼女の名は、石嶺あかりといった。
「石嶺さん……? ここは男子トイレ、だよ……?」
とりあえず彼は言ってみた。
「わかるわよ、そのくらい」
と、あかりはぶっきらぼうに言った。
「どれだけ呼んでも反応してくれないから、出てくるところを捕まえてやろうと思ったの。そしたら急に振り向くんだもの、びっくりしたわ」
「ごめんなさい。まさか僕のことだと思わなくて……」
「トイレに立てこもって様子を伺おうとしたんだ」
渉はごめんさい、と、もう一度謝った。
「まあ、いいわ。それよりも、呉屋くんに聞いてほしい話があるの。これから予定ある?」
「今日は何もないよ」
「じゃあ、場所を変えましょう。少なくともトイレの入り口で話すようなことじゃないから」
そう言って、彼女はどこかに向かって歩き出した。渉はその後を追った。
話を聞いてほしい、とあかりは口にした。いったいどんな話だろうかと渉は考えてみた。日付のことを含めて考えるのなら、内容はいくらか限定される。それは、今日の彼が密かに期待していた類のものだ。