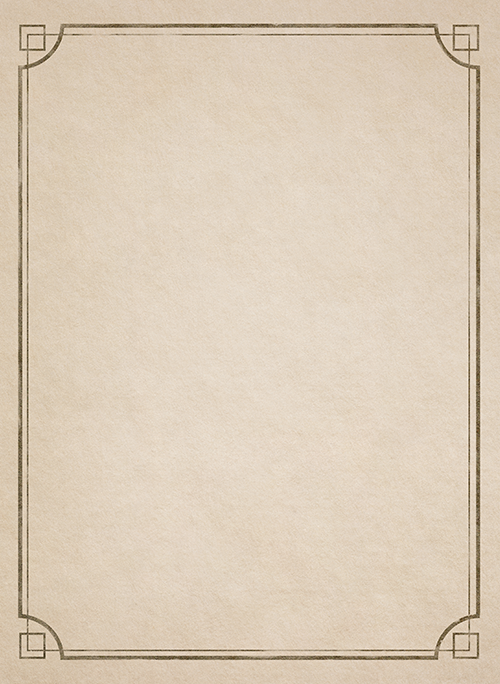その日は、雲が空を支配して今にも雨を降らしそうな天気だった。
空に敷き詰められた灰色のカーペットが、地に足をつけて生活する人々を否応なしにどんよりとした気持ちにさせていた。
高校生の呉屋渉も、どんよりとした一人だった。
渉は生気のない目で辺りを観察しながら、学校の廊下を歩いていた。彼と同じ制服の学生たちは皆、曇り空だろうが元気な顔をして学校を出ていった。
これからアルバイトをする者もいるだろう。あるいは、遊びに出掛けにいくのかもしれない。
そんな周囲の様子とは正反対な表情を、渉は浮かべていた。そして、彼と同じような顔をしている者は、少なくとも校舎二階の廊下にはいなかった。
浮かれやがって、と渉は思った。皆、自分が良い思いをしたからと、浮き足だっているのだ。すぐそこに、惨めな思いをしている人間がいるにもかかわらず。
彼は小さく息を吐いた。失望のために排出された気体は、どこまでも暗い気配を伴う。
今日は二月一四日の水曜日。バレンタインデーである。
周囲の人間は色恋沙汰で夢中になっていた。唯一空に覆い被さる雲だけが、渉の味方をしていた。だが渉は知っている。どれだけ暗い色の雲だとしても、その向こうには晴れ渡った空が広がっていることを。太陽が照らし、澄んだ青空が存在している。
今ある黒雲たちは、取り繕ったうわべだけのものでしかない。渉に歩調を合わせる裏では、爽やかな笑みを湛えている。そう思えば、曇り空を眺めても気分はちっともすぐれなかった。
普段より重く感じるリュックサックを鬱陶しく思いながら歩いている渉に、声がかかったのはその時だった。
「呉屋くん。ちょっといいかな」
声がしたのは、背後からだった。女子の声だった。
最初、渉は同じ苗字をした誰かが呼ばれたのだと思った。だから振り向かず、無視をした。
しかし声はもう一度、渉の苗字を読み上げた。
「呉屋くん、呉屋くん。ねえ、聞いてる?」
もしや、と彼は想像した。ひょっとすると、声の主は自分を呼んでいるのではないか。
彼のいる場所からほんの数メートル先に、トイレが見えた。ちょうどいい、と心の中でつぶやいて、トイレの中に入ろうと心を決めた。
入り口の辺りで立ち止まって、背後を確認するのだ。トイレの前を通り過ぎていく女子がいたら、その人物が渉の苗字を何度も読み上げた者で間違いない。
空に敷き詰められた灰色のカーペットが、地に足をつけて生活する人々を否応なしにどんよりとした気持ちにさせていた。
高校生の呉屋渉も、どんよりとした一人だった。
渉は生気のない目で辺りを観察しながら、学校の廊下を歩いていた。彼と同じ制服の学生たちは皆、曇り空だろうが元気な顔をして学校を出ていった。
これからアルバイトをする者もいるだろう。あるいは、遊びに出掛けにいくのかもしれない。
そんな周囲の様子とは正反対な表情を、渉は浮かべていた。そして、彼と同じような顔をしている者は、少なくとも校舎二階の廊下にはいなかった。
浮かれやがって、と渉は思った。皆、自分が良い思いをしたからと、浮き足だっているのだ。すぐそこに、惨めな思いをしている人間がいるにもかかわらず。
彼は小さく息を吐いた。失望のために排出された気体は、どこまでも暗い気配を伴う。
今日は二月一四日の水曜日。バレンタインデーである。
周囲の人間は色恋沙汰で夢中になっていた。唯一空に覆い被さる雲だけが、渉の味方をしていた。だが渉は知っている。どれだけ暗い色の雲だとしても、その向こうには晴れ渡った空が広がっていることを。太陽が照らし、澄んだ青空が存在している。
今ある黒雲たちは、取り繕ったうわべだけのものでしかない。渉に歩調を合わせる裏では、爽やかな笑みを湛えている。そう思えば、曇り空を眺めても気分はちっともすぐれなかった。
普段より重く感じるリュックサックを鬱陶しく思いながら歩いている渉に、声がかかったのはその時だった。
「呉屋くん。ちょっといいかな」
声がしたのは、背後からだった。女子の声だった。
最初、渉は同じ苗字をした誰かが呼ばれたのだと思った。だから振り向かず、無視をした。
しかし声はもう一度、渉の苗字を読み上げた。
「呉屋くん、呉屋くん。ねえ、聞いてる?」
もしや、と彼は想像した。ひょっとすると、声の主は自分を呼んでいるのではないか。
彼のいる場所からほんの数メートル先に、トイレが見えた。ちょうどいい、と心の中でつぶやいて、トイレの中に入ろうと心を決めた。
入り口の辺りで立ち止まって、背後を確認するのだ。トイレの前を通り過ぎていく女子がいたら、その人物が渉の苗字を何度も読み上げた者で間違いない。