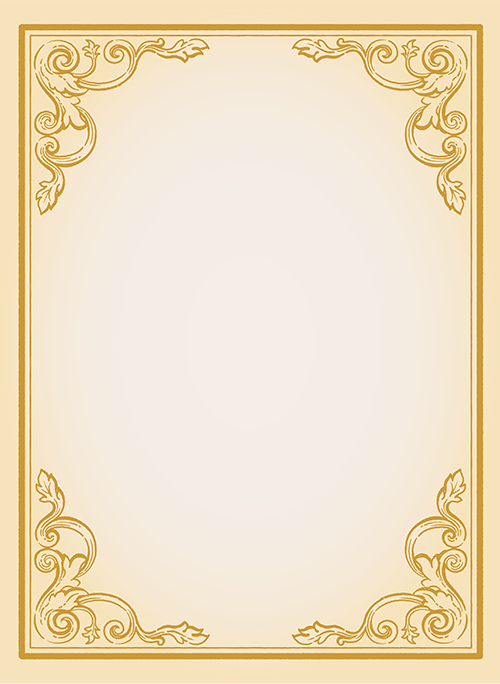夜の満月をバックに、黒の帽子《ハット》がゆるりと通過した。
その帽子は緩やかな風に乗って左右に大きく揺れながらも、住宅街の夜空を前進していく。
深夜、二時。
辺りには誰もいない。
帽子は山頂にそびえ立つ一本の大木の下に辿り着いた。
その木にもたれて休んでいた僕は、腰の辺りにあたった帽子を手に取った。
「……なんだ、これ?」
僕はいつの間にか流していた涙をぬぐい、月夜の明かりに照らされながら手に取った帽子を近くで見た。手品師が使いそうな帽子で、大きさは大人サイズ。悲しみにくれていたからちょうどいいと、僕は自分の涙を隠すためにその帽子をかぶってみた。
すると俯いた僕の目の前にカサっと草の擦れた音をたてて、誰かが舞い降りた。
綺麗に揃えたその足元を見たあとで、僕はゆっくりと顔を上げる。
「今宵のお客様は今日五歳になるロイ、君かい?」
紳士的な声の問いかけを聞き、僕はぽかんと口を開けた。
二十代半ばくらいのタキシード姿の男が立っていた。
男は、僕を見て言った。
「君の嫌なものを消してあげようか、手品で」
男は微笑み、僕は口を一文字に結んだ。
僕は少し固まり、そして立ち上がる。
……あやしい、人、だ。
僕はくるりと向きを変え、男に背を向け走りだした。うっかり、男の帽子を返さないままで。
「おや、逃げる気なのかい?」
男は穏やかな声を張り上げた。
当たり前だろ……!
僕は全速力でまっすぐに走りながら、ちらりと後ろを振り返る。
男は余裕そうな表情で体をふわりと浮かせたまままっすぐに僕を追いかけてきている。
なにあれ、なにあれ。
「わああっ!」
男の目はきつねのようにつり上がっていた。その表情を見てやっぱり男は悪人に違いないと僕は叫んで走り続けた。
とにかく必死に走った、が、いつの間にか男は高く舞い上がっていて、そして瞬時に僕の前に立ちはだかった。
きつねの目。
すらりとした長身。
重く冷たい雰囲気。
タキシード姿。
手品師。
僕は驚きのあまり何も言えないまま尻餅をついた。
「やれやれ考えが甘いね、走って逃げればわたしが追いつかないとでも思ったのかい?」
男はくすくすと笑ったあと、顔をひきつらせている僕の前にかがんだ。
「ねえ、君も月夜の手品師になってみたいと思わないかい?」
「月夜の、手品師?」
「そうさ」
僕は少し眉を寄せた。男は話を重ねる。
「今宵のような満月の光に照らされて、三、二、一で、嫌な感情を消して、月の光となる手品師になるんだ」
男はにこりとする。
僕はさらに驚いたあとで、前のめりに耳を傾ける。
「そんなことが……できるの?」
僕が小さく尋ねると
「できるよ、わたしの力を見せよう。まずは何から消そうか?」
男は微笑んだ。手品師というのはいろんなものを消したり現したりする凄い人という考えのある僕だったが、男に対する警戒心は解けていない。
解けていない、けど……本当に僕を助けてくれる?
助けてくれると、したら……?
僕はまた小さく口を開く。
「家に帰りたくない。その不安な気持ちを消してくれる?」
僕が恐る恐る口にすると、男は頷き、微笑み、人差し指を出した。
「いいですよ。三、二、一……」
0のタイミングで人差し指を小さく回して僕の方にむける。すると僕の心の一部分がぽかぽかと温かくなり、僕の望むとおりになった。完全なる記憶喪失になったわけではない。ただ心の一部分がぼやけた感覚がする。これは消えたと言っていい。
また思い返したら戻ってきそうな気がするけど。
「本当に消せるの? どうやってやったの?」
目を丸めて僕が尋ねると、男は優しく
「君にもできるさ、練習すればね」
と答えた。
「あなたは、誰……?」
僕が尋ねると、男は丁寧にお辞儀をした。
「はじめまして。月夜の手品師、それが今のわたしの名前だよ」
と自己紹介をする。
僕は思う。
何者なんだろう。
ちゃんとした名前も言ってくれない。
それにこんな夜中に手品師がうろついて声をかけてくるなんて、しかも月夜の手品師と名乗るなんて、いかにも怪しい。
でも、今はそんなことどうでもいいと僕は思う。
過去を消してくれるなら、なんだって。
僕は男の不思議な力をさらに信じてみたくなった。
「まだ僕の嫌な感情を消すことはできる? 例えば今日、妹にされた嫌なことの感情、とか」
僕は尋ねた。男は答える。
「もちろんさ、三、二、一」
くるりと小さく回る人差し指が僕のほうを向くと、やはり期待通りになった。心の中にある不安で冷たい一部分がぽかぽかしてきた。
「すごいね、消えてく」
僕は胸に手を当てて、静かに感動していた。
「じんわりとあたたかくなって嫌なことが消える感覚が分かるはず」
男は姿勢を正して、優しく僕に話しかけた。
僕は疑問を持つ。
「もし過去を全部消したらどうなる?」
僕の質問に、男はそっと
「体だけが残る。感情のない、ロボットのような君の姿だけが、ね」
と柔らかく答える。
僕は少し黙りこんだあと、小さく口を開く。
「過去を消したら元に戻せるの?」
僕の問いかけに、男は苦笑いをしながら
「今は、ね」
と答えた。
僕は興味津々で
「あなたの使える手品はそれだけ?」
と尋ねてみた。男は
「そうだね。もう一つ、今手品を使ってるけど、君には分からないと思うからね」
と穏やかに答える。
もう一つとはなんだろうかということに疑問を持ったが、それよりも僕は今聞いてみたかった。
「あなたは悪い人? それともいい人?」
僕のさらなる問いかけに、男は
「……さあ、ね」
と言葉を濁した。そして
「次はどの感情を消す?」
と言葉を付け足した。
「え?」
と僕は驚く。
「まだ消したい過去があるだろ?」
と男は言う。どうして分かったのだろう。
「うん」
僕は頷く。男は凄腕の手品師なのだろうか。
「差し出せばいいよ。この満月の夜に」
男は次に向かって手を広げた。僕はぼんやりと次に何を消そうか考え、ふと顔を上げ、夜空の月を見て呟く。
「月が綺麗ですね」
「……え?」
「夏目漱石の言葉だよ。『月が綺麗ですね』は『あなたが好きです』って意味なんだって。あんなにあたたかな台詞を僕も言えたら良かったけど」
男は少し首をかしげた。
僕は月を見ながら話を続ける。
「月はさ、表面だけ輝いていて中は空洞だったりするのかもしれないなんて僕は考える。その空洞に不安や悲しみを全てを投げ入れて、もとからないことにしているから、輝いていられるのかなって」
僕がそう言うと、男は静かに僕のほうを見て口を開く。
「もしよかったらあの大木に戻って座って話をしないかい? こんな深夜に小さな君が家を抜け出して山頂までやってくるなんてよっぽどの理由があるんだろう? 君とわたしだけの内緒話をしよう」
男がそう提案すると、僕は頷いた。
僕の中にはもう男に対する警戒心は完全になかった。あやしいけど、男は僕に危害を加えない。
ふわりと少し浮かぶ男と一緒にゆっくり、ゆっくりと僕は大木まで戻った。
大木の下に二人で腰かける。
僕は木にもたれて足を伸ばして、男は三角座りをして。
目の前には鮮やかな住宅街の景色が広がっていた。
その中で、僕は口を開く。
「ねえ、月夜の手品師」
「なんだい?」
「あなたは手品で僕の悩みを消してくれたけど、消してもらった過去をまた思い返そうとすると、消した過去がまた戻ってしまいそうな感覚があるんだけど……?」
「手品は魔法ではないんだ」
「ねえ、ぼんやりとじゃなくてさ、完全に過去を消すにはどうすればいい? 僕は全部過去を消せたらそれでいい、過去を消したら……それで」
「……君の根本的な悩みはなんだい?」
男は三角座りをしたまま首を傾けながら僕に尋ねた。男は穏やかな口調だが、その時は目が笑っていなかった。
核心をつかれた気がして、僕はぎくりとした。でも僕は木にもたれるのをやめて、男の姿を真似て三角座りをして口を開く。
「一歳の妹がおもちゃを勢いよく僕に投げてくる。どんなに僕が優しくしてもあっちいけって。父さんも母さんも『まだいろんなことが分からない歳だから』って妹に甘くて、妹が失敗すれば、僕が怒られる、いつも。僕は頑張ってるのに」
「……そう」
「何で妹より早く生まれたからって僕が我慢しなきゃならないの? そりゃ僕だって父さんも母さんも妹の手伝いを必死に頑張りたいよ。僕なりに方法だって考えて、色々やってみたけど、でも結果は同じ。妹を支えてあげたい。でもうまくいかないし、方法が分からない。途方にくれた僕は……どうしたらいい? この木陰で泣くことしかできない?」
男は優しく言った。
「今を受け入れるのが一番優しい方法だよ」と。
僕は首を捻る。
「優しい?」
「そう、もう一度よく考えてみるのがいい。
今ある悩みはいったん全部受け止めるんだ。
痛くても冷たくても不安になっても、何があっても他人だけのせいにはすることは決してないように。相手にも自分にも、ろくなことがない。
そして人にも自分にも優しくする。
側に同じように悩んでいる人がいたら教えてあげるといい。
それが素敵な手品になるとね」
僕ははっとする。
よく見ると、男の姿が少し透明になっている。
男の重く冷たい雰囲気。
最初は怖いと思った、男が何者か分からなくて。
でも、そうじゃない。
僕は知っている。
重く冷たい雰囲気。
何者か分からないその姿を僕は知りすぎていると気づいた、やっと。
「そうか、あなたの正体が……分かったよ」
僕が口を開くと、男は黙ったまま僕を見つめる。そのきつねの目は……今は少し優しい。
「あなたはもう一人の僕だね? 僕が受け入れたら、あなたは……消えるんだね?」
僕が尋ねると男は一瞬黙り、そしてくすりと笑った。
「消えるなんて悪い言い方はよしてくれ。わたしは君と一緒になるだけさ」
僕は静かに言う。
「手品なんて言って本当は僕の痛みは何も消してないんだね。もう一人の僕である君が一時的に預かっただけで」
「見破られてしまったね、もう一つの手品を」
男はくすくすと笑った。
「何故あなたは、月の夜に現れたの?」
「その昔、満月は豊かさの象徴と言われていたらしい。今宵は満月で、君にも豊かな気持ちを思い出してほしかった」
「豊かな、気持ち……?」
「月は空洞なんかじゃない。確かな意思をそこに詰め込んで輝いている。それを知ってほしい。ちゃんと存在してるって」
今は優しい雰囲気があるのに、悲しげに微笑む男の表情を見て、僕は泣きそうになった。
僕は君をなくしていた。
空洞の中に閉じ込めてしまった。
輝けるという希望をもっていたのに、それから逃げた。
必死に逃げてしまった……背を向けて。
光なんかないと言って。
僕は口を強くつむる。
男は僕の悲しみを止めるように、僕の頭上にぽんと手を置く。
「さあ、最後のマジックだ。五歳のよいこは眠る時間だよ。本来、外にも出てはいけない。お父さんとお母さんに見つかる前に君はおうちに帰りなさい。わたしは君の中で長く眠るとしよう」
「……友達になれたと思ったのに」
「友達さ、わたしたちは」
「……消えないで」
「消えるんじゃない。言ったはずだ、君と一緒になるって」
僕は涙をこぼす。
『月は空洞なんかじゃない。確かな意思をそこに詰め込んで輝いている。それを知ってほしい。ちゃんと存在してるって』
さきほどの男の言葉を思い出す。その言葉は今の僕には悲しく聞こえる。
『なんでわたしのことを忘れてしまったの?』
そう聞こえた気がしたから。
男の姿がだんだんと霞んでいく。
男は口を開く。
「教えてあげよう。君が暗闇に紛れないようにするには未来に一つ一つ名前をつけて生きていけばいい。そうしたらもう感情を失うことはない。もうわたしたちが分裂しないように、君は今から素敵な君に化けるんだ。それは決して、君の恐れていることじゃない」
もう一人の僕の、それは最後の声。
月夜の手品師は、ろうそくを消したように静かに消えた。
僕は泣くのを堪えた。
堪えて堪えて堪えきり、胸に手を当てた。
これ以上、あなたがこぼれていかないように。
「消えたんじゃない、受け入れた」
痛みを受け入れ前を向いたら、それは最高の手品《マジック》になる。
『誰かに教えてあげて』と、あなたは言っていた。
今日の出来事を泣いて、全部失いたくなかった。
僕は静かに思う。
生き方として、僕も最高の手品師になろう、と。
人を騙す手品師ではなく、自分も誰かの人生も変える手品師になろう、と。
それにはきっと、練習がいる。
たくさんの、練習が。
満月の夜。
帽子は消え、男も消えた。
「今宵優しいあなたにだまされて、僕は救われたんだね」
受け入れた男を思いながら、僕は月に照らされ、にこりと微笑んだ。
満月を見て、ぽかぽかとあたたかくなる感情を、僕はこの先も失わないようにしたいと思った。
今宵僕は、不思議な手品を体感した。
そしてこれからも僕は僕を見捨てずに生きていく。