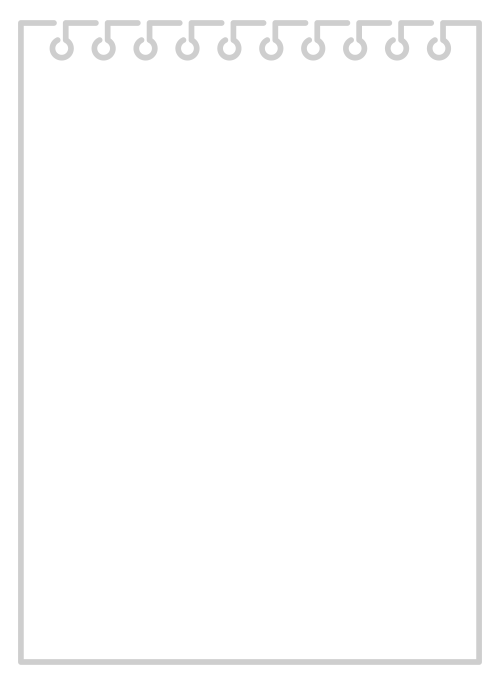夕日が私の部屋をオレンジ色に染め上げるのと比例しているかのように、私の身体が透け始める。
あぁ、死んじゃう。
私は夜、死んでしまう。
息はしてるし、その場には存在している、相手の声も聞こえるのに私の声は何一つ届かない。
歩けるし、どこでも動かせるのに周りからは見えない。自分でも、見えない。
そんなの、死んでるじゃん。
出来ることは、朝日とともに私が生き始めるのを静かに、息を殺して待つだけだ。
だから。
だから私は、夜を知らない—。
あぁ、死んじゃう。
私は夜、死んでしまう。
息はしてるし、その場には存在している、相手の声も聞こえるのに私の声は何一つ届かない。
歩けるし、どこでも動かせるのに周りからは見えない。自分でも、見えない。
そんなの、死んでるじゃん。
出来ることは、朝日とともに私が生き始めるのを静かに、息を殺して待つだけだ。
だから。
だから私は、夜を知らない—。