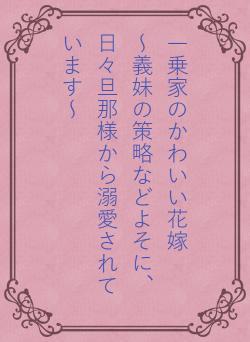昼から始まった菊と黒王の婚儀は、里長や郷の重役達が見守る厳かな雰囲気の中、つつがなく執り行われていた。
大広間に集った者達の姿は人間とまったく同じで、菊は三三九度の杯を傾けながら、ここが常世であることを忘れてしまいそうになる。
それほどに穏やかな陽気に包まれ、祝い事にはもってこいの日和だ。
開け放たれた障子の向こうには庭園が広がっており、松や竹の他にも池や石灯籠、そしてたくさんの桜の木が庭を飾っている。
今こそ本領発揮と満開に咲き誇った桜は、風が吹くたびに薄紅の儚い雨で庭石を色づけていく。誰がこの万感の景色を見て、あの恐ろしいものが棲まう、と言われる常世と思うだろうか。
三三九度を終え、緊張していた誓詞奉読も、ありがたいことに用意された紙は全て平仮名で書かれており、無事に終えることができた。
そうして、全ての儀式を終えれば、集まっていた皆が一斉に叩頭する。
自分よりも年上の里長や、配膳に動いていた女官や若葉、進行を支えていた灰墨まで皆が黒王と菊に頭を下げている状況に、菊はおたおたと動揺するが黒王は泰然としていた。
「祝着至極に存じます。ただ今よりあなた様は、我らが鴉一族の母となられました」
姿勢を低くした白髪の老爺が、趣のある寂声で菊を迎える言葉を述べれば、後を追って他の者達が一斉に「祝着至極に存じます」と声を揃えた。
「良かったな、これで俺達は正式に夫婦だ」
「ふう、ふ……ですか……」
「どうした、何か気掛かりなことでもあるのか」
己の胸にそっと手を置き見つめている菊に、黒王は首を傾げる。
「いえ、あの、その……それは……」
「それは?」
「……っとても、心がふわふわするものですね」
頬を桜色に染めてへにゃりと柔らかく笑う菊に、黒王はごくりと喉を鳴らした。しかし、すぐに何事もなかったように、温かな眼差しで「そうか」と頷いた。
二人にとっては何気ないやり取りだったのだろうが、これを見ていた里長や重役達は、目を丸くして黒王以上に驚く。
花御寮が来てからは少し雰囲気が柔らかくなったと思っていたが、これはその比ではない。
黒王は母親の件以降、あまり感情を露わにしなくなった。
次期黒王としての強い責任感からかあまり人を寄せ付けず、いつも冷然として物事に淡々とあたっていた印象がある。彼の父親が亡くなった時だとて、彼は泣くこともせず新たな黒王としての役目を義務的にこなしていた。
そんな彼が、見たこともない顔をして、感情をめっぽうあふれ出させている。
驚くなというほうが無理だろう。
「お二人の仲が良いとは聞いていたが……まさかこれほどとは」
里長のひとりが呟けば、周囲の者達も首振り人形のようにうんうんと頷いていた。
「それでは、花御寮様あらため、菊様。屋敷の外で皆が待っておりますので、行きましょう」
皆が待っているとはどういうことだろう、と菊は隣の黒王を見上げると、黒王は菊の手を握って頷く。その握り方があまりにも優しすぎて、むしろくすぐったいくらいで、菊は笑みを漏らしてしまう。
「その可愛い笑みを、郷の者達にも見せてやってくれ」
菊の頬に朱がさした。
「こ……黒王様は、なぜそのように恥ずかしいことばかり……っ」
可愛いだの、美しいだのと、ことある毎に言われ正直そのたび頭がクラクラしてしまう。出会った頃のあの冷たさは、はたしてどこに行ったのか。
「恥ずかしいことはないさ。可愛いものを可愛いと言っているだけだからな」
耳の先まで赤くなって俯くしかできなくなった菊を、皆が微笑ましく眺めていた。
◆
烏色の夜が東からやって来ていた。
そんな中でも、若葉の言うとおり、屋敷の前には大勢の者達がずらりと居並んでいて、皆、口々に祝いの言葉を叫び、菊と黒王に拍手を送っていた。
「きくしゃまぁ! おめでとうごじゃいます!」
「おめとー!」
すると人だかりの中から、トテトテとした足取りで子供たちが駆けてくるではないか。手には野花を握りしめ、皆「はい!」と元気よく菊に突き出している。
ニコニコと向けられる顔は一切の曇りがなく、純粋に自分が黒王の花御寮となったことを喜んでいるのだと分かって、菊の口元もほころぶ。
「皆さん、ありがとうございます」
腰までしかない子供達に合わせて屈み、順番にひとりずつから花をもらっていく。
「とっても綺麗です。お部屋にかざりますね」
「ありがとー、きくしゃま!」
次々にもらっていき、ひとりの少年が一歩前へ進み出た。少年の肩にはこれまた小さな烏が乗っていたのだが、なんとくちばしにくわえた野花を、少年と一緒についと菊へと差し出したのだ。
これには菊も驚き「え!?」と上体を僅かに揺らし、目をぱちぱちと瞬かせる。
慌てた少年が丸い頭を下げる。
「ご、ごめんなさい、菊さま! この子、ぼくの弟なんだけど、まだ小さいから転化できなくて……」
そういえば、以前に黒王が、鴉の妖は〝転化〟して人の姿になっていると言っていた覚えがある。郷に来ても人の姿をした者達が多くあまり意識したことなかったが、少年の肩に乗っている烏を眺め、菊はこういうことかと納得する。
「ごめんなさい……菊さまを怖がらせちゃって……」
少年は申し訳なさそうに顔を俯け、胸元で指をいじっていた。心なしか、少年の肩に乗った小烏もしょんぼりと項垂れているように見える。
こんなに烏とは感情豊かなものなのか。
村にいる時は、特別気にして見てはいなかったが、黒い羽根に覆われた真っ黒な瞳からは、『しょぼん』といった感情がありありと伝わってくる。
――なんて愛らしいのかしら……っ!
菊は、小烏の前に掌を上向けて差し出した。
「可愛い烏さん。そのお花を私にくださいますか」
たちまち少年も小鴉も目をキラキラと輝かせ、嬉しそうに口をパクパクさせる。
「大丈夫、怖いだなんて思ってませんから。愛らしいことをしてくれる烏さんに驚いただけですよ」
小烏から花を受け取ると、彼は小さな羽をパタパタと扇いでいた。なんだか言っていることが分かる気がして、菊も「私もです」と肩をすくめれば、小烏と一緒に兄の少年もキャッキャと嬉しそうに跳ねたのだった。
そこで、菊はふと村での出来事を思い出す。
――そういえば、村にいる時一度だけ、烏と会話したような気がするのよね。
泣いている菊を慰めるように、涙が乾くまでじっとこちらを見つめていた。
深い紫色の目をした烏だったと思う。
――まるで黒王様みたいな……。
振り返った先で、里長達と話していた国王と目があい、ふっと首を傾げられる。背中に流れていた彼の紫の毛先が、わきからちらっと見えた。
――あの烏の羽根も、毛先だけ紫がかっていたような……。
そんなことを思っていると、視界の端からジリジリと近寄ってくる影に気付く。
「灰墨……さん?」
名前を呼べば、灰墨はビクッと大仰に身体を跳ねさせて足を止めた。
何か用事でもあるのかと菊のほうから近寄れば、灰墨の額にじわりと汗が滲む。視線は明後日の方へと飛ばされ、上体は後ろへと反っている。
――やっぱり……そうよね。婚儀を上げたからって、急に受け入れられるものじゃないわよね。
「あ、あの、やはりまだまだ不十分でしょうが、たくさん学んで黒王様の妻の名に恥じないようになりますので……どうか、それまでもう少し待っていただけると――」
「ち、違う!」
「え?」
違うとは何がだろうか。
「ああ、いや……黒王様の妻の名に恥じないようにしてほしいのは、違わないけど……あーその……」
菊が首を傾げて見つめれば、灰墨は額を抑えたり、口元を隠したり、後頭部を掻いたりと動きが忙しない。
そして、「あー」と呻くような声をしばらく出した後、菊に真剣な顔を向け、真面目な声をだした。
「僕は、まだ人間のことが嫌いだ。人間がした黒王様への仕打ちを未だに許せない」
「はい」
それはそうだろう。
黒王の話を聞いて、菊ですら胸を痛めたくらいだ。傍にいた者達はどれだけ辛い思いをしたことだろうか。
「でも、あんたは、その……少しは信じてもいいのかな、って……」
段々と声は小さくなっていき、最後はごにょごにょしてほとんど聞こえなかった。が、彼の気持ちは伝わった。
「私を……信じてくださるんですか?」
「黒王様のために、僕より先に動いたあんたは、きっと他の人間よりかはマシだと思うから」
きっと本当は、すごくすごく人間が憎いはずだ。それでも彼は、自分を信じると言ってくれた。喜びよりも嬉しさがこみ上げる。
「……っありがとうございます」
「あっ! でも、これからは自重してよね! あんたは羽根もなけりゃ、術を使えるわけでもないんだからさ――――どわっ!?」
突然、菊に照れ隠し半分の説教をしていた灰墨の首に、見覚えのある袖が巻き付いた。
「あんた何様よ、灰墨。菊様、こんなアホズミのことなんて気にしなくて良いですからね。たんに黒王様をとられて拗ねていただけですから」
若葉は横から灰墨の首を抱き込んでおり、灰墨は腰を折って地面を覗き込む体勢を強いられる。
「は、離せよ!? バカバ! 近いんだよっ!!」
「お口が悪いわあ? 聞こえなぁい」
「ああ、そういえば、黒王様も合わせた三人は幼馴染みでしたよね。そういう関係って羨ましいです」
「いや、この状況で羨ましいとか意味分かんないから!?」
辺り一帯に笑いがこだました。
そして菊は、若葉に袂で目元を拭われて初めて、自分の目に涙が浮いていたのだと知った。
◆
郷の子供達と戯れている菊の姿を、黒王は後ろの方から愛おしそうな眼差しで眺めていた。
「いやぁ、本当に良き花御寮様を迎えましたなあ!」
里長のひとりである南嶺が隣にやって来て、太い腕を組みながら満足げに頷いている。
「にしても、まさか別の娘を送ってきていたとは」
当初、界背村より奉納された、花御寮の名前が書いてある紙には『古柴レイカ』と記してあった。しかし、実際に花御寮としてやって来たのは『菊』である。
「まあ、私共にとっては界背村の娘であれば誰でも構いませんからな。それに、結果的にとても素敵な花御寮様でしたし、むしろ別の娘にしてくれて感謝しかありませんわ!」
ガハハと豪快に笑う南嶺に、黒王もそうだなと同意を示す。
ただし、心の中では密かに違うことを思う。
――俺にとっちゃ、〝誰でも構わない〟ことはないんだがな。
「本当、菊が花御寮でいてくれて良かったよ」
――俺は、彼女が良かったんだ。彼女じゃないと駄目なんだ。
花御寮にするのなら、最初から彼女がいいと思っていた。
界背村で黒王がやったことについては、一部だが、婚儀の前に重役達に伝えてある――古柴家は神事を軽んじ、身ごもっていた姉のふりをさせて妹を差し出した。故に罰を与えた、と。
話を聞いた重役達は、身ごもった娘を送ってこられるくらいなら、身代わりのほうがありがたいと、口を揃えて言っていた。
ただし菊が、村の血が半分しか入っていない〝忌み子〟と呼ばれる存在だということは伏せた。
彼らが知れば反対されるだろうし、反対されたところで、黒王は菊以外を迎える気などさらさらないのだから。同族間で下手に争うより、多少宿る妖力が低くとも、胸にしまって穏便に済ませたほうが良いに決まっている。
そうして、本当のことを知るのは黒王と灰墨のみ。
それは、古柴家を片付け、郷へと戻ってきた時のこと。
『何か言いたそうだな、灰墨』
母屋を歩く中、郷に帰ってからずっとむくれた顔をして後ろをついてきている灰墨に、黒王は私室を目の前にしてようやく尋ねた。
まあ、灰墨が何を思っているのかは考えがつく。
『……忌み子ってあの家族は言ってました』
『ああ、そうだな』
黒王はそれを菊の口から直接聞いていたし、特に驚きはなかったがやはり彼は気になるのだろう。
『お前を連れて行かなければ良かったな』
『僕はあなたの近侍ですよ! 常にお傍にいるのが役目です! そんなこと言わないでください!』
『だったら、受け入れろ。俺の決めたことだ』
『でも……それじゃあ次代の黒王様のお力が……』
『元々お前は、この因習をやめたがっていたじゃないか。同じ郷の娘を嫁にとるのと、妖力が半分しかない娘を嫁にとるのとでは、大差ないだろう』
異なった力を掛け合わせるから強い者が生まれるのであって、同族であれば大した意味はない。水に水を混ぜるのと同じことだ。
『それに』と、黒王は足元を見つめている灰墨に、腰を折ってずいっと顔を近づける。
『だったらお前は、あの女の方に来てほしかったとでも言うのか』
『あんなの絶っ対! 嫌です!』
ぶんぶんと横に首を振って間髪容れず拒絶した灰墨に、苦笑が漏れる。
『だったら分かっているな? 彼女のような花御寮は稀有なんだ。あんな……春のように温かな者は』
さて、ここまで言ったがそれでも反論してくるかな、と黒王が灰墨の反応を窺っていれば、予想外にも、彼はケロッとして頷いた。
『確かに、それもそうですね』
『……急に物わかりがいいな』
灰墨は、やれやれと言わんばかりに、両手を上向け肩をすくめた。
『だって、あなたのそんな顔を見たら、もう何も言えませんよ』
そうして、菊が忌み子である件については、黒王と灰墨の胸にだけしまわれることになったのだが。
「何をしているんだ? あいつは」
そわそわと、灰墨が遠くもなく近くもない微妙な距離から、菊を窺っているではないか。
「今まで花御寮に反対だと言っていたし、彼女につらい態度をとったこともあったからなあ……どうやって接すれば良いのか、分からないんだろう」
「なあ? 玄泰」と、黒王は人の輪から一歩後ずさり、後ろでひとり佇んでいた玄泰に並ぶ。
白髪白髭の老爺は細かい皺がたくさん入った顔で、菊を見るともなく見ていた。
微動だにしない彼の表情からは、感情が読み取れない。
「郷の外をうろついていた妖だが……確かに対応は済んだんだったな?」
賑やかな場の中、二人の間にだけ沈黙がまとわりつく。
二人は祝い事だと騒いでいる者達の方を向いたまま、互いの視線も交わさない。
「……なぜ婚儀の前にわたくしを処分されなかったのです」
ややあって、掠れた溜息と共に玄泰が口を開いた。
「もう全て分かっていらっしゃるのでしょう。わたくしが鬼を手引きしていたことを」
やはりその声も、年季が入ったもので掠れている。
「それなのに……彼女をまた傷つけるかもしれないのに、どうして皆に黙ったまま何も咎められないのです」
昨日、菊が郷外に出たこともそこで鬼の妖に襲われたことも、重役達は知らない。知るのは、菊の潔斎に付き従っていた者と現場にいた者だけだ。
「俺は、玄泰に菊を見てほしかった。人間ではなく俺が選んだ菊を。お前が取り仕切る婚儀で」
「なぜ……」
「確かに、人間の血に頼らねば維持できない血筋など、脆弱だと思う気持ちも分かる。人間に頼らずに生きていく方法があれば、そうしたほうが良いことも」
ただでさえ皺だらけの玄泰の目元に、さらに深い皺が刻まれる。
「人間は醜い。何も持たない者達に力を授けた過去の恩を忘れ、まるで初めから自分たちは特別だったと言わんばかりの振る舞い。なのに、花御寮に選ばれると、自分たちは被害者だとばかりに騒ぐのがわたくしは気に食わなかったのですよ」
自分よりはるかに年上で、自分よりも長くこの郷を、代々の黒王と共に見てきた重鎮。
きっと自分が見てきたことや、書物で読んだものよりも、ずっと色々なものを目の当たりにしてきたのだろう。
「先代様も先々代様も、花御寮様がどうやったら少しでも穏やかに過ごせるのかと、心を砕いておりました。しかし……」
切った先の言葉は、聞かずとも分かっていた。
自分の母親は最悪の結末を迎えた。
それは彼女にとってだけでなく、父や子である自分、そして鴉一族にとっても最悪な結末だったのだろう。
あれから父は随分と憔悴し一気に老け込んで、今はもう帰らぬ人となった。
「わたくしはこれ以上、我らが主が苦しむ姿など見たくなかったのですよ。もう……たくさん我らも苦しんできた。人間も我らも苦しむのであれば、力など捨ててしまえば良い」
確かにそれもひとつだろう。
だが今回、鴉一族の立場を再確認させられた。
鴉は、あんな雑魚の鬼にも侮られている。
もし、郷の守り主である黒王の力が徐々に失われていけば、きっと他の妖も乗り込んでくるだろう。鴉の耳目の多さと情報の早さは、どの妖も喉から手が出るほどほしいはずだ。
「では聞くが、お前から見て菊という人間はどうだった」
「…………」
彼お得意の皮肉すら出てこないということは、そういうことだろう。ただ、それでも無言というところが彼らしいというか、なんというか。
「三代にわたって、お前はよく仕えてくれた。まあ、俺にとっちゃ、何考えてるか分からない恐ろしい爺さんだったという印象が強いがな」
「あなたは、よく先代様の言いつけを破りなさったから」
「そうだったか?」
静かに喉だけで苦笑すると、隣からもふっと鼻で笑う気配があった。
「玄泰、そろそろ次の世代にその席を譲ったらどうだ」
暗に、今回の咎めを伝える。
「……そうですね。そろそろ、里でゆっくりするのもいいかもしれませんな」
玄泰は、珍しく黒王の言葉に反論を唱えなかった。
「安心しろ。一族は俺が守っていく……彼女と共に」
そこで初めて、玄泰は菊をしっかりと視界の中心に捉える。
郷の者達に囲まれている彼女は、時折焦りながら、また恥ずかしがりながら、それでも皆の顔を見て一生懸命何やら話していた。
「……善き春になりそうですな」
玄泰が空を仰ぐ。つられて黒王も空を見上げた。
風に流れていく薄紅の花弁が、郷の景色を華やかに色づける。
深い鴉色の夜に際立つ繊細な薄紅は、まるで真っ黒な鴉が棲まう郷にやってきた彼女のようで、自ずと黒王の口元も和らぐ。
「そうだな。長かった冬も……もう終わりだ」
横目で玄泰の様子を窺えば、横顔には憂愁といくらかの喜色が見えた気がした。
◆
「大丈夫か、菊。随分と皆にもみくちゃにされていたが」
「皆さんとても楽しくて親切で、私もちょっとはしゃぎすぎてしまいました」
結い上げていた髪は乱れたからと若葉がほどいてくれ、今はいつも通り下ろしている。
婚儀の衣装のまま、菊と黒王はいつもの場所――東棟の広間で並んで、欄干の向こうに見える庭を眺めていた。
満月の煌々とした灯りに、薄紅の桜がぼんやりと青白く浮かび上がって、幽玄な景色をつくりだす。
「あの、黒王様。本当に皆さんは私で良かったんでしょうか」
「ああ、大丈夫だ。入れ替わりについては皆了解してくれた。むしろ、そんな女が来るより、菊が来てくれて良かったと喜んでいたよ」
「それは嬉しい限りです。それにしても、古柴家がまさかそんなことになるだなんて……」
「菊が心配することじゃないさ。きっと村の外で何事もなく生きていくだろうし」
「それも……そうですね。レイカ姉様はずっと街に出たがっていましたし、意外と喜んでいるかもしれませんね」
「菊は優しいな」
昨夜、黒王は界背村の村長と話してくると出て行ったわけだが、戻ってきて彼が教えてくれたのは、『村は古柴家の掟破りについて、古柴家全員を村外追放に処した』ということだった。具体的に何をどこまで話し合ったのかは聞いていないが、村のことにはもう興味がなかった。
「これで、もしあの鳥居を通って現世へ行くことがあっても、会わずにすむな」
「そう思うと、ちょっとホッとします」
「良かった」
黒王に肩を抱き寄せられる。
「そういえば、菊」
「はい」
「菊は、俺に嘘は吐かないと約束したよな?」
あっ、と菊は肩を跳ねさせ、じわりと窺うように下から黒王の顔を見つめる。
「あれはその……ど、どうせ捨てられる身だからと思っていて……お許しください」
膝に置いていた手が、着物をぎゅうと掴んでいた。
菊の反応に、黒王は目を弧にして意地悪な顔で菊を見下ろす。
「いいや、許さない」
「ええ!? それは……ど、どうしましょう」
「嘘を吐いたら俺の好きなようにして良いんだったな」
黒王は菊の肩を両手で掴むと、自分のほうへと菊を向かせた。
「え、あの!?」
戸惑う菊に対し、正面の黒王の表情は、先ほどまでの茶目っ気たっぷりのものではなく、とても真剣なもので、それが「あの!?」とさらに菊を戸惑わせていた。
黒王が真剣さにおされ、菊も口を閉じる。
二人の間の空気が薄くなった、次の瞬間。
「菊……俺の妻になってくれないか……」
予想していなかった言葉に、菊は思わず「え」と間抜けな声を出してしまう。
確か昼間に婚儀は済ませたはずだが。もしかして全て夢だったのだろうかなどと、頓珍漢なことすら考えてしまう。
「夢でなければ婚儀はすでに……」
「それは黒王と花御寮としてのだろう? 掟とか因習とか関係なく、俺は菊と結婚したいんだ」
真っ直ぐな紫色の瞳に射抜かれ、胸の内側がざわめきたった。
「私と、ですか……」
まつげを震わせ、目を大きく見開いている菊の頬を、黒王の手が撫でる。
「ああ。たとえ花御寮でなくても、俺は菊と結婚したかった」
「そんな……いつから……」
「初めて会った時から、かな。きっと、俺は最初からお前に恋をしていたんだ」
――恋……。
触れられた頬から伝わる彼の熱が、首から胸へ、胸から背中を通って全身へと広がっていく。熱を持った身体はジンジンと痺れるようで、耳の奥で聞こえる鼓動は早鐘を打っていた。
「……初めてというと、迎えの儀の夜ですか」
黒王はただ曖昧に苦笑だけしていた。どこか気恥ずかしそうに。
それでも菊から視線は外れない。
ただただ真っ直ぐに、菊だけを紫に映していた。深い紫の宝玉の中に。
「……怪我をした烏……」
思うより先に、脳裏によぎった光景を口に出していた。
「やはり、彼女は間違いなく菊だったんだな」
「――っ本当に?」
今思えば、烏の妖なのだから烏姿になれるのは当然だ。事実、灰墨の烏姿も見たし、かつて黒王より転化というものも教えてもらっていた。
それでも、今の今まであの烏が彼に結びつかなかったのは、まさか人間である黒王が烏姿になれるとは思わなかったからで。
「それじゃあ、最初って……」
黒王の目が細まれば、それが肯定だと分かるくらいには日々を共にしてきた。
「なあ、菊。返事を聞かせてくれないか?」
尋ねる声はとても穏やかだ。
どうしてだろう、胸に酢を掛けられたように締め付けられ痛む。けれど、それは決して嫌な痛さではない。
「ああ……菊、泣かないでくれ。驚かせてすまない」
黒王が困ったように笑うが、菊は首をぶんぶんと横に振った。
余計に目が溶けそうなくらいに熱くなり、瞳の表面に水膜が張った端から、鱗のようにぽろぽろと剥がれ落ちていく。
剥がれ落ちた透明な鱗は、黒王の手をさらに濡らす。
「私……っわたし、こんなに……っ幸せで……良い、んですか……」
今日一日だけで一生分どころか、来世までの幸せも使い切ってはいないだろうか。
それほどに、今日は信じられないほど嬉しいがあふれすぎている。
いない者とされた自分の名前を、郷の者達がたくさん呼んでくれた。何度も何度も親しみが感じられる声音で「菊様」と、笑顔と共に呼んでくれたのだ。
自分の意思なんかないものとされ、言いなりになることを求められてきたのに、彼は丁寧にひとつひとつ自分の意思を確認してくれた。
涙を拭ってくれる者などおらず、ひとりで全ての感情を飲み下さないといけなかったのが、今は涙を拭ってくれる手があり、心に寄り添ってくれる。
そして掟などではなく、自分の意思で妻に迎えたいと彼が言ってくれている。
それらはどれも、菊が予想し得なかった最高の未来。
「……っこんなに幸せで……私、怖いです……っ」
悔しいことに次々にあふれる涙のせいで、視界が揺れて彼の表情は見えないが、正面で彼が笑った気配は伝わってきた。
「気付いているか、菊? それは俺にとって最高の返事だって」
両手で頬を捕まえられ、そのままコツンと額を合わせられる。
「永遠に菊だけを愛すると誓うから、どうか俺と結婚してくれないか」
「……ッ……っ」
嗚咽のせいで上手く声が出せず、でもこの心の全てを伝えたいとでも言うように、菊は何度も何度も何度も黒王の言葉に頷いていた。
菊から言葉での返事はない。
しかし、時に言葉よりも伝わることはある。
いつも淑やかな彼女が子供のように声を上げて泣く姿を見て、黒王の瞳も揺れ始める。
「なあ、菊。俺の名前を呼んでくれないか」
彼が言う〝名前〟が、いつも呼んでいる名前でないことはすぐに分かった。
それは、決して他人には知られてはならぬ名前。
『二人きりの特別な時にだけ』呼んでほしいと言われ、伝えられた名前。
「俺はお前だけに名前を呼ばれたいんだ」
黒王の気持ちが手に取るように分かる。
きっと、菊は誰よりも、名前を呼ばれたいという欲望を知っている。
そして、慕っている相手から名前を呼んでもらえた時の嬉しさも。
菊は一度、瞼をぎゅっと強く閉じた。それで内側に残っていた雫の欠片もすべて流れ落ちる。
そうして瞼を開ければ、すぐそこには黒王の顔があった。
目を赤らめ、目尻は僅かに湿っている。
紫の瞳が『呼んでくれ』と言っていた。
そこに映った自分は、まるで夜半の檻に囚われているかのようだ。甘やかな欲が瞳の奥でちらちらと揺れ、見つめられるだけで烏王の心が伝わってくる。
無意識に菊は烏王の頬に手を添えていた。
「……紫月様……」
桜の花がさやめくような菊の声は、柔らかく、優しく、そして温かかった。
風がはしった。
ザァッ、と薄紅の花吹雪が夜空に舞い上がる。
月明かりの中、照らし出された黒と薄紅だけが世界のすべてだった。
「私を、紫月様の妻にしてください」
自然と、二人の唇が重なった。
触れるよりも長く、交わすよりも深く。
互いに触れる手や唇は温かく、菊の心はそれ以上に熱かった。
夜空を染めた桜吹雪。
ひらひらと舞い上がった花びらが空から落ちて、まるで祝福の送花のように二人のいる場所を色づける。
「紫月様、見てください。まるで雪みたいです」
「ああ……こんな温かな雪なら、悪くはないな」
それは、辛いことも嫌な過去もすべて忘れていまいそうなくらい幻想的な光景。
ひっそりと夜空に輝く満月だけが、二人だけの誓いを見ていた。
【了】