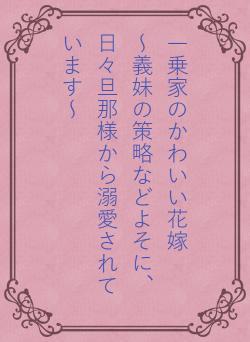1
郷の南側にある霊泉。黒王の屋敷を出て、郷に住む者達の家々を通り抜け、高い針葉樹の木々に囲まれた山裾にそれはあった。
どこか、古柴家の屋敷裏にあった雑木林を彷彿とさせる樹木の乱立具合だったが、薄気味悪さはない。
ここまでは若葉と女官達に案内されてきたが、彼女達が立ち入れるのはこの森の手前までだそうだ。森の中を真っ直ぐ進むと泉があるから。そこで沐浴をして戻ってくるのだそうだ。
着替えの着物を手に持ち、ひたすら木々の合間をぬって歩く。
横から射し込む白い朝日が、大気に何本もの光の帯を描いていく。
影を踏んで、陽だまりを踏む。そしてまた影を踏む。だんだら模様の世界を、菊はひとり歩いた。
そうして、木々の道が終わった先――開けた空間に出る。
真ん中には沐浴の泉であろう霊泉があり、水面にはぷくぷくと水泡が湧いていた。水源地のようで、泉からは川が伸びている。辺りを取り巻く空気には清浄さがあり、ここだけ別世界のようだった。
霊泉を取り囲むように大小様々な岩があり、中には、大の男が五人で手を回してやっとというくらい大きなものもある。その中のひとつ、背が低く平らな岩の上に着替えを置き、菊は襦袢の懐から半分に折られた紙を取り出し、着替え間に挟んだ。
「これで、若葉さん達にも責任は及ばないはず」
菊は森の向こう側で待つ若葉達の方へ一度視線を向けると、しかし、振り切るように踵を返した。
どうやら霊泉は郷の外れにあるようで、近くに家などなく山や草木に囲まれている。
「このままもっと奥に進んだら郷を出られるはず……」
そうして、菊は来た道とは別の方へと歩き出した。
◆
どれくらい歩いただろうか。
「はぁ、はぁ……っ、もう……郷は出てるわよね」
郷から離れるように山へ山へと進んだせいで、息は絶え絶えに、足は膝が震えるほどに疲労していた。
「きっと、他にも現世へと繋がる場所があるはずだわ」
結界で守られた郷の中にある鳥居だけのはずがない。でなければ、現世に魑魅魍魎などわいてこないのだから。
「とにかく歩き続けなきゃ」
坂を上りきり、ようやく少しは平坦な場所へと出た。
振り返ると、小さくなった鴉の郷が木々の合間から見えている。そこでようやく菊は、ほっと胸をなで下ろす。
「あとは探すだけね」
よし、と振り返った先――。
「え、外に出てきてんじゃん」
「やりぃ! 手間が省けたわ」
着物を着崩した、派手な身なりの若い男達がいた。
「……え」
しかも、彼らの頭には、つののようなものが二本ずつ生えていて、鴉の郷の者でないことは一目瞭然だ。
すぐに、黒王や若葉達が言っていたことを思い出す。それは、郷の周囲をうろうろしている妖がいるという話だったが。
――でも、郷の周りの妖はもういなくなったって……。
戸惑いに、菊はよろよろと後ずさるが、それは伸びてきた男の手によって阻まれてしまった。
「きゃっ!」
「はいはい、逃げない逃げない」
「この人間、すっげぇ良い匂いするな! 早く持って帰ろうぜ!」
――どこに。
ゾッ、と感じたことのない恐怖が、足元から這い上がってくる。
「いやっ、離して――っ痛!?」
逃げようともがけば、掴まれた手首が軋みをあげた。
「暴れんなよ、メンドクセー」
男の鋭利な爪が食い込むほどにギリギリと手首を締め上げられ、菊の顔も苦痛に歪む。あまりの痛みと恐怖で「寝てろよ」という声を最後に、菊の意識は閉じたのだった。
◆
潔斎を終え、北の霊泉から戻ってきた黒王が最初に聞いたのは、耳を疑うような言葉だった。
「レイカがいなくなった、だと……」
「申し訳ありませんっ! 霊泉の森には儀式の決まりで花御寮様しか入れず、わたくし共は森の入り口で戻ってくるのを待っていたのですが、いくら待っても戻られず」
里長との会合などが行われる母屋の一室で、今、若葉と女官達が揃って頭を畳にこすりつけていた。
「ほら、黒王様! やっぱり人間なんか信用するものじゃないんですよ!」
「黙れ、灰墨!」
黒王は座るのも忘れ、立ったまま呆然と床に伏す若葉達を見つめる。
脳裏には、最悪の結末が思い浮かんでいた。
レイカと同じ花御寮として連れてこられた人間で、かつて自分の母親だった者の末路。
嫌な汗が背中を流れていく。
「決まりを破ってしまうとも思いましたが、何かあったのではと、わたくしひとりだけ霊泉へ向かいました」
「それでレイカは……」
「周辺をしばらく探しましたがお姿は見えず……霊泉の岩の上に、着替えの着物とこれだけが残されていまして……」
若葉が震える手で差し出したのは、半分にたたまれた一枚の手紙。
「中は見ておりません」
表には、たどたどしい文字で『こくおうさまへ』と記してあり、それを目にするなり、黒王は若葉の手から奪い取るようにして手紙を開いた。
部屋には、紙がこすれる乾いた音のみが響く。
「黒王様、手紙にはなんと!? 花御寮様は誰かに連れ去られてしまったのでしょうか!」
「……っいや」
クシャ、と手紙が黒王の手の中でよれる。
「彼女は自ら姿を消したようだ」
「なぜです!?」
「俺が知りたいわ!!」
「も、申し訳ありませんっ」
空気が震えるほどの黒王の怒号に、若葉達はもうそれ以上は下がらない頭を、それでもさらに下げた。
障子がカタカタと微動する音が、部屋に気まずい余韻を残す。
黒王は額を抑え、自らを落ち着けるように深い溜息を吐いた。
「いや……悪かった。若葉達のせいじゃない」
潔斎を終えたばかりだというのに、黒王の頭の中はとても清浄とは言いがたいほどに、様々な思念が渦巻いていた。
なぜ婚儀を前にしていなくなったのか。
本当に自分の意思なのか。
やはり、妖の妻になるのが嫌だったのか。
あの笑顔も、結んだ手の温もりも、一緒にいたいと言ってくれた言葉も、何もかもが嘘だったというのか。
「黒王……様……」
心配そうに掛けられた若葉の声で、どうにか黒王は『黒王』の役目を思い出す。
「もしかしたら、村へ戻ろうとして鳥居に近付くかもしれない。若葉達は鳥居の周囲を探してみてくれ」
黒王の指示に若葉達は短い返事を返すと、すぐさま、それこそ飛ぶような速さで姿を消した。
部屋に残ったのは黒王と灰墨のみ。
黙れと言われ口を閉ざしていた灰墨が、黙っていられなかったのかぼそりと悪態をつく。
「どうせ、腹の子の父親の元へ戻ろうとしたんでしょ。いよいよになって、騙しきれないと――」
「灰墨は空から郷の中を見て回れ。ただし、玄泰達には知らせるなよ。ここぞとばかしに面倒なことになる」
「黒王様!? どうしてそこまでしてあんな女を――っ!?」
「いいから行け!! これ以上俺に……っ現実を突きつけるな……」
灰墨はまだ何かを言おうとしていたが、黒王が背を向ければ、渋々とだが部屋を出て行った。バサバサッと翼を羽ばたく音が、次第に遠ざかっていく。
「……っ今、お前はどこにいるんだ……」
黒王は手紙を胸に押し当てるようにして、その場で膝を折った。
それから間もなくして灰墨が戻ってきた。
人に転化した姿で現れた灰墨は息を荒くし、額には汗が滲んでいる。なんだかんだ言いながら、命令には忠実に従ってくれたようだ。
「郷の中に花御寮様の形跡はありませんでした」
「そんな……」
ただでさえ重かった身体が、さらに重くなる。
しかし、灰墨の報告はそれだけではなかったらしい。
「……でしたが」
言葉を繋ぎながら灰墨が懐から取り出したものを見て、黒王は飛びついた。
真っ白な台に淡い桜色の鼻緒が愛らしい草履が片方、灰墨の手に乗っていた。
「灰墨、これをどこで……!」
黒王の草履を握る手は震え、目は瞳がこぼれ落ちそうなほどに見開いている。その瞳には微かな希望がわきつつある。
しかし、それも一瞬。
「郷の外です」
「は」
「南の霊泉の裏にある山を上った先で見つけました」
黒王の瞳に宿りかけていた光は霧散した。
『郷の外を妖がうろついている』――どうしてか、そんなことが唐突に思い出される。それについては玄泰が既に対処したはずなのに。
「レイカ――ッ!」
「ちょ!? あっ、黒王様!」
黒王は灰墨の制止を振り切り、空へと羽ばたいた。
2
妖全てが、鴉一族のように人間を受け入れているわけではない。それこそ界背村の者達が言っていたように、人間を食べる妖というのも存在する。
目を覚ました菊は、自分が拘束されていることに気付いた。目を開けて、視界に映る自分の両手には、しっかりと茶色の縄が巻き付いている。幸いにも足は拘束されておらず、手も身体の前面で結ばれていたため、菊は苦労しつつも、なんとか身を起こすことができた。
「ここは……」
辺りを窺った限りでは、おそらく浅い洞穴の中だろうことが分かった。
左右と背後はゴツゴツとした岩壁に囲まれ、正面だけぽっかりと大きな口が開いている。
口から見える景色は、菊が山登り中によく見た景色と同じで、この洞穴が山中のどこかにある場所だと推測できた。
「逃げなきゃ」
菊は、意識が途切れる直前の記憶を思い出す。そこに映っていた男達は間違いなく鬼の妖で、とても友好的な目的で攫われたのではないだろう。
ぶるっと身体が震えた。しんとした冷たさが足元から這い上がってくる。
足元を見てみれば、片方の足は草履を履いていなかった。連れてこられる時に落としたのだろう。
菊は息を殺して、洞穴の入り口の方へと神経を集中させる。しかし、誰かがいるような気配はなく、風に葉が揺れる音しか聞こえてこない。
「今のうちに……!」
意を決して、菊が洞穴から頭を出した時だった。
「ほら、言ったとおりだろ。目を覚ましたら絶対逃げ出すって。賭けはオレの勝ちね」
「うはー……人間がここまで馬鹿なんて思わなかったんだよ、チクショウ」
頭上から声が降ってきて、次に声だけでなく、目の前に男達までもが降ってきたのは。二人とも頭につのはあるが、最初に会った自分を捕まえた男とはまた別の者だった。いったい何人いるのか、また身体が恐怖に震える。
しかし突然、震えを打ち消すほどの痛みが菊の頭皮に走った。
「きゃっ!? 痛い――ッ!」
男のひとりが菊の長い髪を、無造作に鷲づかんだ。
手加減という言葉を知らないのか、男は髪を掴んだまま、洞穴から菊を引きずり出そうとする。
「ほら、ちょうど良いから遊ぼうぜ」
「いや!? やめて!!」
菊の拒絶の言葉など聞こえないようで、髪を引っ張る男は鼻歌交じりだ。
両手を縛られた不安定な体勢で、強引に引っ張られたことにより、菊は前のめりに倒れてしまった。幸か不幸か、髪を男が掴んでいたおかげで顔を打つことはなかったが、ぐいっと無理矢理に頭を持ち上げられ首が痛む。
すると、男はクンと鼻を動かし片眉を歪めると、菊の首元へと顔を近づけた。鼻先が首筋に触れ、ぞわりと不快感が全身を這いずり回る。
「ひっ……!」
同じ妖でも、黒王に近寄られた時はこんな不快感など感じなかったのに。今は、髪の毛すら逆立ちそうなほど全身が粟立っていた。
できるだけ男から離れたくて首を反らせるものの、髪の毛をがっしりと握られ叶わない。
「なあ、思ったんだけどさ……この人間の女、すっごい美味そうな匂いしねぇ」
――美味しそう……?
それはやはり、食糧として見られているということだろうか。
「あ、やっぱり? 俺も思ったわ」
「あー、お前ら何勝手に手ぇ出してんの」
「抜け駆けはずるいぞ」
そこへ、菊を攫った者達も戻ってくる。顔を巡らせることはできないが、周囲に人が集まってくる気配があった。
――ああ……私はここで死ぬのね。
虚ろな菊の瞳から、雪解けのような冷たい雫が頬を伝う。
せめて最後に見るのは彼が良いと、菊は閉じた瞼の裏に彼を思い描いた。
背中で藤の花が咲いたような髪を揺らながらやって来る彼は、いつも優しい声音で語りかけ、大きな手で握ってくれ、紫の瞳で心に安心を宿してくれた。
どうせ食べられるのなら彼が良かったな、と思った次の瞬間。
「ぎゃああああッ!」
突如目の前から聞こえた耳障りなダミ声に、菊は閉じた瞼をすぐに開き、目の前の光景に瞠目した。
菊の髪を掴んでいた男の、反対の腕が燃えているではないか。
「ああぁっ! なんで突然!?」
男は火を消そうと懸命に腕を振り回し、困惑に声を上げながら地面を転がりまわる。その様子を、他の男達も状況を掴めずに、戸惑った様子で眺めているばかり。
一瞬にして場は騒然となり、皆の意識が菊から遠ざかる中、菊は先ほど記憶の中で聞いた声と同じ声を、耳元で聞いた。
「もう大丈夫だ」
え、という間もなく菊の身体はふわりと宙に浮き、どんどんと地面から遠ざかっていく。しかし、怖いという気持ちは微塵もわかない。それは、自分の身体を支えてくれる手の頼もしさに覚えがあったから。
いつかの日のごとく、膝裏と背中に添えられた手は力強く、菊は彼を見上げた。
「こ……黒王様……どうして……」
「――っ良かった」
抱いた菊の肩口に顔をうずめ、黒王は衣擦れの音がするくらいきつく、菊を抱きしめた。
声には安堵が滲み、彼の首筋はうっすらと汗ばんでいる。
「やっと見つけたよ、俺の花御寮」
肩口から上げられた彼の顔は、柔和な笑みが載っていた。
勝手に逃げ出したのに、どうして怒りもせずそんな優しい顔を向けてくれるのか。
言いたいことが分かったのだろう。黒王は「今は何も言わなくていいから」と囁いて、菊を地面に下ろした。そこは先ほどまで菊が入っていた洞穴の上で、地面からの高さは、男の背丈の三倍はある。
どうやってここまで上って来れたのか。
それは、彼の背後に見えている、折りたたまれた真っ黒な翼が全てを物語っていた。
しっとりとした黒色は木漏れ日を受け、紫にも銀色にも輝き、濡れ羽色という言葉の意味を知る。
「もうっ! 置いていかないでくださいよ、黒王様」
そこへ、一羽の烏が飛んできたと思ったら、着地すると同時に青年の姿となった。灰がかった髪色の、ちょっと生意気そうな顔をした青年――灰墨だ。
話には聞いていたが、初めて転化というものを間近に見て、菊が目をまたたかせた。
「ちょうど良い。灰墨はレイカを守っていてくれ」
「は、はぁ!? この女をですか!? こんな裏切り者の女をですかぁ!?」
裏切り者という言葉が胸に刺さる。
しかし、それが事実で何も言い返せない。
「黙れ、灰墨。命令だ頼んだぞ」
有無を言わせぬ黒王の言葉に、灰墨はぐぬぬぬと奥歯を噛んでいたが、結局は大人しく言うことを聞いて菊の隣へとさがった。それでも間に一人分の空間があるのは、彼なりの抵抗だろう。
「随分と命知らずの妖もいたものだ。以前から郷の回りをうろついていたのは、お前達だな?」
黒王は岩山の縁に立ち、眼下を見下ろした。
そこには、困惑した表情で見上げてくる男達が大勢居並んでおり、ようやく腕の火を消した男がよろりと立ち上がる。
「うるせーよ! たかが鴉が偉そうに言ってんじゃねえって!」
「目的はなんだ。誰の指図で郷の周りをうろついていた」
「言うわけねーだろ、馬鹿か!?」
聞こえてくる声は実に対照的だ。
「はぁ……力の差も分からないとは、随分と低級の妖のようだ。仕方ない。では力づくで聞き出すとしようか」
「誰が低級だあ! たかが鴉の分際で鬼に楯突こうなんて、そっちこそ、女の前で恥じさらす前に謝れば半殺しで許してやるよ!」
「気遣ってもらって悪いな。だが、男とは好きな女の前では格好をつけるものだろう?」
言い終わると同時に、黒王は岩下の男達が群れる中へと飛び込んでいった。
「あっ、黒王様!?」
心配に菊が声を上げるが、横の灰墨はどこか余裕な口調で「大丈夫だって」と菊を止めたのだった。
何が大丈夫なのか。すぐに菊は理解した。
怖々と岩の縁から下を覗き込むと、そこには地面を埋め尽くすように、多くの鬼の男達が横たわっていた。あちらこちらから、苦しそうなうめき声が上がっている。
その真ん中で、黒王だけが悠然と立っていたのだ。
「うそ……これだけの人数を、ひとりであっという間に……」
呆気にとられていれば、隣にやって来た灰墨が、ふんっと鼻を鳴らす。
「当然だよ。元々烏ってのは、神の眷属である神使なんだ。そこら辺の動物の妖と一緒にされちゃ困るってもんさ」
「でも、どうやって……」
地面でうごめいている男達は皆、火傷を負っていた。しかし不思議なことに、髪や着物は一切燃えていない。
「火だよ」
「火? 烏と火ってあまり結びつきませんが」
これだから人間は、と灰墨は肩をすくめて、ヤレヤレと首を横に振った。
「いい? 烏ってのはさっき言ったように神の眷属なのっ。僕たちは日輪を背負う存在で、金烏なんて呼ばれたりもして、天照様の力である火とは切っても切れない関係なんだよ」
出てきた偉大な神の名に、思わず菊は「すごい」と漏らすように呟いていた。
菊の感嘆に気を良くしたのか、灰墨の胸の張りが良くなったように見える。
「まあ、その中でも黒王様は別格だけどね」
まるで自分のことのように誇らしげに話す灰墨を横目に、菊は再び黒王へと目を向けた。
「あっ!」
そこで、菊は気付いた。
黒王の後ろから、密かに忍び寄る男の存在に。
「危ない、黒王様!」
「え、ちょ!? あんた!」
叫ぶよりも先に、気付いた時には身体が動いていた。菊は岩山の上から、黒王に近付く男めがけて飛び降りた。
声に気付いた黒王が振り返り、目に映った光景に驚愕の表情を浮かべる。
菊はギュッと目を閉じ、男にぶつかる衝撃に備えた。
「レイカッ!」
しかし、衝撃より先に黒王の切羽詰まった声と、「がぁっ!」という悲鳴じみた叫び声が聞こえただけで、覚悟していた痛みはいつまでも襲ってこず。
「え……」
その代わり、菊の身体を襲ったのは、真綿でくるまれたような温かな抱擁だった。
目を開ければ、肩で息をして眉根をひそめた黒王の顔が、菊を覗き込んでいた。どうやら、黒王が抱き留めてくれたらしい。
「まったく……無茶をしてくれる。俺の花御寮殿は」
「ひゃあっ!?」
地面に下ろされると、そのまま黒王の腕の中に閉じ込められてしまった。
チラと黒王の腕の向こう側を窺えば、彼に襲いかかろうとしていた男がのびている。
「すみません、かえってご迷惑を……」
「そんなことより、お前が無事で良かった」
柔らかに髪を梳く手に、また菊の胸は甘やかに締め付けられる。
しかし、そんな雰囲気も一瞬。
さて、と辺りを見回した黒王に甘い雰囲気は微塵もない。
「鴉一族の縄張りを荒らそうとしただけでなく、俺の花御寮にまで手をだすとはな。どうしてくれようか」
「ひぃっ!?」
黒王の眼光の鋭さに、足腰立たない男達は、地面を這うように後ずさっていく。
「はいはーい、ちょっと待ってねぇ」
そこへ、場にそぐわぬ軽い声が飛んできた。
黒王の影から窺えば、やはり頭につのを二本はやした、派手な柄の着流しを着た鬼の男だ。
「やあやあやあ、こりゃ随分と派手にやってくれたなあ。あんたひとりで?」
鬼の男は雪のように白い短髪を掻き上げながら、黒王に挑発的な笑みを向けた。目元にいれられた朱色の線が、細めた目と一緒に歪む。
「だとしたらどうする」
「鴉の王って本当に強かったんだ? 適当にふいてるだけかと思ったけど……へえ?」
「お前も試してみるか?」
「ははっ、遠慮しとくよ。ていうか、この場はどうか穏便におさめてくれって言いに来たんだし。ああ、自己紹介がまだだったな。俺はハクってんだ」
へらっと笑っているが、彼の軽口や肩をすくめた軽妙な態度からは想像できないほどの圧が、ひしひしと伝わってくる。倒れている男達とは描くが違うというのは、妖に詳しくない菊でも分かった。
ハクは鷹揚とした足取りで黒王へと近付くと、スンスンと鼻を鳴らしニヤリと笑う
「あー、あんたかなり強いな。下手したらうちの大将くらいはありそうな匂いしてる」
「匂い?」
黒王が眉をひそめる。
「鬼族は嗅覚が良いもんでね、鴉と違って」
ふと、ハクの視線が黒王から、背後に隠れる菊へと向けられた。
「ああ、あんたからか! この甘ったるい美味そうな匂いは!」
「……それ、他の方にも言われましたけど、どういう意味でしょうか」
確かに普段着物には香が焚きしめてあるようだが、今は潔斎用の着物で香りなど何もないはずだ。
「自覚なしってわけ。でも、分かる妖は分かるよ。最高級の食事が落ちてるようなもんだし」
嬉しそうな声を上げたハクは、さらに菊へと顔を近づけようとする。が、それは黒王の手によって防がれる。
「それ以上、俺の花御寮に近付くな」
「へえ、花御寮……なるほど。あんたの力が強いのもこういった人間を奪ってきたおかげか」
間髪容れず、菊が反論する。
「う、奪われてないです! 私は自らの意思で、この方の隣にいるんです!」
これには、ハクはもちろんのこと、黒王までもが目をまたたかせ驚いていた。
菊は背後から黒王の着物の袖をぎゅうと握り、精一杯ハクを睨み付ける。効いているのかまるで分からないが、とりあえず彼が離れるまで睨み続けた。
ハクはスッと目を細くし、もう菊に興味を失ったかのように遠ざかっていく。
「まあ、いいさ。今日は争いに来たんじゃないし。下っ端がやんちゃしたってことで許してな」
「このまま見逃せと?」
「そんなツンケンするなよ。特別に良い情報を教えてやるから、それでおあいこな」
「勝手に決めるな」
黒王が苦々しい顔で言うも、ハクはもう彼に背を向けている。自由というかなんというか、身勝手な男という印象だ。
「鴉の中に狸が交じってるよ……古狸が」
「まさか……」
菊には意味が分からなかったが、黒王には何か思い当たる節があったらしい。菊を庇っていた手が拳を握っていた。
「ほらっ、お前ら起きろ起きろ! ざまないねぇ、さっさと起きないと置いてくからな!」
手をパンパンと叩いて、ハクは地面に伏せっていた男達を起こしていく。近くにいた何人かは結構な強さで蹴られていた。
身を起こした男達は肩を貸しあいながら、ぞろぞろと山の奥へと消えていく。
「じゃあ、そゆことで。今回の件はお互いなかったってことで」
ハクは顔の前で手を立て、茶目っ気たっぷりな流し目を残して男達と共に、あっというまに姿を消した。
「なんですか、あれ。嵐に巻き込まれたみたいな」
烏姿になった灰墨が、黒王の肩に着地する。烏の姿なのに、溜息を吐いているのだろうなと伝わってきて、菊は小さく笑ってしまった。
目の前に大きな手が差し出される。
顔を上げれば、黒王が春の陽射しを思わせる温かな笑みで、こちらを見ていた。
「共に帰ってくれるか?」
ぐっと喉が詰まる。
勝手に逃げたのに、まだ『帰る』と言ってくれるのか。
きっととても傷つけた。
それでも、彼はこうしてまだ手を差し出してくれる。
「はい……っ」
菊は、黒王の手に自分の手を重ねた。
もう、これ以上自分の気持ちを隠すのは難しかった。
「泣かないでくれ」
そう言われて菊は、自分が泣いていることに気付いたのだった。
3
黒王の屋敷に帰ってきた途端、若葉に抱きしめられた。
「心配したんですからっ!」と言って、ぐすっと鼻をすすった彼女の、抱きしめた腕の強さは一生忘れないと思う。
どうやら、黒王や若葉達が内々で動いていたことと潔斎の日だったということで、花御寮や黒王の姿が見えずとも特に騒ぎにはならなかったようだ。
ただ、潔斎の日は一日会ってはいけない、という決まりを破ることになってしまった。
「申し訳ありませんでした、黒王様」
灰墨と若葉によって母屋は人払いが済まされ、今、菊は締め切られた部屋の中で、黒王と向かい合っていた。
畳に額をくっつけた菊の身体を、黒王が助け起こす。
「謝らなくていい。ただ……」
黒王は懐から、丁寧に折りたたまれた手紙を取り出し、菊の前に置いた。
「どうしてこのような手紙だけを残して、姿を消したのかは教えてくれるな?」
手紙には、よろよろとした下手な字で短い文が綴られている。
「自分は黒王の隣にいる資格のない人間だから、このまま姿を消す。どうか新しい花御寮を迎えてくれ――と。こんな言葉で俺が納得するとでも思ったのか。俺の気持ちがその程度だとでも」
黒王の言葉は責めるものではなかった。慈愛すら感じられる響きがある。それでも、やはり彼の気持ちを裏切ったことへの罪悪感で、菊の顔は自然と俯いてしまう。
「しかもこんな一言を最後に残していくだなんて……」
手紙の一番最後。紙の下端ぎりぎりのところに、他の文字よりひとまわり小さく書かれた文字。
《すきです》
それは、こんな言葉残していっては駄目だという気持ちと、この気持ちを伝えたいという菊の心がせめぎ合った末の文字だった。
「この時の俺の気持ちを教えてやろうか? 叫びたいほどに嬉しくて、だが、息ができないくらいに苦しかったよ」
「黒王……っさま……」
顔を上げた先には、「ん?」と目を細めた黒王がいた。
ささやかれる穏やかな声音、向けられたその眼差しで菊は分かってしまった。
彼も自分と同じ気持ちなのだと。
はらり、と桜の花弁が散るように、菊の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちる。一度落ちてしまえば、後は次から次に、先を急ぐように雫がとめどなくあふれてとまらなかった。
「なぜ泣く。泣かないでくれ。俺は、お前にはずっと笑っていてほしいんだ」
「……嬉しくて……苦しくて……っ、胸が痛いんです……っ」
自分はニセモノなのに。
嘘吐きなのに。
願ってしまった。
この人とどこまでも添い遂げたいと……。
「ずっと……ずっと、私は嘘を吐いていました」
「嘘?」
指で流れ落ちる涙を拭われる。少しかさついた自分と違う熱さの指が触れるたび、離れないでと心が叫んでいた。
「元より私には花御寮になる資格なんかないんです」
ピタリと涙を拭い続けていた指が止まり、「それは」と、一度黒王が言いにくそうに言葉を切る。
「……それは、他の男との子を身ごもっているからか?」
「ど……どうしてそのようなことを……」
いったい、どこからそのような考えが出てきたのか。
あまりにも驚きすぎて、目どころか口まであんぐりと開けてしまった。そして驚いていたのは菊だけでなく、目の前の黒王も同じで、予想外の菊の反応に目を大きく見開いて眉をひそめていた。
なぜそう思うに至ったか、「実は」と黒王は話してくれた。
黒王は菊の言葉や、事前に調べて聞いていた〝古柴レイカ〟の人柄とあまりにかけ離れていることに不信感を抱き、再び〝古柴レイカ〟について村で噂を集めたのだと言った。そこで、古柴レイカは妊娠していて村で騒ぎになっている、という報告を受けたらしい。 ただでさえ丸く開いていた菊の目は、黒王の話を聞いていよいよ眦が裂けそうなほどにまで見開かれていた。
そんな馬鹿な、と思うと同時に、菊は、レイカの身代わりにされた理由を悟った。
――ああ……そういうことだったのね。
なぜあれだけ村の掟だからと、レイカや叔母が喚いても花御寮を変えることは無理だと言っていた叔父まで突然掌を返したのか、ずっと不思議だった。
すべて――レイカが身ごもったのを叔父も叔母も知っていたのだ。
おそらく相手は、レイカとよく一緒にいた一平という男だろう。
なるほど。妊娠したレイカを花御寮にはできない。しかし、誰かに変わってもらうことなど、娘の掟破り暴露するようなものでそれもできなかったのだろう。そこへ、レイカと背格好がよく似た、村でも存在を忘れられた自分がいたということか。
誰も自分が消えたとて、気づきもしないだろう。
「俺だとて信じたくはなかった。だが……レイカは未だに、女官達に身体を見られるのを拒んでいるだろう」
「もしかして、その噂を知られたのは……潔斎の数日前ですか」
黒王が瞼で返事をしたことで、菊は彼が突然訪ねてこなくなった理由に納得した。
それでも彼は、迎えに来てくれた。
帰ろうと言ってくれた。
「――っレイカ!? 突然どうしたんだ」
菊は突然立ち上がると、自分の帯に手をかけはじめた。
「私は黒王様に嘘を吐いていました」
シュルシュルと床にわだかまっていく帯を、黒王は目を白黒させて凝視する。
「何、を……」
一体何をしているのか想像もつかないといった様子で、彼は菊と足元との間で視線を往復させる。
「私が誰にも身体を見せなかったのは――」
まとっていた最後の一枚が床に落ちれば、黒王は息をのんだ。
「――この身体を、見られたくなかったからなんです」
「その身体は……」
菊の身体は至るところに痣や傷があった。
古いものから最近できたであろうものまで。決して転んだり自ら怪我をしただけではできない場所にまで傷痕があった。
それは、故意に傷つけられたものということ。
「このような汚い身体、黒王様にも……誰にも見せたくなかったんです。汚い娘だと、黒王様にふさわしくないと……っまた、蔑まれるのが怖かったんです」
黒王は自らの羽織を脱ぐと、菊の身体を覆いその上から抱きしめた。
「すまない、辛い思いをさせた」
羽織の中でどんどんと小さくなり身体を震わせる菊に、黒王は羽織の上から頬ずりをして全身で慰める。
「レイカが身体を見せない理由は分かった。だが……」
烏王は菊の身体を見て、傷の多さだけでなくもうひとつ驚いたことがあった。
「その腹はまるで……」
菊の腹は、まるで妊娠していない女のものだった。
膨らみは微かもなく、手や指の細さから想像した通りの華奢さだった。
村を出る時に既に妊娠が分かっていたのなら、多少なりともそれと分かる膨らみがあるはずだ。
「私は、古柴レイカじゃないんです」
やはりか、と黒王には口の中で呟いた。
「本来の古柴レイカは私の従姉です」
菊は、本当の母親に村において行かれたことから、育ての家での生活の全てを、今度は嘘偽りなく話した。
それを聞いて、彼女は猫を被っていたわけではなく全くの別人だったというオチに、黒王は今まで溜めていたものを全て吐き出すかのような深い溜息を吐いた。
「では、当然身ごもってもないんだな?」
「もちろんです」
「はぁ」と、黒王は菊にしな垂れるようにして頭を肩に乗せる。
菊の耳元で「良かった」と囁かれる声の細さは、彼の心の底からの安堵を表わしていた。
しかし、菊が告げなければならないのはこれだけではない。
まだひとつ残っている。
身代わりよりもずっと重い罪。
この身体にたくさんつけられた傷も、元はそれが原因なのだ。
「黒王様、私は元より花御寮になる資格を持たないのです」
「資格? さっきからずっと言っているが、それはどういうことなんだ?」
「私は、母が村外の男との間につくった子です。村の者の血を半分しかひいておらず、花御寮の候補にすらなれない忌み子なんです」
「なるほどな」
烏王は全て理解した。
妖に怖がっているというより、怯えている様子だったのは、身代わりがばれたらと不安だったのだろう。
「俺の手はもう怖くないか?」
「と、当然です!」
怖くなどない。それどころか彼に触れられると心地好いくらいだ。
なぜそのようなことを聞くのか、という顔を向ければ、黒王は片眉を下げて逡巡する。
「初めの頃、お前の髪についた花びらを取ろうとしたら、怖がられたから……あれは意外と堪えてな」
菊の顔から、サーッと血の気が引いていく。
「も、も申し訳ありませんっ! それは黒王様を怖がったわけではなく……っ」
菊は言うかどうか迷ったが、結局は全てを話すことにした。
村にいた時、従姉の恋人に襲われかけたことを正直に話した。それで、黒王の大きな手を見てその記憶が蘇ったのだと。
黒王は何も言わずに聞いていたが、話し終えるとそのままただ抱きしめてくれた。
肩口に頭を乗せられて彼の表情は窺えない。
ただ、彼が長く息を吐いた音だけは聞こえた。
「やはり、こ、こんな汚い……身体の女など……っ、私が黒王様の隣にいたら、め、迷惑を掛けてしまいます、だから……」
「だから、俺の前から姿を消そうとしたのか」
再びふーと細く長い息を吐くと、黒王はようやく菊の肩から顔を上げ、菊の頬を両手で覆った。
「私は……どのようになるのでしょうか」
「どうしようか」
――やっぱり、このままじゃいられな――。
「どうしよう……すごく嬉しいんだが……」
「は、え?」
口元を手で押さえ、恥ずかしそうに目を伏せた黒王の初めて見る姿に、菊はすっとんきょうな声を漏らした。
予想していた言葉と、あまりに違う言葉が聞こえた気がするのだが。
黒髪の隙間から見えている耳が赤くなっているように見えるのは、勘違いだろうか。
「お前の行動が全て俺を想ってのことだったと思うとたまらない。あー……すまん。きっと今、気持ち悪い顔をしているからこっちを見ないでくれ」
手を菊の顔の前に出して、懸命に視界を遮ろうとする黒王は、あまりにも可愛らしくて。菊のほうもたまらずに笑みを漏らした。
「ふっ、あははは……っ」
いいのだろうか。
「やっぱり笑っているお前は可愛いな」
忌み子の自分が、こんなに喜びを感じてもいいのだろうか。
涙が目尻を伝って流れ落ちる。
だけど、この涙はちっとも苦しくない。
「なあ、古柴レイカではないのなら本当の名前があるんだろう? 教えてくれないか」
彼の親指が涙を拭いとっていく。
「菊と申します」
「よく似合った素敵な名前だ、菊」
ああ、どうしよう……涙が止まらない。
「ずっと……ずっと、そう呼んでほしかったんです。あなた様に」
◆
菊と黒王がいた部屋から廊下を渡った対面の部屋。
いつまで待たされるのだろうか、どうなるのだろうか、と焦れた思いをしながら正座して待っていた灰墨の元へ、ようやく黒王が現れた。
「黒王様! 花御寮様はやはり身ごもって――!?」
黒王が後ろ手にふすまを閉めるなり、ばったが跳ぶように灰墨は黒王に飛びかかる。
「いや、身ごもってなどなかった」
「ええっ!? そんな! 嘘でしょ!?」
「彼女の身体を見せることはできんが……むしろ見たら両目をつぶす……とても綺麗な身体だったよ。お前の母――乳母にも診てもらったが、やはり身ごもってはないと」
「怖っ……じゃ、じゃあ僕が村で聞いた話は?」
「そうだな。それについても、直接きっちりと説明してもらわねばな」
彼女から聞いた話は驚くことばかりだった。正直、冷静を装うのが大変だった。
しかし途中、耐えられそうになくて、彼女の肩に頭をのせて表情を隠した。
彼女は気付いていただろうか。抱きしめた手が血が出そうなほどに拳を握っていたことに。
「俺が羽目を外しすぎないように一応お前もついてこい、灰墨」
「羽目じゃなくてたがでしょ」
「誰のものを傷つけたか、しっかりと分からせてやろうか」
黒王のにやりとしたほの暗い笑みに、灰墨は界背村に「あーあ」と、憐憫の情をもよおした。
4
それは、花御寮がレイカに決まったと分かった日の古柴家での出来事。
叔母の仕打ちで菊が気を失った後、レイカは『いーこと思いついちゃったんだぁ』と言って笑った。
泣いていた娘が突然、化粧がドロドロに崩れた顔で笑いはじめたのだ。レイカの両親は娘が醸し出す得も言われぬ凄まじさに息をのみ、彼女の言う『いーこと』に耳を傾ける。
『菊にあたしのふりをさせて、花御寮にすれば良いじゃない』
年はひとつしか離れておらず、従姉妹ということもあり、背格好も顔立ちも似ていたレイカと菊。声と髪はまったく違うのだが、声は喋らなければ良いし、髪も白無垢に身を包んでしまえばいい。日頃から菊の姿を見ていない村人達なら、だまし通せるだろうという話だった。
『ねっ、良い考えでしょ! あたしは菊のふりして地下で身を隠していれば良いんだし』
『でも、使用人の目があるぞ』
『そんなの娘が花御寮になって辛いから、しばらく家には来なくて良いって言えばいいじゃない。傷心の家族には、皆きっと優しくしてくれるわよ』
『しかし、いつまでもレイカを家に閉じ込めておくわけにはいかないが……』
『安心して。ほとぼりが冷めた頃に一平と村を出て行くから。〝菊〟が村から消えたところで誰もなんとも思わないわよ』
レイカは床で気を失っている菊を一瞥して、舌打ちをする。忌々しげに吐かれたそれは、とてもただの従姉妹相手にするようなものではなかった。
『まあ、一時とは言えこんな女のふりをしなきゃだなんて、不本意で仕方ないけど』
『それは名案だわ!』
今までレイカの話を大人しく聞いていた母親は、表情をきららかに輝かせ、娘のレイカに抱きついて喜んだ
『この子が生きていてくれるなら、村の外だろうがどこでも良いわよ。ねえ、あなたもそう思いますでしょ!』
声も身体も弾ませたレイカの母親が、期待に満ちた顔で父親に目を向けるが、しかし父親の方の顔色はよろしくない。
『そんなこと許されるはずがないだろう! もし身代わりがばれたら、どんなお咎めがあるか……っ』
『どうしてです! あなたはそんなに娘を化け物の生け贄にしたいんですか!?』
『そんなことはない……っ! 俺だってできることなら……いやしかし、やはり……』
村を欺くだけではない。強大な力を持った黒王という相手まで欺くことになるのだ。彼が二の足を踏むのも当然と言えよう。
身代わりにする菊も、村の血が半分しか入っていない忌み子であり、他の村娘を差し出す方がまだ問題鴉は少ない。しかし、当然ながら代わりなど見つかるはずもない。
誰だとて、謎に包まれた妖などに嫁ぎたくも、嫁がせたくもないのだから。
『それより、レイカ。さっきお前は、自分を差し出せば後悔すると言ったが、それはどういう意味なんだ』
訝しげな目を向ける父親に、レイカはにんまりと唇に深い弧を描く。
『あたしのここに赤ちゃんがいるの……一平との』
ここ、と言った時、レイカの手は自らの腹を撫でており、父親の顔からは血の気が失せ、抱きついていた母親は、腹を凝視しながらよろりと半歩後ずさった。
『元々、あたしは花御寮になんかなれないのよ』
『レイカ、お前……掟を……』
『本当、神様って適当よね。わざわざこんな身ごもった女を選ぶんだから』
クスクスと誰へ向けてか分からない嘲笑をして、腹を押さえながら身体を揺らすレイカを、両親は恐ろしいものでも見るかのような目で見つめる。
『しょせん神事なんてそんなもの。掟も契約もそんなもの。守る意味なんてある?』
ここまで来れば、両親も腹をくくらざるを得なかった。
『ああ……一平は今仕事で村を出てたのよね。ちゃんと伝えといてね、お父さん。あなたの愛妻はちゃんと生きてるわよ、って』
こうしてあずかり知らぬ間に、菊の運命は決められてしまったのだった。
◆
日も暮れ始めた頃。
東の空が夜を連れて西に沈む夕日を追いかけはじめた中、界背村の村人達も皆、帰路を急ぐ。
しかし、ふといつもより夜が早いことに気付く。まだ夜は東の端にあらわれた程度のはずなのに、やけに頭上の空は黒い。
そして、「なんだ?」と空を見上げた最初のひとりが、驚きの声をあげ腰をぬかせば、異変に気付いた他の村人達も空を見上げ、次々に鳩が豆鉄砲を食らったような顔になっていく。
「こりゃ、いった何事だ!?」
村の上空を、烏の大群が覆い尽くしているではないか。
そして、黒く覆い尽くしているのは空だけではなかった。
「待て、見ろ!! 村長の屋敷が!」
村人が指差した先――村長の屋敷は、瓦よりも黒々としたものに覆われ、周囲を警戒するように烏が飛び交っている。
「不吉の前触れだ……」
誰かがそう呟いた。
そして、そう思ったのは遠くから眺めている村人だけではなく、屋敷を烏に取り囲まれた村長もだった。
一日ももう終わるというところで家の扉を叩かれ、不機嫌まじりに村長は玄関扉を開けた。しかし、目の前にあらわれた、不吉を体現したような黒ずくめの男を見れば、村長の不機嫌などあっという間に跳んでいく。
「突然の来訪を許せ」
背の高い黒ずくめの男。浮世離れした臈長けた面ざしは、帝都の貴人でもやって来たのかと思うほどに気品があふれている。
だが、そうではないと村長は判断できた。
藤の花を思わせるような紫の瞳と、髪の毛先。
ハイカラな帝都の貴人はもとより、人間ですらない。
「あ、あのっ……ど、どちら様で……」
目の前に立つ男の正体に薄々とは気付きつつ、それでも頭の片隅にあった『そんなはずはない』という常識が、村長に男を確認させた。
男はふっと、どこか馬鹿にしたように笑う。
「黒王……と言えば分かるか? それとも、妖は現世には来られないとでも高をくくっていたか」
「こっ……黒王……!?」
そんなはずはない、がはっきりと現実となり、村長は声を震わせ、尻から地面に落ちた。
「どうやら、この黒王をたばかった阿呆どもがいると聞いてな」
すぐに村長は彼の言う〝謀った〟が何を指しているのかを理解する。
しかし、どうやってばれたのか、なぜ花御寮を送ってひと月近く経った今頃になって言ってくるのか、と疑問は尽きない。
「う、噂の件は……その、わたくしも知ったばかりと言いますか……」
「ほう、どうやら噂は、しっかりと長の耳にも届いていたようだな。ならば話は早い。その阿呆どもに、こちらで沙汰をくだしても文句はあるまい?」
黒王は許可を求めている言葉を口にしているはずなのに、村長にはただの決定事項にしか聞こえなかった。いっぺんの反論も許さぬ威圧感に、村長はぶるぶると身体を震わせながら頷くほかなかった。
「し、しかし、どのようにして黒王様はこの件をお知りに……」
すでに踵を返していた黒王が、ゆるりと顔だけで振り向く。肩口から覗く目が細められ、内側の紫はにぶく光った。
途端に、彼の向こうで見たこともない数の烏たちが、バサバサと羽音を立てて舞い飛び始めたではないか。
黒王は何も言葉にしなかったが、目の前の光景を見れば充分だった。
「烏の……妖……」
言葉を失い口の動きだけでそう呟けば、黒王は口端をつり上げ村長から視線を切った。
この世の者とは思えない美しい顔がニヤリと笑う姿は凄艶で、村長は黒王の背にあらわれた黒翼で空へと上っていく姿を、どこか他人事のように見つめていた。
古柴家は、娘を花御寮に出してからというもの、晴れでも昼でも常に雨戸は締め切られ、使用人の出入りもなくなり暗い雰囲気が漂っている。
どこか村の中でも浮いている。
しかし、それもそうだろう。
最初は娘を花御寮に取られて可哀想に、と村人達は古柴家に同情していた。それが、村外の仕事から帰ってきた一平の『レイカは俺の子を身ごもっていた』という発言によって、腫れ物に触るようなものに変わった。
もう花御寮として送ってしまったのだ。もし一平の発言が本当だとしても、村はどうしようもない。だから村人達は、万が一妖からのお咎めがあった場合、無関係だと言えるように関わりを控えるようになったのだが……。
「一平ったらもう帰っちゃうの?」
「ちょうど日も暮れたしな。それに明日は、また村外の仕事が入ってるんだよ」
レイカ達にとっては好都合だった。
二人は古柴家の地下につくられた座敷牢で、逢瀬を続けていたのだ。
そんな二人にとって、いや古柴家にとって、周囲の目がなくなるのはちょうど良いことだった。
「にしても、本当にレイカが連れて行かれたと思って焦ったよ」
「だからって、あんな騒がなくても良いじゃない。おかげで妊娠してるってばれちゃったし」
「でも、その妊娠したレイカはもう村にいないんだ。村長も相手が古柴家ってこともあって、折を見て水に流すつもりだって話さ」
「それに相手が一平だもんね。古柴家も一平の家も村の顔役だし、さすがに二家を敵には回せないでしょ」
男は、レイカの少しばかり丸みを帯びた腹を撫でた。
「もう、あたし以外に手を出しちゃ駄目よ」
「まだ言ってんのかよ。お前の妹……菊だっけ? 確かに、脅かしてやろうと思って、ちょっかいは掛けたけど未遂だよ。忌み子なんて本気で相手にするわけねえだろ」
「それもそうね」
わざと甘えるように男の胸にしなだれかかるレイカに、男の鼻の下が伸びる。
村で一番の器量好しで、他の村娘達を従える彼女が自分に懐いているというのが、たまらなく男の征服欲を満たしていた。村の若手で一番の男前と言われる自分と、彼女。互いの家は村を支える大家。
お互いこれ以上にない最高の相手だろう。
「レイカ、落ち着いたら村の外で暮らそう。俺は仕事って言えば、村外に出るのなんてわけないしな」
「もちろん! こんな古くさい村なんかさっさと出たかったのよ! じゃあ、街で結婚式を挙げましょうよ! 今流行のハイカラなドレスってのを着たやつ!」
そう遠くない未来に、レイカはキャッキャと少女のようにはしゃいでいた。
「本当、菊には感謝だわ。きっと、この時のためにあの子は生きてたのね」
「やっと役に立てたって、天国で喜んでんじゃねえの」
「あはっ! それってもう食べられちゃったって意味ぃ? まっ、でも実際そうかもね」
ひとしきり笑い、男が帰るからと腰を上げようとした瞬間、上から女の悲鳴が聞こえた。
「――っお母さん!?」
その声は間違いなくレイカの母親の声で、レイカは立ち上がりかけていた男よりも早く地下を飛び出し、悲鳴の元へと向かった。
そこで最初に見た光景に、レイカは眉根を思いっきり寄せて絶句していた。
両親が普段よくいる座敷に向かえば、そこには両親以外に見知らぬ男までいるではないか。彼は身体の側面をこちらに向けているため、顔は髪に隠れはっきりとしないが、間違いなく村の人間ではなかった。
黒の着物に黒の袴に黒の羽織。
背中に流れた髪の毛先だけは不思議な色をしていたが、それ以外は全部黒という不気味な出で立ちの男。
そして、彼の足元で、両親は畳にひたいをこすりつけていたのだ。
「な、何……してるの? そこの奴誰よ」
両親からの反応はなく、ただ虫の羽音のようなものが聞こえる。耳を澄ましてみると、それが父親が「申し訳ありません」と、母親が「すみません」と呟き続けている声だと分かり、急激な嫌悪感が込み上がってくる。
「――っちょっと、あんた! あたしのお父さんとお母さんに何させてんのよ!!」
黒い男が、ゆるりとレイカに顔を向けた。
「――っ!?」
レイカは黒い男の顔を見て、思わず息をのんだ。
向けられた表情は穏やかで、口元は柔和な線を引いている。瞳は紫色をしており、宝石のような硬質的な輝きは驚くほどに冷たかった。しかし、その冷たさすら彼の魅力のひとつになっており、つまりレイカは、一目で男に心を奪われたのだった。
「よくも、黒王たる俺をたばかったな」
その一言で、レイカは瞬時に相手の男が誰だか察した。
「黒王……って、まさか……妖の……鴉の王?」
黒王はにやりと笑んでいた口端を、さらにつり上げてみせる。
「お前が本物のレイカだな。会いたかったぞ」
「本物……って、もしかしてあたしを迎えに来てくれたんですか!」
たちまち、レイカの表情が輝きに満ちた。
「やっぱり忌み子の菊じゃ駄目だったんですね! お気持ち分かります! 確かにあなた様には、あんな醜くてみすぼらしい女など釣り合いませんものね!」
あれだけ妖の嫁は嫌だと喚いていたレイカだが、黒王を目の当たりにしてコロリと掌を返した。
「おい、レイカ! 大丈夫か!?」
そこへ、一足遅れてやって来た自分の恋人だが、レイカは彼に冷ややかな目を向ける。
村一番の男前と称された者だとて、浮世離れした美男と並べば、春霞よりも霞むというもの。
レイカは抜け目なく、黒王に婀娜っぽい視線を送った。
しかし、黒王は鼻で一笑した程度で態度に変化は見られない。黒王の視線はレイカの顔からどんどんと下がり、ピタリと帯の部分で止まる。
「なるほど。その腹の丸み……噂は本当だったか。そして、相手はそっちの男というわけだな」
黒王の紫が男へと向けられれば、男はぶわっと全身から汗を吹き出し、気圧されたように廊下で尻餅をついた。
「な、なんだこいつ……っ、こんな妖見たことねえ……」
ガクガクと震えながら、尻で後ずさる恋人の情けない姿をレイカは無視して、黒王へとすり寄る。
「黒王様、この妊娠はあたしの意思ではなかったのです。そこの男に無理矢理襲われ……」
レイカは同情を引くように目元を着物のたもとで押さえ、黒王の胸へとしなだれた。しかし、やはり黒王は特に反応は示さず、菊と同じくらいに低いレイカの頭を無感情な目で「ほう」と言って見下ろすのみ。
そこへ、レイカの母親が声を大にして入ってくる。
「む、娘の言うとおりでございます! わたくしどもは神事の決定に従おうとしたのですが……そ、そう! 我が家で養っていた忌み子がそこの男と結託して、娘を無理矢理手籠めにしたのです!」
「腹の膨らみからするに、神事が行われるより以前からのような気がするが?」
矛盾をつかれ、母親が青い顔して唇を噛む中、今度はレイカが話の続きを引き取った。
「妹はずっと、家での待遇に不満を持っていたのです。母の姉の子である自分のほうがあたしよりも偉いだとか、忌み子の自分は花御寮にはならないからと、家を抜け出しそこにいるような男達と遊んだり……」
一瞬、黒王の目の下が引きつったことに、レイカは気付かない。
「とにかく妹の菊は! 高慢でわがままで男癖も悪く……あたしはいつもそれを諫めていたのですが、その仕返しをされこのような身体に。しまいには、花御寮を代わらなければ、掟破りだと村中に吹聴して回ると……うぅっ」
はらはらと涙を流すレイカは黒王の羽織にしがみつき、分かってくれと言うように羽織に涙を染みこませていく。
「と、娘は言っているが……親はどうなんだ? 真実か」
「娘の言うとおりでございます!」
「わたくし共には、どうしようもないことだったのでございます!」
間髪容れず、両親はレイカの言葉を〝是〟と認めた。
途端に、黒王は大口をあけて咆哮するかのように笑い出した。
「あっははははは! なるほどなるほど、全て理解したわ」
両親とレイカの間に、ほっと安堵の空気が流れる。
「では、黒王様。あたしを黒王様の花御寮にしていただけるんですね!」
「ああ、連れて行こう」
「本当ですか!」
黒王が羽織を握っていたレイカの手首を掴めば、レイカは頬を喜色に染め、目に希望を宿らせた。
「お前の両親も共にな。実に立派な親子だ、ここまでそっくりだとは」
「え?」
「ここに来てまで俺をたばかろうとはな。親子共々ここまで腐っていたとは」
「え……あの……えと? 黒王様、く、腐っているとは……?」
クスクスとまるで馬鹿にしたように笑う黒王に、危険を察したレイカは黒王から距離を取ろうとする。が、黒王に手首を掴まれていて離れられない。
「痛――ッ!?」
それどころか、手首を握る力はどんどんと増し、ギチギチと締め上げられる。
「勘違いしているようだが、俺はお前たちに罰を与えに来ただけだ。誰がお前のような餓鬼以下の女を花御寮にするものか」
吐き捨てるように言われた台詞にまざった〝罰〟という言葉を、三人はしっかりと聞き取った。薄暗い部屋の中で三人は顔を蒼白にし、カチカチと奥歯を鳴らす。
「ちゃんと連れて行ってやるさ、三人まとめて……黄泉の国へな」
「い――っ、いやああああああっ!! 助けてっ! 助けなさい、一平!!」
床でへたり込んだままの恋人に向かって、レイカは必死に手を伸ばすが、相手の男は助けるどころか、彼女を恨めしそうな目で睨み付けるばかり。
「っなんでよ! 菊が気に入らなかったからって、どうしてあたし達が罰を受けないといけないのよ! そんなに花御寮がほしければ、他の娘でも攫っていけばいいじゃない!」
「あの娘がお気に召さなかったのですね!? だからそのように罰などと……!」
「娘はこの通り器量好しです! 腹の子はこちらでどうとでもいたしますので、何卒お許しください!」
この期に及んで問題がどこにあったのか分かっていない三人に、黒王は憐れみすら覚えた。
口々に「やめてください」と、餌を欲しがる雛鳥のように喚いている。
雛鳥と違ってまるで可愛くはないし、情もわかないが。
「菊も、お前達に何度折檻をやめてくれと思っただろうなあ……。お前達はどれほど菊の言葉を聞き入れたんだ? どれだけ菊に涙を流させてきた」
「菊……って、嘘! まさかそんな……っ!?」
そこで、三人はようやく黒王が何に怒っているのかを理解した。そして、今までの自分達の発言が全て、彼を逆撫でするようなものだったことも。
「ある意味お前達には感謝している。このような餓鬼よりも欲深い娘ではなく、清らかで愛らしい菊を送ってくれたことに。あれは俺の最愛のつがいだ」
だから、と黒王はまだ逃げようとするレイカの手首を、容赦なく握りしめる。
「血など流させず綺麗に死なせてやろう。数百年と同じ村の中で婚姻し続けても病が出なかった理由が分かるか? お前達の身に流れる祓魔の力が、血の悪もおさえていたからだ。では、その力がなくなったら?」
もう声すら出ないのだろう。
「これからお前達は急激に老い、この世に存在する数多の病がその身を蝕む。あらゆる痛みにさいなまれ、早々と死ねるだろうさ」
黒王の言葉を聞いても、三人は首をぶるぶると横に振るばかり。
何かを言い足そうに開いては閉じを繰り返す口からは、荒く浅い息が漏れている。
「黄泉の国も常世とも繋がっているからな。運が良ければ、向こうで俺に会えるかもしれんぞ」
運が良ければな、と黒王が言い終わると同時に、三人は糸が切れた人形のようにべちゃりと床に突っ伏した。「え」と、レイカは声を出したのだろうが、その声はしわがれ、ただの息と変わりなかった。
次第に三人の手は、干からびたように皺が刻まれ始める。
「――ッいやあああ、ああ!? あっああああああ! あぁ……っ…………」
「これからの菊には、優しい世界しかいらないからな」
三人は悲鳴にならない悲鳴を上げた後、完全に沈黙した。
黒王は、レイカの涙が染みこんだ己の羽織を脱ぐと、汚いものを見るような目を向け、動かなくなった三人の上へと放り投げた。
真っ黒の羽織は、醜くなった三人をすっぽりと覆い隠し、黒王は満足げに踵を返し、開け放たれた雨戸へと向かう。
しかし、黒王は廊下で腰を抜かしていた男の横で足を止めた。
「男、お前はしっかりと村の者達に伝えろ。常世の者を軽んじるとこのようになる、とな」
男はぶんぶんと勢いよく首を縦に振る。
「お前が菊にした所業は知っているぞ」
腰を折り、耳元で囁かれた言葉に、上下していた頭の動きがビタッと止まった。
「本当ならばこの場でお前も殺してやりたいが、伝える者がいなければならないだろう? 黒王を侮ったらどうなるか」
青を通り越して死人のように真っ白になった男を見て、黒王は再び上体を起こして屋敷を出て行く。
「ゆめゆめ忘れるな。俺達鴉ははいつでも見ているからな」
黒王が姿を消しても、古柴家の外からは、豪雨のような数多の鳥の羽音だけが聞こえていた。