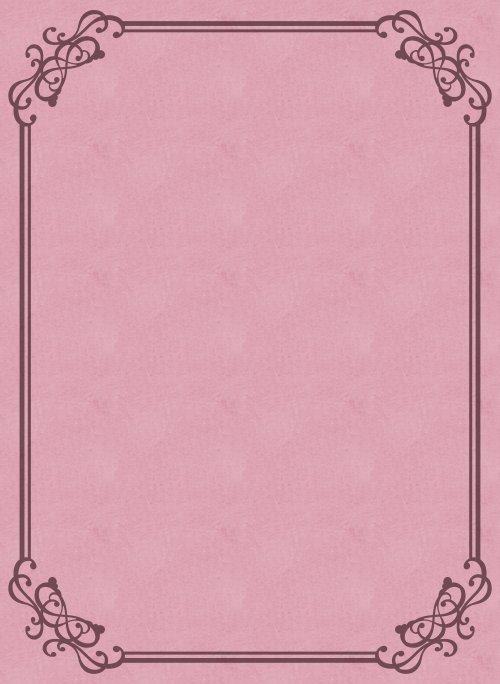音楽というのは良い。自分の中に好きなだけ正しい音と好きな音を選び、または選ばずに無作為に浴びるように、流し込んでいくように聴く。それだけでいい。難しいことはなにもない。音楽理論とか、理屈とかいらない。余計な知識なんていらない。耳が正常ならそのことに感謝して、思う存分に耳を傾けると良いだろう。きれいな音は心を創り出すし、ロックな歪んだ音はわくわくとした冒険心を沸き立たせてくれる。ピアノの調律された旋律、ギターのストリングス、ドラムのリズム、どれか単品でも良いし、合わさっても良い。人間の作り出した文化の極みだと、たしかにそう思う。音楽は良い。それに尽きる。
広場はたくさんのカプでごった返していた。中心にはステージが用意されていて、マイクやらアンプやらが設置されていた。先頭の方には到底辿り着けそうにないほどたくさんいて、密集していた。さながらライブやフェスの会場のようである。
「すごい数だな……」
その数に圧倒されていると、やがて主役の登場。国王様と呼ばれるそれはまさに人物だった。不思議な生き物カプとは違い、スタイリッシュで人間的だ。手足が長く、本当にスタイリッシュという言葉がぴったりな人物であった。これまでの不思議な生き物という呼称は似合わない、人間そのものであった。
「みんな今日は来てくれてどうもありがとうー」
王様がマイクに向かって挨拶をする。大歓声が巻き起こった。それだけで、この王様が信頼されていることがわかる。
そして王様は説明する。このギターは世界を平和にする音色を奏でる世界唯一のギターです。これは天からの贈り物、奇跡です。と。
そして王様は演奏をするためにギターを手にした。そしてそれは、よく見ると、僕の父からもらったあのギターだった。フォルム、色合い、ヘッドの傷。間違いない。僕のギターだ。
僕は強欲にも、しかし当たり前にもそれを取り返したく思った。
先程のカプを群衆から見つけて声を掛ける。
「な、なあ、カプ。あの王様のギター、あれ僕の無くしたやつなんだ。傷とか色合いとか、刻んだ文字とかが間違いない。なんとか取り返したいんだけど」
「え? なんだ、人間。王様のギターを奪いたいっていうのか?」
「だから、あれは僕の無くしたやつなんだよ」
「無くしたも、捨てたも、どちらも同じだろう」
「違うよ、違うんだよ。きっと、君たちカプが勝手に持っていったに違いないんだ」
「さあ、どうだか……まあ、どちらにしても関係ないね。どうにかするなら、自分でどうにかするんだな。ライブの邪魔はしてほしくないけど」
「そ、そんな……」
カプはまた群衆へと消えてしまった。たしかにみんなが楽しみに、楽しんでいるライブに乱入してそれを壊すのは罪悪感を覚える。しかし、ギターを取り戻せるのは今しかないとも思える。曲と曲の間、ギターをスタンドに置いたその時がチャンスだ。
カプの奏でる音楽はわからなかった。王様の音楽はでたらめに近く、そしてその歌もカプの言葉で歌われていたからまるでわからなかった。人間の歌ではないし、人間にわかる歌ではなかった。太鼓の律動や、ギターの音色はわかる。僕はそれを楽しんでいるふりをしつつ、隙を狙っていた。
曲間、ギターを置いて話し始めた。チャンスだった。エムシーの時間は、アーティストが一番調子に乗って、気分が良くなる時間帯だ。取り返すならばここしかない。
話が佳境に入り、盛り上がっているその時だった。一人の男が、人間がステージに乱入した。男はそれはもちろん僕だった。その男はギターをかっさらうと颯爽と街へ逃げ出した。王様はナニカ叫んでいたが、人間の言葉ではなかったのでわからなかった。
すぐに追手が追いかけてきた。王様のものを盗むなどけしからんというわけだ。僕は逃げた。あちこちへと逃げた。ギターをストラップで背に掛けて、背負って走って逃げた。しかし土地勘のない場所である。すぐに詰み、行き止まりにあたってしまった。左右も高い家の壁の塀で囲まれている。後ろも高い塀で登ることも難しそうだ。追手が王手をかけに、そろそろとやってきた。逃げ場はない。どうする。
僕はギターを取った。さっき歌っていたからチューニングは、一応されているようだ。よし。
この様子に追手たちも困惑していた。更に向こうからやってきて犯人を見てやろうという野次馬たちも何事かとざわざわし始めた。僕はそれらをよそ見に歌を歌いだした。もちろんギターを弾きながら。
それは少し前に流行った歌だった。もう懐メロになってしまうのかという残念感と、いつまでも色褪せないでいてほしいという思いを込めて歌った。それは人間による人間のための、人間の歌だった。意味していることはわかるだろう。
僕はいつも後悔していた。父が生きている間にもっと話しをしていればよかったと、死ぬなんてそんな悲しいことが来るなんて思いもしなかった。本当に来ないでほしいと、そう思う時間もあった。このギターは、やっぱりこのギターだ。手に馴染む。思い出が詰まってる。色々と思い出す。色々と後悔していることを思い出す。僕は、そう後悔しているのだ。おや、どうだろう。それは罪悪感なのかもしれない。自分の父に対する罪悪感。ああ、そうか。僕は後悔と罪悪感とが混ざっているんだ。きっと区別ができなくてごっちゃになっているんだろう。情けない。
音楽はニ回目のサビを迎えた。カプたちは人間の、本物の人間の歌に涙していた。涙は不思議な感情を生み出し、そして僕の歌と合わさる。当然のように僕も泣いていた。不思議だ。感情的に揺さぶられたわけでもないのに、泣いていた。そしてそこは、やがて不思議な空間となり、そして異空間と成り果てた。歌を終えた僕は一礼して、拍手をもらって、それから再びギターを背負って真後ろにできたその異空間へと足を踏み出した。少し振り返ると王様も頷いていて、多くのカプたちが手を振っていた。僕は手を振り返して、それから一礼した。丸い扉はそこで閉じた。
不思議な物語はここまでである。気がつくと僕はギターを持ってあの小さな桶の前に立っていた。そして、それからギターを背にして僕は家と足を向けたのだ。
何事もなかったかのように、僕は今日も家の隅でギターを弾いて日々を過ごしている。もう無くさないように、失わないように。大事に大切にして、そして後悔しないように毎日を生きるのだ。明日死ぬことになっても後悔しないように今日を生きる。
僕の涙は、決して間違いじゃなかったと証明するために。
広場はたくさんのカプでごった返していた。中心にはステージが用意されていて、マイクやらアンプやらが設置されていた。先頭の方には到底辿り着けそうにないほどたくさんいて、密集していた。さながらライブやフェスの会場のようである。
「すごい数だな……」
その数に圧倒されていると、やがて主役の登場。国王様と呼ばれるそれはまさに人物だった。不思議な生き物カプとは違い、スタイリッシュで人間的だ。手足が長く、本当にスタイリッシュという言葉がぴったりな人物であった。これまでの不思議な生き物という呼称は似合わない、人間そのものであった。
「みんな今日は来てくれてどうもありがとうー」
王様がマイクに向かって挨拶をする。大歓声が巻き起こった。それだけで、この王様が信頼されていることがわかる。
そして王様は説明する。このギターは世界を平和にする音色を奏でる世界唯一のギターです。これは天からの贈り物、奇跡です。と。
そして王様は演奏をするためにギターを手にした。そしてそれは、よく見ると、僕の父からもらったあのギターだった。フォルム、色合い、ヘッドの傷。間違いない。僕のギターだ。
僕は強欲にも、しかし当たり前にもそれを取り返したく思った。
先程のカプを群衆から見つけて声を掛ける。
「な、なあ、カプ。あの王様のギター、あれ僕の無くしたやつなんだ。傷とか色合いとか、刻んだ文字とかが間違いない。なんとか取り返したいんだけど」
「え? なんだ、人間。王様のギターを奪いたいっていうのか?」
「だから、あれは僕の無くしたやつなんだよ」
「無くしたも、捨てたも、どちらも同じだろう」
「違うよ、違うんだよ。きっと、君たちカプが勝手に持っていったに違いないんだ」
「さあ、どうだか……まあ、どちらにしても関係ないね。どうにかするなら、自分でどうにかするんだな。ライブの邪魔はしてほしくないけど」
「そ、そんな……」
カプはまた群衆へと消えてしまった。たしかにみんなが楽しみに、楽しんでいるライブに乱入してそれを壊すのは罪悪感を覚える。しかし、ギターを取り戻せるのは今しかないとも思える。曲と曲の間、ギターをスタンドに置いたその時がチャンスだ。
カプの奏でる音楽はわからなかった。王様の音楽はでたらめに近く、そしてその歌もカプの言葉で歌われていたからまるでわからなかった。人間の歌ではないし、人間にわかる歌ではなかった。太鼓の律動や、ギターの音色はわかる。僕はそれを楽しんでいるふりをしつつ、隙を狙っていた。
曲間、ギターを置いて話し始めた。チャンスだった。エムシーの時間は、アーティストが一番調子に乗って、気分が良くなる時間帯だ。取り返すならばここしかない。
話が佳境に入り、盛り上がっているその時だった。一人の男が、人間がステージに乱入した。男はそれはもちろん僕だった。その男はギターをかっさらうと颯爽と街へ逃げ出した。王様はナニカ叫んでいたが、人間の言葉ではなかったのでわからなかった。
すぐに追手が追いかけてきた。王様のものを盗むなどけしからんというわけだ。僕は逃げた。あちこちへと逃げた。ギターをストラップで背に掛けて、背負って走って逃げた。しかし土地勘のない場所である。すぐに詰み、行き止まりにあたってしまった。左右も高い家の壁の塀で囲まれている。後ろも高い塀で登ることも難しそうだ。追手が王手をかけに、そろそろとやってきた。逃げ場はない。どうする。
僕はギターを取った。さっき歌っていたからチューニングは、一応されているようだ。よし。
この様子に追手たちも困惑していた。更に向こうからやってきて犯人を見てやろうという野次馬たちも何事かとざわざわし始めた。僕はそれらをよそ見に歌を歌いだした。もちろんギターを弾きながら。
それは少し前に流行った歌だった。もう懐メロになってしまうのかという残念感と、いつまでも色褪せないでいてほしいという思いを込めて歌った。それは人間による人間のための、人間の歌だった。意味していることはわかるだろう。
僕はいつも後悔していた。父が生きている間にもっと話しをしていればよかったと、死ぬなんてそんな悲しいことが来るなんて思いもしなかった。本当に来ないでほしいと、そう思う時間もあった。このギターは、やっぱりこのギターだ。手に馴染む。思い出が詰まってる。色々と思い出す。色々と後悔していることを思い出す。僕は、そう後悔しているのだ。おや、どうだろう。それは罪悪感なのかもしれない。自分の父に対する罪悪感。ああ、そうか。僕は後悔と罪悪感とが混ざっているんだ。きっと区別ができなくてごっちゃになっているんだろう。情けない。
音楽はニ回目のサビを迎えた。カプたちは人間の、本物の人間の歌に涙していた。涙は不思議な感情を生み出し、そして僕の歌と合わさる。当然のように僕も泣いていた。不思議だ。感情的に揺さぶられたわけでもないのに、泣いていた。そしてそこは、やがて不思議な空間となり、そして異空間と成り果てた。歌を終えた僕は一礼して、拍手をもらって、それから再びギターを背負って真後ろにできたその異空間へと足を踏み出した。少し振り返ると王様も頷いていて、多くのカプたちが手を振っていた。僕は手を振り返して、それから一礼した。丸い扉はそこで閉じた。
不思議な物語はここまでである。気がつくと僕はギターを持ってあの小さな桶の前に立っていた。そして、それからギターを背にして僕は家と足を向けたのだ。
何事もなかったかのように、僕は今日も家の隅でギターを弾いて日々を過ごしている。もう無くさないように、失わないように。大事に大切にして、そして後悔しないように毎日を生きるのだ。明日死ぬことになっても後悔しないように今日を生きる。
僕の涙は、決して間違いじゃなかったと証明するために。