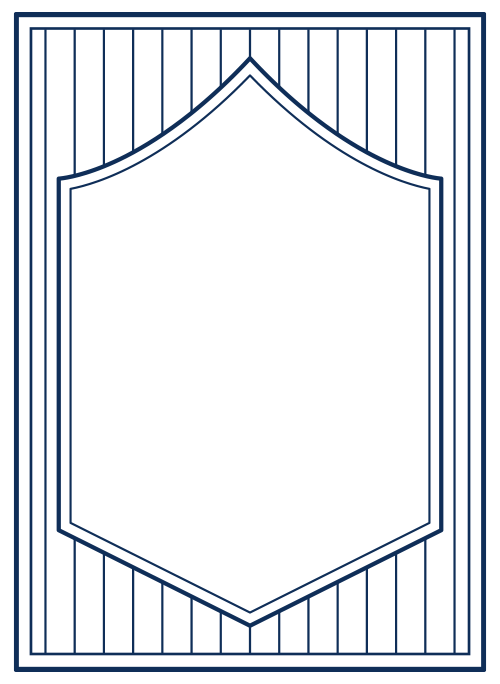一
「セルケト教にあったって言うの?」
「うん」
「セルケト教徒がいるのはここよりずっと北の方じゃない」
「そうだけど、ハイラル教がこの大陸に伝来するまで一番信者が多かったのはセルケト教だったんだよ。当然この辺もセルケト教の勢力範囲だったしハイラル教もかなり影響受けてるよ」
「ふうん……それで?」
「セルケト教の神儀書に出てくる聖獣の中に僕らが倒したのと対応するのがいたんだ」
神儀書というのはアスラル教で言うところの教典、ハイラル教での聖典に当たるもので、神話や教えなどが書いてある本だ。
カイルは地図をテーブルの上に開いた。
ヘメラ、ケナイ、アイオンの順に指す。
「神儀書に出ていた聖獣は全部で八匹。順番も僕らが倒したのと同じなんだ。だから間違いないと思うんだけど、どうかな」
ミラが肩を竦める。
一瞬、頭に血が上り掛けたが、すぐに今のが「どうでもいい」という態度の現れではなく「自分には分からない」という意味だと悟る。
カイルは気を取り直して地図を指した。
「もし、あってるなら次はこの辺なんだ。リキアかロークか、ちょっとズレるけどファイユ」
「私が分かんないのはそれがなんなのかってことよ」
「それは……僕も分からない。けど、セルケト教ではそいつらの事〝世界の守護者〟って言うんだ」
「だから?」
「気になんない?」
「よく分かんない」
ミラの言葉にカイルは返答に詰まった。
カイルもなんと説明すればよいのか分からない。
考え込んでいるうちにいつの間にか眠り込んでしまっていた。
目が覚めてみるとミラの姿が無かった。
神官長が一人で事務処理をしている。
まさか、また神殿を抜け出したんじゃ……。
カイルはミラを探しに出た。
ミラは神殿の裏にいた。
カイルが裏口から出た時、十歳くらいの女の子と話していたミラが踵を返したところだった。
町に向かおうとしているらしい。
「ミラ、どこ行くの! 謹慎が解けてもいないうちから抜け出す気!?」
「ちょっとだけよ。この子のお母さんが大変なんだって」
「なに言って……」
「すぐ戻るからラースには黙ってて」
「ミラ!」
ミラはカイルが捕まえるより早く駆けていってしまった。
追い掛けようとした時、
「リース、どうしたの? こんなところで」
女の子がミラの後に続こうとした時、マイラの声が降ってきた。
見上げるとマイラが神殿の窓から身を乗り出している。
ミラに会いに来た女の子に声を掛けたのだ。
ミラを追い掛けようとしていた女の子――リースがマイラの方を振り向いた。
「その……」
「皆元気にしてる?」
「うん、あの、早く行かないと……」
「そう、それじゃ。あたしの母さんに会ったら元気にしてるって伝えといて」
「うん」
リースはミラの跡を追うようにして走っていった。
マイラの母さん?
「マイラ!」
カイルはマイラを呼び止めた。
マイラが振り返る。
「なんですか?」
「今の子、ケナイに住んでるの?」
「はい」
「そう、ありがとう」
マイラが行ってしまうとカイルは憤然としながら神殿へ入った。
ケナイの子がミラに会いに来た。
という事はこの前の話は嘘だったのだ。
……ったく!
言いたくないなら言わなくていいって言ったのに!
何も嘘吐く事ないじゃないか!
腹が立っていたカイルは思わず執務室の扉を乱暴に開けてしまった。
その途端、机に向かって書類を書いていたラースと目が合った。
「カイル、またミラと喧嘩したのか?」
ラースが苦笑いを浮かべた。
「確か仲良くしてくれる約束だったはずだが」
「す、すみません。けど、喧嘩はしてません」
嘘ではない。
「そうか。なら、どうしたんだい?」
「……え、あ、その……ミラがケナイ山を吹き飛ばした犯人に……」
「ああ、その話か。仕方なかったんだよ」
「え……?」
「慣れすぎてしまったんだ」
「慣れ?」
ラースの言っている意味が分からず首を傾げた。
「ミラは神官の真似事をしていたとは言え、基本的には居るだけで豊穣をもたらすし、災いに見舞われる事も無い」
いつからかミラのお陰だという事を忘れてしまったのだ。
そして錯覚した。
ミラが居なくても同じ状態が続くだろうと。
「それで逆にミラの力が怖くなったんだ」
ミラへのお礼として持ってきたものは全て村の人間達が受け取っていてミラには渡していなかった。
もしバレたらミラが腹を立てるのではないか。
その時ミラの力を自分達に向けられたら……。
ケナイ山の魔物が吹き飛んだ事が決定打になり村の者達はミラを犯人として警備兵に突き出した。
後ろ暗いところがあったのだとしたら尚更恐怖を覚えただろう。
もしかしたらミラに頼みに来る人達に高価な謝礼を吹っ掛けていたのかもしれない。
最近依頼人が減っていた。
謝礼が手に入らなくなり、豊穣は続いている。
それでミラが自分達に牙を剥く前に始末しようと考えたのだろう。
「ホントの話だったんですか? だって、それじゃあ……」
「どうかしたのか?」
ラースの問いにカイルは神殿の裏での事を話した。
二
ミラは神殿から離れた森の奥にいた。
目の前に数人の男が立っている。
その後ろにはリースと呼ばれた女の子とその母親が男達に捕まっていた。
「ったく、ハイラル教ってのはいつから犯罪集団になったのよ。教祖様が泣くわよ」
「我々に教祖などいない」
「じゃ、ハイラルってのは誰よ」
「軽々しく我々の救世主の名を口にするのはやめてもらおうか。知りたければあの世で勉強したまえ」
「アスラル教にあの世なんかないわよ」
「無駄口はいい。とっととやれ!」
リーダーらしい初老の男が命令した。
直線的で無駄のない紫色の服はしわ一つない。
ハイラル教の聖衣である。
聖衣を着ているのは初老の男だけだ。
他の男達は信者らしい。
剣を持った男がミラに向き直る。
「下手な真似はするなよ。魔法は防げなくても、あの二人を道連れにする事くらいは出来るんだからな」
「分かったわよ。その代わりその二人を放しなさいよ」
「お前が死んだらな」
「死んだら、あんた達が約束守ったかどうか分からないじゃない」
「それは信用してもらうしかないな」
「こんな事する連中、信じられると思ってんの?」
「なら、この二人を見捨てて逃げるか?」
「ったく」
ミラが男を睨み付けた。
「悪く思うなよ」
「思うわよ!」
ミラが言い返す。
男が剣を振り上げた。
「待て!」
全員が一斉に声の方を向く。
木の陰から青年が出てきた。
優男風の青年だが赤い瞳には感情が無い。
見た瞬間、ミラの全身が総毛立った。
こいつ……。
見た目は人間だが人ではない。
青年を見たミラが身構える。
「その娘を殺したら連中はあいつを生かしてはおかないだろうが。少しは考えろ」
青年はそう言うとミラの方に向き直った。
「久し振りだね」
「たった今助けてくれた相手にこんなこと言うのもなんだけど、初対面よ」
「何度も会ってるんだよ。最近だと千年前に」
「私が千歳越えてるように見えるわけ?」
男の顔に笑みが広がった。
本気で面白がっているらしい。
「確かに。改めて自己紹介しないといけないな。私の名はシーアス」
ミラはシーアスの差し出した手を無視した。
シーアスは愛想笑いを浮かべてミラの手を取る。
本能的に恐怖を覚えて慌てて手を振り払った。
「馴れ馴れしく触んないでよ!」
「シーアス様!」
初老の男がシーアスに呼び掛けた。
声がかなり苛立っているのはミラが目障りだからだろうか。
ハイラル教徒にとって異教徒は悪魔の手先である。
まして異教の神官など悪魔そのもの以外の何者でもない。
ミラを早く殺してしまいたいのだろう。
「なんだ、カート」
カートというのが初老の男の名前らしい。
役職名でなければ、だが。
アスラル教の事すらよく知らないミラに他の教団の事は全く分からない。
「その女は契約の妨げになります。前回邪魔をしたのはその女だと仰ったのはあなたではないですか!」
「バカだな。この娘がいればあいつが殺されても契約は遂行できる。それとも、もう千年待ちたいのか?」
カートが苦々しげに顔を歪める。
その時、いきなり地面が波打ち始めた。
地震の不意打ちに全員が地面に投げ出される。
リースと母親が男達の手から放れた。
ミラは地震が終わると同時に立ち上がってリース達に駆け寄った。
男達も起き上がると取り押さえようと向かってくる。
ミラは突風を巻き起こした。
男達が吹き飛ばされる。
「大丈夫? 逃げ……」
「はい、そこまで」
最後まで言う前にシーアスが背後からミラの肩に両手を置いた。
「この!」
ミラは背中を向けたままシーアスに風を叩き付けた。
が、シーアスは何事も無かったように肩に手を置いていた。
普通の人間なら挽き肉より細かくなっているはずだ。
ミラが眉を顰めて振り返った。
シーアスが涼しい顔で微笑み掛けてくる。
「邪魔しないでよ!」
もう一度手加減なしで魔法を使った。
やはりシーアスには通じない。
その間に男達はリースと母親を取り押さえてしまった。
「それなら……」
ミラはシーアスに回し蹴りを放った。
シーアスがミラから手を離して蹴りを避ける。
その隙にミラはリース達の方へ駆け出そうとした。
が、次の瞬間には後ろからシーアスに抱き締められていた。
ミラの顔から血の気が引く。
「ちょ、ちょっと! 何するのよ! 放してよ!」
「君に逃げられたら困るんでね」
「だからって……どこ触ってるのよ! 嫌らしいわね!」
ミラは必死で暴れたがシーアスの腕から逃れることは出来なかった。
ハイラル教の男達は呆気に取られた様子でミラとシーアスを見ていた。
カートは思い切り顔を顰めている。
ミラがカートを睨み付けた。
「サイテー! あんた達いつもこんな嫌らしい真似してるの!?」
「ち、違う! そいつは信者でも聖職者でもない!」
カートは慌てて手を振った。
動揺していて敬語を忘れている。
ハイラル教の聖職者は妻帯禁止である。
その上、子供のうちから神殿に入れられて異性と接触する事なく育つ者も少なくない。
子供の頃から神殿で生活している者にとっては人前で異性を抱き締めることさえ不埒なのだ。
それでもシーアスを止めようとはしなかった。
「じゃあなんなのよ! 見てないでなんとかしなさいよ!」
ミラはカート以上に動転していた。
半分泣き声になっていた。
父親にさえ抱き締められた事などないのだ。
赤ん坊の時の事は覚えてないが。
しかしシーアスはミラの涙声にも心を動かされた様子はなかった。
「君が逃げようとしている間はダメだね」
楽しんでいるとしか思えない声が耳元で聞こえた。
ミラの背筋を悪寒が走る。
「分かった! 逃げない! 逃げないから放して!」
ミラが必死で藻掻きながら言った。
「ホントに? 俺はずっとこのままでも構わないんだけど」
「私は構うの! 放してよ!」
「……シーアス様、こう申してますしアスラル神官は嘘を吐きませんから」
異教徒への憎悪よりシーアスの行為への嫌悪の方が僅かに勝ったようだ。
カートの声にはシーアスを咎めるような響きがあった。
シーアスが残念そうに溜息を吐いて手を離した。
その息が首筋に触れてミラは身震いした。
三
「あの方の事は……」
「この娘を餌にして呼び出せ」
「はい……それで、その女は」
「無論、連れていく。あいつにもしもの事があったらこの娘にやってもらわなければならないからな」
「そうですか」
カートの残念そうな表情はミラを殺せない事によるものか、それともシーアスの態度に対する懸念によるものか……。
カイルの話が終わる前にラースは神殿中の神官にミラの捜索を命じた。
神殿長はおろか神官長にすら許可を求めなかった。
にも関わらず神殿長も神官長も咎めようとしないどころか、むしろ当然のような顔をしていた。
「ミラに何かあったと思うんですか?」
カイルの問いにラースは安心させるように微笑んだ。
「大丈夫。魔法が使えるんだ。滅多な事は無いだろう」
「お言葉を返すようですけど、ミラって使える魔法の種類が少ないって言うか……」
言い辛くてつい眼を伏せてしまった。
ミラの魔法を貶すのは彼女に教えてるラースを非難する事でもある。
ラースが苦笑した。
「確かに、聖句はまるっきり覚えてないな」
ラースの言葉にカイルの方が慌てた。
「別に、まるっきりなんて、そんな……」
「本当に全然知らないんだよ。唯一覚えたテル・ルーズの聖句も間違ってるんだ。一度言わせてみれば分かるよ」
ラースは事も無げに言った。
カイルは呆気に取られてラースを見上げた。
「確かに黙って使ってますけど……聖句を知らなくても使えるものなんですか?」
少なくともカイルは回復と障壁以外の神聖魔法は聖句を唱えないと使えない。
「魔法は願望の具現化だ。基本的に術者が望めばそれで十分なんだ」
「それは知ってますけど」
それでもラースですら魔法を使う時は聖句を唱えている。
「聖句って言うのは初心者の為にあるんだよ。例えばテル・ルーズは魔法で火の玉を出すものだが最初は上手く想像したものを具現化出来ない。そこで聖句が必要になってくるんだ。聖句の言葉は具体的だろう」
確かに聖句は具現化される現象を具体的に言っているし、初歩的なものほどその状態になるまでの過程が詳しく形容している。
「けど……それじゃ、ミラはどうやって魔法を覚えたんですか?」
「見れば真似出来るから目の前で実演したんだ」
「それならなんであんなに種類が少ないんですか?」
カイルの質問にラースが肩を落とした。
調子に乗って余計な事を……!
カイルはすぐに言った事を後悔した。
「一応、私が知ってる限りの魔法を全部やって見せたんだが……」
ラースに使える魔法があれだけのはずがない。
ラースはセネフィシャルである。
セネフィシャルとは神に不貞を働く輩に懲罰を与える役割を担っている神徒だ。
当然その名を冠した神官も攻撃魔法に熟達した者が就く。
ラースの答えはカイルの予想通りだった。
「覚えられなかったんだ……派手で印象に残りやすいもの以外……」
カイルはミラに魔法の指導をしなければならないラースに心底同情した。
そのうち下級神官の一人が「ミラがハイラル教徒と一緒にいるところを町の人間が見た」という報告を持ってきた。
ラースはそれを聞くと捜索を打ち切った。
五日後、ミラはハイラル教徒の家と思しき建物の一室に閉じこめられていた。
昨日まではずっと移動ばかりで馬車の中で寝泊まりさせられていた。
夕辺ようやく個室のベッドで寝る事が出来たのだ。
当初、シーアスが不埒な振る舞いに及んだら、と思うと気が気ではなかった。
が、カートも同じ疑念を抱いていたらしい。
流石に悪事を働いていても聖職者である。
常時見張りを付ける事によって防いでくれた。
単に逃げられたら困るというのもあったのだろうが。
しかし常に張り付いていたのは監視だけではない。
見張りの隙を突こうとしたのかどうかは定かではないが、とにかくシーアスも一日中ミラの側にいた。
「君も懲りないね」
シーアスが愉快そうに笑った。
椅子に反対向きに座り、背もたれに両腕を乗せている。
見張りへの泣き落としを言ったのだ。
捕まって以来、ミラは見張りに対して宥めたり賺したりと色々試みていた。
一番沢山試したのが泣き落としである。
しかし最初に魔法で吹き飛ばしてしまったことを根に持っているのか、誰一人心を動かされてはくれなかった。
リース達が捕まっている限り逃げ出せない。
なんとか彼らの方からリース親子ともども解放してくれるように仕向けたいのだが……。
「ね、お願い。こんな事、ホントはしたくないんでしょ。人質取ったり、誘拐したりするなんてハイラル教でだって悪い事のはずよ」
しかし見張りはミラの顔を無表情に見返すだけだった。
「確かにハイラルの教えではない」
カートが入ってくるなり言った。
「じゃあ……」
「君達現世利益の教団の人間には分からないかもしれないが我々にとって神の国へ行けるかどうかは大問題なんだ」
「そんなの私には関係ないでしょ」
カートは聞いていなかった。
「神の国では病も争いもなく、身分の上下もない」
「結構ね。異教徒を巻き込まないでくれるなら」
「人間は花の蜜だけで生きていけるようになり、狼も草を食べるようになる」
「狼が羊を食べるのが悪い事ならなんで神様はそういう風に造ったのよ」
「神の国が到来した時――」
カートは辛抱強く説教を続けた。
流石聖職者である。
「我々は三千年もの間、神の国が到来するのを待ち続けてきたのだ」
「時間を無駄にしたわね。ハイラル教徒の人数と影響力を使って世界をより良く変えるように努力してれば神の国なんか待たなくたってこの世は住み易くなってたわよ」
ミラがそう言った途端シーアスが弾かれたように笑い出した。
「何がおかしいのよ!」
「何がおかしいんですか!」
ミラとカートが同時に言った。
シーアスはしばらく笑い続けた。
やがて笑いの発作が収まると顔を上げた。
「この娘は間違いなく我々が探し求めていた〝約束の子〟だ」
「それ何?」
誰もそれには答えてくれなかった。
カートは忌々しげにミラを睨むと出ていってしまった。
四
シーアスも消えた。
文字どおりミラの目の前から掻き消すように見えなくなったのだ。
ミラはシーアスがいなくなると張り番の一人の方を向いた。
「ね、あいつ何者? 信者でも聖職者でもないって言ってたわよね?」
見張り達は顔を見合わせた。
目顔で答えるかどうか相談している。
「……ヘルティスだと聞いています」
監視の言葉遣いが丁寧になっていた。
さっきのシーアスの台詞のせいだろう。
「ヘルティスって?」
見張りは無知を蔑むような目でミラを見た。
「神の使いです」
「神の使い~? それってアスラル教の神徒と同じものよね? 天使って言ったっけ」
「そう、です」
今までぞんざいだった分、言いにくそうだった。
「ホントにそれ信じてるの?」
「今、消えるのを見たでしょう」
「消えただけで信じちゃうわけ? 魔法が使えれば出来るわよ、あのくらい」
あんな魔法を見るのは初めてだが理論上は可能なはずだ。
「やるなよ。いや、やらないで下さい。やったらあの親子を殺します」
「やらないわよ。けど……」
「なんですか」
「あいつはあんた達が思ってるようなもんじゃないわよ」
「知り合いではないと言ったではないですか」
「分かるのよ」
見張りは肩を竦めただけだった。
ミラはちょっと考えてから再度見張りに話し掛けた。
「ね、悪い事した人は神の国へは行けないんでしょ。誘拐なんかしたら死んだあと間違いなく地獄行きよ」
ミラの言葉に監視達が笑い出した。
「何がおかしいのよ」
「神の国とはあの世の事ではありません」
「じゃあ、何?」
「神の国とはこの世が滅びた後の世界です」
「……よく分かんないんだけど、あんた達、世界が滅びるの待ってるわけ?」
「そうです」
「この世を滅ぼしたいほどのどんな不満があるのよ」
「不満があるとかないとかではありません。神の国は完全な世界なのです」
「後ろ向きな宗教ね」
「あなたも今に分かります」
「分かりたくないわよ」
ミラがそう言った時、シーアスが戻ってきた。
消えた時と同様いきなり現れたのだ。
「君の片割れが来たようだ」
「私、双子じゃないわよ」
言い終わる前に外が騒がしくなった。
見張り達が身構える。
「心配するな。もう一人の約束の子が来ただけだ」
シーアスの言葉に見張りは緊張を解くと顔を見合わせた。
ミラと扉を交互に見比べる。
好奇心と神の国を秤に掛けているのだろう。
監視の一人は好奇心が勝った。
戸口に歩み寄ると扉を開ける。
ミラも行こうとして、もう一人の張り番に阻まれた。
「覗くくらい良いじゃない」
「どうせすぐにカートがここへ連れてくる」
シーアスが言い終える前に見張りが慌てて扉を閉めた。
複数の足音が近付いてくる。
足音は部屋の前で止まった。
扉が開くと同時にカイルが飛び込んできた。
「ミラ! 無事だった?」
「言ったでしょう。何もしてませんよ」
カイルはカートの言葉を無視してミラの側に来た。
カイルはハイラル教の上等そうな紫色の聖衣を着ている。
ミラの方は染色すらされていない生成りの服だ。
「カイル……」
ミラはカイルの顔を見詰めた。
「……助けに来てくれたんじゃないのね」
「うん、ごめん。捕まっちゃった。それに……」
言い掛けて周りの男達を見回した。
シーアスと眼があったカイルは眉を顰めた。
あいつ、人間じゃないな……。
「カート、しばらく外してやれ。そいつらもな」
「しかし……」
「俺が残る」
ミラは露骨に嫌そうな顔をしたが、カートを始めとした男達は出ていってしまった。
三人だけになってしまうとミラはカイルを連れて椅子に座っている男から一番離れた場所へ移動した。
しがみつくようにカイルの聖衣を握りしめている。
「ミラ、あいつに何かされたの?」
「されそうになったのよ。それより、なんであんたがこんなとこにいるの?」
「なんでって……」
「ここ、レラスからかなり離れてるでしょ。どうやってここまで来たの? あいつらに連れてこられたの?」
「ミラがハイラル教徒と一緒にいたって話を聞いて攫われたんだんじゃないかと思ったんだ」
そこまで言ったところで部屋の反対側からこちらを見ている男を一瞥した。
薄笑いを浮かべてこちらを見ている。
「もしかしたらアイオンのやつと関係あるのかなって思ってリキア方面に行こうとしたんだ」
二人がアイオンで封印獣を倒した時、ミラはアスラル神官を装ったハイラル教徒に攫われそうになった。
そしてカイルが予想した次に封印獣が現れる場所がリキアかローク、ファイユである。
三ヶ所は同じ方角だからとりあえず一番近いリキアに向かっていてハイラル教徒に捕まったのだ。
「聞いていい?」
「うん」
「それ、ラースも知ってる?」
「実はそれを今言おうとしてたんだ」
カイルは男を気にしながらもミラがいなくなってからの事を話し始めた。
捜索が打ち切られた後、カイルは執務室に呼び出された。
そこからラースに連れて行かれたのは神殿の奥にある半地下の部屋だった。
「すまない、カイル。ミラが戻ってくるまでここにいてくれないか?」
頼んでいるようだがこれは命令だった。
「僕もミラを捜しに行ってはいけないんですか?」
「……すまない」
ラースはもう一度カイルに謝った。
辛そうなラースの顔を見たらそれ以上は逆らえなかった。
「分かりました」
入口に中級神官が二人、部屋に背を向けて立っているのが見えた。
見張りか……。
「悪いな。欲しいものはなんでも持ってこさせるからしばらく我慢してくれ」
「はい」
ラースが出ていくと当然ながら鍵が掛けられた。
一、二、三。
鍵を掛ける音は三回した。
三重に鍵が掛けられらのだ。
訳が分からなかった。
殺されるなら分かる。
カイルは処刑されるだけの罪を犯して殺されるところをラースに助けられた。
今はラース――というかレラスのアスラル神殿――が身柄を預かるという形を取っているだけで罪が許されたわけではない。
罪状はそのまま残っているから、いつそれを理由に処刑されてもおかしくないのだ。
けれど何故閉じこめられるのか分からない。
カイルは部屋を見回した。
室内はカイルの自室と大して変わらなかった。
ベッドと机があるだけの飾り気のない簡素な部屋である。
強いていえば僅かに狭い。
それに机の上に積まれた本の山も無かった。
教典だけはしっかり置いてあったがカイルの物ではない。
窓には布が掛かっていた。
一見幕のように偽装してあるが外が見えないようになっている。
少しでも外が見えないかと布を軽く引っ張ってみた。
布を触った時、固い物が手に触れた。
布と布の間に格子があるのだ。
外からも格子が見えないようになってるのか……。
布を引くと端が僅かに開いた。
破れている。
というか前に誰かが破ったのを後から打ち付け直したのだろう。
カイルの前にこの部屋に入れられた者が何人いるかは知らない。
だが、ここを抜け出した人間は一人だけのはずだ。
カイルはベッドに座りながら戸口の方を窺った。
扉の上と下には小さな窓が付いている。
下は食事を差し入れるため、上は覗き窓だ。
覗くのは当然ながらカイルの方ではなく見張りの方である。
「セルケト教にあったって言うの?」
「うん」
「セルケト教徒がいるのはここよりずっと北の方じゃない」
「そうだけど、ハイラル教がこの大陸に伝来するまで一番信者が多かったのはセルケト教だったんだよ。当然この辺もセルケト教の勢力範囲だったしハイラル教もかなり影響受けてるよ」
「ふうん……それで?」
「セルケト教の神儀書に出てくる聖獣の中に僕らが倒したのと対応するのがいたんだ」
神儀書というのはアスラル教で言うところの教典、ハイラル教での聖典に当たるもので、神話や教えなどが書いてある本だ。
カイルは地図をテーブルの上に開いた。
ヘメラ、ケナイ、アイオンの順に指す。
「神儀書に出ていた聖獣は全部で八匹。順番も僕らが倒したのと同じなんだ。だから間違いないと思うんだけど、どうかな」
ミラが肩を竦める。
一瞬、頭に血が上り掛けたが、すぐに今のが「どうでもいい」という態度の現れではなく「自分には分からない」という意味だと悟る。
カイルは気を取り直して地図を指した。
「もし、あってるなら次はこの辺なんだ。リキアかロークか、ちょっとズレるけどファイユ」
「私が分かんないのはそれがなんなのかってことよ」
「それは……僕も分からない。けど、セルケト教ではそいつらの事〝世界の守護者〟って言うんだ」
「だから?」
「気になんない?」
「よく分かんない」
ミラの言葉にカイルは返答に詰まった。
カイルもなんと説明すればよいのか分からない。
考え込んでいるうちにいつの間にか眠り込んでしまっていた。
目が覚めてみるとミラの姿が無かった。
神官長が一人で事務処理をしている。
まさか、また神殿を抜け出したんじゃ……。
カイルはミラを探しに出た。
ミラは神殿の裏にいた。
カイルが裏口から出た時、十歳くらいの女の子と話していたミラが踵を返したところだった。
町に向かおうとしているらしい。
「ミラ、どこ行くの! 謹慎が解けてもいないうちから抜け出す気!?」
「ちょっとだけよ。この子のお母さんが大変なんだって」
「なに言って……」
「すぐ戻るからラースには黙ってて」
「ミラ!」
ミラはカイルが捕まえるより早く駆けていってしまった。
追い掛けようとした時、
「リース、どうしたの? こんなところで」
女の子がミラの後に続こうとした時、マイラの声が降ってきた。
見上げるとマイラが神殿の窓から身を乗り出している。
ミラに会いに来た女の子に声を掛けたのだ。
ミラを追い掛けようとしていた女の子――リースがマイラの方を振り向いた。
「その……」
「皆元気にしてる?」
「うん、あの、早く行かないと……」
「そう、それじゃ。あたしの母さんに会ったら元気にしてるって伝えといて」
「うん」
リースはミラの跡を追うようにして走っていった。
マイラの母さん?
「マイラ!」
カイルはマイラを呼び止めた。
マイラが振り返る。
「なんですか?」
「今の子、ケナイに住んでるの?」
「はい」
「そう、ありがとう」
マイラが行ってしまうとカイルは憤然としながら神殿へ入った。
ケナイの子がミラに会いに来た。
という事はこの前の話は嘘だったのだ。
……ったく!
言いたくないなら言わなくていいって言ったのに!
何も嘘吐く事ないじゃないか!
腹が立っていたカイルは思わず執務室の扉を乱暴に開けてしまった。
その途端、机に向かって書類を書いていたラースと目が合った。
「カイル、またミラと喧嘩したのか?」
ラースが苦笑いを浮かべた。
「確か仲良くしてくれる約束だったはずだが」
「す、すみません。けど、喧嘩はしてません」
嘘ではない。
「そうか。なら、どうしたんだい?」
「……え、あ、その……ミラがケナイ山を吹き飛ばした犯人に……」
「ああ、その話か。仕方なかったんだよ」
「え……?」
「慣れすぎてしまったんだ」
「慣れ?」
ラースの言っている意味が分からず首を傾げた。
「ミラは神官の真似事をしていたとは言え、基本的には居るだけで豊穣をもたらすし、災いに見舞われる事も無い」
いつからかミラのお陰だという事を忘れてしまったのだ。
そして錯覚した。
ミラが居なくても同じ状態が続くだろうと。
「それで逆にミラの力が怖くなったんだ」
ミラへのお礼として持ってきたものは全て村の人間達が受け取っていてミラには渡していなかった。
もしバレたらミラが腹を立てるのではないか。
その時ミラの力を自分達に向けられたら……。
ケナイ山の魔物が吹き飛んだ事が決定打になり村の者達はミラを犯人として警備兵に突き出した。
後ろ暗いところがあったのだとしたら尚更恐怖を覚えただろう。
もしかしたらミラに頼みに来る人達に高価な謝礼を吹っ掛けていたのかもしれない。
最近依頼人が減っていた。
謝礼が手に入らなくなり、豊穣は続いている。
それでミラが自分達に牙を剥く前に始末しようと考えたのだろう。
「ホントの話だったんですか? だって、それじゃあ……」
「どうかしたのか?」
ラースの問いにカイルは神殿の裏での事を話した。
二
ミラは神殿から離れた森の奥にいた。
目の前に数人の男が立っている。
その後ろにはリースと呼ばれた女の子とその母親が男達に捕まっていた。
「ったく、ハイラル教ってのはいつから犯罪集団になったのよ。教祖様が泣くわよ」
「我々に教祖などいない」
「じゃ、ハイラルってのは誰よ」
「軽々しく我々の救世主の名を口にするのはやめてもらおうか。知りたければあの世で勉強したまえ」
「アスラル教にあの世なんかないわよ」
「無駄口はいい。とっととやれ!」
リーダーらしい初老の男が命令した。
直線的で無駄のない紫色の服はしわ一つない。
ハイラル教の聖衣である。
聖衣を着ているのは初老の男だけだ。
他の男達は信者らしい。
剣を持った男がミラに向き直る。
「下手な真似はするなよ。魔法は防げなくても、あの二人を道連れにする事くらいは出来るんだからな」
「分かったわよ。その代わりその二人を放しなさいよ」
「お前が死んだらな」
「死んだら、あんた達が約束守ったかどうか分からないじゃない」
「それは信用してもらうしかないな」
「こんな事する連中、信じられると思ってんの?」
「なら、この二人を見捨てて逃げるか?」
「ったく」
ミラが男を睨み付けた。
「悪く思うなよ」
「思うわよ!」
ミラが言い返す。
男が剣を振り上げた。
「待て!」
全員が一斉に声の方を向く。
木の陰から青年が出てきた。
優男風の青年だが赤い瞳には感情が無い。
見た瞬間、ミラの全身が総毛立った。
こいつ……。
見た目は人間だが人ではない。
青年を見たミラが身構える。
「その娘を殺したら連中はあいつを生かしてはおかないだろうが。少しは考えろ」
青年はそう言うとミラの方に向き直った。
「久し振りだね」
「たった今助けてくれた相手にこんなこと言うのもなんだけど、初対面よ」
「何度も会ってるんだよ。最近だと千年前に」
「私が千歳越えてるように見えるわけ?」
男の顔に笑みが広がった。
本気で面白がっているらしい。
「確かに。改めて自己紹介しないといけないな。私の名はシーアス」
ミラはシーアスの差し出した手を無視した。
シーアスは愛想笑いを浮かべてミラの手を取る。
本能的に恐怖を覚えて慌てて手を振り払った。
「馴れ馴れしく触んないでよ!」
「シーアス様!」
初老の男がシーアスに呼び掛けた。
声がかなり苛立っているのはミラが目障りだからだろうか。
ハイラル教徒にとって異教徒は悪魔の手先である。
まして異教の神官など悪魔そのもの以外の何者でもない。
ミラを早く殺してしまいたいのだろう。
「なんだ、カート」
カートというのが初老の男の名前らしい。
役職名でなければ、だが。
アスラル教の事すらよく知らないミラに他の教団の事は全く分からない。
「その女は契約の妨げになります。前回邪魔をしたのはその女だと仰ったのはあなたではないですか!」
「バカだな。この娘がいればあいつが殺されても契約は遂行できる。それとも、もう千年待ちたいのか?」
カートが苦々しげに顔を歪める。
その時、いきなり地面が波打ち始めた。
地震の不意打ちに全員が地面に投げ出される。
リースと母親が男達の手から放れた。
ミラは地震が終わると同時に立ち上がってリース達に駆け寄った。
男達も起き上がると取り押さえようと向かってくる。
ミラは突風を巻き起こした。
男達が吹き飛ばされる。
「大丈夫? 逃げ……」
「はい、そこまで」
最後まで言う前にシーアスが背後からミラの肩に両手を置いた。
「この!」
ミラは背中を向けたままシーアスに風を叩き付けた。
が、シーアスは何事も無かったように肩に手を置いていた。
普通の人間なら挽き肉より細かくなっているはずだ。
ミラが眉を顰めて振り返った。
シーアスが涼しい顔で微笑み掛けてくる。
「邪魔しないでよ!」
もう一度手加減なしで魔法を使った。
やはりシーアスには通じない。
その間に男達はリースと母親を取り押さえてしまった。
「それなら……」
ミラはシーアスに回し蹴りを放った。
シーアスがミラから手を離して蹴りを避ける。
その隙にミラはリース達の方へ駆け出そうとした。
が、次の瞬間には後ろからシーアスに抱き締められていた。
ミラの顔から血の気が引く。
「ちょ、ちょっと! 何するのよ! 放してよ!」
「君に逃げられたら困るんでね」
「だからって……どこ触ってるのよ! 嫌らしいわね!」
ミラは必死で暴れたがシーアスの腕から逃れることは出来なかった。
ハイラル教の男達は呆気に取られた様子でミラとシーアスを見ていた。
カートは思い切り顔を顰めている。
ミラがカートを睨み付けた。
「サイテー! あんた達いつもこんな嫌らしい真似してるの!?」
「ち、違う! そいつは信者でも聖職者でもない!」
カートは慌てて手を振った。
動揺していて敬語を忘れている。
ハイラル教の聖職者は妻帯禁止である。
その上、子供のうちから神殿に入れられて異性と接触する事なく育つ者も少なくない。
子供の頃から神殿で生活している者にとっては人前で異性を抱き締めることさえ不埒なのだ。
それでもシーアスを止めようとはしなかった。
「じゃあなんなのよ! 見てないでなんとかしなさいよ!」
ミラはカート以上に動転していた。
半分泣き声になっていた。
父親にさえ抱き締められた事などないのだ。
赤ん坊の時の事は覚えてないが。
しかしシーアスはミラの涙声にも心を動かされた様子はなかった。
「君が逃げようとしている間はダメだね」
楽しんでいるとしか思えない声が耳元で聞こえた。
ミラの背筋を悪寒が走る。
「分かった! 逃げない! 逃げないから放して!」
ミラが必死で藻掻きながら言った。
「ホントに? 俺はずっとこのままでも構わないんだけど」
「私は構うの! 放してよ!」
「……シーアス様、こう申してますしアスラル神官は嘘を吐きませんから」
異教徒への憎悪よりシーアスの行為への嫌悪の方が僅かに勝ったようだ。
カートの声にはシーアスを咎めるような響きがあった。
シーアスが残念そうに溜息を吐いて手を離した。
その息が首筋に触れてミラは身震いした。
三
「あの方の事は……」
「この娘を餌にして呼び出せ」
「はい……それで、その女は」
「無論、連れていく。あいつにもしもの事があったらこの娘にやってもらわなければならないからな」
「そうですか」
カートの残念そうな表情はミラを殺せない事によるものか、それともシーアスの態度に対する懸念によるものか……。
カイルの話が終わる前にラースは神殿中の神官にミラの捜索を命じた。
神殿長はおろか神官長にすら許可を求めなかった。
にも関わらず神殿長も神官長も咎めようとしないどころか、むしろ当然のような顔をしていた。
「ミラに何かあったと思うんですか?」
カイルの問いにラースは安心させるように微笑んだ。
「大丈夫。魔法が使えるんだ。滅多な事は無いだろう」
「お言葉を返すようですけど、ミラって使える魔法の種類が少ないって言うか……」
言い辛くてつい眼を伏せてしまった。
ミラの魔法を貶すのは彼女に教えてるラースを非難する事でもある。
ラースが苦笑した。
「確かに、聖句はまるっきり覚えてないな」
ラースの言葉にカイルの方が慌てた。
「別に、まるっきりなんて、そんな……」
「本当に全然知らないんだよ。唯一覚えたテル・ルーズの聖句も間違ってるんだ。一度言わせてみれば分かるよ」
ラースは事も無げに言った。
カイルは呆気に取られてラースを見上げた。
「確かに黙って使ってますけど……聖句を知らなくても使えるものなんですか?」
少なくともカイルは回復と障壁以外の神聖魔法は聖句を唱えないと使えない。
「魔法は願望の具現化だ。基本的に術者が望めばそれで十分なんだ」
「それは知ってますけど」
それでもラースですら魔法を使う時は聖句を唱えている。
「聖句って言うのは初心者の為にあるんだよ。例えばテル・ルーズは魔法で火の玉を出すものだが最初は上手く想像したものを具現化出来ない。そこで聖句が必要になってくるんだ。聖句の言葉は具体的だろう」
確かに聖句は具現化される現象を具体的に言っているし、初歩的なものほどその状態になるまでの過程が詳しく形容している。
「けど……それじゃ、ミラはどうやって魔法を覚えたんですか?」
「見れば真似出来るから目の前で実演したんだ」
「それならなんであんなに種類が少ないんですか?」
カイルの質問にラースが肩を落とした。
調子に乗って余計な事を……!
カイルはすぐに言った事を後悔した。
「一応、私が知ってる限りの魔法を全部やって見せたんだが……」
ラースに使える魔法があれだけのはずがない。
ラースはセネフィシャルである。
セネフィシャルとは神に不貞を働く輩に懲罰を与える役割を担っている神徒だ。
当然その名を冠した神官も攻撃魔法に熟達した者が就く。
ラースの答えはカイルの予想通りだった。
「覚えられなかったんだ……派手で印象に残りやすいもの以外……」
カイルはミラに魔法の指導をしなければならないラースに心底同情した。
そのうち下級神官の一人が「ミラがハイラル教徒と一緒にいるところを町の人間が見た」という報告を持ってきた。
ラースはそれを聞くと捜索を打ち切った。
五日後、ミラはハイラル教徒の家と思しき建物の一室に閉じこめられていた。
昨日まではずっと移動ばかりで馬車の中で寝泊まりさせられていた。
夕辺ようやく個室のベッドで寝る事が出来たのだ。
当初、シーアスが不埒な振る舞いに及んだら、と思うと気が気ではなかった。
が、カートも同じ疑念を抱いていたらしい。
流石に悪事を働いていても聖職者である。
常時見張りを付ける事によって防いでくれた。
単に逃げられたら困るというのもあったのだろうが。
しかし常に張り付いていたのは監視だけではない。
見張りの隙を突こうとしたのかどうかは定かではないが、とにかくシーアスも一日中ミラの側にいた。
「君も懲りないね」
シーアスが愉快そうに笑った。
椅子に反対向きに座り、背もたれに両腕を乗せている。
見張りへの泣き落としを言ったのだ。
捕まって以来、ミラは見張りに対して宥めたり賺したりと色々試みていた。
一番沢山試したのが泣き落としである。
しかし最初に魔法で吹き飛ばしてしまったことを根に持っているのか、誰一人心を動かされてはくれなかった。
リース達が捕まっている限り逃げ出せない。
なんとか彼らの方からリース親子ともども解放してくれるように仕向けたいのだが……。
「ね、お願い。こんな事、ホントはしたくないんでしょ。人質取ったり、誘拐したりするなんてハイラル教でだって悪い事のはずよ」
しかし見張りはミラの顔を無表情に見返すだけだった。
「確かにハイラルの教えではない」
カートが入ってくるなり言った。
「じゃあ……」
「君達現世利益の教団の人間には分からないかもしれないが我々にとって神の国へ行けるかどうかは大問題なんだ」
「そんなの私には関係ないでしょ」
カートは聞いていなかった。
「神の国では病も争いもなく、身分の上下もない」
「結構ね。異教徒を巻き込まないでくれるなら」
「人間は花の蜜だけで生きていけるようになり、狼も草を食べるようになる」
「狼が羊を食べるのが悪い事ならなんで神様はそういう風に造ったのよ」
「神の国が到来した時――」
カートは辛抱強く説教を続けた。
流石聖職者である。
「我々は三千年もの間、神の国が到来するのを待ち続けてきたのだ」
「時間を無駄にしたわね。ハイラル教徒の人数と影響力を使って世界をより良く変えるように努力してれば神の国なんか待たなくたってこの世は住み易くなってたわよ」
ミラがそう言った途端シーアスが弾かれたように笑い出した。
「何がおかしいのよ!」
「何がおかしいんですか!」
ミラとカートが同時に言った。
シーアスはしばらく笑い続けた。
やがて笑いの発作が収まると顔を上げた。
「この娘は間違いなく我々が探し求めていた〝約束の子〟だ」
「それ何?」
誰もそれには答えてくれなかった。
カートは忌々しげにミラを睨むと出ていってしまった。
四
シーアスも消えた。
文字どおりミラの目の前から掻き消すように見えなくなったのだ。
ミラはシーアスがいなくなると張り番の一人の方を向いた。
「ね、あいつ何者? 信者でも聖職者でもないって言ってたわよね?」
見張り達は顔を見合わせた。
目顔で答えるかどうか相談している。
「……ヘルティスだと聞いています」
監視の言葉遣いが丁寧になっていた。
さっきのシーアスの台詞のせいだろう。
「ヘルティスって?」
見張りは無知を蔑むような目でミラを見た。
「神の使いです」
「神の使い~? それってアスラル教の神徒と同じものよね? 天使って言ったっけ」
「そう、です」
今までぞんざいだった分、言いにくそうだった。
「ホントにそれ信じてるの?」
「今、消えるのを見たでしょう」
「消えただけで信じちゃうわけ? 魔法が使えれば出来るわよ、あのくらい」
あんな魔法を見るのは初めてだが理論上は可能なはずだ。
「やるなよ。いや、やらないで下さい。やったらあの親子を殺します」
「やらないわよ。けど……」
「なんですか」
「あいつはあんた達が思ってるようなもんじゃないわよ」
「知り合いではないと言ったではないですか」
「分かるのよ」
見張りは肩を竦めただけだった。
ミラはちょっと考えてから再度見張りに話し掛けた。
「ね、悪い事した人は神の国へは行けないんでしょ。誘拐なんかしたら死んだあと間違いなく地獄行きよ」
ミラの言葉に監視達が笑い出した。
「何がおかしいのよ」
「神の国とはあの世の事ではありません」
「じゃあ、何?」
「神の国とはこの世が滅びた後の世界です」
「……よく分かんないんだけど、あんた達、世界が滅びるの待ってるわけ?」
「そうです」
「この世を滅ぼしたいほどのどんな不満があるのよ」
「不満があるとかないとかではありません。神の国は完全な世界なのです」
「後ろ向きな宗教ね」
「あなたも今に分かります」
「分かりたくないわよ」
ミラがそう言った時、シーアスが戻ってきた。
消えた時と同様いきなり現れたのだ。
「君の片割れが来たようだ」
「私、双子じゃないわよ」
言い終わる前に外が騒がしくなった。
見張り達が身構える。
「心配するな。もう一人の約束の子が来ただけだ」
シーアスの言葉に見張りは緊張を解くと顔を見合わせた。
ミラと扉を交互に見比べる。
好奇心と神の国を秤に掛けているのだろう。
監視の一人は好奇心が勝った。
戸口に歩み寄ると扉を開ける。
ミラも行こうとして、もう一人の張り番に阻まれた。
「覗くくらい良いじゃない」
「どうせすぐにカートがここへ連れてくる」
シーアスが言い終える前に見張りが慌てて扉を閉めた。
複数の足音が近付いてくる。
足音は部屋の前で止まった。
扉が開くと同時にカイルが飛び込んできた。
「ミラ! 無事だった?」
「言ったでしょう。何もしてませんよ」
カイルはカートの言葉を無視してミラの側に来た。
カイルはハイラル教の上等そうな紫色の聖衣を着ている。
ミラの方は染色すらされていない生成りの服だ。
「カイル……」
ミラはカイルの顔を見詰めた。
「……助けに来てくれたんじゃないのね」
「うん、ごめん。捕まっちゃった。それに……」
言い掛けて周りの男達を見回した。
シーアスと眼があったカイルは眉を顰めた。
あいつ、人間じゃないな……。
「カート、しばらく外してやれ。そいつらもな」
「しかし……」
「俺が残る」
ミラは露骨に嫌そうな顔をしたが、カートを始めとした男達は出ていってしまった。
三人だけになってしまうとミラはカイルを連れて椅子に座っている男から一番離れた場所へ移動した。
しがみつくようにカイルの聖衣を握りしめている。
「ミラ、あいつに何かされたの?」
「されそうになったのよ。それより、なんであんたがこんなとこにいるの?」
「なんでって……」
「ここ、レラスからかなり離れてるでしょ。どうやってここまで来たの? あいつらに連れてこられたの?」
「ミラがハイラル教徒と一緒にいたって話を聞いて攫われたんだんじゃないかと思ったんだ」
そこまで言ったところで部屋の反対側からこちらを見ている男を一瞥した。
薄笑いを浮かべてこちらを見ている。
「もしかしたらアイオンのやつと関係あるのかなって思ってリキア方面に行こうとしたんだ」
二人がアイオンで封印獣を倒した時、ミラはアスラル神官を装ったハイラル教徒に攫われそうになった。
そしてカイルが予想した次に封印獣が現れる場所がリキアかローク、ファイユである。
三ヶ所は同じ方角だからとりあえず一番近いリキアに向かっていてハイラル教徒に捕まったのだ。
「聞いていい?」
「うん」
「それ、ラースも知ってる?」
「実はそれを今言おうとしてたんだ」
カイルは男を気にしながらもミラがいなくなってからの事を話し始めた。
捜索が打ち切られた後、カイルは執務室に呼び出された。
そこからラースに連れて行かれたのは神殿の奥にある半地下の部屋だった。
「すまない、カイル。ミラが戻ってくるまでここにいてくれないか?」
頼んでいるようだがこれは命令だった。
「僕もミラを捜しに行ってはいけないんですか?」
「……すまない」
ラースはもう一度カイルに謝った。
辛そうなラースの顔を見たらそれ以上は逆らえなかった。
「分かりました」
入口に中級神官が二人、部屋に背を向けて立っているのが見えた。
見張りか……。
「悪いな。欲しいものはなんでも持ってこさせるからしばらく我慢してくれ」
「はい」
ラースが出ていくと当然ながら鍵が掛けられた。
一、二、三。
鍵を掛ける音は三回した。
三重に鍵が掛けられらのだ。
訳が分からなかった。
殺されるなら分かる。
カイルは処刑されるだけの罪を犯して殺されるところをラースに助けられた。
今はラース――というかレラスのアスラル神殿――が身柄を預かるという形を取っているだけで罪が許されたわけではない。
罪状はそのまま残っているから、いつそれを理由に処刑されてもおかしくないのだ。
けれど何故閉じこめられるのか分からない。
カイルは部屋を見回した。
室内はカイルの自室と大して変わらなかった。
ベッドと机があるだけの飾り気のない簡素な部屋である。
強いていえば僅かに狭い。
それに机の上に積まれた本の山も無かった。
教典だけはしっかり置いてあったがカイルの物ではない。
窓には布が掛かっていた。
一見幕のように偽装してあるが外が見えないようになっている。
少しでも外が見えないかと布を軽く引っ張ってみた。
布を触った時、固い物が手に触れた。
布と布の間に格子があるのだ。
外からも格子が見えないようになってるのか……。
布を引くと端が僅かに開いた。
破れている。
というか前に誰かが破ったのを後から打ち付け直したのだろう。
カイルの前にこの部屋に入れられた者が何人いるかは知らない。
だが、ここを抜け出した人間は一人だけのはずだ。
カイルはベッドに座りながら戸口の方を窺った。
扉の上と下には小さな窓が付いている。
下は食事を差し入れるため、上は覗き窓だ。
覗くのは当然ながらカイルの方ではなく見張りの方である。