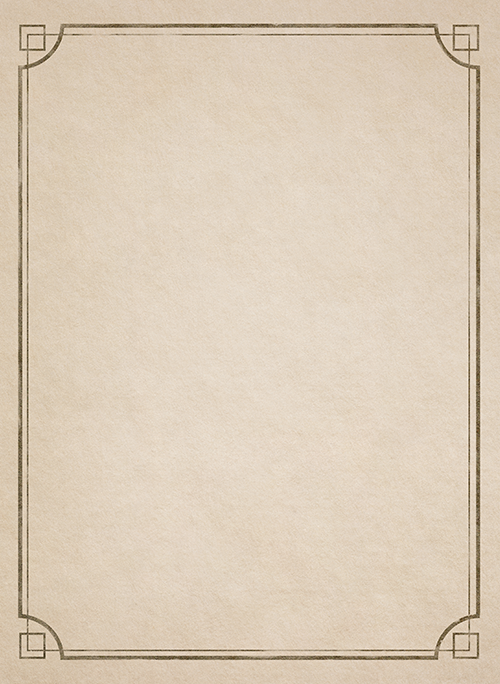しかも休日には、時間を作って会うようになった。
相手は元々、男性的な部分の強い性格をしていたから、会話は弾んだ。その頃には、向こうも僕の気持ちに気づいていたに違いない。だから告白をした時、即答で「はい」と答えたのだ。
元々仲の良い友人同士だったが、一度関係性が恋人に変わるとどうにも調子が狂った。目の前にいるのは、片思いをしている友人ではなく、僕の恋人なのだ。そう思えば、何をするにも照れ臭く、歯痒かった。情けない僕を引っ張るかのようにしてあれこれ振り回したのが彼女だった。
それまで通りの接し方をしていると思えば、二人きりになると手を繋いでくる。そんな事が度々あって、相手の女性的な部分が表面に出てくる度に、僕の心臓は破裂しそうになった。
今、僕のいるこの島に行こうと言い出したのも夏海だった。理由を尋ねてもはぐらかされるだけで、僕も行けばわかるだろうと深く追求はしなかった。
彼女は事故に遭い死んでしまった。どうしてこの島なのかという理由はついにわからないままだ。
「知りたいんです」
窓の外を眺めながらそう溢した僕に、男は「知りたい? 何をですか?」と続きを促す。
「どうして、ここを行き先に選んだのか。実際に見てみれば、何かわかるかもって思ったんです。何を考えているのか分からない人でしたから、こうでもしないときっと、理解できないと思うんです」
「なるほど、理由ですか……」
男が呟いたのと同時に、バスが停車した。信号のせいかと思ったが、ドアが開いたので停留所が理由だとわかった。
僕の隣にいた男は、席を立った。
「僕はここで降ります。彼女さんの思いが、わかるといいですね」
優しい笑顔だった。心の底から思ってくれているというのが伝わってくる。
「すみませんでした。せっかくの旅行を邪魔するような話をしてしまって」
「こちらだって浮かれ過ぎてたんですよ。事情を察して、話しかけないようにする事だってできたはずなんです。いつも、周りからはピントがズレてるなんて言われるんですよ。だからこうして、南の島にマフラーだって持ってくるんです」
男は手にしたマフラーを僕に見せる。
「でも、今の時期は寒いですし、対策するのは良い事ですよ」
「思ってたよりずっと暑いのでもう出番はないでしょうが、そう言っていただけると嬉しいです。じゃあ、僕はこれで」
相手は元々、男性的な部分の強い性格をしていたから、会話は弾んだ。その頃には、向こうも僕の気持ちに気づいていたに違いない。だから告白をした時、即答で「はい」と答えたのだ。
元々仲の良い友人同士だったが、一度関係性が恋人に変わるとどうにも調子が狂った。目の前にいるのは、片思いをしている友人ではなく、僕の恋人なのだ。そう思えば、何をするにも照れ臭く、歯痒かった。情けない僕を引っ張るかのようにしてあれこれ振り回したのが彼女だった。
それまで通りの接し方をしていると思えば、二人きりになると手を繋いでくる。そんな事が度々あって、相手の女性的な部分が表面に出てくる度に、僕の心臓は破裂しそうになった。
今、僕のいるこの島に行こうと言い出したのも夏海だった。理由を尋ねてもはぐらかされるだけで、僕も行けばわかるだろうと深く追求はしなかった。
彼女は事故に遭い死んでしまった。どうしてこの島なのかという理由はついにわからないままだ。
「知りたいんです」
窓の外を眺めながらそう溢した僕に、男は「知りたい? 何をですか?」と続きを促す。
「どうして、ここを行き先に選んだのか。実際に見てみれば、何かわかるかもって思ったんです。何を考えているのか分からない人でしたから、こうでもしないときっと、理解できないと思うんです」
「なるほど、理由ですか……」
男が呟いたのと同時に、バスが停車した。信号のせいかと思ったが、ドアが開いたので停留所が理由だとわかった。
僕の隣にいた男は、席を立った。
「僕はここで降ります。彼女さんの思いが、わかるといいですね」
優しい笑顔だった。心の底から思ってくれているというのが伝わってくる。
「すみませんでした。せっかくの旅行を邪魔するような話をしてしまって」
「こちらだって浮かれ過ぎてたんですよ。事情を察して、話しかけないようにする事だってできたはずなんです。いつも、周りからはピントがズレてるなんて言われるんですよ。だからこうして、南の島にマフラーだって持ってくるんです」
男は手にしたマフラーを僕に見せる。
「でも、今の時期は寒いですし、対策するのは良い事ですよ」
「思ってたよりずっと暑いのでもう出番はないでしょうが、そう言っていただけると嬉しいです。じゃあ、僕はこれで」