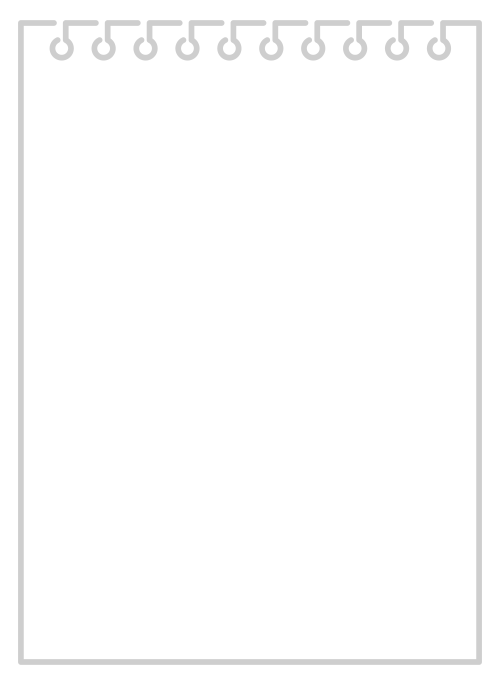ーーー
九条は、遠い儚い記憶の底に沈んだ。
夜ごはんの匂いが鼻をくすぐって、嬉しくなって手に持っているそれを鳴らした。
夕方の6時、テレビの前に待ち構えて大好きな音楽が耳に入ってくる。体を揺らしながら弾んだ声を出す。
「ばあちゃん始まる!」
アニメのオープニング曲が始まると、決まって夜ごはんを作っている最中の祖母を呼んだ。
台所に立っている祖母が優しく微笑んで、エプロンで手を拭きながらこちらに歩いてきた。
「なぎくんは、本当にこの曲が好きね」
「うん!」
隣に座った祖母。母は夜遅くまで働きに出ており小さい頃の面倒は主に祖母が見ていた。
『なぎくん』とそう呼ばれていた。その優しい声をきかなくなったのはいつの頃だったか。
宝物だったタンバリンを手に持って、隣にいる祖母と大好きなアニメ。
幸せがぎゅっとつまっていた空間だ。
いつもアニメが始まれば、オープニングを祖母と2人できいて、そして祖母は
「お腹空いたでしょ、なぎくん」
そう言う。
その言葉に大きく頷けば、祖母は暖かい手で九条の頭を撫でる。
祖母のおかげで寂しくはなかった。そして、早くに祖父を亡くしてしまった祖母の寂しさを埋める役割を自分が担っているような気がしていた。
九条が小学生から中学生、高校生と成長していくとともに祖母との距離ができていく。
それでも大切で、大好きな存在なのは変わらない。
ただ、自らの感情を吐き出すことは少なくなった。
虚勢を張るように髪の毛を金髪に染め、外では喧嘩を売られるようになって、負けたくないからとやり返す日々。自らが思い描いていた幸せがどんどん遠ざかっていく。
「おばあちゃんといろいろ相談したんだけど、おばあちゃん施設に行くことにしたの」
母がそう言った。
確かに仕事で忙しい母が祖母の面倒を見られるとは思わなかったが、少し無責任なような気もして怒りをおぼえたが、ブーメランのように九条自身も刺さる気がしたので言葉には出さなかった。
「誰よ、あんた」
最初九条にそう言った祖母の顔は九条の脳裏に焼きついたままである。
施設に顔を出せば、いつからか祖母は九条のことが分からなくなっていた。いつも九条が施設に顔を出せば怪訝な顔をする。
祖母自身のせいではないと分かっていた。
分かっていたが、大切な人に忘れられることがこんなにつらいことというのは分からなかった。
どうにかして自分のことを思い出してほしいと願って歌った思い出の曲は、
「うるさいって言ってるでしょ!!」
サビにも入らずあっけなく散った。
「大切な人だからこそ、その人が聴いていた音楽も知りたいと思わないか」
音代から言われた言葉が頭に響く。
九条は率直に知りたいと思った。
九条と同じように、祖母にも大切な音楽の記憶があるはずだ。
「ん」
紙の上に頬を乗せいつの間に寝ていた九条は、顔上げた時頬に紙がへばりついており、それを寝ぼけ眼でぺらりと剥がす。
「珍しいわね、そんなところで寝るなんて」
珍しく母親が家にいる。
時計を確認すれば、20時を少し過ぎたところだ。
いつもは九条が寝静まった頃に帰ってきて、朝早くにでていくので、顔を合わせることもなくなりつつあった。
台所から顔を出した母親。珍しく料理をしており、九条のお腹が鳴った。
「なんでいんだよ」
「いいじゃない、今日は仕事が早く終わったの あんたもこの時間に家にいるの珍しいじゃない」
そう言って料理を運んできた母親が、「テーブル片付けて」と九条に言う。
そして、九条の腕とテーブルに挟まれている紙に視線をおとした。
「何書いてたの?」
「うるせぇ見んな」
テーブルに料理を置いた母親がそれを覗き込んでくる。
くしゃりと紙を手で掴んでテーブルの下に持っていこうとしたが母親に抜き取られた。
「おい」
「あら、懐かしいアーティストの名前ばっかり よく知ってるわね」
「返せクソババア」
手を伸ばすが、ひょいと避けられ九条は膝をテーブルにぶつける。
茶碗に入っている味噌汁が少しだけこぼれたが、母親はお構いなしにそれを興味深そうに眺めている。
「美空ひばりって、おばあちゃんが好きだったわよ 施設でおばあちゃんに聞いてきたの?」
「ちげぇよ、普通にばあちゃんが10代の頃流行った曲調べてるだけ」
反抗するのも面倒くさくなり、ぶっきらぼうにそう答えると母親は「へえ」と九条の考えていることを読み取ったように頷く。
「あら、この真赤な太陽なんておばあちゃんよく歌ってたわ」
そう言って口ずさみ始める母親。
九条はいつもすれ違っている母親とこんな会話をしていることに少し不思議な感覚になる。この母親にも思い出の曲があるんだろうか、と。いつも仕事に追われ、女で一つで息子を食わせているこの人は音楽を楽しむ余裕なんてあるんだろうかとふと思う。
「うるせぇな歌うな音痴」
「なによ、口の悪い息子ね!音痴の息子は音痴って知らないの?」
「俺は音痴じゃねぇ」
「自覚のない音痴が1番たちが悪いんだからね」
そう言って再び紙を眺める母親。胸のあたりがむず痒くなって味噌汁をちびちびと啜った。味が薄い。母親は料理が下手である。
「あら、ねえ!あんたキャンディーズ知ってるの?お母さんキャンディーズ大好きなのよ!
この、春一番なんてお母さん春になったら絶対聴いているわ
でもこれ、下に書いてるのおばあちゃんの10代の頃って言うよりお母さんの小さい頃聴いてたものよ」
九条の書いたそれを両手で掴んで嬉しそうに笑う母親。
母親の生まれた年あたりの流行った曲も調べていた九条は、得意げな顔で「そうかよ」と返事をした。
「この曲聴くとね、お父さんと春にドライブデート行った時のこと思い出すのよね 私がキャンディーズ好きだからってずっと車で流すのよ」
「離婚したのに、そういうの忘れないんだな」
そういうと、母親が九条の頭を軽く叩く。
「どんなに憎くてもね、その人と一緒にいた時にきいてた音楽とか、そういうのって一生記憶に残んのよ」
「一生?」
「そ、一生」
なら思い出したくない過去も音楽の中に潜んでいることもあるってことか、と九条は頭を抱える。祖母にとっては「ホッピーラッキーシュッキー」が憎い思い出だとしたら。
孫の面倒をおしつけられ、自分の時間をなくしてしまった嫌な記憶だとすれば、自分のことを思い出したとしても、憎い存在として残っているかもしれない。
祖母が若い頃に流行っていた音楽を調べるだけではいけないかもしれない。
もっと、祖母のことを知らねば。
「ばあちゃんの好きな曲とかしらねぇの」
「うーん、美空ひばりが好きなのは知ってたけど、よく口ずさんでたのは違った気がするのよね」
「なんでしらねぇんだよ」
「親とそういう話しなかったもの、あんただって今の今までお母さんの好きな音楽とか興味なかったでしょ」
何も言い返せない九条に母親は笑ってため息をついた。
そして、九条に紙を返す。
「確かね、おばあちゃんの幼馴染がレコードショップ開いててそこにおばあちゃんよく行ってたみたいよ」
「レコードショップ?」
「あら、あんたレコード知らない?ほら、これくらいの大きいのがクルクル回ってそこにね」
「レコードくらいは知ってる その店どこにあんの」
「この時代でまだやってるかしらね、おじいちゃん死んじゃって家売り払ったからお母さんもちゃんと場所を把握してるわけじゃないけど、昔の家の住所なら分かるわよ」
「明日行ってみるから、住所教えろ」
「分かった分かった ひとまずご飯にしましょ」
そう言って立ち上がって台所に行った母親が思い出したように「あ」と少し低い声を出してひょこっと顔を出した。
「あんた明日って学校でしょ」
その言葉は何も聞こえていないふりをして、九条は味の薄い味噌汁をすすった。