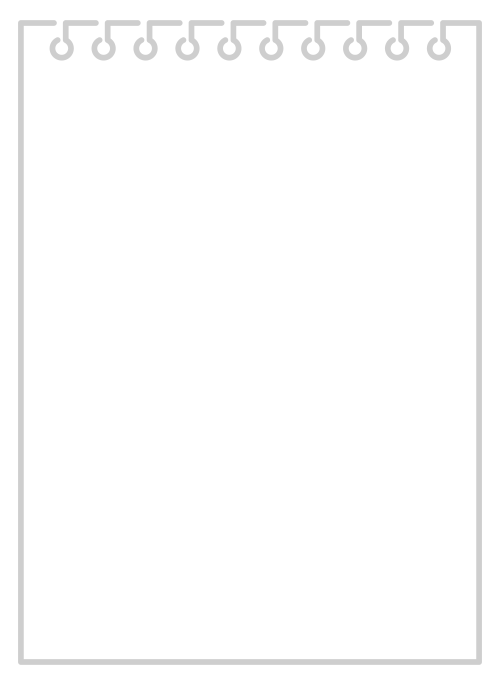深見聡太は自分が衝動的に発してしまった言葉と行動を悔やんでいた。
大会の前日というのに家の近くの公園のベンチで足元を見つめる。
今日は、大会前の最後の練習だった。というより、今も体育館では練習が行われている。
深見は勝ちにこだわっていた。どれだけ練習を頑張っても結果がついてこないと何も意味がないからだ。
生ぬるいと思った。声を出さない部員や、大会前日というのに生ぬるい練習量と雰囲気。
他の部員との温度差に耐えきれなくなり、気持ちをぶつけた深見。
「お前さ、勝ちたいのは分かるし俺たちだって俺たちなりに頑張ってんだからよ、熱量とか部活への価値観をみんなに押し付けるのは間違ってる。そんなに嫌なら出てけよ」
そう、同級生に言われて勢いのまま体育館を出てきてしまったのだ。
何をやっているんだと頭を抱える。
一気に自分以外の人間が敵にみえたあの瞬間。自分の思いや勝ちへのこだわりはぶつけてはいけなかったのだと思った。
だが、やるからには本気で勝ちたい。
どうしても分かり合えないのだろうか。部活なんて入らなければよかった。やめたい。自分は1人だと闇に沈んでいくような感覚になる。
今なら、このまま逃げられるかな。そう思う。
戻ったところで部員から冷めた目で見られるのは分かっている。明日からどうやって自分を保てばいいのか分からない。
1人の空間で、深見はスマホを取り出しいつも聴いていた音楽を流し始めた。
いつもはイヤホンをしているが、周りに人がいないのでそのまま流す。
なぜか曲がはいってこない。イメトレをしようと目を瞑るが黒い部分ばかりが頭を支配していた。
『深見先輩って、なんであんな部活にこだわってんすかね』
『たかが部活でバカみたいだ』
『どうせ一回戦敗退だし、練習するだけ無駄だろ』
言われたこともない言葉を勝手に想像した。もしかしたら今体育館では自分の悪口が溢れかえっているのだろうか。
考えれば考えるほど頭が爆発しそうで、音楽を止めた。
「くそ」
深見はくしゃりと自分の髪の毛を乱して、どうにもならない気持ちをひとまず落ち着けたくてスマホをいじった。
「何もかもから逃げたい」そう画面に打った。
よく分からない哲学のような言葉が溢れかえっている中で、SNSの中で気になるものを見つけた深見はそれをタップする。
「なんだ、これ」
「話題の曲」とタイトルがつけられており、深見はそれを再生した。
顔はうつっていないが女性がギターを抱えて歌っている動画だった。どうやら投稿者本人ではないらしい。
少しハスキーな声で歌い始める女性。
ふと、深見は気になってコメントのボタンを押してスクロールする。そのコメントたちが目に入るのと同時に歌声が深見の耳に入っていく。
ーーー孤独のなかにある希望が私の手をひっぱって
『俺、これ聴いて今日死にます。みんな死ぬことはこわいことじゃないよ』
ーーーひとりじゃないよ、みんな一緒だと笑いかけた
『みんな一緒だと思えばこわくないよね』
ーーーいつか会おうと手を振ってさよならを
『さよなら』
ーーー別の世界で君を待つよ
『これ最後まで聴いたら絶対自殺したくなるんだって』
「っ!」
その強烈な文字をみた瞬間画面が着信の画面に変わり、思わず肩をびくりとあげる。
着信画面には真里とかいてある。
恐怖と、焦りと、不思議な感覚になっているのを落ち着かせようと深呼吸をした深見。
息を整えて、スマホを耳にあてた。
「もしもし」
「あ、聡太、今どこ?まだ部活だよね、ごめんね」
「いや、今公園にいる」
「公園?分かった今から向かうね」
「来なくていいよ」
弱っている自分を見せたくなかった。好きな人の前では何事にも一生懸命で少々のことではへこたれない自分でいたい。
「じゃあ、今から送るものがあるからそれ絶対聴いてね!絶対だよ!じゃあね!」
一方的に電話が切られる。「なんだよ」と顔を顰めるも幼馴染の声が聞けて少し安心した深見。
ベンチの背もたれに背中を預けた。あの曲、最後まできいてたら自分は死にたくなったのだろうか。
自分はたかが部活で、自分が今ここで消えてしまったらどれだけの人が悲しんでくれるんだろうか、とまで考えてしまっていたのは確かだ。
学校が生活の主な部分を占めている今、居場所がなくなったら、と考えれば考えるほど途方もない暗闇に迷い込んでしまう。
スマホの画面が光った。
真里から何かが送られてきた。
「聡太へ」というファイル名でどうやら何かのデータのようだった。
ダウンロードをして深見はそれをひらいた。
「お、」
それが音楽であることが分かった深見。ドラムとピアノが鳴り出して思わず驚いて音量を下げる。
そしてしばらくして、
「これ、真里の声」
歌い始めたのは、幼馴染だった。
下げていた音量をあげる。
荒々しく吹き荒れていた波が静かになるように、深見はその曲に聴き入った。
そしてクスリと笑ったり、少し泣きだしそうになりながら耳から入ってくるそれは安定剤のようだった。
すべてが聴き終わった頃、
「ねえ、せめてイヤホンして聴いてくんない?なにわたしの歌声公開処刑してんの」
「はは」
「何笑ってんのよ」
会いたかった幼馴染が目の前にいた。
息を切らしている真里が息を整えながら深見の横に座った。
「この曲、なんかのカバー?もしかして真里のオリジナル?」
「わたしのっていうか、色んな人の協力を経てつくりあげた応援歌です」
深見は「へえ」と答えて画面をなぞる。
「すごい、ほんとに。真里が俺のためにつくった曲ってこと?」
「まあ、うん」
少し照れた表情で正面をみた真里は足揺らしながら返事をした。
深見は人の努力を笑うような人間ではないが、オリジナルの音楽を人へプレゼントするというのはおそらく一般的ではないことは真里にも分かっていたのでどう反応されるか少しこわかった。
「宝物にするよ、これ。毎日聴く」
深見の真剣な眼差しで本心だと分かる。真里は何か込み上げてくるものがあった。真里にとってもこの曲は宝物だ。
「真里、明日試合みにくるよな」
「うーん、聡太がいっていいって言うなら」
「来いよ、絶対」
深見がそう行って立ち上がる。
真里はうん、と頷いた。
「俺、行くね」
「うん」
色々あったのだろうと、深見の赤い目をみて真里は思ったが何も聞かなかった。すべて曲に込めたから。
走り出した深見の背中を目で追っていると、ふと深見が振り返り、そしてまた真里の方へ戻ってきた。首を傾げて深見を見上げた真里。
すると、深見が少し屈んだ。
「っ」
重なった唇。キスをされたと理解する前に
それは離れてしまった。
あっけにとられる真里に、深見はにっと笑った。
「次はラブソングよろしく」
そう言って走っていった深見。
彼らしい、愛の告白だと真里は思った。