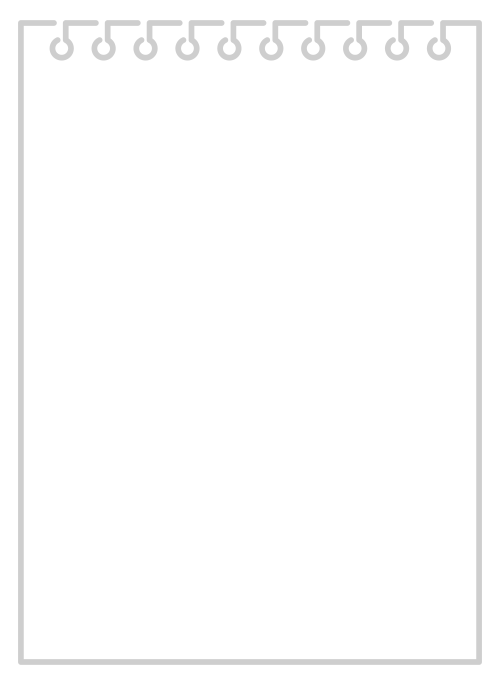ーーーー
学校終わりの放課後で、地道にレコーディングをしていくことになった。
地道にと言っても、深見のバスケの大会まであと4日である。あまりゆっくりはしていられないと、飛田のスタジオにはひとまず参加するメンバーが全員集まった。だが、そこには音代は来ず、学校やクラスでは顔を合わせるものの同じグループには属さない者たちが集まっていた。
「とりあえず時間ないからちゃちゃっと自己紹介して同じ学校で同じ学年なんでしょ?かしこまらなくていいじゃない」
飛田が人見知りを発動している高校生たちに釘を刺した。円になって高校生たちが気まずそうに顔を見合わせているのが飛田にとっては滑稽でしかたがない。最近の若いもんは、とまたもやお局のような言葉がでそうになるのをぐっと飲み込んだ。
そしてやっと、3人で固まっている女子の中の1人が口を開く。
「わたしは特に呼ばれてないんだけど、軽音楽部でボーカルやってて、今回コーラスとかで参加できたらなあと思って来たんだけど、参加してもいい?相原さん」
「もちろんだよ、池尻さん。ありがとう協力してくれて」
クラスでは話したことはないが、文化祭の時などに池尻たちが軽音楽部で有志に参加していたのは知っていた真里。心強い助っ人が来たと安堵の息を吐く。音代はちゃんと真里が知っている同級生を集めてくれていた。
「わたしは相原さんと違うクラスだから一応自己紹介しとくね、天野凛っていいます。軽音楽部でドラムやってます」
「ギターの佐々木香澄です」
さらりと軽音楽部の自己紹介がおわり、3人の女子生徒は気まずそうにある人物へ目を向けた。
真里もその視線をおって、その人物を視界に入れる。
その女子はベースギターをぎゅっと抱えて瞳を泳がす。
「畑 愛子です。ベース、やってます」
小さな声。
文化祭の時は畑も軽音楽部だったはずだが、と真里は首を傾げる。
そして軽音楽部の3人は顔を見合わせ、池尻がゆっくりと歩いていき、愛子の前に立つ。
「ベース続けてくれてありがとう」
「っ」
愛子が驚いたように池尻をみつめる。そしてなんと答えたらいいか分からないような表情をしたあと、きゅっと唇をかんで「うん」と頷く。
「こうやって、咲たちともう一回演奏できるの、嬉しいよ」
畑がそう言えば、池尻は少し複雑な顔をして、「わたしもだよ」と笑った。ドラムの凛や、ギターの香澄も愛子にかけよる。
何か喧嘩でもしていたのだろうかと真里はますます首を傾げるが、女子というのは団体で活動していれば何かしらの事件はおこるものだと理解はしているのであまり深入りはしないでおこうと思った。
そして、真里は隣にいる間宮に手を向けた。
「今回ピアノで間宮さんが参加してくれますので、みなさんよろしくお願いします」
そういうと、間宮が深々と頭を下げる。喋らない分自分の気持ちを伝えようと精一杯である。「よろしくお願いします」真里は間宮のつむじからそう聞こえた気がした。
そして、先ほどからこの場で異様な雰囲気を醸し出しているヤンキーが1人。
「九条凪っす、俺も音代先生に頼まれました」
「楽器は?」
飛田が腕を組んでそう問いかけると、九条がスクール鞄から何かを取り出す。シャラン、と軽快な音が鳴った。
「タンバリン」
学校でもこわがられているヤンキーからでてきた言葉に、思わず真里やその他女子が吹き出す。
「九条くんタンバリン叩けるの意外なんだけど、てかなんでタンバリン?」
真里がそういうと、九条はにっ、と笑う。
「音代先生が賑やかし担当で参加してこいって言うからよ、俺といえばタンバリンだろ。あとその他小物の楽器あれば俺がやるよ」
「俺といえばタンバリンだろ、の意味がよく分かんないけど、ありがとう、九条くん」
学校のヤンキーの意外な一面をみたところで、飛田がため息混じりに口を開く。
「ま、素人軍団でもわたしの力でなんとか形にはしてやっから、ひとまず始めるわよ」
皆のぎこちなさが解けたところでそれぞれが楽器の準備をし始める。
真里はその姿をみながら、改めて「音代先生って何者なんだ」という気持ちが頭をうめつくしていく。
何か問題が起きていたであろう軽音楽部や、ヤンキーの九条。どんな頼み方をしたらこのメンバーが集まれるのだろうか。
「みんな、わたしのわがままに付き合わせてごめんね」
気づいたら真里はそう呟いていた。
自分が何かをやり遂げるため、幼馴染だけのために曲を作りたいから。そんなエゴの塊でこれだけの人たちが動くことが申し訳ない。そう思ってしまう。
「音代先生から今回の曲作りこと、話きいてるよね」
学校では仲良く話すこともないただの同級生である。
先生に頼まれたからしかたなく、嫌だけど。そう思っている人がいるのではないか。
何かを突き詰めることで人に迷惑をかけてしまうのでないかとどんどんネガティブな思考になっていく真里。そんな中
「幼馴染、いいよね」
「え?」
真里に言葉をかけたのは池尻だった。
「相原さんにここまで想ってもらえてんだもん。デモ音源で曲きいたけど、絶対この曲きいたら背中押してもらえる」
「池尻さん」
「それにさ、夢だったんだよね。レコーディングするの。こう、ヘッドホンしてさ音録って。いろんな音が重なって音楽ができあがっていくんでしょ、ワクワクするよね」
ポン、と真里の肩に池尻の手がのる。
いろんな音が重なって1つの音楽になる。
そして、それが人の背中をおす。深見にとっても、真里にとっても、この曲が宝物になるように。
真里は、「うん」と頷いた。
「音代先生は少し濁して説明してたけど、要は相原さんは深見くんのこと好きなんでしょ?」
「え」
池尻の後ろから顔を覗かせてそうきいたのはドラムの凛だ。
真里が戸惑っていると「わー、照れてるかわいい!」とますますからかいムードになる一同。
「じゃあ、相原さんの恋は私たちの楽器の腕にかかってるってことね」
ギターの香澄のその言葉に、みんなが頷く。そして、真里は火照った顔を冷ますように手で顔をあおぎながら、「違う」と否定になりそうもない顔で否定した。
「俺、恋成就しますようにって願いながらタンバリン叩くわ」
「そ、そういう曲じゃないから、九条くん」
苦笑いを浮かべながらそう答えた真里。最初の緊張が嘘のように和やかな空気に包まれる。
「まかせとけって。さあ、レコーディング始めようぜ」
「あんたが仕切るな、金髪ヤンキー」
飛田が軽く九条の頭をはたく。
そして前髪をかきあげて、飛田は言葉をはなった。
「やるからにはビシバシいくからね!真里の恋心、全力で実らせるよ!」
「飛田さんまで!」
慌てる真里の声は、他のみんなの「おー!」という声にかき消された。