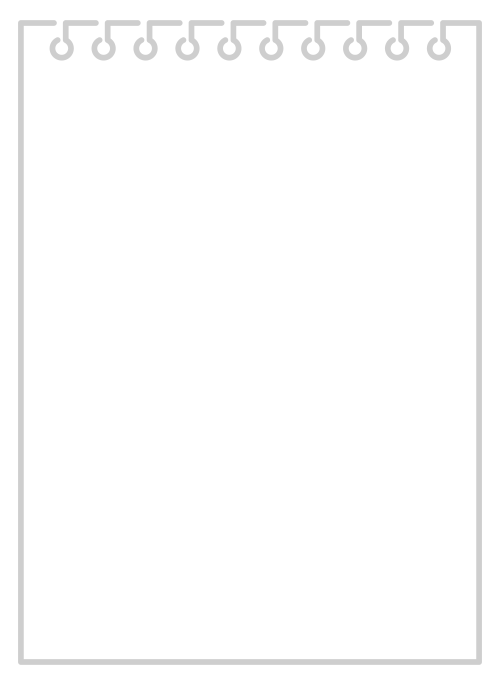ーーーー
「歌詞、みてもらえますか」
2度目の訪問も、いちご大福を持参した。
部屋に入って早々あけられ、するするとあっけなく飛田の胃袋におさまっていく。
歌詞が書いた紙を差し出すと飛田は「大福持ってきたからみてあげる」と言って受け取る。
しばらく歌詞を読んで、飛田は顔をあげた。
「いいんじゃない」
「やった!」
徹夜で仕上げた自分の感情をぶつけた歌詞。そして日曜日にもかかわらず真里は早朝から飛田のスタジオへ向かった。案の定飛田は髪もボサボサで不機嫌そうに出てきたが、いちご大福でなんとか機嫌を損なわずにすんだ。
真里が両手をあげて喜んでいると、飛田はソファから立ち上がり3台のパソコンが連なっているデスクの前に座って電源をつけた。
「音代の頼みだし、協力してあげる」
そう言った飛田。隣に丸椅子を置き、顎で真里に座るように促す。
真里は電源がついたパソコンの画面を興味深そうに眺めながら飛田の隣に座った。
「音代先生と飛田さんってどんな関係ですか?今から何するんですか?てかわたし何したらいいですか?」
「やめてくんない?怒涛の質問攻め。なんなの、最近の高校生こわすぎ」
「すいません」
「何が1番聞きたいの」
「うーん、音代先生との関係?」
音代は変人だが、顔はとてつもなくいい。
学校でも黙っていれば完璧なのにと女子たちが騒いでいるのを真里は知っている。
彼女がいてもおかしくないと思った。そしてその相手は音楽関係で同じく変人であり、今真里の目の前にいる飛田しかいないというしようもなく、浅はかな見立てである。
「ひとつ言っとくけど、あたし結婚してっから」
「え!?音代先生と?」
「アホか、あんな変人男と結婚するわけないでしょ!」
「じゅうぶんあなたも変人ですけど」という言葉は飲み込んだ真里。
だが、「音代の頼みだし」という言葉が出るということは何かしらの恩が音代にたいしてあるということではないのだろうか。
「ただならぬ、深い関係なのは確かですよね」
「その言い方やめてくんない?すごく嫌。ただの腐れ縁よ」
カチャカチャとパソコンを操作しながら顔を顰める飛田。
「言っていいのか分かんないけど、あたしの兄が音代の師匠なの」
「師匠って何のですか?」
「ピアノ、作曲、音楽諸々かな」
「なーるほど、私と飛田さんみたいな感じですね!」
天井に人差し指を向けた真里。飛田は片手で真里の両頬を掴んだ。
真里の唇が前に飛び出てタコのような顔になる。
「私はこんなクソ素人を弟子にした覚えはない」
クソ素人呼ばわりされてしまった真里は、「しゅみましぇん」と小さく開く口で謝罪した。
飛田の手が離れたあと、真里は自らの頬を撫でながら飛田を見つめる。飛田は少し言いづらそうにパソコンの画面を見ながら言葉を続ける。
「ま、師弟関係だったって言うべきだけど」
「え?」
「大人になると色々あんの」
はぐらかすようにそう言って飛田はくるりと真里に向き直った。
「まっすぐな子どものうちに曲つくれることに感謝しな。時間ないんでしょ、急ピッチでデモ音源つくるわよ」
「その、デモ音源ってなんですか?」
飛田は「そんなのも知らないのか」と盛大なため息をついて、画面に顔を向ける。
真里も何が何だか分からないが、ひとまず開かれた画面を見つめた。
「レコーディングまでに楽器弾く人たちに渡すためのものよ。楽譜と、デモ音源を渡して本番までに練習してきてもらうの」
「へえ、なるほど」
「他人事じゃないわよ、あんたがつくった曲なんだからあんたがやんの」
飛田は自分の座っている椅子を少しずらして、頬杖をついた。顎でクイッと真里にマウスをいじるように促す。自分が今から何をしたらいいかも分からず真里は促されるままひとまずマウスを触る。
画面は4段ほどに分かれている枠が写っており、左端には英語で楽器名が書いてある。
「こっからが地獄よ、楽器の音を打ち込んでいく作業だから」
「私、全く分かんないんですが」
「今の世の中、楽器弾けなくても音源ってつくれるようになってっから大丈夫。そしてやっていけば嫌でも慣れてくるから。そんで、あくまでデモ音源だから、楽器やるやつらがこんな曲だなあて分かればいいの、楽勝でしょ」
未経験者の真里からしてみれば何ひとつ楽勝ではないが、飛田という強い姉御がいることで未知のことでも突き進める気がしてきている真里。
「まずはドラムからねビシバシいくわよ」
椅子の上で鼻をふんとならし、あぐらをかいた飛田。
1人の少女の音楽への嫉妬。
幼馴染への想い。
すべての感情を音にのせていく。
完成していく感情の音とともに案の定、飛田の怒号と徹夜明けで変なテンションになっている真里の声が一日中そこに響き渡った。