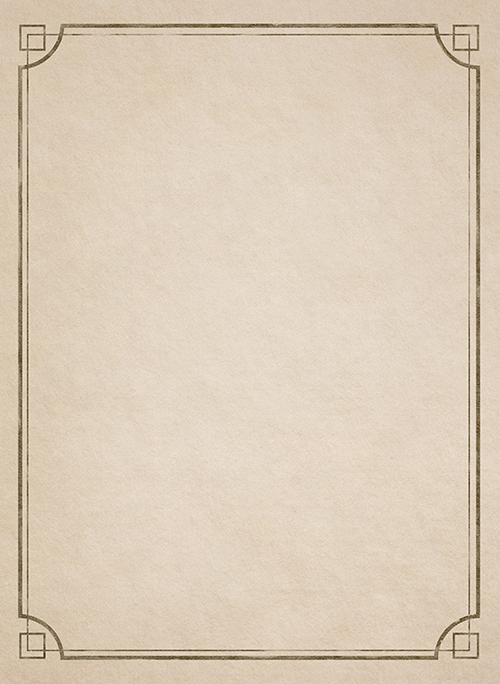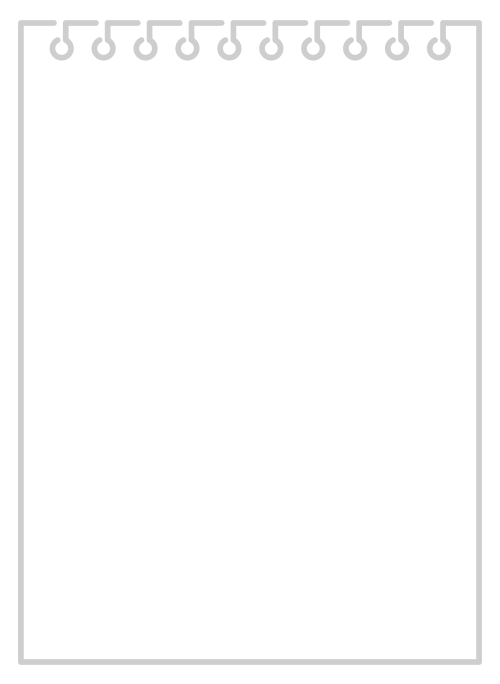「正確に、忠実にすることがすべてじゃない」
何度も何度もきき、憧れに近づくために正確にやらないと、その気持ちに音代は自身も潰されそうになったことがある。
「かたちは違うが、ピアノで俺も正確さに囚われていたことはある」
音代もそれが正解だと思っていたからだ。
「機械のように、一曲を聴いて聴いて聴きまくって、忠実に再現して、憧れの人のコピーになった」
「音代先生は、やめたくならなかったの?」
「なったよ、実際に俺も逃げたしな」
そう言った音代に、畑はどこかほっとしたような表情になる。自分の逃げは自分だけのものではない。誰しもがぶつかるものだと。
「だが、音楽の世界はそこだけじゃない」
「え?」
音代はポケットに突っ込んでいる財布から名刺のような紙をとりだし、畑に差し出した。
「自由さを求めてるなら行ってみろ」
畑はそれを受け取り、不思議そうに眺める。
音代は立ち上がった。
まだ、音代にはやるべきことが残っている。
畑に背を向け歩きだした音代。
その顔は怒りで満ちていた。
意図的じゃないにしても、音楽をこんな方法で使うことに対しての怒りだった。
畑は知らない間に闇に飲まれたのだ。できない自分を責めていた畑。その心情を利用したやつが許せない。
「先生、ありがとう」
その声が後ろから聞こえてきて、音代はくっと喉に力が入る。
願わくば、音楽を嫌いにならないでほしい。
「ああ」と振り返らないまま返事をし、病室をあける。
「よ、」
「じじい、何しにきた」
現れた神城に音代は神城を外に追いやり、畑から見えないようにすぐに扉をしめる。
「目を覚ましたってきいてな」
「もう事情は聞いた。帰るぞ」
「俺はきいてない」
「うるせえ」
と、神城の腕を掴み歩き始める音代。
「なんでそんなにキレてんだよ、音代」
その問いには答えず、病院の外まで連れ出し荒々しく手を離す。「早く帰れ」と神城の背中をおした。
「自殺の曲とは、関係がなかった。それが知りたかったんだろう、はやく帰れ」
「原因はなんだった」
「決着がついたらまた話す」
「音代」
「俺は、こんなかたちで音楽をつかった奴らが許せない。じじいが調べてる自殺の曲についてもだ」
音代の言葉に、神城は言葉を詰まらせる。
名の通り、音を楽しむためにうまれたものが人を苦しめることはあってはならない。人を死にいたらしめるなんてことはもってのほかだった。
だが、
「あるやつに言われたよ、俺みたいに音楽で身内を殺してみたいって」
その言葉で、音代自身の闇に埋もれている過去を掘り起こすことは簡単だった。音楽で人を苦しめてはならないと音代は胸に刻んでいる。刻んでいるからこそ、苦しい。
「誰だ、そんなこと言ったのは」
「じじいも、本当は思ってんだろ、親友を殺したのは大好きな親友の息子だって」
「音代!」
「俺をそう呼ぶのは、父と俺を重ねているからか」
神城は、苦い薬を飲んだような顔をしておしだまる。
音代はふう、と小さく息を吐いた。
今はこんなことを言い合っている場合ではない。
「音代先生!」
殺伐とした空気の中、病院の自動ドアから慌てたようにでてきたのは坂木だった。
そして音代の方に走ってくる。
音代の先にいる神城に気づき小さく会釈をした。今回の件で神城は坂木にも話をきいており、2人は軽く面識がある。だが、神城は坂木に自殺の曲のことは言っていない。
ひとまず、飛び降りた生徒に何があったかをきくことが最優先だったからだ。
神城も会釈をして、「またな」と音代に告げ、歩き出した。音代は、その姿を見送り、坂木に向き直る。
「もう、学校に帰るんですか?」
「はい」
坂木の問いかけにそう返事をする。
「親御さんは大丈夫でしたか」
「はい。本人がやるって言ったって断言してる以上、責められないって」
「そうですか」
「何か、怒ってますか」
「怒ってるように見えますか」
「はい、すごく」
坂木に顔を覗き込まれ、音代は身をそる。
坂木は少しいつもの調子に戻っていた。
泣き腫らした目はいまだに赤いが。
「今から、畑さんに話をきいてきます。私も逃げないです。もうこんな思いしたくないので」
「分かりました」
「頑張ってください」というのは少し上から目線だと思い、音代は小さく頷いた。
教員としての経歴は彼女の方が何年も上である。畑の話をしっかりときき、支えてくれるだろうと音代は思った。
坂木が再び病院に踵を返した時、
「あ、坂木先生」
思い出したように声をかけた音代。
決着をつける前に1つ確認しておきたいことがあったのだ。
振り返った坂木に音代は言葉を続ける。
「1つ、ききたいことがありまして」