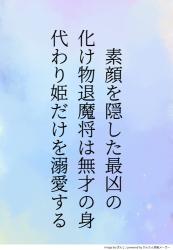「まさか、柳原先輩がほんとにオレの頼みを聞いてくれるなんて思わなかったです」
「へっへん。感謝してよね、橋本少年」
「ひとつしか歳変わらないのに、少年扱いするのやめてくれませんか」
「憧れのさくらの前で、背伸びしたいんだぁ~。かわいいねぇ」
「ち、ちがっ! あ、いや……。ちがくは、ないかもですけど」
優希と、隣あって座っている男の子のやりとりを、落ちつかない気持ちで眺める。
わたしたち三人、透也もいれると四人は、月ヶ丘高校近くのファミレスチェーン店にやってきていた。一度こうだと決めた優希の行動力は凄まじく、彼の話が出てから一週間も経たないうちに今日の会をセッティングしてしまったというわけだ。
橋本少年と呼ばれた彼が、優希が話していた塾の男の子だ。
すこし童顔気味で、髪型は爽やかなマッシュショート。彼も高校帰りなので、学ランを着ている。
第一印象だけで言うと、どちらかといえば、かわいい系だ。
いきなり派手な人が来なくて良かったと、内心、ホッとしてしまう。
「二人とも、めーっちゃくちゃ緊張してんじゃん。ウケる」
「ふーん。髪も染めていなさそうだし、見た目的に、チャラそうではないね。僕ほどじゃないけど、まあまあ好青年なんじゃないかな? 実は、優希ちゃんが連れてくるって聞いて、ちょっと心配してたんだよねー。ド金髪にピアスの男が出てきたら猛反対するところだったけど、まずは及第点」
コーラを飲みながらケラケラと笑う優希に、腕を組みながら目の前の橋本くんを凝視している透也。……控えめに言って、かなりカオスだ。
橋本くんは、わたしの沈黙を、緊張だと受け取ったのかもしれない。
すこし強張ったような面持ちで、話しかけてきた。
「えと……。初めまして、東雲先輩。オレは、橋本真っていいます。その、すこし前から、東雲先輩のことが気になってたんです。柳原先輩と歩いてるところ見て、良いなぁって思ってて……」
たどたどしい口調で、しどろもどろになっていく姿から、少なくともウソをついてはいなさそうだと感じる。
透也と出会っていないわたしが聞いていたら、年下の男の子の一生懸命な感じに、すこしは心動かされていたかもしれない。自分でもかなしくなるほどに、この場をどうやり過ごそうとしか思えていなかった。
「あ、ありがとうございます」
「さくら、敬語じゃなくて良いよ。後輩なんだし」
「柳原先輩に許可される筋合いはないけど、まぁ、そっすね。東雲先輩、オレには敬語じゃなくて大丈夫です!」
「わ、わかった。そうさせてもらうね」
「その……、良かったら、連絡先を教えてもらえませんか?」
「うん」
流れ的にここで断るのもヘンな感じだしなぁと、あまり気乗りしないけれどスクバから携帯を取り出す。彼が表示させたQRコードを読み取りながら、虚しい気持ちがふくらんだ。
透也の連絡先も知らないのに、どうしてわたしは、今日知りあったばかりの男の子を連絡先に追加しているんだろう。
目の前の橋本くんは、わたしの心を占める陰気な気持ちに気がつくわけもなく、はしゃいでいる。
「ありがとうございますっ! 連絡させてもらいますねっ」
「はーーっ。いいねぇ、甘酸っぱいね~。うまくいったら、ダブルデートしようね!」
「ちょ、ちょっと優希」
いくらなんでも囃したてすぎだ。
悪ノリしている優希を責めたい気持ちと、流されるままに今日この場へ来てしまった自分への罪悪感とで、背筋に嫌な汗が伝った。
「柳原先輩、あんまりからかわないでくださいよ。東雲先輩は、あなたと違ってピュアそうなタイプなんですから」
「はいはい、わかったよ。んじゃ、そろそろお邪魔虫は退散しようかね」
「えっ」
スクバを手に、さっと立ち上がった優希を見て、今度は目がまるくなる。
「ほんとは、もーちょっとこの場で二人をからかっていたいところだけど、あたしはそろそろ塾の自習室に向かうね。これでも一応、受験生だからさ」
優希は長い髪をふわふわと揺らしながら、自分のドリンク代だけ置いて、とっとと去っていった。
まるで嵐のようだ。
こんなに急に二人きりにされるなんて聞いてないよ!
いや、正確には、わたし目線で見ると三人なんだけど……。
「うーん。もしかして僕も、席を外した方が良かったりする?」
「ごほっごほっ」
透也まで妙なことを言いだして、飲みかけのアイスティーをむせそうになった。
「東雲さん、大丈夫ですか!」
「う、うん。ちょっとむせただけ」
「やっぱり、もうすこし彼を観察することにするよ。さくらを任せるに値する男なのかしっかり見極めないとね」
むせて涙目になったわたしに、ニヤニヤとした視線を送ってくる透也は、やっぱり意地が悪いと思う。面白がっているとしか思えない。
「柳原先輩って、ほんと自由ですよね。あのひと受験大丈夫なのかなぁ」
「なんだかんだで、努力しているんじゃないかな。彼氏と同じ大学に通うんだってはりきってるみたいだし」
「あのひとは、のろけすぎなんですよ。いいよなー……」
ただの優希への感想だとわかっているのに、中途半端な気持ちでここにいるわたしを責めているようにも聞こえて、なんだか息苦しくなる。
気まずい。なにか会話を続けなきゃ。そう思えば思うほど、焦ってなにも言葉が出てこない。周囲の喧騒ばかりが耳につく。
「オレ、東雲先輩のことを、もっと知りたいと思ってます」
純粋で、きらきらとしたその視線は、今の情けないわたしにとって眩しすぎる。
焼け爛れそうだ。
「先輩のことを教えてください」
「わたしのこと?」
「はい。趣味とか、好きなこととか。なんでもいいです!」
趣味。好きなこと。
そう問われた瞬間、なぜだか、夢中になって物語を紡いでいた中学時代の自分が脳裏によぎった。
『なぁ。俺にも、東雲の書いた小説を読ませてよ』
それと同時に、明らかに人を見下しているとわかる下卑た笑い声も、耳の奥からねっとりと蘇る。
よりにもよって、なんで今さら、あんな最低な記憶を思い出すんだろう。
わたしは、書くのをやめた。
一時期は夢中で読んでいた小説も、今ではほとんど読んでいない。
妄想を書きつづって満足する痛々しい自分のことなんて、もう捨てたはずなのに。
「ええと……。音楽を聴いたり、動画を見たりとか」
「へぇ! どんな音楽を聴くんですか?」
想像以上に食いつきが良くて、びくびくとしてしまう。
「あー、えっと、バンドなんだけど、なんて名前だったかな。友だちに勧められて知ったから、そんなに詳しいわけじゃないんだけど……」
愛想笑いをしながらスマホをいじって、プレイ済リストから茜に勧められたバンド名を慌てて探す。
ほんとは、なんとなく聴いて、へぇと思った程度だ。思い入れはない。
だけど、趣味だと言った以上、やっぱりそんなに好きじゃないという本音を言い出せる空気でもなくて。取りつくろってばかりの自分に、どんどん嫌気が差していく。
「あー! 虹色セカイかぁ。ハイトーンボイスがかっこいいバンドっすよねぇ」
わたしのスマホ画面をひょいっとのぞきこんで、橋本くんの方から勝手に話をつないでくれたので、なんとか助かった。ほっと胸をなでおろす。
その後も、どうやって違和感なくこの場をお開きにしようかということばかり考えていて、目の前の橋本くんの話は耳を滑っていくばかりだった。
ドリンクバーで取ってきたオレンジジュースも、ぜんぜん味がしなかった。
*
「はああぁ……。つっかれたなぁ」
「ふふっ。盛大なため息だねぇ。ため息が、真っ白だよ」
肺に滑りこんでくる空気はとても冷たくて、だけど、心地が良かった。
からだの中にたまっていた淀んだ気持ちが浄化されていくような感じ。
宿題をするという適当な言い分を並べて橋本くんと分かれたあと、わたしは透也と一緒に近所の公園にやってきていた。
ブランコが二つと、ベンチが一つだけしかない、小さな公園だ。
最近は、日が落ちるのがとても早くなったので、あたりはすでに薄暗い。
なんとなく、このまま家に帰る気分になれず、たまたま人が見あたらなかったのを良いことに、わたしはブランコへと腰かけた。透也も、わたしを真似するように、隣のブランコへと腰かける。
人気のない場所に来ると、とても落ちつく。
その理由には、もう、ずいぶん前から気がついていた。
他の誰といるときよりも、わたしは、幽霊の透也と過ごす時間が好きだから。
「そりゃ、疲れるよ。優希は、とっとと帰っちゃうしさー。初対面の男の子となんて、なにを話したら良いのかわかんないもん」
「そう? 僕と初対面だったときも、そう思っていたの?」
「……透也とは、比べられないよ」
「まぁ、僕は幽霊だしねー」
それは、間違っていないんだけど。
あえて話を茶化されたような感じがして、ムッとしてしまう。
「さくら。橋本くんのことは、どう思った?」
「……うーん。まだ、よくわかんないけど、悪い人ではないと思う」
「そうだね、僕も同じことを思ったよ」
透也の何気ない同調に、胸が切り裂かれたように痛む。
「そんな渋い顔しないで、もっとまじめに考えてあげたら? 彼は、さくらにちゃんと向きあってくれそうな、普通の男の子に見えたよ」
普通ではない、幽霊の自分とは違って。
彼がそう言っているようにも聞こえて、無性に切なくなる。
「……ごめん。きみが迷ってしまうのは、僕のせいでもあるよね。だからね、さくら。僕たち、さようならをしようか」
「えっ」
「僕がきみのそばにいても、きみが幸せになる邪魔にしかならないと思う」
耳を疑った。
彼がなにを言っているのか、本気で理解できなかった。
いや、したくなかったんだ。
「なんで? なんで透也がいなくなる話になるの。わけわかんない、いくら意地悪だからって冗談きついよ!」
透也は、なにも言わない。
さびしそうな顔で、泣きながら怒っているわたしをじっと見つめている。
「未練はどうなったの⁉ まだ解消できていないから、成仏していないんでしょ! ねえっ、そうなんでしょ!」
「それは、そうだけど……。僕の未練のことは、もう良いんだよ」
「良くないよ! 人のこと散々振りまわしておいて、いざとなったら、大事なこと一つも話してくれずに勝手に去ろうとするわけ? そんな、そんなの……あまりにも、ひどいよ」
痛々しいほど必死な叫びに、透也のきれいな顔が、今まで見たこともないほど感情的に歪んだ。
感情をむき出しにしたような怒りの表情に気圧されて、ひゅっと心臓が縮む。
「……願っても、叶えられないんだよ! だってきみは、もう小説をやめたんだろ!」
「えっ……」
「僕の未練は、ある日を境に、更新が止まった小説を最後まで読むことだった。そのために、きみに近づいたんだよ。きみにだけは、なぜだか僕の姿が見えているようだったから、きっときみがあの小説の作者なんだって僕にはわかった」
なんで? どうして透也の口から、わたしの小説の話が出てくるの。
息をすることも忘れて、彼の激白に聞き入る。
「きみ自身の意志で再び書きたいと願ってくれなきゃ、意味がないと思ってた。だから、待ち続けたんだ。でも……さくらは、毎日つまらなそうな顔で友だちの真似をするばかりだし、おまけに小説の話題は頑なに避けていた。もう、待つのは疲れたよ! きみのそばにいても、どうにもならないじゃないか!」
あまりの衝撃に、呆然として言葉を失ったわたしに目をやって、透也はしまったというように瞳をハッと見ひらいた。
「ご、めん。言いすぎた。……言うつもり、なかったのになぁ」
透也はよろよろと立ちあがり、そのまま公園を出ていった。
しばらくの間、雷に撃たれたように、その場から動けずにいた。
動悸がする。呼吸が浅い。心臓が、バクバクと熱く脈打っている。
どうして透也は、わたしが昔に小説を書いていたことを知っていたの?
冬の夜風が、コートの中まで浸透するように、骨身を冷たくする。
その日、透也は、わたしのもとへと帰ってこなかった。
*
透也がわたしの前から立ち去ったその夜、悪夢を見た。
正確には、ただの夢じゃない。
これは心の奥底に鍵をかけて沈めた、中学時代の辛い記憶だ。
中学時代のわたしは、小説を書くことが趣味の、夢見がちな少女だった。
本を読むのも大好きで、小説家になりたいって本気で思っていた。だけど、わたしの通っていた中学校に文芸部はなかったし、みんなに小説を書いていることを知られるのはなんとなく気恥ずかしくて、インターネットの小説投稿サイトへ書いた作品をひっそりとアップロードしていた。
『凛。あのね、みんなには言わないでほしいんだけど……実はわたし、小説家を目指しているの』
その夢を、クラスの中で一番仲の良かった、凛にだけ打ち明けた。
秘密にしたい気持ち以上に、親友にだけは知ってもらいたい気持ちが勝ったから。
『そうなの? さくら、すごいね! 私、読んでみたいな! ペンネームを教えてくれる?』
『ありがとう! えっとね、チェリーって名前で活動しているんだけど……』
自分の名前と同じ名の花、桜は英語でチェリーブロッサムという。そう習って、安直につけたペンネームだった。
今までずっと内緒にしていた分、好きなことを自由に話せるのは本当に楽しくて。
夢中になって凛に書いた小説の話をしているうちに、間抜けなわたしは、その場所がいつクラスの誰が入ってくるかもわからない放課後の教室だということを忘れていた。
『へえぇ~。東雲って、小説とか書くんだ』
背筋が凍るような思いだった。
忘れ物を取りにきたらしいサッカー部のクラスメイトに、いつの間にか、会話を聞かれてしまっていたんだ。
しかも、見つかってしまった相手もまた最低最悪だった。
よく通る大きな声で、自分が目立つためならば、なんでも面白おかしく話すようなやつだったから。
『なぁ。俺にも、東雲の書いた小説を読ませてよ』
あざけりの含まれたような声は、悪意に満ちていて。面白いおもちゃを見つけたというような嗜虐心が、ニヤニヤとした嫌な視線から即座に伝わってきた。心臓が、痛くなる。
小説を書いているなんて、痛いね。
彼の発した言葉が、そう変換されて、脳内で何度も再生される。
『さくら、場所を変えようか』
『……うん』
『おい、無視すんなよー』
その日は凛の助け舟があったから、それ以上絡まれずに済んだけど、その翌日からも地獄のようだった。
『東雲ってさー、小説書いてるらしいよ』
『え、小説? なにそれ、ウケるんだけどー』
『あ、ウワサをすればご本人の登場じゃん。なぁ、なんで昨日無視したの?』
わたしの大事な作品は、彼のおちゃらけたような軽い口でたやすく拡散され、笑いものにされていた。
もちろん、無言を貫いてまともに相手をすることはなかったけど、いくら平気な顔をしてみたところで心は徐々に病んでいった。
『さくら、気にすることはないよ』
凛だけは、日に日に顔色を悪くしていくわたしを慰めてくれたけど、段々、学校に通うことすら辛くなっていった。
教室のどこにいても、妄想好きの痛いやつだとあざ笑われているような気がする。胃がムカムカとしてきて、何度かお手洗いに駆けこみ、そのまま吐いてしまったこともあった。
体調が悪化するのと同時に、創造の翼も折れてしまった。
それまでは、毎日心躍らせながら、楽しく小説を書いていたのに。
まっさらな白い原稿を前にしても、想像が広がらない。文字を打ちこむ手もさっぱり動いてくれなくなった。書こうとすると、『小説? ウケるんだけど』という呪詛が耳の奥からゾンビのように蘇ってきて、動悸すらする。
書けない。
書けない書けない書けない。
こんなに辛いのなら、もう、書くのをやめてしまおう。
どうせ、投稿サイトにアップした小説にも、ほとんどPVはついていない。
世の中には、感動的で、面白い小説を書くひとが星の数ほどいる。
拙いわたしの小説を待っている人なんて、どこにもいない。
どうして小説家になるだなんて不相応な夢を今まで本気で見られていたのかも、さっぱりわからなくなった。
高校は、わたしのことを誰も知らない、遠い場所を受験しよう。
そして今度こそは、絶対に同じ失敗をしない。
小説を書いていたことは忘れて、みんなから浮かないように過ごす。
普通の高校生になって、普通の幸せを得ることだけを目標に、わたしは通学に一時間近くかかる月が丘高校を受験したんだ。
*
目覚めたとき、瞳から涙が流れていた。
もう二度と思い出したくない最悪な記憶を夢に見たのは、たぶん、透也の怒ったような顔が胸に突き刺さって消えなかったからだ。
『……願っても、叶えられないんだよ! だってきみは、もう小説をやめたんだろ!』
辛そうな顔をしてわたしの前から消えた透也は、朝になっても帰ってきていなかった。
九か月ぶりに訪れた、一人きりの静かな休日の朝だ。
部屋に一人だと、こんなにもだだっ広くて心細いものなのかと、今さら気がつく。
いつの間にか、透也に「おはよう、さくら。寝顔、かわいかったよ」とからかわれながら目覚めるのが、当たり前になってしまっていたらしい。
透也がいなくなった今、わたしは正真正銘、普通の女子高生になったんだと思う。
学校で浮いているわけでもなく、友だちがいて、後輩の男の子と普通の恋を始められそうな予感もある。
中学時代の、苦しかったわたしが切実になりたいと願った、理想そのままのわたし。
――本当に?
【おはようございます。昨日は、ありがとうございました! 東雲先輩のこと、さくら先輩って呼んでもいいですか?】
せっかく橋本くんがメッセージをくれたというのに、返信をする気力もわいてこない。
これが理想ならば、どうしてわたしは、胸をかきむしりたくなるほど腑に落ちていないんだろう。
なによりも、今のわたしが求めているのは、透也のことだけだ。
彼のことをなにひとつ知らないまま、終わりになんてできない。できるはずがない。
これが普通の幸せ? ふざけんな。全然ハッピーじゃないし、望んでもいない。
こんな結末、認めてたまるものか!
『僕の未練は、ある日を境に更新が止まった小説を最後まで読むことだった。そのために、きみに近づいたんだよ。きみにだけは、なぜだか僕の姿が見えているようだったから、きっときみがあの小説の作者なんだってすぐにわかった』
透也につながる手がかりはほとんどないに等しいけど、彼が、わたしが小説を書いていたことを知っていたのがどうにも引っかかっている。
中学時代、わたしが小説を書いていたことは悪意をもって広められたけど、チェリーというペンネームで投稿活動していたことを打ち明けたのは凛だけなのに。
……凛にだけ?
些細だけど重要なことに思えて、わたしは震える手で、数年ぶりにかつての親友へと連絡を取った。
【久しぶり。凛、元気にしてる?】
【さくら! ほんとに久しぶりだね、私は元気だよ。さくらはどう?】
すぐに返事が返ってきて、ほっとした。
【うん、元気だよ。ずっと連絡が取れていなくて、ごめんね】
【気にしないで。連絡を取っていなかったのはお互いさまだし、さくらだけのせいじゃないでしょ】
数年ぶりに凛のやさしさに触れて、じわりと目頭が熱くなる。
月ヶ丘高校に入学してからのわたしは、中学の記憶を呼び起こす全てを切り捨てたくて、凛とも距離を置いてしまっていた。
凛はなにも悪くない。わたしの薄情な態度に怒っていてもおかしくないのに。そんな態度はみじんも見せずに、かつてのやさしさをそのまま向けてくれることが、とてもありがたい。
【あのね、凛。わたし、凛に聞きたいことがあって、連絡をとったの。もし心当たりがあったら、教えてくれる?】
【なんの話し?】
【中学時代に、わたしが小説を書いていた話をしたと思うんだけど。そのことを、他の誰かにしたことってあったりする?】
それまでスムーズに返ってきていた返信が、急にぴたりと止まった。
もしかして、文章だけだと責めているように感じただろうか。
そういう意味じゃなくて、ただ純粋に知りたいだけだと慌ててメッセージを追加しようとしたところで、着信が入った。
凛からだ。
「もしもし。さくら、いま、電話は大丈夫?」
「う、うん……」
「あぁ、さくらの声だ。久しぶりに話せて、うれしいよ」
「わたしも。凛と話せて、うれしい」
凛は、今でも中学時代と変わらずに吹奏楽部を続けているらしい。
私立の付属高校なので受験もなく、のんびり過ごしていると語った。
数年ぶりの会話なのに、久しぶりだという感覚は薄く、会話が尽きないのがとても心地よかった。相手にどう思われているか気にすることなく話せるこの感覚は、透也と話しているときと似ている。
お互いの近況を一通り話し終わり、凛が深呼吸をしたとき、緊張が走った。
「えっとね、さくらの小説の話なんだけど……当時、一人の男の子にだけしたことがあるの。さくらに許可も取らずにごめんね」
やっぱり。
あいまいな予感に過ぎなかったものが確信へと近づいて、胸が熱を帯びた。
「詳しく、教えてくれる?」
「うん」
それは、わたしたちが中学三年生だったときのこと。
当時の凛は、祖母のお見舞いで、大学の総合病院に通っていたらしい。
「そう、だったんだね……。凛も大変だったのに、わたし、ぜんぜん知らなかった」
「いいの。さくらは、それどころじゃなかったから……」
当時のわたしは、自分だけが辛くて苦しい思いをしていると思いこんで、塞ぎこんでいた。
「私ね、さくらが小説を書いているって打ち明けてくれたこと、本当にうれしかったし尊敬したの。だから……あのことがあって苦しんでいるさくらに、なんにもしてあげられない自分が本当に悔しくて、惨めだった」
さくらを元気づけたいのに、どうすれば良いのかわからない。
凛が病院の待合室で泣いていたときに、声をかけてきたのが、車椅子に乗ったとてもきれいな男の子だったそうだ。
「泣いているわたしを心配して、彼は、どうしたの? って声をかけてくれたんだ」
その瞬間、誰かに話を聞いてほしいという凛の願いが弾けた。
学校のひとじゃなくて、見ず知らずのこの男の子になら、打ち明けても問題ないと思ったらしい。
「彼は、私たちと同い年の男の子だった。名前は、柊透也くん。生まれつき心臓が悪くて、ほとんど病院の外に出たことがないって言っていたよ」
「柊透也……」
いま初めて、彼の苗字を知った。
透也は、数年前まで、本当にこの世界に生きていたんだ。
そして凛は、生前の彼に会ったことがある。
彼につながる手がかりを得たうれしさと同時に、どうしてわたしは生前の彼に会えなかったんだろうという悔しさが募って、涙がぽろぽろとこぼれ落ちる。
「私の話を熱心に聞いてくれたあと、透也くんが、その子の小説を読んでみたいって言い出したの。だから、教えちゃったんだ。……勝手なことをして、ごめんね」
「ううん、大丈夫……。教えてくれて、ありがとう」
「透也くんね、さくらの小説を本当に気にいっていたんだよ。この小説の続きが読みたい。先が気になるのにずっと更新が止まってるんだって、さびしそうに言ってた」
涙が止まらない。
わたしなんかの小説の続きを、待ってくれていたひとがいたことが、たまらなくうれしくて。
小説を書いていたことでボロボロに傷つけられた過去の傷が、癒えるように塞がっていく。
中学時代のわたしが、やっと救われたような気持ちだ。
「ずっと、さくらにも伝えたかったんだけど、遅くなっちゃってごめんね」
「凛は、なんにも悪くないよ……。小説の話も、凛のことまでも、ぜんぶ遠ざけようとしたわたしが悪いの。ごめんね」
「ううん。私こそ、あのとき、さくらの力になれなくてごめん。さくらには、透也くんの感想を直接聞かせてあげたかったんだけど……」
凛の愁いを帯びた声音から、彼女も、透也が亡くなったことを知っているのだと察した。
直接聞かせてあげたかった、か。
凛。わたしも心の底から、そう思うよ。
それに、まだその可能性を諦めてもいない。
「話を聞かせてくれて、ありがとう。今度は、直接会おうね」
「うん! 久しぶりに連絡をくれてありがとうね。私、さくらの知りたかったことを話せたかな?」
「ばっちりだよ。凛には、感謝してもしきれない」
「そっか。今度、遊んだときにまた話そうね」
凛との通話を切ると、わたしは、のろのろとパソコンの前に座って電源をつけた。
なにを書けば良いのか思いつかず、ずっと真っ白のままだった原稿を呼び起こす。
キーボードに手を載せると、題名がぱっと思い浮かんで、即座に手が動いた。
題『ラブレター 三年B組 東雲さくら』
これからわたしが書こうとしていることを透也が知ったら、卒倒するかもしれない。
みんなから頭がおかしいと言われるだろうし、最悪、茜と優希からも軽蔑されるだろう。
それでも、不思議と恐怖はなかった。
無難でどうでもいいような卒業文集を書こうとしていたときの苦しさがウソのように消えて、手が滑らかに動いていく。
やっと、気がついたんだ。
わたしは、透也の存在しない普通なんていらない。
だけど、あなたの連絡先すら知らないから、賭けに出る。
今さらをこんなことをしても無駄で、ただの自己満足に終わるのかもしれないけど、なにもせずにはいられないから。
まずはこの卒業文集を全力で書きあげて、けじめをつけようと思う。
*
あんなに書くのがしんどく思えていた卒業文集は、覚悟を決めて書きはじめたら、あっという間に完成した。
できあがったら、一番に読んでほしかった彼は、まだ帰ってこない。
透也がいなくなってからも、日々は淡々と過ぎていく。
結局、橋本くんには、実は好きなひとがいるのだと正直に打ち明けた。今は他のひとのことを考える余裕がないと話したら、しょんぼりはしていたけど納得してくれた。
もしかすると、逃した魚は大きかったのかもしれない。
だけど、もやもやとしたまま彼に半端な態度を取り続けるよりも、ずっと良かったはずだ。
受験シーズンも終わり、優希は、無事に第一志望に合格した。これで晴れて彼氏と同じ大学に通えるんだと喜んでいた。
そして、卒業式を一週間後に控えた今日、卒業文集の完成品がみんなに配られる。
みんなからしたら、思い入れすらないのかもしれないけど。
わたしにとっては、決戦の日。
震えそうになる足を奮いたたせるように、大きく息を吸いこむ。
透也と出逢った一年近く前のあの日も、今日のように、きれいな青空だった。
家を出て、学校へ向かおうと歩き出したそのとき、懐かしい声が耳をくすぐった。
「久しぶりだね、さくら」
「透也……!」
今まで、三か月近くもの間、一体どこへいっていったの。
ずっとずっと、会いたくてたまらなかった。
胸の真ん中から愛おしさがあふれてきて、涙が止まらない。
「さくら。そんなに泣いたら、学校へ行けなくなっちゃうよ」
「だって……っ。透也が、勝手にいなくなったりするからっ」
「……いなくなるのが、きみのためだと思ったんだよ。だけどね、どうやっても、成仏することができなかったんだ。だからもう一度、きみに会いにきた」
彼が、わたしのそばにいるために戻ってきたわけじゃないと知って、落胆する。
だけど、どんな理由であれ、透也と再会できたことは神さまがわたしにくれたチャンスなんだと思う。
「ねえ、透也。わたしね、ちゃんと卒業文集を書けたよ。今日、配られるんだ」
「そっか……。よく、がんばったね」
「一番に、透也に読んでほしいと思って書いたの。あれは、あなたへのラブレターだから」
*
「わたしには、好きなひとがいる。彼の名前は、透也。心臓の病で亡くなっている男の子なんだけど、どういうわけか、彼はわたしにだけは見えている……」
「ねえ、さくら。卒業文集のこの内容、どういうこと……? 大がかりな冗談?」
茜と優希の面喰ったような表情に、審判のときが来たと歯を食いしばる。
彼女たちだけじゃなく、他のクラスメイトも、わたしのページを見て奇妙な顔をしているかもしれない。
「さくら! 今からでも遅くない、卒業文集に書いたことはぜんぶ妄想だったって言おう! みんなを驚かせたかっただけだよって笑い飛ばせば、みんな冗談にしてくれる。お願い、お願いだから、そうしよう! 僕は、こんなことをきみに望んでいたんじゃないっ」
教室中から奇異の目を向けられてるわたしに、透也だけが、泣きそうな顔で懇願している。
ごめんね、透也。
大好きなあなたの言うことでも、それだけは聞いてあげられない。
だってわたしは、透也を見えていないフリなんて、もうしたくないから。
「ううん。ずっと黙っていただけで、そこに書いたのは、ぜんぶ本当のことなの」
休み時間だとは思えないほど、教室がしんと静まる。
これ以上にないほどの視線を感じる中、わたしは震える足できちんと立って、目の前の透也だけを見つめた。
「ねえ、透也。わたしは、透也のことが好きだよ」
この恋は、普通じゃない。
透也の存在は、どうやっても証明できない。
彼は、わたしの妄想力が激しい頭が生み出した幻覚なのだと言われても、否定はできない。もしかするとわたしは、とっくに狂っているのかもしれないし、おかしいのかもしれない。病院に行けと言われるほどの重症なのかもしれない。
そうだとしても、かまわない。
なんでとも言われる覚悟はできている。
透也を手放すくらいならば、わたしはこの茨の道を進みたい。
「透也。あなたはまだ、わたしの小説を最後まで読んでいない。だから、もう勝手にいなくなったりしないで」
「さく、ら……」
「凛から、あなたの話を聞いたの。わたし、これから、またあの小説を続きを書きたいと思ってるんだ。だからね、透也にはわたしの小説の一番の読者でいてほしい。お願い!」
「そんなの、ダメに決まってる……っ! だって、僕は、きみに普通の幸せをなにひとつあげられないんだよ……? きみを抱きしめることもできなければ、話しているだけで周りからおかしな目で見られる。きみは、普通が良いんじゃなかったの? 僕なんかを選んだら、いつか絶対に後悔するよ!」
「後悔するかどうかは、わたしが決めるの! それに、やってみるまではわからないでしょ?」
「あぁ、もうっ。ああいえばこう言うんだから! 僕が、どれだけきみのことを心配していると思って……!」
「お願い、透也。わたしのことを想うなら、諦めて、ずっとわたしのそばにいて?」
もっと言うなら、あの小説を完成させたとしても、いなくならないでほしい。
わたしはね、あなたの未練そのものになりたいんだ。
「ほんとにもう……。きみは、信じられないほどの大バカだよ」
「ふふっ。ひどい言い草だなぁ」
「だけど……すごく、かっこよかった。かっこよすぎて……こんなの、もっと好きになるしかないし、きみを遺して成仏なんてできるわけなくなったじゃん。バカさくら」
目を疑った。
いつも、余裕の表情でわたしをからかうばかりだった彼が、珍しく照れたような顔をしていたから。
胸が苦しいほど締めつけられて、痛いくらいで。
ものすごく……幸せだ。
「ありがとう、透也。大好きだよ」
高校を卒業するまでの明日からの一週間は、みんなから遠巻きにされるだろう。
優希にも、茜にも、透也を信じてもらうのは難しいかもしれない。
二人との信頼関係を疑っているというよりも、そのぐらい、わたしの選んだ道が普通ではない自覚があるという意味で。
きっと、幽霊が見えているだとかいう頭のおかしな迫真演技をした女子として、中学時代の比ではないほど注目を浴びる。下手をしたら、この先、月ヶ丘高校の伝説として語り継がれるレベルかも。
それでも、後悔は一切していない。
それどころか、やっと、みんなの前で堂々と透也と話をすることができた喜びの方が勝っている。
明日からも、怖くはない。
わたしにとっては、透也が見えているし、存在していることが現実だ。
透也が存在していることを証明できないのと同じように、みんなだって、透也が存在していないことを証明はできない。
難しい話はわからないけど、わたしとっては、透也がそばにいてくれることだけが全てなんだ。
普通に固執していた自分からは、もう卒業だ。【完】
「へっへん。感謝してよね、橋本少年」
「ひとつしか歳変わらないのに、少年扱いするのやめてくれませんか」
「憧れのさくらの前で、背伸びしたいんだぁ~。かわいいねぇ」
「ち、ちがっ! あ、いや……。ちがくは、ないかもですけど」
優希と、隣あって座っている男の子のやりとりを、落ちつかない気持ちで眺める。
わたしたち三人、透也もいれると四人は、月ヶ丘高校近くのファミレスチェーン店にやってきていた。一度こうだと決めた優希の行動力は凄まじく、彼の話が出てから一週間も経たないうちに今日の会をセッティングしてしまったというわけだ。
橋本少年と呼ばれた彼が、優希が話していた塾の男の子だ。
すこし童顔気味で、髪型は爽やかなマッシュショート。彼も高校帰りなので、学ランを着ている。
第一印象だけで言うと、どちらかといえば、かわいい系だ。
いきなり派手な人が来なくて良かったと、内心、ホッとしてしまう。
「二人とも、めーっちゃくちゃ緊張してんじゃん。ウケる」
「ふーん。髪も染めていなさそうだし、見た目的に、チャラそうではないね。僕ほどじゃないけど、まあまあ好青年なんじゃないかな? 実は、優希ちゃんが連れてくるって聞いて、ちょっと心配してたんだよねー。ド金髪にピアスの男が出てきたら猛反対するところだったけど、まずは及第点」
コーラを飲みながらケラケラと笑う優希に、腕を組みながら目の前の橋本くんを凝視している透也。……控えめに言って、かなりカオスだ。
橋本くんは、わたしの沈黙を、緊張だと受け取ったのかもしれない。
すこし強張ったような面持ちで、話しかけてきた。
「えと……。初めまして、東雲先輩。オレは、橋本真っていいます。その、すこし前から、東雲先輩のことが気になってたんです。柳原先輩と歩いてるところ見て、良いなぁって思ってて……」
たどたどしい口調で、しどろもどろになっていく姿から、少なくともウソをついてはいなさそうだと感じる。
透也と出会っていないわたしが聞いていたら、年下の男の子の一生懸命な感じに、すこしは心動かされていたかもしれない。自分でもかなしくなるほどに、この場をどうやり過ごそうとしか思えていなかった。
「あ、ありがとうございます」
「さくら、敬語じゃなくて良いよ。後輩なんだし」
「柳原先輩に許可される筋合いはないけど、まぁ、そっすね。東雲先輩、オレには敬語じゃなくて大丈夫です!」
「わ、わかった。そうさせてもらうね」
「その……、良かったら、連絡先を教えてもらえませんか?」
「うん」
流れ的にここで断るのもヘンな感じだしなぁと、あまり気乗りしないけれどスクバから携帯を取り出す。彼が表示させたQRコードを読み取りながら、虚しい気持ちがふくらんだ。
透也の連絡先も知らないのに、どうしてわたしは、今日知りあったばかりの男の子を連絡先に追加しているんだろう。
目の前の橋本くんは、わたしの心を占める陰気な気持ちに気がつくわけもなく、はしゃいでいる。
「ありがとうございますっ! 連絡させてもらいますねっ」
「はーーっ。いいねぇ、甘酸っぱいね~。うまくいったら、ダブルデートしようね!」
「ちょ、ちょっと優希」
いくらなんでも囃したてすぎだ。
悪ノリしている優希を責めたい気持ちと、流されるままに今日この場へ来てしまった自分への罪悪感とで、背筋に嫌な汗が伝った。
「柳原先輩、あんまりからかわないでくださいよ。東雲先輩は、あなたと違ってピュアそうなタイプなんですから」
「はいはい、わかったよ。んじゃ、そろそろお邪魔虫は退散しようかね」
「えっ」
スクバを手に、さっと立ち上がった優希を見て、今度は目がまるくなる。
「ほんとは、もーちょっとこの場で二人をからかっていたいところだけど、あたしはそろそろ塾の自習室に向かうね。これでも一応、受験生だからさ」
優希は長い髪をふわふわと揺らしながら、自分のドリンク代だけ置いて、とっとと去っていった。
まるで嵐のようだ。
こんなに急に二人きりにされるなんて聞いてないよ!
いや、正確には、わたし目線で見ると三人なんだけど……。
「うーん。もしかして僕も、席を外した方が良かったりする?」
「ごほっごほっ」
透也まで妙なことを言いだして、飲みかけのアイスティーをむせそうになった。
「東雲さん、大丈夫ですか!」
「う、うん。ちょっとむせただけ」
「やっぱり、もうすこし彼を観察することにするよ。さくらを任せるに値する男なのかしっかり見極めないとね」
むせて涙目になったわたしに、ニヤニヤとした視線を送ってくる透也は、やっぱり意地が悪いと思う。面白がっているとしか思えない。
「柳原先輩って、ほんと自由ですよね。あのひと受験大丈夫なのかなぁ」
「なんだかんだで、努力しているんじゃないかな。彼氏と同じ大学に通うんだってはりきってるみたいだし」
「あのひとは、のろけすぎなんですよ。いいよなー……」
ただの優希への感想だとわかっているのに、中途半端な気持ちでここにいるわたしを責めているようにも聞こえて、なんだか息苦しくなる。
気まずい。なにか会話を続けなきゃ。そう思えば思うほど、焦ってなにも言葉が出てこない。周囲の喧騒ばかりが耳につく。
「オレ、東雲先輩のことを、もっと知りたいと思ってます」
純粋で、きらきらとしたその視線は、今の情けないわたしにとって眩しすぎる。
焼け爛れそうだ。
「先輩のことを教えてください」
「わたしのこと?」
「はい。趣味とか、好きなこととか。なんでもいいです!」
趣味。好きなこと。
そう問われた瞬間、なぜだか、夢中になって物語を紡いでいた中学時代の自分が脳裏によぎった。
『なぁ。俺にも、東雲の書いた小説を読ませてよ』
それと同時に、明らかに人を見下しているとわかる下卑た笑い声も、耳の奥からねっとりと蘇る。
よりにもよって、なんで今さら、あんな最低な記憶を思い出すんだろう。
わたしは、書くのをやめた。
一時期は夢中で読んでいた小説も、今ではほとんど読んでいない。
妄想を書きつづって満足する痛々しい自分のことなんて、もう捨てたはずなのに。
「ええと……。音楽を聴いたり、動画を見たりとか」
「へぇ! どんな音楽を聴くんですか?」
想像以上に食いつきが良くて、びくびくとしてしまう。
「あー、えっと、バンドなんだけど、なんて名前だったかな。友だちに勧められて知ったから、そんなに詳しいわけじゃないんだけど……」
愛想笑いをしながらスマホをいじって、プレイ済リストから茜に勧められたバンド名を慌てて探す。
ほんとは、なんとなく聴いて、へぇと思った程度だ。思い入れはない。
だけど、趣味だと言った以上、やっぱりそんなに好きじゃないという本音を言い出せる空気でもなくて。取りつくろってばかりの自分に、どんどん嫌気が差していく。
「あー! 虹色セカイかぁ。ハイトーンボイスがかっこいいバンドっすよねぇ」
わたしのスマホ画面をひょいっとのぞきこんで、橋本くんの方から勝手に話をつないでくれたので、なんとか助かった。ほっと胸をなでおろす。
その後も、どうやって違和感なくこの場をお開きにしようかということばかり考えていて、目の前の橋本くんの話は耳を滑っていくばかりだった。
ドリンクバーで取ってきたオレンジジュースも、ぜんぜん味がしなかった。
*
「はああぁ……。つっかれたなぁ」
「ふふっ。盛大なため息だねぇ。ため息が、真っ白だよ」
肺に滑りこんでくる空気はとても冷たくて、だけど、心地が良かった。
からだの中にたまっていた淀んだ気持ちが浄化されていくような感じ。
宿題をするという適当な言い分を並べて橋本くんと分かれたあと、わたしは透也と一緒に近所の公園にやってきていた。
ブランコが二つと、ベンチが一つだけしかない、小さな公園だ。
最近は、日が落ちるのがとても早くなったので、あたりはすでに薄暗い。
なんとなく、このまま家に帰る気分になれず、たまたま人が見あたらなかったのを良いことに、わたしはブランコへと腰かけた。透也も、わたしを真似するように、隣のブランコへと腰かける。
人気のない場所に来ると、とても落ちつく。
その理由には、もう、ずいぶん前から気がついていた。
他の誰といるときよりも、わたしは、幽霊の透也と過ごす時間が好きだから。
「そりゃ、疲れるよ。優希は、とっとと帰っちゃうしさー。初対面の男の子となんて、なにを話したら良いのかわかんないもん」
「そう? 僕と初対面だったときも、そう思っていたの?」
「……透也とは、比べられないよ」
「まぁ、僕は幽霊だしねー」
それは、間違っていないんだけど。
あえて話を茶化されたような感じがして、ムッとしてしまう。
「さくら。橋本くんのことは、どう思った?」
「……うーん。まだ、よくわかんないけど、悪い人ではないと思う」
「そうだね、僕も同じことを思ったよ」
透也の何気ない同調に、胸が切り裂かれたように痛む。
「そんな渋い顔しないで、もっとまじめに考えてあげたら? 彼は、さくらにちゃんと向きあってくれそうな、普通の男の子に見えたよ」
普通ではない、幽霊の自分とは違って。
彼がそう言っているようにも聞こえて、無性に切なくなる。
「……ごめん。きみが迷ってしまうのは、僕のせいでもあるよね。だからね、さくら。僕たち、さようならをしようか」
「えっ」
「僕がきみのそばにいても、きみが幸せになる邪魔にしかならないと思う」
耳を疑った。
彼がなにを言っているのか、本気で理解できなかった。
いや、したくなかったんだ。
「なんで? なんで透也がいなくなる話になるの。わけわかんない、いくら意地悪だからって冗談きついよ!」
透也は、なにも言わない。
さびしそうな顔で、泣きながら怒っているわたしをじっと見つめている。
「未練はどうなったの⁉ まだ解消できていないから、成仏していないんでしょ! ねえっ、そうなんでしょ!」
「それは、そうだけど……。僕の未練のことは、もう良いんだよ」
「良くないよ! 人のこと散々振りまわしておいて、いざとなったら、大事なこと一つも話してくれずに勝手に去ろうとするわけ? そんな、そんなの……あまりにも、ひどいよ」
痛々しいほど必死な叫びに、透也のきれいな顔が、今まで見たこともないほど感情的に歪んだ。
感情をむき出しにしたような怒りの表情に気圧されて、ひゅっと心臓が縮む。
「……願っても、叶えられないんだよ! だってきみは、もう小説をやめたんだろ!」
「えっ……」
「僕の未練は、ある日を境に、更新が止まった小説を最後まで読むことだった。そのために、きみに近づいたんだよ。きみにだけは、なぜだか僕の姿が見えているようだったから、きっときみがあの小説の作者なんだって僕にはわかった」
なんで? どうして透也の口から、わたしの小説の話が出てくるの。
息をすることも忘れて、彼の激白に聞き入る。
「きみ自身の意志で再び書きたいと願ってくれなきゃ、意味がないと思ってた。だから、待ち続けたんだ。でも……さくらは、毎日つまらなそうな顔で友だちの真似をするばかりだし、おまけに小説の話題は頑なに避けていた。もう、待つのは疲れたよ! きみのそばにいても、どうにもならないじゃないか!」
あまりの衝撃に、呆然として言葉を失ったわたしに目をやって、透也はしまったというように瞳をハッと見ひらいた。
「ご、めん。言いすぎた。……言うつもり、なかったのになぁ」
透也はよろよろと立ちあがり、そのまま公園を出ていった。
しばらくの間、雷に撃たれたように、その場から動けずにいた。
動悸がする。呼吸が浅い。心臓が、バクバクと熱く脈打っている。
どうして透也は、わたしが昔に小説を書いていたことを知っていたの?
冬の夜風が、コートの中まで浸透するように、骨身を冷たくする。
その日、透也は、わたしのもとへと帰ってこなかった。
*
透也がわたしの前から立ち去ったその夜、悪夢を見た。
正確には、ただの夢じゃない。
これは心の奥底に鍵をかけて沈めた、中学時代の辛い記憶だ。
中学時代のわたしは、小説を書くことが趣味の、夢見がちな少女だった。
本を読むのも大好きで、小説家になりたいって本気で思っていた。だけど、わたしの通っていた中学校に文芸部はなかったし、みんなに小説を書いていることを知られるのはなんとなく気恥ずかしくて、インターネットの小説投稿サイトへ書いた作品をひっそりとアップロードしていた。
『凛。あのね、みんなには言わないでほしいんだけど……実はわたし、小説家を目指しているの』
その夢を、クラスの中で一番仲の良かった、凛にだけ打ち明けた。
秘密にしたい気持ち以上に、親友にだけは知ってもらいたい気持ちが勝ったから。
『そうなの? さくら、すごいね! 私、読んでみたいな! ペンネームを教えてくれる?』
『ありがとう! えっとね、チェリーって名前で活動しているんだけど……』
自分の名前と同じ名の花、桜は英語でチェリーブロッサムという。そう習って、安直につけたペンネームだった。
今までずっと内緒にしていた分、好きなことを自由に話せるのは本当に楽しくて。
夢中になって凛に書いた小説の話をしているうちに、間抜けなわたしは、その場所がいつクラスの誰が入ってくるかもわからない放課後の教室だということを忘れていた。
『へえぇ~。東雲って、小説とか書くんだ』
背筋が凍るような思いだった。
忘れ物を取りにきたらしいサッカー部のクラスメイトに、いつの間にか、会話を聞かれてしまっていたんだ。
しかも、見つかってしまった相手もまた最低最悪だった。
よく通る大きな声で、自分が目立つためならば、なんでも面白おかしく話すようなやつだったから。
『なぁ。俺にも、東雲の書いた小説を読ませてよ』
あざけりの含まれたような声は、悪意に満ちていて。面白いおもちゃを見つけたというような嗜虐心が、ニヤニヤとした嫌な視線から即座に伝わってきた。心臓が、痛くなる。
小説を書いているなんて、痛いね。
彼の発した言葉が、そう変換されて、脳内で何度も再生される。
『さくら、場所を変えようか』
『……うん』
『おい、無視すんなよー』
その日は凛の助け舟があったから、それ以上絡まれずに済んだけど、その翌日からも地獄のようだった。
『東雲ってさー、小説書いてるらしいよ』
『え、小説? なにそれ、ウケるんだけどー』
『あ、ウワサをすればご本人の登場じゃん。なぁ、なんで昨日無視したの?』
わたしの大事な作品は、彼のおちゃらけたような軽い口でたやすく拡散され、笑いものにされていた。
もちろん、無言を貫いてまともに相手をすることはなかったけど、いくら平気な顔をしてみたところで心は徐々に病んでいった。
『さくら、気にすることはないよ』
凛だけは、日に日に顔色を悪くしていくわたしを慰めてくれたけど、段々、学校に通うことすら辛くなっていった。
教室のどこにいても、妄想好きの痛いやつだとあざ笑われているような気がする。胃がムカムカとしてきて、何度かお手洗いに駆けこみ、そのまま吐いてしまったこともあった。
体調が悪化するのと同時に、創造の翼も折れてしまった。
それまでは、毎日心躍らせながら、楽しく小説を書いていたのに。
まっさらな白い原稿を前にしても、想像が広がらない。文字を打ちこむ手もさっぱり動いてくれなくなった。書こうとすると、『小説? ウケるんだけど』という呪詛が耳の奥からゾンビのように蘇ってきて、動悸すらする。
書けない。
書けない書けない書けない。
こんなに辛いのなら、もう、書くのをやめてしまおう。
どうせ、投稿サイトにアップした小説にも、ほとんどPVはついていない。
世の中には、感動的で、面白い小説を書くひとが星の数ほどいる。
拙いわたしの小説を待っている人なんて、どこにもいない。
どうして小説家になるだなんて不相応な夢を今まで本気で見られていたのかも、さっぱりわからなくなった。
高校は、わたしのことを誰も知らない、遠い場所を受験しよう。
そして今度こそは、絶対に同じ失敗をしない。
小説を書いていたことは忘れて、みんなから浮かないように過ごす。
普通の高校生になって、普通の幸せを得ることだけを目標に、わたしは通学に一時間近くかかる月が丘高校を受験したんだ。
*
目覚めたとき、瞳から涙が流れていた。
もう二度と思い出したくない最悪な記憶を夢に見たのは、たぶん、透也の怒ったような顔が胸に突き刺さって消えなかったからだ。
『……願っても、叶えられないんだよ! だってきみは、もう小説をやめたんだろ!』
辛そうな顔をしてわたしの前から消えた透也は、朝になっても帰ってきていなかった。
九か月ぶりに訪れた、一人きりの静かな休日の朝だ。
部屋に一人だと、こんなにもだだっ広くて心細いものなのかと、今さら気がつく。
いつの間にか、透也に「おはよう、さくら。寝顔、かわいかったよ」とからかわれながら目覚めるのが、当たり前になってしまっていたらしい。
透也がいなくなった今、わたしは正真正銘、普通の女子高生になったんだと思う。
学校で浮いているわけでもなく、友だちがいて、後輩の男の子と普通の恋を始められそうな予感もある。
中学時代の、苦しかったわたしが切実になりたいと願った、理想そのままのわたし。
――本当に?
【おはようございます。昨日は、ありがとうございました! 東雲先輩のこと、さくら先輩って呼んでもいいですか?】
せっかく橋本くんがメッセージをくれたというのに、返信をする気力もわいてこない。
これが理想ならば、どうしてわたしは、胸をかきむしりたくなるほど腑に落ちていないんだろう。
なによりも、今のわたしが求めているのは、透也のことだけだ。
彼のことをなにひとつ知らないまま、終わりになんてできない。できるはずがない。
これが普通の幸せ? ふざけんな。全然ハッピーじゃないし、望んでもいない。
こんな結末、認めてたまるものか!
『僕の未練は、ある日を境に更新が止まった小説を最後まで読むことだった。そのために、きみに近づいたんだよ。きみにだけは、なぜだか僕の姿が見えているようだったから、きっときみがあの小説の作者なんだってすぐにわかった』
透也につながる手がかりはほとんどないに等しいけど、彼が、わたしが小説を書いていたことを知っていたのがどうにも引っかかっている。
中学時代、わたしが小説を書いていたことは悪意をもって広められたけど、チェリーというペンネームで投稿活動していたことを打ち明けたのは凛だけなのに。
……凛にだけ?
些細だけど重要なことに思えて、わたしは震える手で、数年ぶりにかつての親友へと連絡を取った。
【久しぶり。凛、元気にしてる?】
【さくら! ほんとに久しぶりだね、私は元気だよ。さくらはどう?】
すぐに返事が返ってきて、ほっとした。
【うん、元気だよ。ずっと連絡が取れていなくて、ごめんね】
【気にしないで。連絡を取っていなかったのはお互いさまだし、さくらだけのせいじゃないでしょ】
数年ぶりに凛のやさしさに触れて、じわりと目頭が熱くなる。
月ヶ丘高校に入学してからのわたしは、中学の記憶を呼び起こす全てを切り捨てたくて、凛とも距離を置いてしまっていた。
凛はなにも悪くない。わたしの薄情な態度に怒っていてもおかしくないのに。そんな態度はみじんも見せずに、かつてのやさしさをそのまま向けてくれることが、とてもありがたい。
【あのね、凛。わたし、凛に聞きたいことがあって、連絡をとったの。もし心当たりがあったら、教えてくれる?】
【なんの話し?】
【中学時代に、わたしが小説を書いていた話をしたと思うんだけど。そのことを、他の誰かにしたことってあったりする?】
それまでスムーズに返ってきていた返信が、急にぴたりと止まった。
もしかして、文章だけだと責めているように感じただろうか。
そういう意味じゃなくて、ただ純粋に知りたいだけだと慌ててメッセージを追加しようとしたところで、着信が入った。
凛からだ。
「もしもし。さくら、いま、電話は大丈夫?」
「う、うん……」
「あぁ、さくらの声だ。久しぶりに話せて、うれしいよ」
「わたしも。凛と話せて、うれしい」
凛は、今でも中学時代と変わらずに吹奏楽部を続けているらしい。
私立の付属高校なので受験もなく、のんびり過ごしていると語った。
数年ぶりの会話なのに、久しぶりだという感覚は薄く、会話が尽きないのがとても心地よかった。相手にどう思われているか気にすることなく話せるこの感覚は、透也と話しているときと似ている。
お互いの近況を一通り話し終わり、凛が深呼吸をしたとき、緊張が走った。
「えっとね、さくらの小説の話なんだけど……当時、一人の男の子にだけしたことがあるの。さくらに許可も取らずにごめんね」
やっぱり。
あいまいな予感に過ぎなかったものが確信へと近づいて、胸が熱を帯びた。
「詳しく、教えてくれる?」
「うん」
それは、わたしたちが中学三年生だったときのこと。
当時の凛は、祖母のお見舞いで、大学の総合病院に通っていたらしい。
「そう、だったんだね……。凛も大変だったのに、わたし、ぜんぜん知らなかった」
「いいの。さくらは、それどころじゃなかったから……」
当時のわたしは、自分だけが辛くて苦しい思いをしていると思いこんで、塞ぎこんでいた。
「私ね、さくらが小説を書いているって打ち明けてくれたこと、本当にうれしかったし尊敬したの。だから……あのことがあって苦しんでいるさくらに、なんにもしてあげられない自分が本当に悔しくて、惨めだった」
さくらを元気づけたいのに、どうすれば良いのかわからない。
凛が病院の待合室で泣いていたときに、声をかけてきたのが、車椅子に乗ったとてもきれいな男の子だったそうだ。
「泣いているわたしを心配して、彼は、どうしたの? って声をかけてくれたんだ」
その瞬間、誰かに話を聞いてほしいという凛の願いが弾けた。
学校のひとじゃなくて、見ず知らずのこの男の子になら、打ち明けても問題ないと思ったらしい。
「彼は、私たちと同い年の男の子だった。名前は、柊透也くん。生まれつき心臓が悪くて、ほとんど病院の外に出たことがないって言っていたよ」
「柊透也……」
いま初めて、彼の苗字を知った。
透也は、数年前まで、本当にこの世界に生きていたんだ。
そして凛は、生前の彼に会ったことがある。
彼につながる手がかりを得たうれしさと同時に、どうしてわたしは生前の彼に会えなかったんだろうという悔しさが募って、涙がぽろぽろとこぼれ落ちる。
「私の話を熱心に聞いてくれたあと、透也くんが、その子の小説を読んでみたいって言い出したの。だから、教えちゃったんだ。……勝手なことをして、ごめんね」
「ううん、大丈夫……。教えてくれて、ありがとう」
「透也くんね、さくらの小説を本当に気にいっていたんだよ。この小説の続きが読みたい。先が気になるのにずっと更新が止まってるんだって、さびしそうに言ってた」
涙が止まらない。
わたしなんかの小説の続きを、待ってくれていたひとがいたことが、たまらなくうれしくて。
小説を書いていたことでボロボロに傷つけられた過去の傷が、癒えるように塞がっていく。
中学時代のわたしが、やっと救われたような気持ちだ。
「ずっと、さくらにも伝えたかったんだけど、遅くなっちゃってごめんね」
「凛は、なんにも悪くないよ……。小説の話も、凛のことまでも、ぜんぶ遠ざけようとしたわたしが悪いの。ごめんね」
「ううん。私こそ、あのとき、さくらの力になれなくてごめん。さくらには、透也くんの感想を直接聞かせてあげたかったんだけど……」
凛の愁いを帯びた声音から、彼女も、透也が亡くなったことを知っているのだと察した。
直接聞かせてあげたかった、か。
凛。わたしも心の底から、そう思うよ。
それに、まだその可能性を諦めてもいない。
「話を聞かせてくれて、ありがとう。今度は、直接会おうね」
「うん! 久しぶりに連絡をくれてありがとうね。私、さくらの知りたかったことを話せたかな?」
「ばっちりだよ。凛には、感謝してもしきれない」
「そっか。今度、遊んだときにまた話そうね」
凛との通話を切ると、わたしは、のろのろとパソコンの前に座って電源をつけた。
なにを書けば良いのか思いつかず、ずっと真っ白のままだった原稿を呼び起こす。
キーボードに手を載せると、題名がぱっと思い浮かんで、即座に手が動いた。
題『ラブレター 三年B組 東雲さくら』
これからわたしが書こうとしていることを透也が知ったら、卒倒するかもしれない。
みんなから頭がおかしいと言われるだろうし、最悪、茜と優希からも軽蔑されるだろう。
それでも、不思議と恐怖はなかった。
無難でどうでもいいような卒業文集を書こうとしていたときの苦しさがウソのように消えて、手が滑らかに動いていく。
やっと、気がついたんだ。
わたしは、透也の存在しない普通なんていらない。
だけど、あなたの連絡先すら知らないから、賭けに出る。
今さらをこんなことをしても無駄で、ただの自己満足に終わるのかもしれないけど、なにもせずにはいられないから。
まずはこの卒業文集を全力で書きあげて、けじめをつけようと思う。
*
あんなに書くのがしんどく思えていた卒業文集は、覚悟を決めて書きはじめたら、あっという間に完成した。
できあがったら、一番に読んでほしかった彼は、まだ帰ってこない。
透也がいなくなってからも、日々は淡々と過ぎていく。
結局、橋本くんには、実は好きなひとがいるのだと正直に打ち明けた。今は他のひとのことを考える余裕がないと話したら、しょんぼりはしていたけど納得してくれた。
もしかすると、逃した魚は大きかったのかもしれない。
だけど、もやもやとしたまま彼に半端な態度を取り続けるよりも、ずっと良かったはずだ。
受験シーズンも終わり、優希は、無事に第一志望に合格した。これで晴れて彼氏と同じ大学に通えるんだと喜んでいた。
そして、卒業式を一週間後に控えた今日、卒業文集の完成品がみんなに配られる。
みんなからしたら、思い入れすらないのかもしれないけど。
わたしにとっては、決戦の日。
震えそうになる足を奮いたたせるように、大きく息を吸いこむ。
透也と出逢った一年近く前のあの日も、今日のように、きれいな青空だった。
家を出て、学校へ向かおうと歩き出したそのとき、懐かしい声が耳をくすぐった。
「久しぶりだね、さくら」
「透也……!」
今まで、三か月近くもの間、一体どこへいっていったの。
ずっとずっと、会いたくてたまらなかった。
胸の真ん中から愛おしさがあふれてきて、涙が止まらない。
「さくら。そんなに泣いたら、学校へ行けなくなっちゃうよ」
「だって……っ。透也が、勝手にいなくなったりするからっ」
「……いなくなるのが、きみのためだと思ったんだよ。だけどね、どうやっても、成仏することができなかったんだ。だからもう一度、きみに会いにきた」
彼が、わたしのそばにいるために戻ってきたわけじゃないと知って、落胆する。
だけど、どんな理由であれ、透也と再会できたことは神さまがわたしにくれたチャンスなんだと思う。
「ねえ、透也。わたしね、ちゃんと卒業文集を書けたよ。今日、配られるんだ」
「そっか……。よく、がんばったね」
「一番に、透也に読んでほしいと思って書いたの。あれは、あなたへのラブレターだから」
*
「わたしには、好きなひとがいる。彼の名前は、透也。心臓の病で亡くなっている男の子なんだけど、どういうわけか、彼はわたしにだけは見えている……」
「ねえ、さくら。卒業文集のこの内容、どういうこと……? 大がかりな冗談?」
茜と優希の面喰ったような表情に、審判のときが来たと歯を食いしばる。
彼女たちだけじゃなく、他のクラスメイトも、わたしのページを見て奇妙な顔をしているかもしれない。
「さくら! 今からでも遅くない、卒業文集に書いたことはぜんぶ妄想だったって言おう! みんなを驚かせたかっただけだよって笑い飛ばせば、みんな冗談にしてくれる。お願い、お願いだから、そうしよう! 僕は、こんなことをきみに望んでいたんじゃないっ」
教室中から奇異の目を向けられてるわたしに、透也だけが、泣きそうな顔で懇願している。
ごめんね、透也。
大好きなあなたの言うことでも、それだけは聞いてあげられない。
だってわたしは、透也を見えていないフリなんて、もうしたくないから。
「ううん。ずっと黙っていただけで、そこに書いたのは、ぜんぶ本当のことなの」
休み時間だとは思えないほど、教室がしんと静まる。
これ以上にないほどの視線を感じる中、わたしは震える足できちんと立って、目の前の透也だけを見つめた。
「ねえ、透也。わたしは、透也のことが好きだよ」
この恋は、普通じゃない。
透也の存在は、どうやっても証明できない。
彼は、わたしの妄想力が激しい頭が生み出した幻覚なのだと言われても、否定はできない。もしかするとわたしは、とっくに狂っているのかもしれないし、おかしいのかもしれない。病院に行けと言われるほどの重症なのかもしれない。
そうだとしても、かまわない。
なんでとも言われる覚悟はできている。
透也を手放すくらいならば、わたしはこの茨の道を進みたい。
「透也。あなたはまだ、わたしの小説を最後まで読んでいない。だから、もう勝手にいなくなったりしないで」
「さく、ら……」
「凛から、あなたの話を聞いたの。わたし、これから、またあの小説を続きを書きたいと思ってるんだ。だからね、透也にはわたしの小説の一番の読者でいてほしい。お願い!」
「そんなの、ダメに決まってる……っ! だって、僕は、きみに普通の幸せをなにひとつあげられないんだよ……? きみを抱きしめることもできなければ、話しているだけで周りからおかしな目で見られる。きみは、普通が良いんじゃなかったの? 僕なんかを選んだら、いつか絶対に後悔するよ!」
「後悔するかどうかは、わたしが決めるの! それに、やってみるまではわからないでしょ?」
「あぁ、もうっ。ああいえばこう言うんだから! 僕が、どれだけきみのことを心配していると思って……!」
「お願い、透也。わたしのことを想うなら、諦めて、ずっとわたしのそばにいて?」
もっと言うなら、あの小説を完成させたとしても、いなくならないでほしい。
わたしはね、あなたの未練そのものになりたいんだ。
「ほんとにもう……。きみは、信じられないほどの大バカだよ」
「ふふっ。ひどい言い草だなぁ」
「だけど……すごく、かっこよかった。かっこよすぎて……こんなの、もっと好きになるしかないし、きみを遺して成仏なんてできるわけなくなったじゃん。バカさくら」
目を疑った。
いつも、余裕の表情でわたしをからかうばかりだった彼が、珍しく照れたような顔をしていたから。
胸が苦しいほど締めつけられて、痛いくらいで。
ものすごく……幸せだ。
「ありがとう、透也。大好きだよ」
高校を卒業するまでの明日からの一週間は、みんなから遠巻きにされるだろう。
優希にも、茜にも、透也を信じてもらうのは難しいかもしれない。
二人との信頼関係を疑っているというよりも、そのぐらい、わたしの選んだ道が普通ではない自覚があるという意味で。
きっと、幽霊が見えているだとかいう頭のおかしな迫真演技をした女子として、中学時代の比ではないほど注目を浴びる。下手をしたら、この先、月ヶ丘高校の伝説として語り継がれるレベルかも。
それでも、後悔は一切していない。
それどころか、やっと、みんなの前で堂々と透也と話をすることができた喜びの方が勝っている。
明日からも、怖くはない。
わたしにとっては、透也が見えているし、存在していることが現実だ。
透也が存在していることを証明できないのと同じように、みんなだって、透也が存在していないことを証明はできない。
難しい話はわからないけど、わたしとっては、透也がそばにいてくれることだけが全てなんだ。
普通に固執していた自分からは、もう卒業だ。【完】