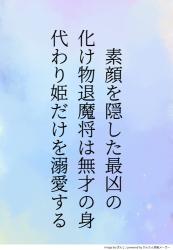はぁ……、どうしようかな。なにを書けば良いのか、全く思い浮かばないや。
一向に埋まる気配のない白い原稿を前に、気分が重たく沈んでいく。
昔はこの空白を前にすると、なにを書いても良いんだと思えて心が躍ったのに。今のわたしにとっては重荷にしか思えない。たった八百文字を埋めるだけなのに、一文字も書けないまま、もう一時間近くが経過しようとしている。
わたし――東雲さくらは、卒業文集という難題にぶつかり、途方に暮れていた。
だって、なにを書いたら良いのか、本当に思いつかない。
成績は平凡、部活は帰宅部、美化委員にもこれといった思い出はなし。
わたしが月ヶ丘高校で過ごした二年半とちょっとの日々に、特筆すべきことは、なにもないんだ。
カーテンを閉めきった暗い自室で一人パソコンの薄明りを前にうなだれていたら、背後から、柔らかな声が耳をくすぐった。
「さくら。さっきから、ずーっと難しい顔をしてるよ」
……いや。
正確に言うと、なにもないと言いきってしまうのは、大ウソになるかもしれない。
「卒業文集って、なにを書けば良いのかな。透也は、どう思う?」
「うーん、そうだねぇ。いっそのこと、書くことがないというテーマで、原稿を埋めてみるのはどう?」
「却下」
「えー、即答しなくてもいいじゃない」
「真剣に考えてるんだから、茶化さないでよ」
「僕なりに、真剣なんだけどなぁ。テーマは自由なんでしょ? だったら、どんな内容で原稿を埋めてきても、誰も文句は言えないと思うけどな」
「そうかもしれないけど、文集って学校のみんなに配られるんだよ。形として手元に残っちゃうんだから、無難な内容にしておかないと」
「本当のことを書いたら面白いとは思うけどねぇ。実は死んだ男の子が見えていて、憑かれていた高校生活でした、ってカミングアウトするとかどう?」
「そんな常識外れなこと、わたしが書くわけないって、わかってて言ってるでしょ」
透也は、思いっきり顔をしかめたわたしを見て、ニヤリと唇の端を吊りあげた。
そう。
透也――きれいな顔に似合わずちょっと意地悪なこの男の子は幽霊なのだ。唇を尖らせて拗ねるわたしを、面白がるようにくつくつと笑う彼は、亡くなっている。
まぁ、わたしは生前の透也のことを知らないのだけど。
「ふふ。面白そうだとは思うけど、実現してほしいとは思っていないよ。さくらは目立つことが嫌いだもんね」
実体のない彼はどこもかしこも透けていて、触れようと思っても触れられない。
今の彼は、深緑色のブレザーに、明るいグレーのスラックス姿だ。透也は、うちの高校の制服を気に入っているみたい。どういう理屈なのかわからないけど、頭の中で思い浮かべたイメージ通りの服を身にまとうことができるんだって。もちろん、その服にも実体がないから、全体的に半透明に透けているけれど。
「そうだよ。……変わり者扱いされるのは、ごめんだもん」
口にしたとき、胸に鈍い痛みが走った。
そう。
普通でいるのが一番だ。
みんなと足並みをそろえて、同じでいるのが賢い生き方。特に、学校という狭い水槽でうまくやっていくには必要不可欠な考え方だって、わたしは中学時代に嫌というほど学んだから。
実際に、高校でのわたしは、それなりに普通の女子高校生をやれていると思う。
お昼休みには、一緒にお弁当を食べる友人がいる。彼女たちの部活やバイトが休みの日には、カラオケに行って騒いだり、新発売の飲み物を写真に撮って、SNSにアップロードしたりもする。
高校三年の冬といえば大学受験生からすると最も大事な時期だけど、わたしは指定校推薦枠を勝ち取って楽をした。十二月となった今も、勉強に必死な同級生を横目に、残り少ない高校生活をのんびりと過ごしている。
不満はない。
透也のことを除けば、望んでいた通りの、平穏な高校生活を送ってきたと思う。
それなのに、いざ卒業文集を書こうとすると手が止まるのは、どうしてなんだろう。
「……そうだね。幽霊の男の子が見えているなんて、口が裂けても言えるわけがないよね」
笑っているはずの彼が、どうしてか泣いているように見えて、胸がざわついた。
*
透也との出会いは、衝撃的だった。
今でも、目を閉じると、あのときの情景を鮮明に思い描くことができる。
あれは、雲一つない青空が眩しいけれども、まだかすかに冬の気配を残した三月の終わりのことだった。
その日のわたしは、物思いに沈みながら、帰宅路へついているところだった。
もう、高校生活の三分の二が終わっちゃったな。
なんの実感もないまま、明日から高校三年生になる。
わたし、このまま、なにも頑張らない高校生活で良いのかな。
よく一緒にいる友だち二人が、きらきらとして見える。バスケ部に入って、熱心に練習へ打ちこむ茜は文句なしに眩しいし、ずっと片想いをしていた先輩と付き合いはじめたという優希のこともうらやましいと思う。
みんな、人生で一度きりの高校生活を、楽しそうに謳歌しているな。
友人の幸せを、純粋に喜ぶことができなかった。わたしだけが取り残されているような、底知れぬ不安も胸に渦巻いて。
だからといって、今のわたしには、新しくやってみたいこともなければ、好きなひともいない。なんにもない自分には、二人のことをうらやむ資格すらないと余計に落ちこむ。
鬱々として、うつむきかけた顔を弾きあげるように、その声はわたしの耳へ飛びこんできた。
『さくらだ』
わたしの名前……?
とっさに声のしてきた方を向いたら、そこには線路沿いの桜を見上げて、眩しそうに瞳を細めている男の子がいた。
咲きほこった桜から、薄桃色の花びらが、ふわふわと舞い降りてきて。
桜を見上げる彼も、花に見劣りしないほどきれいな男の子だったから、びっくりして思わず見入ってしまった。
抜けるように白い肌、指通りの良さそうな色素の薄い髪、すらっとした細身の体型。
鼻筋の通った形の良い鼻に、はなびらのような唇。
桜と彼との組み合わせは、まるで映画のワンシーンみたいに、幻想的で。
それなのに、桜の背後を駆けていく電車は日常そのもので。日常と非日常とが交差してしまったような、奇妙な感覚だった。
『きれいだ。こんなに近くで見上げるのは、初めてかも』
そんな彼は、月ヶ丘高校の制服を着ていて、胸がとくんと高鳴った。
まさか、同じ高校の男の子?
でも、こんな芸能人みたいにかっこいい男の子がいたら、もうすでに有名になっていそうなものだ。イケメンに目がない優希の話にも中性的な容姿をした彼の話が出てきたことはないし、見た記憶もない顔だった。
『あれ……?』
あまりにも見つめすぎたからだろうか。
彼のやさしげな瞳と、視線がかち合ってしまった。
その瞬間、はっと我に返って、とんでもなく顔に熱が集まった。
恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい!
まず、自分の名前と桜を勘違いしたことが、第一の失敗。それは不可抗力だったとしても、いくら彼がかっこよかったとはいえ、初対面のひとを思いっきりガン見するなんてありえない!
止まった時が動き出したように、わたしは全力でその場から逃げ出そうとした。今さら逃げたところで、一方的に凝視した事実は変わらない。そんなのわかってるけど、恥ずかしすぎて、一刻も早く彼の視界から逃れたかったんだ。
それなのに――、
『待って!』
――呼び止められて、息が止まるかと思った。
足を止めたわたしを見て、彼は、小さな子供のようにはしゃぎはじめた。
『待ってくれた! ほんとに待ってくれたよ! すごく、うれしいな』
一体なにを言っているの?
わたしは、待ってと切羽つまったように言われたから、足を止めただけ。
そんな当たり前のことに、彼はクリスマスプレゼントをもらった子供のように喜んでいる。
『きみには、僕が見えているんだね』
『……は、はい。えっ?』
『はじめまして、僕は透也。驚かせないようにはじめに言っておくんだけど、実は、もう死んでいるんだ。幽霊みたいなものかな』
のんびりとした口調で、あまりにも非現実的なことを、のたまいはじめた。
ここで微妙な表情になってしまったわたしを、誰も責められないと思う。
ええと……。そういう設定、なのかな?
いわゆる中二病的な感じなのか、それとも、実は俳優の卵とかでドラマか映画撮影の練習かなにか?
透也は、見たところ同年代だ。高校生ともなれば初対面の人間相手に幽霊のフリはさすがに痛いと思う。見た目の良さに騙されちゃいけない。この男子は、関わっちゃいけないタイプの危険人物だ。わたしの脳内危険察知センサーが、けたたましく鳴りはじめる。
『待って待って! そんな不審者に向けるような目をしないでよ。僕、繊細なんだからさぁ』
本当に繊細なひとは絶対に口にしなさそうな台詞を吐いたあと、透也が、『まあ、見て信じてもらったほうが早いか』と呟いた瞬間、信じられないことが起きた。
風が運んできた桜が、彼のからだを通り抜けたのだ。
いちまい、にまい、さんまい、よんまい、ごまい。
信じられない光景に絶句したわたしに対して、彼は落ちついた様子でしゃがみこむと、自分を通り抜けていった桜の花びらを拾おうとした。
だけれども、一向に掴めなかった。
長細い指は、なににも触れることができず、それどころか道路さえ通り抜けてしまう。
それでよく目を凝らして見たら、彼自体が半透明に透けていた。
『ね? これで僕が幽霊だってことを、証明できたかな?』
わたしを見上げるその瞳には、いたずらな光が宿っていた。
やっぱり信じがたいけど、この瞳で目撃してしまったことを端から否定することもできなくて。
『……わたし、夢でも見てる?』
必死に頭をフル回転させて出てきたのは、往生際の悪い言葉だけ。
『あははっ。夢みたいに奇跡的な出来事だとは思うけど、現実なんじゃないかなぁ』
『な、なんで、そう言いきれるの?』
『そうであってほしいから、だよ』
『えっ……。ただの願望?』
『不満そうな顔をしないでよ。今みてるこの世界が現実なのか、それとも夢なのかは誰にも証明できないんだからさ』
『それって、荘子の胡蝶の夢?』
中国の思想家、荘子の見た夢に由来する言葉だ。
ある日、荘子は蝶になった夢を見た。蝶として、花の間を飛びまわる間、荘子は自分が人間であることを忘れている。しかし、夢から覚めると、自分はもう蝶ではない。
そのとき、荘子は、考えこんだ。
人間である自分が夢を見て、その夢の中で蝶であったのか。
もしくは、本当の自分は実は蝶で、夢の中で人間として振る舞っているのか。
どちらの自分が本当の自分であるのか、証明はできない。
『詳しいんだね。きみ、言葉に興味があるの?』
どきり、と心臓が嫌な風に高鳴った。
そのことを悟られまいと、視線をそらす。
『べ、ベツに。ちょっと人よりも本を読んでた時期があっただけ』
『そうなんだ』
深堀りはしてこないんだ。少し意外に思いつつも、ホッとしている自分がいた。
それで良い。中学時代の痛々しい自分のことなんて、思い出したくもないから。
『話は変わるんだけどさ、僕には未練ってやつがあるんだと思う』
未練。諦めきれないことを、意味する言葉。
『未練があるから、成仏できてないってこと?』
『そういうこと。それでね、これは僕の直観なんだけど、その未練はきみに関わることだと思うんだ』
『わ、わたし?』
って、いやいやいや。どう考えてもひと違いだろう。
だってわたしは、生前に彼と会ったことすらない。今が完全に初対面だ。
それなのに、彼がこの世にとどまるきっかけになっただなんて、どう考えてもありえない。
『それはないと思うけど。なんの心当たりもないし』
そういうのは、生前から想いあっていた恋人同士とか、恋焦がれていた片想いの相手とか、恋愛が関係なくても大親友だったとか相棒だったとか、なにかしらの理由があってしかるべきでしょ。
少なくとも、わたしの知っている、幽霊モノの王道は全部そうだった。
『でも、きみにだけ、僕が見えているし声も聴こえている。それは事実だよ』
『えっ。わたしだけなの?』
『うん。きみは今、はたから見たら、空中に向かって話しかけているように見えているだろうね』
言われてみれば、先ほどから、周囲の人々の妙な視線を感じるような……。
華やかな容貌をしている透也に対して、わたしはどこにでもいるような、ちょっと背の低い女子高生。
どこまでも平均的なわたしと、立っているだけで目立つ透也が一緒にいれば、通行人の視線は彼へと集中するはずなのに。
『いや。でも、まさか、そんなわけ……』
嫌な予感がして後ずさったら、通りすがりの女の子の無垢な瞳が、わたしへと向けられた。
『ねえ、ママ。あのお姉ちゃん、さっきから誰とお話しているのかなぁ』
『こら。人に指をさしちゃダメでしょ』
その親子の反応が、決定打だった。
ここまできたら、さすがに認めざるをえない。
透也は幽霊であり、わたしにしか見えていないということを。
『ね。だから言ったでしょう?』
青空に負けないぐらい爽やかに微笑んだ透也をポカンと見つめながら、きれいな顔に似合わず良い性格をしているなぁと思ったことは忘れない。
これが、忘れもしない、透也との出逢いだった。
驚くことに、あれから九か月経った今でも、透也は成仏せずわたしのそばにいる。
*
「さくら、おっはよ~!」
「おはよう、茜。今日も朝から元気だね」
「朝練してきたしね! 身体動かすと、脳も活性化する気がするよ」
八重歯を見せながらニカリと笑う茜は、ショートカットがよく似合うバスケ女子。
本来なら、三年生の茜はとっくに部活を引退している時期なんだけど、彼女もわたしと同じ推薦組だ。持ち前の運動神経を活かしてスポーツ推薦枠を勝ち取り、今でも部活に勤しんでいる。
「ふあ〜。二人とも、おはよー」
あくびをしながらわたしたち二人に近づいてきたのは、もう一人の親友の優希だ。
優希は、ちょっと目立つくらい、かわいい女の子。
ピンクブラウン色のロングヘアには、ゆるくパーマがかかっている。
リップを塗っている桜色の唇は肉感的で、同性のわたしから見ても色っぽい。
無難な茶色に染めているわたしのセミロングの髪は、元々は優希を真似して染めたものだ。
高校への入学当初、優希が『高校生になったら、絶対染めるって決めてたんだ~』と明るめの茶髪を指に巻きつけていたのを見て、地味な黒髪のままでいるのが無性に恥ずかしくなって以来、ずっとこの色に染めている。
優希のことは好きだけど、華やかな彼女のそばにいると、ふとした瞬間にわたしは引き立て役に過ぎないんじゃないかって湿り気を帯びた感情も生まれる。そんな風に感じてしまう自分のことが、とても嫌いだ。
「優希、ねむそーだねぇ。やっぱ受験勉強?」
「いや。昨日は、久しぶりに彼氏と長電してたー」
「えー。余裕綽々かよ」
「だって、陽くんが久々にかまってくれたのがめーっちゃうれしかったんだもん! 陽くんさー、かっこいいからモテるだろうし心配なんだよねぇ……。ほら、向こうは大学生なわけじゃん? 大学生なんてさぁ、周りはぜったいチャラい女ばっかじゃん」
優希には、大学一年生の彼氏がいる。
その彼氏も、去年までは月ヶ丘高校の生徒だった。
文化祭実行委員で知りあってから、優希がずっと片想いをしていたんだけど、先輩が卒業するときに、優希からの告白で付き合ったらしい。
そして、彼女は今、大好きな彼氏と同じ大学を目指している。
「大学生が、全員チャラいわけではないと思うけどなぁ。それに、優希はかわいいから先輩も目移りはしないと思うよ」
「えーっ! さくら、かわいいこと言ってくれるじゃんっ」
ぱあっと花が咲いたような笑顔を浮かべながら、優希が思いっきり抱きついてくる。甘いような香水の匂いが鼻をくすぐった。
「恋は、良いものだよぉ。さくらは、最近どうなのさ? 相変わらずなの?」
「わたし?」
「うん。いつも、好きなひとはいないって言ってるけど、それってほんとなのー? 好きとまではいかなくてもさ、なんとなく気になるとか、そういう話でも聞かせてほしいんだけど」
優希のパッチリとした大きな瞳に至近距離でのぞきこまれて、ドキリとした。
恋バナは、正直に言って苦手だ。
友だちの話を聞いている分には楽しいけど、自分の話になると困ってしまう。
気になるひとなら、いる。
気になるどころか、多分この気持ちは恋だ。
いつの間にか、透也に憑かれている非日常が、わたしにとっての日常になってしまっていた。
彼と他愛もない会話をするのは、とても楽しい。
透也の前でだけは、深く考えずに、素のままの自分でいられる気がする。
でも、彼は幽霊だ。いつ未練を解消して、いなくなってしまうかもわからない不安定な存在だって頭ではわかっている。
「ん? さくら、僕の顔をそんなに見つめてどうかした?」
彼の姿が見えているのも、やさしい声が届いているのも、全部わたしだけ。
今だってこんなに近くにいるのに、茜にも、優希にも、クラスの誰にも見えていない。
わたしの恋は、世界の誰にも、理解されない。
「うーん。……好きなひと、かぁ。わたしには、ピンとこないかな」
今日もわたしは、世界で一番大好きなひとから視線をそらして、この恋をなかったことにする。
「えーっ。華の女子高生なのに、もったいない」
「っつーか、優希はなんで私には聞かないんだよ」
「そりゃあ、茜の恋人はバスケだって聞かなくてもわかるもん」
「くっそ。その通りなだけに、言い返せないのがムカつく」
「あっ、そーだ! ねえ、さくら。あたし、良いこと思いついちゃったんだけど」
優希の瞳が怪しく光って、なんだか嫌な予感がした。
「な、なに?」
「さくらは、恋に興味がないわけではないんだよねぇ?」
「そ、それは……そうだけど」
「じゃさ、あたしが良さげな男を紹介してあげるよ」
「……へ?」
「あー、もちろん、ゼッタイ付き合え! って言ってるわけじゃないよ? ちょっと会ってみて、そういう気にはなれないって思ったら、即刻、振ってくれてオッケーだから」
「え、ええっと……」
「そいつ、さくらに会いたいって、うるさいのよ。あたしのことを助けると思って、一度で良いから、会ってやってくんない?」
「どういうこと?」
優希いわく、わたしに会いたいという奇特な男子は、優希が通っている塾の知り合いらしい。他校で、一学年下の男の子なんだとか。
「あたし、さくらに塾までよく送ってもらうじゃん。それで、そいつもさくらのことを何度か見かけて、癒し系のかわいい女の子だと思ったって言ってたよ」
「ふーん。そういうことなら、一度だけでもその人に会ってみれば?」
「茜まで、なに言ってるの」
「や。単純に面白そうだと思っただけ」
「無責任だなぁ」
「減るもんじゃないし、良いじゃん。さくらが好きなひとに出会えないのは、単純に出会いが少ないからかもしれないよ。ほら、最初はあたしも同席するからさ!」
出会いが少ないから、か。
じゃあ、わたしと透也との出会いは、なんだったんだろう。
悪気のない優希の言葉に、勝手に棘を感じて、傷ついている。
「そ、そこまで言うなら、わかったよ」
優希が善意で申し出てくれているのもわかるし、表向きには好きなひとがいないことになっているので、強く断ることもできなかった。
まぁ、一度会ってみるだけだし、と自分を無理やり納得させる。
透也は、そんな情けないわたしを少し遠くから見ていて、凪いだ海のように穏やかな表情をしていた。
*
「寒そうだね」
「そりゃ、寒いよ。もう十二月だもん」
吐いた息が、すぐに白く凍っていく。この季節は、街路樹も丸裸でさびしい感じがする。
選択授業を終えて、わたしは透也と共に帰宅していた。
月ヶ丘高校では、三年生の授業のほとんどが選択制となっている。
茜や優希と顔を合わせるのも、数少ない必修の授業と、お昼休みの時間ぐらいだ。
放課後は基本的に、茜は部活へ行くし、優希は塾に行くので、いつも暇をしているのはわたしだけ。
「そうだよねぇ~。寒いのは心細くて嫌いだったんだけどさ、寒いがどんな感覚だったか、もう忘れつつあるな」
高校から自宅までは一時間近くかかるけど、人通りが少なければ彼と会話できる時間でもある。暇人のわたしにとことん付きあってくれるのは、同じく、暇人の透也だけだ。
「いま失礼なことを考えなかった?」
「気のせいだよ」
「ほんとかなぁ。ウザいからそろそろ成仏しろよ、とか思っていない?」
「え!」
驚きすぎて、思わず、大きめの声が出た。
目をまるくして、隣にいる彼を見つめる。
透也は、わたしを見つめかえして、くすくすと笑った。
「いや、なんでそんなに驚いてるの。そりゃあ、僕だっていつかは成仏するよ」
彼が、当たり前のようにそう口にしたとき、ひゅるりと冷たい風が通り抜けた。
二人同じ制服姿なのに、わたしのスカートだけが心もとなく揺れる。
からだと同じくらい、いや、それ以上に心が冷たく凍っていく。
「なんで……急にそんなことを言うの? 九か月もの間、ろくに成仏する気もなく、ずっとわたしのそばにいたじゃない」
わたしだって、最初は、大いに戸惑った。
あの桜の樹の下で透也と出会って、当然のようにわたしの家までついてこようとしたときには、言葉も出なかった。
『え? やだって言われても、ついていく気満々だけど。だって、幽霊になってからやっと話せる人と会えたんだよ?』
『わたしには関係ない。はやく成仏してよ』
『言われなくても、心残りがなくなったときには成仏するさ。それまでの間だけで良いから、一緒にいさせてよ』
『強引すぎるって』
『必死にもなるよ。きみに見捨てられたら、僕は、話し相手すらいなくなるんだから。あぁ、かわいそうなぼく。未練を解消することもできずに、きみを呪いながらさまようんだろうなぁ』
『わ、わかったから、呪うのはやめて! ……とりあえず、うちに来て良いから』
『ふふっ、ありがとう。ねえ、きみの名前を教えてくれる?』
『……東雲さくら、だけど』
『あぁ、そういうこと』
名前を告げた瞬間、透也がやさしく微笑んで、なんだか胸がそわそわとした。
『そういうことって、どういうこと』
心の不思議な揺らぎを誤魔化した反動で、少し言葉がきつくなる。
『いや? ただ、桜と自分の名前を勘違いして、僕の言葉で振り返ったんだなぁと思っただけだよ』
思いっきりバレていた上に、指摘されるとまでは思ってもみなくて、のぼせるように顔が熱くなったことは、今でも忘れられない恥ずかしい記憶だ。
出会ってすぐの頃は、どうやってこのはた迷惑な幽霊を成仏させようかということで頭がいっぱいだったのに。
彼と過ごす日々は意外にも楽しくて、わたしは少しずつ、彼が幽霊だという事実から目をそらすようになっていった。
透也はとてもアクティブで、事あるごとに、色々な場所へと出かけたがった。
元々はインドアタイプだったわたしも、『僕はさくらと一緒に行きたいの!』という率直な誘いに、すっかりほだされてしまった。
夏には、きらきらとした海を眺めに行った。
『うわぁ……。すごく、きれいだなぁ』
『ほんとに。水天一碧って感じ』
『ん? さくら、その言葉はどういう意味?』
『空と海の青色が溶けあって、一続きに見えることを言うの。境目がわからないでしょ?』
『そうなんだ! ……ふふっ』
『なにがおかしいの』
『ううん。よく知っているなぁと思っただけ』
秋には、少し遠出をして、近所の山まで紅葉を見に行った。
『わたし、ちゃんと紅葉狩りに出かけるのって、初めてかも』
『僕もだよ。そういえばさ、紅葉を鑑賞することを、どうして紅葉狩りって言うんだろうね』
『気になって調べたことがあるよ。一言でいうなら、貴族が格好つけるためだったんだって』
『どういうこと?』
『紅葉を楽しむためには、山や渓谷に足を運ばなきゃいけないでしょ? でも、昔の貴族にとって、ただ歩くことは下品な行為とされていたらしいの。だから、紅葉を見に出かけることを狩りにたとえたんだって』
『ふうん。……下品、ねえ。自分の足で自由に歩けるのは、素晴らしいことだと思うけど』
透也と会話をするのは、悔しいぐらいに心地が良かった。
わたしが、そのままのわたしでいてもゆるされる時間を、彼がくれたように感じた。
だから。
今さら成仏だとか言われても困るし、納得できるわけがない。
「さくらと過ごす日々がとても楽しくて、つい長居しちゃったね。この九か月は、生きていたころを含めても一番楽しかったって断言できるよ。成仏したら、もう、さくらをからかえなくなるんだと思うとすっごくさびしい」
「……性格、悪いね」
涙がこぼれ落ちそうになるのをこらえようとして、つい、かわいくない言葉が出てしまう。
なんで、どうして。
楽しいと思っているなら、これから先も、ずっとそばにいたら良いじゃない。
「でも、きみは、僕とは違って生きているから。いつかは、こんな奇妙な日々から卒業しなくちゃいけないでしょ」
わたしの大好きな声で、わたしとの間に、見えない線を引く。
「例えば、きみに彼氏ができたら、さすがに僕の存在って野暮じゃない? そのぐらいの自覚は僕にもあるからね」
「……もしかして、今朝の優希たちとの会話を気にしてる?」
あんなの、透也が気にするような話じゃない。
こんなこと優希には言えないけど、わたしは、今朝の話に出てきた男子のことなんてどうでも良いと思ってる。
会ったところで、きっとこの気持ちは変わらない。
だって、わたしがずっとそばにいてほしいとこんなにも切に願うのは、ただ一人だけだ。
「んー。全く気にしていないと言ったら、ウソになるかな。でも、覚悟はしていたことだから大丈夫。きみの邪魔はしないよ」
「とう、やは……邪魔なんかじゃ、ないよ。だって、わたしは……透也の、ことが」
「さくら」
歩みを止めた彼が、わたしの顔をのぞきこむ。
透也は、つられたように立ち止まったわたしの目元に、そっと手を伸ばした。
何度も何度も、半透明な指が、いつの間にか流れていた涙を拭おうとする。
彼の手が、わたしの涙を拭える瞬間は訪れない。
それでも、彼が触れようとしてくれた目元をあたたかく感じるのは、わたしがそう思いこみたいだけなのだろうか。
「それ以上は、言っちゃダメだよ。きっと、その気持ちは勘違いみたいなものだ。勘違いをさせてしまった僕が言うのは、最低だけど」
なんで。
「ごめんね。きみのことを素敵だと思った男の子が、きみと同じくらい魅力的であることを願っているよ」
透也にだけは、他の男の子との幸せなんて願われたくなかったのに。
その日はずっと上の空で、今日の灰色の空を映しとったみたいに胸が晴れなかった。
もちろん、卒業文集も、一文字も進まなかった。
*
一向に埋まる気配のない白い原稿を前に、気分が重たく沈んでいく。
昔はこの空白を前にすると、なにを書いても良いんだと思えて心が躍ったのに。今のわたしにとっては重荷にしか思えない。たった八百文字を埋めるだけなのに、一文字も書けないまま、もう一時間近くが経過しようとしている。
わたし――東雲さくらは、卒業文集という難題にぶつかり、途方に暮れていた。
だって、なにを書いたら良いのか、本当に思いつかない。
成績は平凡、部活は帰宅部、美化委員にもこれといった思い出はなし。
わたしが月ヶ丘高校で過ごした二年半とちょっとの日々に、特筆すべきことは、なにもないんだ。
カーテンを閉めきった暗い自室で一人パソコンの薄明りを前にうなだれていたら、背後から、柔らかな声が耳をくすぐった。
「さくら。さっきから、ずーっと難しい顔をしてるよ」
……いや。
正確に言うと、なにもないと言いきってしまうのは、大ウソになるかもしれない。
「卒業文集って、なにを書けば良いのかな。透也は、どう思う?」
「うーん、そうだねぇ。いっそのこと、書くことがないというテーマで、原稿を埋めてみるのはどう?」
「却下」
「えー、即答しなくてもいいじゃない」
「真剣に考えてるんだから、茶化さないでよ」
「僕なりに、真剣なんだけどなぁ。テーマは自由なんでしょ? だったら、どんな内容で原稿を埋めてきても、誰も文句は言えないと思うけどな」
「そうかもしれないけど、文集って学校のみんなに配られるんだよ。形として手元に残っちゃうんだから、無難な内容にしておかないと」
「本当のことを書いたら面白いとは思うけどねぇ。実は死んだ男の子が見えていて、憑かれていた高校生活でした、ってカミングアウトするとかどう?」
「そんな常識外れなこと、わたしが書くわけないって、わかってて言ってるでしょ」
透也は、思いっきり顔をしかめたわたしを見て、ニヤリと唇の端を吊りあげた。
そう。
透也――きれいな顔に似合わずちょっと意地悪なこの男の子は幽霊なのだ。唇を尖らせて拗ねるわたしを、面白がるようにくつくつと笑う彼は、亡くなっている。
まぁ、わたしは生前の透也のことを知らないのだけど。
「ふふ。面白そうだとは思うけど、実現してほしいとは思っていないよ。さくらは目立つことが嫌いだもんね」
実体のない彼はどこもかしこも透けていて、触れようと思っても触れられない。
今の彼は、深緑色のブレザーに、明るいグレーのスラックス姿だ。透也は、うちの高校の制服を気に入っているみたい。どういう理屈なのかわからないけど、頭の中で思い浮かべたイメージ通りの服を身にまとうことができるんだって。もちろん、その服にも実体がないから、全体的に半透明に透けているけれど。
「そうだよ。……変わり者扱いされるのは、ごめんだもん」
口にしたとき、胸に鈍い痛みが走った。
そう。
普通でいるのが一番だ。
みんなと足並みをそろえて、同じでいるのが賢い生き方。特に、学校という狭い水槽でうまくやっていくには必要不可欠な考え方だって、わたしは中学時代に嫌というほど学んだから。
実際に、高校でのわたしは、それなりに普通の女子高校生をやれていると思う。
お昼休みには、一緒にお弁当を食べる友人がいる。彼女たちの部活やバイトが休みの日には、カラオケに行って騒いだり、新発売の飲み物を写真に撮って、SNSにアップロードしたりもする。
高校三年の冬といえば大学受験生からすると最も大事な時期だけど、わたしは指定校推薦枠を勝ち取って楽をした。十二月となった今も、勉強に必死な同級生を横目に、残り少ない高校生活をのんびりと過ごしている。
不満はない。
透也のことを除けば、望んでいた通りの、平穏な高校生活を送ってきたと思う。
それなのに、いざ卒業文集を書こうとすると手が止まるのは、どうしてなんだろう。
「……そうだね。幽霊の男の子が見えているなんて、口が裂けても言えるわけがないよね」
笑っているはずの彼が、どうしてか泣いているように見えて、胸がざわついた。
*
透也との出会いは、衝撃的だった。
今でも、目を閉じると、あのときの情景を鮮明に思い描くことができる。
あれは、雲一つない青空が眩しいけれども、まだかすかに冬の気配を残した三月の終わりのことだった。
その日のわたしは、物思いに沈みながら、帰宅路へついているところだった。
もう、高校生活の三分の二が終わっちゃったな。
なんの実感もないまま、明日から高校三年生になる。
わたし、このまま、なにも頑張らない高校生活で良いのかな。
よく一緒にいる友だち二人が、きらきらとして見える。バスケ部に入って、熱心に練習へ打ちこむ茜は文句なしに眩しいし、ずっと片想いをしていた先輩と付き合いはじめたという優希のこともうらやましいと思う。
みんな、人生で一度きりの高校生活を、楽しそうに謳歌しているな。
友人の幸せを、純粋に喜ぶことができなかった。わたしだけが取り残されているような、底知れぬ不安も胸に渦巻いて。
だからといって、今のわたしには、新しくやってみたいこともなければ、好きなひともいない。なんにもない自分には、二人のことをうらやむ資格すらないと余計に落ちこむ。
鬱々として、うつむきかけた顔を弾きあげるように、その声はわたしの耳へ飛びこんできた。
『さくらだ』
わたしの名前……?
とっさに声のしてきた方を向いたら、そこには線路沿いの桜を見上げて、眩しそうに瞳を細めている男の子がいた。
咲きほこった桜から、薄桃色の花びらが、ふわふわと舞い降りてきて。
桜を見上げる彼も、花に見劣りしないほどきれいな男の子だったから、びっくりして思わず見入ってしまった。
抜けるように白い肌、指通りの良さそうな色素の薄い髪、すらっとした細身の体型。
鼻筋の通った形の良い鼻に、はなびらのような唇。
桜と彼との組み合わせは、まるで映画のワンシーンみたいに、幻想的で。
それなのに、桜の背後を駆けていく電車は日常そのもので。日常と非日常とが交差してしまったような、奇妙な感覚だった。
『きれいだ。こんなに近くで見上げるのは、初めてかも』
そんな彼は、月ヶ丘高校の制服を着ていて、胸がとくんと高鳴った。
まさか、同じ高校の男の子?
でも、こんな芸能人みたいにかっこいい男の子がいたら、もうすでに有名になっていそうなものだ。イケメンに目がない優希の話にも中性的な容姿をした彼の話が出てきたことはないし、見た記憶もない顔だった。
『あれ……?』
あまりにも見つめすぎたからだろうか。
彼のやさしげな瞳と、視線がかち合ってしまった。
その瞬間、はっと我に返って、とんでもなく顔に熱が集まった。
恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい!
まず、自分の名前と桜を勘違いしたことが、第一の失敗。それは不可抗力だったとしても、いくら彼がかっこよかったとはいえ、初対面のひとを思いっきりガン見するなんてありえない!
止まった時が動き出したように、わたしは全力でその場から逃げ出そうとした。今さら逃げたところで、一方的に凝視した事実は変わらない。そんなのわかってるけど、恥ずかしすぎて、一刻も早く彼の視界から逃れたかったんだ。
それなのに――、
『待って!』
――呼び止められて、息が止まるかと思った。
足を止めたわたしを見て、彼は、小さな子供のようにはしゃぎはじめた。
『待ってくれた! ほんとに待ってくれたよ! すごく、うれしいな』
一体なにを言っているの?
わたしは、待ってと切羽つまったように言われたから、足を止めただけ。
そんな当たり前のことに、彼はクリスマスプレゼントをもらった子供のように喜んでいる。
『きみには、僕が見えているんだね』
『……は、はい。えっ?』
『はじめまして、僕は透也。驚かせないようにはじめに言っておくんだけど、実は、もう死んでいるんだ。幽霊みたいなものかな』
のんびりとした口調で、あまりにも非現実的なことを、のたまいはじめた。
ここで微妙な表情になってしまったわたしを、誰も責められないと思う。
ええと……。そういう設定、なのかな?
いわゆる中二病的な感じなのか、それとも、実は俳優の卵とかでドラマか映画撮影の練習かなにか?
透也は、見たところ同年代だ。高校生ともなれば初対面の人間相手に幽霊のフリはさすがに痛いと思う。見た目の良さに騙されちゃいけない。この男子は、関わっちゃいけないタイプの危険人物だ。わたしの脳内危険察知センサーが、けたたましく鳴りはじめる。
『待って待って! そんな不審者に向けるような目をしないでよ。僕、繊細なんだからさぁ』
本当に繊細なひとは絶対に口にしなさそうな台詞を吐いたあと、透也が、『まあ、見て信じてもらったほうが早いか』と呟いた瞬間、信じられないことが起きた。
風が運んできた桜が、彼のからだを通り抜けたのだ。
いちまい、にまい、さんまい、よんまい、ごまい。
信じられない光景に絶句したわたしに対して、彼は落ちついた様子でしゃがみこむと、自分を通り抜けていった桜の花びらを拾おうとした。
だけれども、一向に掴めなかった。
長細い指は、なににも触れることができず、それどころか道路さえ通り抜けてしまう。
それでよく目を凝らして見たら、彼自体が半透明に透けていた。
『ね? これで僕が幽霊だってことを、証明できたかな?』
わたしを見上げるその瞳には、いたずらな光が宿っていた。
やっぱり信じがたいけど、この瞳で目撃してしまったことを端から否定することもできなくて。
『……わたし、夢でも見てる?』
必死に頭をフル回転させて出てきたのは、往生際の悪い言葉だけ。
『あははっ。夢みたいに奇跡的な出来事だとは思うけど、現実なんじゃないかなぁ』
『な、なんで、そう言いきれるの?』
『そうであってほしいから、だよ』
『えっ……。ただの願望?』
『不満そうな顔をしないでよ。今みてるこの世界が現実なのか、それとも夢なのかは誰にも証明できないんだからさ』
『それって、荘子の胡蝶の夢?』
中国の思想家、荘子の見た夢に由来する言葉だ。
ある日、荘子は蝶になった夢を見た。蝶として、花の間を飛びまわる間、荘子は自分が人間であることを忘れている。しかし、夢から覚めると、自分はもう蝶ではない。
そのとき、荘子は、考えこんだ。
人間である自分が夢を見て、その夢の中で蝶であったのか。
もしくは、本当の自分は実は蝶で、夢の中で人間として振る舞っているのか。
どちらの自分が本当の自分であるのか、証明はできない。
『詳しいんだね。きみ、言葉に興味があるの?』
どきり、と心臓が嫌な風に高鳴った。
そのことを悟られまいと、視線をそらす。
『べ、ベツに。ちょっと人よりも本を読んでた時期があっただけ』
『そうなんだ』
深堀りはしてこないんだ。少し意外に思いつつも、ホッとしている自分がいた。
それで良い。中学時代の痛々しい自分のことなんて、思い出したくもないから。
『話は変わるんだけどさ、僕には未練ってやつがあるんだと思う』
未練。諦めきれないことを、意味する言葉。
『未練があるから、成仏できてないってこと?』
『そういうこと。それでね、これは僕の直観なんだけど、その未練はきみに関わることだと思うんだ』
『わ、わたし?』
って、いやいやいや。どう考えてもひと違いだろう。
だってわたしは、生前に彼と会ったことすらない。今が完全に初対面だ。
それなのに、彼がこの世にとどまるきっかけになっただなんて、どう考えてもありえない。
『それはないと思うけど。なんの心当たりもないし』
そういうのは、生前から想いあっていた恋人同士とか、恋焦がれていた片想いの相手とか、恋愛が関係なくても大親友だったとか相棒だったとか、なにかしらの理由があってしかるべきでしょ。
少なくとも、わたしの知っている、幽霊モノの王道は全部そうだった。
『でも、きみにだけ、僕が見えているし声も聴こえている。それは事実だよ』
『えっ。わたしだけなの?』
『うん。きみは今、はたから見たら、空中に向かって話しかけているように見えているだろうね』
言われてみれば、先ほどから、周囲の人々の妙な視線を感じるような……。
華やかな容貌をしている透也に対して、わたしはどこにでもいるような、ちょっと背の低い女子高生。
どこまでも平均的なわたしと、立っているだけで目立つ透也が一緒にいれば、通行人の視線は彼へと集中するはずなのに。
『いや。でも、まさか、そんなわけ……』
嫌な予感がして後ずさったら、通りすがりの女の子の無垢な瞳が、わたしへと向けられた。
『ねえ、ママ。あのお姉ちゃん、さっきから誰とお話しているのかなぁ』
『こら。人に指をさしちゃダメでしょ』
その親子の反応が、決定打だった。
ここまできたら、さすがに認めざるをえない。
透也は幽霊であり、わたしにしか見えていないということを。
『ね。だから言ったでしょう?』
青空に負けないぐらい爽やかに微笑んだ透也をポカンと見つめながら、きれいな顔に似合わず良い性格をしているなぁと思ったことは忘れない。
これが、忘れもしない、透也との出逢いだった。
驚くことに、あれから九か月経った今でも、透也は成仏せずわたしのそばにいる。
*
「さくら、おっはよ~!」
「おはよう、茜。今日も朝から元気だね」
「朝練してきたしね! 身体動かすと、脳も活性化する気がするよ」
八重歯を見せながらニカリと笑う茜は、ショートカットがよく似合うバスケ女子。
本来なら、三年生の茜はとっくに部活を引退している時期なんだけど、彼女もわたしと同じ推薦組だ。持ち前の運動神経を活かしてスポーツ推薦枠を勝ち取り、今でも部活に勤しんでいる。
「ふあ〜。二人とも、おはよー」
あくびをしながらわたしたち二人に近づいてきたのは、もう一人の親友の優希だ。
優希は、ちょっと目立つくらい、かわいい女の子。
ピンクブラウン色のロングヘアには、ゆるくパーマがかかっている。
リップを塗っている桜色の唇は肉感的で、同性のわたしから見ても色っぽい。
無難な茶色に染めているわたしのセミロングの髪は、元々は優希を真似して染めたものだ。
高校への入学当初、優希が『高校生になったら、絶対染めるって決めてたんだ~』と明るめの茶髪を指に巻きつけていたのを見て、地味な黒髪のままでいるのが無性に恥ずかしくなって以来、ずっとこの色に染めている。
優希のことは好きだけど、華やかな彼女のそばにいると、ふとした瞬間にわたしは引き立て役に過ぎないんじゃないかって湿り気を帯びた感情も生まれる。そんな風に感じてしまう自分のことが、とても嫌いだ。
「優希、ねむそーだねぇ。やっぱ受験勉強?」
「いや。昨日は、久しぶりに彼氏と長電してたー」
「えー。余裕綽々かよ」
「だって、陽くんが久々にかまってくれたのがめーっちゃうれしかったんだもん! 陽くんさー、かっこいいからモテるだろうし心配なんだよねぇ……。ほら、向こうは大学生なわけじゃん? 大学生なんてさぁ、周りはぜったいチャラい女ばっかじゃん」
優希には、大学一年生の彼氏がいる。
その彼氏も、去年までは月ヶ丘高校の生徒だった。
文化祭実行委員で知りあってから、優希がずっと片想いをしていたんだけど、先輩が卒業するときに、優希からの告白で付き合ったらしい。
そして、彼女は今、大好きな彼氏と同じ大学を目指している。
「大学生が、全員チャラいわけではないと思うけどなぁ。それに、優希はかわいいから先輩も目移りはしないと思うよ」
「えーっ! さくら、かわいいこと言ってくれるじゃんっ」
ぱあっと花が咲いたような笑顔を浮かべながら、優希が思いっきり抱きついてくる。甘いような香水の匂いが鼻をくすぐった。
「恋は、良いものだよぉ。さくらは、最近どうなのさ? 相変わらずなの?」
「わたし?」
「うん。いつも、好きなひとはいないって言ってるけど、それってほんとなのー? 好きとまではいかなくてもさ、なんとなく気になるとか、そういう話でも聞かせてほしいんだけど」
優希のパッチリとした大きな瞳に至近距離でのぞきこまれて、ドキリとした。
恋バナは、正直に言って苦手だ。
友だちの話を聞いている分には楽しいけど、自分の話になると困ってしまう。
気になるひとなら、いる。
気になるどころか、多分この気持ちは恋だ。
いつの間にか、透也に憑かれている非日常が、わたしにとっての日常になってしまっていた。
彼と他愛もない会話をするのは、とても楽しい。
透也の前でだけは、深く考えずに、素のままの自分でいられる気がする。
でも、彼は幽霊だ。いつ未練を解消して、いなくなってしまうかもわからない不安定な存在だって頭ではわかっている。
「ん? さくら、僕の顔をそんなに見つめてどうかした?」
彼の姿が見えているのも、やさしい声が届いているのも、全部わたしだけ。
今だってこんなに近くにいるのに、茜にも、優希にも、クラスの誰にも見えていない。
わたしの恋は、世界の誰にも、理解されない。
「うーん。……好きなひと、かぁ。わたしには、ピンとこないかな」
今日もわたしは、世界で一番大好きなひとから視線をそらして、この恋をなかったことにする。
「えーっ。華の女子高生なのに、もったいない」
「っつーか、優希はなんで私には聞かないんだよ」
「そりゃあ、茜の恋人はバスケだって聞かなくてもわかるもん」
「くっそ。その通りなだけに、言い返せないのがムカつく」
「あっ、そーだ! ねえ、さくら。あたし、良いこと思いついちゃったんだけど」
優希の瞳が怪しく光って、なんだか嫌な予感がした。
「な、なに?」
「さくらは、恋に興味がないわけではないんだよねぇ?」
「そ、それは……そうだけど」
「じゃさ、あたしが良さげな男を紹介してあげるよ」
「……へ?」
「あー、もちろん、ゼッタイ付き合え! って言ってるわけじゃないよ? ちょっと会ってみて、そういう気にはなれないって思ったら、即刻、振ってくれてオッケーだから」
「え、ええっと……」
「そいつ、さくらに会いたいって、うるさいのよ。あたしのことを助けると思って、一度で良いから、会ってやってくんない?」
「どういうこと?」
優希いわく、わたしに会いたいという奇特な男子は、優希が通っている塾の知り合いらしい。他校で、一学年下の男の子なんだとか。
「あたし、さくらに塾までよく送ってもらうじゃん。それで、そいつもさくらのことを何度か見かけて、癒し系のかわいい女の子だと思ったって言ってたよ」
「ふーん。そういうことなら、一度だけでもその人に会ってみれば?」
「茜まで、なに言ってるの」
「や。単純に面白そうだと思っただけ」
「無責任だなぁ」
「減るもんじゃないし、良いじゃん。さくらが好きなひとに出会えないのは、単純に出会いが少ないからかもしれないよ。ほら、最初はあたしも同席するからさ!」
出会いが少ないから、か。
じゃあ、わたしと透也との出会いは、なんだったんだろう。
悪気のない優希の言葉に、勝手に棘を感じて、傷ついている。
「そ、そこまで言うなら、わかったよ」
優希が善意で申し出てくれているのもわかるし、表向きには好きなひとがいないことになっているので、強く断ることもできなかった。
まぁ、一度会ってみるだけだし、と自分を無理やり納得させる。
透也は、そんな情けないわたしを少し遠くから見ていて、凪いだ海のように穏やかな表情をしていた。
*
「寒そうだね」
「そりゃ、寒いよ。もう十二月だもん」
吐いた息が、すぐに白く凍っていく。この季節は、街路樹も丸裸でさびしい感じがする。
選択授業を終えて、わたしは透也と共に帰宅していた。
月ヶ丘高校では、三年生の授業のほとんどが選択制となっている。
茜や優希と顔を合わせるのも、数少ない必修の授業と、お昼休みの時間ぐらいだ。
放課後は基本的に、茜は部活へ行くし、優希は塾に行くので、いつも暇をしているのはわたしだけ。
「そうだよねぇ~。寒いのは心細くて嫌いだったんだけどさ、寒いがどんな感覚だったか、もう忘れつつあるな」
高校から自宅までは一時間近くかかるけど、人通りが少なければ彼と会話できる時間でもある。暇人のわたしにとことん付きあってくれるのは、同じく、暇人の透也だけだ。
「いま失礼なことを考えなかった?」
「気のせいだよ」
「ほんとかなぁ。ウザいからそろそろ成仏しろよ、とか思っていない?」
「え!」
驚きすぎて、思わず、大きめの声が出た。
目をまるくして、隣にいる彼を見つめる。
透也は、わたしを見つめかえして、くすくすと笑った。
「いや、なんでそんなに驚いてるの。そりゃあ、僕だっていつかは成仏するよ」
彼が、当たり前のようにそう口にしたとき、ひゅるりと冷たい風が通り抜けた。
二人同じ制服姿なのに、わたしのスカートだけが心もとなく揺れる。
からだと同じくらい、いや、それ以上に心が冷たく凍っていく。
「なんで……急にそんなことを言うの? 九か月もの間、ろくに成仏する気もなく、ずっとわたしのそばにいたじゃない」
わたしだって、最初は、大いに戸惑った。
あの桜の樹の下で透也と出会って、当然のようにわたしの家までついてこようとしたときには、言葉も出なかった。
『え? やだって言われても、ついていく気満々だけど。だって、幽霊になってからやっと話せる人と会えたんだよ?』
『わたしには関係ない。はやく成仏してよ』
『言われなくても、心残りがなくなったときには成仏するさ。それまでの間だけで良いから、一緒にいさせてよ』
『強引すぎるって』
『必死にもなるよ。きみに見捨てられたら、僕は、話し相手すらいなくなるんだから。あぁ、かわいそうなぼく。未練を解消することもできずに、きみを呪いながらさまようんだろうなぁ』
『わ、わかったから、呪うのはやめて! ……とりあえず、うちに来て良いから』
『ふふっ、ありがとう。ねえ、きみの名前を教えてくれる?』
『……東雲さくら、だけど』
『あぁ、そういうこと』
名前を告げた瞬間、透也がやさしく微笑んで、なんだか胸がそわそわとした。
『そういうことって、どういうこと』
心の不思議な揺らぎを誤魔化した反動で、少し言葉がきつくなる。
『いや? ただ、桜と自分の名前を勘違いして、僕の言葉で振り返ったんだなぁと思っただけだよ』
思いっきりバレていた上に、指摘されるとまでは思ってもみなくて、のぼせるように顔が熱くなったことは、今でも忘れられない恥ずかしい記憶だ。
出会ってすぐの頃は、どうやってこのはた迷惑な幽霊を成仏させようかということで頭がいっぱいだったのに。
彼と過ごす日々は意外にも楽しくて、わたしは少しずつ、彼が幽霊だという事実から目をそらすようになっていった。
透也はとてもアクティブで、事あるごとに、色々な場所へと出かけたがった。
元々はインドアタイプだったわたしも、『僕はさくらと一緒に行きたいの!』という率直な誘いに、すっかりほだされてしまった。
夏には、きらきらとした海を眺めに行った。
『うわぁ……。すごく、きれいだなぁ』
『ほんとに。水天一碧って感じ』
『ん? さくら、その言葉はどういう意味?』
『空と海の青色が溶けあって、一続きに見えることを言うの。境目がわからないでしょ?』
『そうなんだ! ……ふふっ』
『なにがおかしいの』
『ううん。よく知っているなぁと思っただけ』
秋には、少し遠出をして、近所の山まで紅葉を見に行った。
『わたし、ちゃんと紅葉狩りに出かけるのって、初めてかも』
『僕もだよ。そういえばさ、紅葉を鑑賞することを、どうして紅葉狩りって言うんだろうね』
『気になって調べたことがあるよ。一言でいうなら、貴族が格好つけるためだったんだって』
『どういうこと?』
『紅葉を楽しむためには、山や渓谷に足を運ばなきゃいけないでしょ? でも、昔の貴族にとって、ただ歩くことは下品な行為とされていたらしいの。だから、紅葉を見に出かけることを狩りにたとえたんだって』
『ふうん。……下品、ねえ。自分の足で自由に歩けるのは、素晴らしいことだと思うけど』
透也と会話をするのは、悔しいぐらいに心地が良かった。
わたしが、そのままのわたしでいてもゆるされる時間を、彼がくれたように感じた。
だから。
今さら成仏だとか言われても困るし、納得できるわけがない。
「さくらと過ごす日々がとても楽しくて、つい長居しちゃったね。この九か月は、生きていたころを含めても一番楽しかったって断言できるよ。成仏したら、もう、さくらをからかえなくなるんだと思うとすっごくさびしい」
「……性格、悪いね」
涙がこぼれ落ちそうになるのをこらえようとして、つい、かわいくない言葉が出てしまう。
なんで、どうして。
楽しいと思っているなら、これから先も、ずっとそばにいたら良いじゃない。
「でも、きみは、僕とは違って生きているから。いつかは、こんな奇妙な日々から卒業しなくちゃいけないでしょ」
わたしの大好きな声で、わたしとの間に、見えない線を引く。
「例えば、きみに彼氏ができたら、さすがに僕の存在って野暮じゃない? そのぐらいの自覚は僕にもあるからね」
「……もしかして、今朝の優希たちとの会話を気にしてる?」
あんなの、透也が気にするような話じゃない。
こんなこと優希には言えないけど、わたしは、今朝の話に出てきた男子のことなんてどうでも良いと思ってる。
会ったところで、きっとこの気持ちは変わらない。
だって、わたしがずっとそばにいてほしいとこんなにも切に願うのは、ただ一人だけだ。
「んー。全く気にしていないと言ったら、ウソになるかな。でも、覚悟はしていたことだから大丈夫。きみの邪魔はしないよ」
「とう、やは……邪魔なんかじゃ、ないよ。だって、わたしは……透也の、ことが」
「さくら」
歩みを止めた彼が、わたしの顔をのぞきこむ。
透也は、つられたように立ち止まったわたしの目元に、そっと手を伸ばした。
何度も何度も、半透明な指が、いつの間にか流れていた涙を拭おうとする。
彼の手が、わたしの涙を拭える瞬間は訪れない。
それでも、彼が触れようとしてくれた目元をあたたかく感じるのは、わたしがそう思いこみたいだけなのだろうか。
「それ以上は、言っちゃダメだよ。きっと、その気持ちは勘違いみたいなものだ。勘違いをさせてしまった僕が言うのは、最低だけど」
なんで。
「ごめんね。きみのことを素敵だと思った男の子が、きみと同じくらい魅力的であることを願っているよ」
透也にだけは、他の男の子との幸せなんて願われたくなかったのに。
その日はずっと上の空で、今日の灰色の空を映しとったみたいに胸が晴れなかった。
もちろん、卒業文集も、一文字も進まなかった。
*