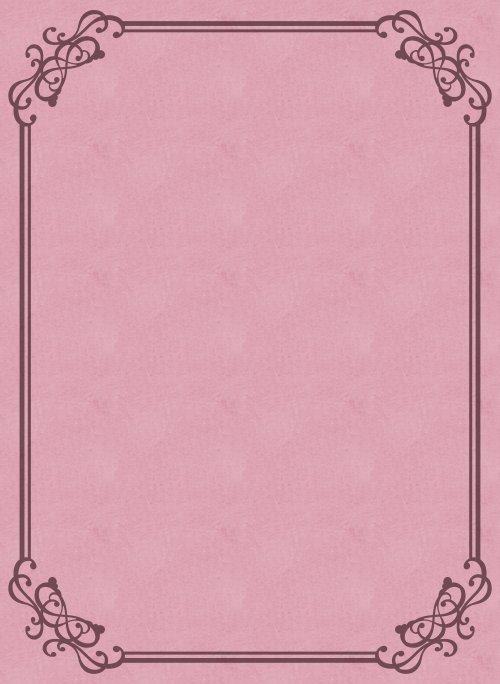「友達になっていただけますか?」
「その前に」
「なんでしょう」
「誰もいないよな?」
「大丈夫。鍵もかけてきたし、尾行もなかったからふたりきりだよ。えっちなことだってし放題。どうする? 手始めにスカートでもめくってみる?」
「ばか言え。そんなこと微塵も思っていないくせに」
「あら、なんでそう思うの」
「手が震えてるぞ。……まあ、安心しろ。僕はそういうのは要求しないから」
「紳士なのね」
「まあね」
僕はギターを手繰り寄せて、近くに寄せてから続けた。
「僕からの要求は二つに一つ。一つは僕と友達なんてならず、そして二度と屋上に来ないこと。僕のこの時間を壊さないこと。もしくは僕と、その、友だちになって、二人で軽音楽部を結成すること。僕のギターの時間の邪魔をしないこと。どちらにしても他の誰かに、クラスの人とか、他の友達とかに話してはいけない。ここでの利用は秘密にすること。これは絶対だ。僕は許可貰ってここに来ている。鍵だって預かってる」
「それなら、私も鍵を持ってる」
「桜田……さんも」
「明美」
「……明美さんも、許可もらってるってこと? 山田先生?」
「そう! 山田先生。ねえ、私のこと話ししても良い?」
「どうぞ。是非とも聞きたい」
「私ね、引きこもりで不登校だったんだ」
え?
「不登校なのは今も、かな。教室には行ってないから、まだ不登校だ。山田先生にせめて学校に来ることはしてみないかって言われて、それで屋上に連れてきてもらったの。それがだいたい一年前くらい」
「僕が屋上に来たのは半年前くらいだ。じゃあ、先客だったのは、明美さんのほうだったのか」
「そうだね。ある日、そう半年くらい前からかな。ギターの音がして。歌も歌っていて。ここの屋上って広くて陰になるようなところたくさんあるじゃない? だから、隠れて聞いていたんだ。私不登校だから、午前中にはやってきて、給食は一緒には食べられないからお弁当食べて、放課後になってあなたの音楽を聞く。それが日課だった。それまでは、携帯音楽プレーヤーで、イヤホンで聞いていたの。ゴイステか銀杏ボーイズかわからないけど、君の弾くベイビーベイビー、良かったな。また聞きたいね」
「銀杏なんて分かるのか!? 今時の中学生なのに」
しかも前身バンドのゴーイングステディまでわかるとは。何歳だよ。
「偶然にも音楽の趣味は合いそうだな。それは悪いことじゃない。むしろいいことだ」
「ね、私は誰にも言わないよ。言う相手がいないっていうのもあるけど。ほら、不登校だから。だから、友達になってよ。軽音楽部? なら、それでもいいからさ。邪魔はしない。隣で聞いてるだけ。本当に。ね、だからお願い」
僕はナナを呼び出したかった。「どうする?」って意見を聞きたかった。でも、呼び出したところで「良いんじゃない? 友達というのも今の君には必要だよ」とか言うに決まっている。わかるさ。僕と彼との付き合いは世界一長いんだから。
手を合わせて、頭を下げる彼女に、僕は断ることは出来なかった。ナナの助言もあるし、たまには友達というのをやってみてもいいかな。相手は僕以外に知り合いいないみたいだし。まあ、そういうのもいいかな。そう思って、僕は口を開いた。
「頭を上げてよ。ほら」
そして握手をした。
「じゃあ、まあ、ほら。友達な。よろしく」
ぱっと、笑顔を見せた。少しどきりとした。
「よろしく! 友達ね」
俺は適当に握手をして、それから座り直した。ケースを開けてギターを取り出す。俺はこの時間を壊されないために仕方なく友達をやることにしたんだから、ここでギターを辞めてしまっては意味がない。ギターを弾いてこそ、そこに価値が生まれるってものである。
チューニングを始める。彼女も隣りに座った。本当に黙っている。目をつぶって、静かに眠るように。僕はチューニングを合わせていく。ベンベンベン……キュキュキュ……。
「よし。じゃあ、今日はpillowsかな」
課題曲を選ぶ。いつも気分で適当に選んでいる。ロックバンドの曲が多いのは、趣味嗜好が偏っているからである。
ジャ、ジャン。
ギターを弾き始める。練習なので、コード譜やタブ譜を見ながら、覚えながら、覚えたらその小節を弾いてを繰り返す。音を、原曲を何度も聞いて、合わせていく。少ししたら、その曲は弾けるようになっていた。そしてら、それに合わせて、あとは歌うだけだ。完成である。
ジャカジャン!
隣から拍手が聞こえた。そういえば居たのだったな。あまりも静かだったから一瞬忘れていたぜ。
「オーディエンスがいるのは、新鮮な気分だな」
「すぐに一曲できるようになるのね、すごいね」
「まあ、毎日練習しているからな。ある程度は弾けるんだよ。あとは聞き込みだよ。どれだけたくさん正解の音を聞いて覚えるか。つまり原曲。サブスクの時代は好きな曲を何度でも聞けるからありがたいね」
「ふーん、そうなんだ」
それからふたりで音楽の話をした。好きな曲とか、バンドとか、そういう話。誰かと熱心に話をしたのは、それこそナナ以外には初めてだったかもしれない。なかなか新鮮な気分だった。
「その前に」
「なんでしょう」
「誰もいないよな?」
「大丈夫。鍵もかけてきたし、尾行もなかったからふたりきりだよ。えっちなことだってし放題。どうする? 手始めにスカートでもめくってみる?」
「ばか言え。そんなこと微塵も思っていないくせに」
「あら、なんでそう思うの」
「手が震えてるぞ。……まあ、安心しろ。僕はそういうのは要求しないから」
「紳士なのね」
「まあね」
僕はギターを手繰り寄せて、近くに寄せてから続けた。
「僕からの要求は二つに一つ。一つは僕と友達なんてならず、そして二度と屋上に来ないこと。僕のこの時間を壊さないこと。もしくは僕と、その、友だちになって、二人で軽音楽部を結成すること。僕のギターの時間の邪魔をしないこと。どちらにしても他の誰かに、クラスの人とか、他の友達とかに話してはいけない。ここでの利用は秘密にすること。これは絶対だ。僕は許可貰ってここに来ている。鍵だって預かってる」
「それなら、私も鍵を持ってる」
「桜田……さんも」
「明美」
「……明美さんも、許可もらってるってこと? 山田先生?」
「そう! 山田先生。ねえ、私のこと話ししても良い?」
「どうぞ。是非とも聞きたい」
「私ね、引きこもりで不登校だったんだ」
え?
「不登校なのは今も、かな。教室には行ってないから、まだ不登校だ。山田先生にせめて学校に来ることはしてみないかって言われて、それで屋上に連れてきてもらったの。それがだいたい一年前くらい」
「僕が屋上に来たのは半年前くらいだ。じゃあ、先客だったのは、明美さんのほうだったのか」
「そうだね。ある日、そう半年くらい前からかな。ギターの音がして。歌も歌っていて。ここの屋上って広くて陰になるようなところたくさんあるじゃない? だから、隠れて聞いていたんだ。私不登校だから、午前中にはやってきて、給食は一緒には食べられないからお弁当食べて、放課後になってあなたの音楽を聞く。それが日課だった。それまでは、携帯音楽プレーヤーで、イヤホンで聞いていたの。ゴイステか銀杏ボーイズかわからないけど、君の弾くベイビーベイビー、良かったな。また聞きたいね」
「銀杏なんて分かるのか!? 今時の中学生なのに」
しかも前身バンドのゴーイングステディまでわかるとは。何歳だよ。
「偶然にも音楽の趣味は合いそうだな。それは悪いことじゃない。むしろいいことだ」
「ね、私は誰にも言わないよ。言う相手がいないっていうのもあるけど。ほら、不登校だから。だから、友達になってよ。軽音楽部? なら、それでもいいからさ。邪魔はしない。隣で聞いてるだけ。本当に。ね、だからお願い」
僕はナナを呼び出したかった。「どうする?」って意見を聞きたかった。でも、呼び出したところで「良いんじゃない? 友達というのも今の君には必要だよ」とか言うに決まっている。わかるさ。僕と彼との付き合いは世界一長いんだから。
手を合わせて、頭を下げる彼女に、僕は断ることは出来なかった。ナナの助言もあるし、たまには友達というのをやってみてもいいかな。相手は僕以外に知り合いいないみたいだし。まあ、そういうのもいいかな。そう思って、僕は口を開いた。
「頭を上げてよ。ほら」
そして握手をした。
「じゃあ、まあ、ほら。友達な。よろしく」
ぱっと、笑顔を見せた。少しどきりとした。
「よろしく! 友達ね」
俺は適当に握手をして、それから座り直した。ケースを開けてギターを取り出す。俺はこの時間を壊されないために仕方なく友達をやることにしたんだから、ここでギターを辞めてしまっては意味がない。ギターを弾いてこそ、そこに価値が生まれるってものである。
チューニングを始める。彼女も隣りに座った。本当に黙っている。目をつぶって、静かに眠るように。僕はチューニングを合わせていく。ベンベンベン……キュキュキュ……。
「よし。じゃあ、今日はpillowsかな」
課題曲を選ぶ。いつも気分で適当に選んでいる。ロックバンドの曲が多いのは、趣味嗜好が偏っているからである。
ジャ、ジャン。
ギターを弾き始める。練習なので、コード譜やタブ譜を見ながら、覚えながら、覚えたらその小節を弾いてを繰り返す。音を、原曲を何度も聞いて、合わせていく。少ししたら、その曲は弾けるようになっていた。そしてら、それに合わせて、あとは歌うだけだ。完成である。
ジャカジャン!
隣から拍手が聞こえた。そういえば居たのだったな。あまりも静かだったから一瞬忘れていたぜ。
「オーディエンスがいるのは、新鮮な気分だな」
「すぐに一曲できるようになるのね、すごいね」
「まあ、毎日練習しているからな。ある程度は弾けるんだよ。あとは聞き込みだよ。どれだけたくさん正解の音を聞いて覚えるか。つまり原曲。サブスクの時代は好きな曲を何度でも聞けるからありがたいね」
「ふーん、そうなんだ」
それからふたりで音楽の話をした。好きな曲とか、バンドとか、そういう話。誰かと熱心に話をしたのは、それこそナナ以外には初めてだったかもしれない。なかなか新鮮な気分だった。