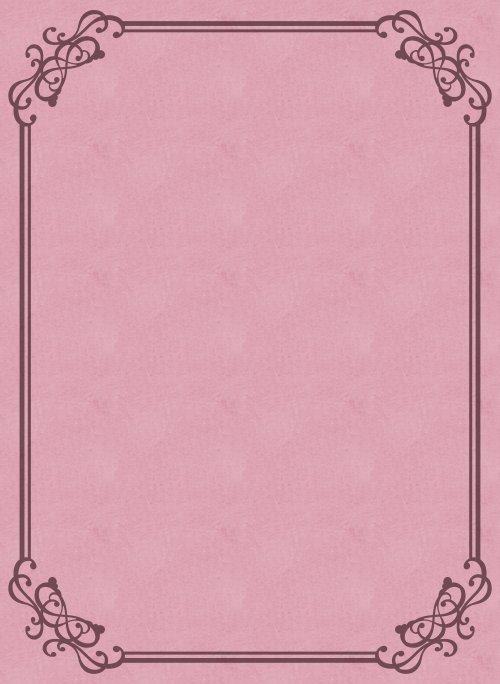「友達になってください」
それは屋上でギターを弾いていたことを見られてしまった日のことであった。
僕は自分の中学校に軽音楽部がなく、吹奏楽部しかないことを不満に思っていた。しかし、なぜだか学校には高いギターが数本並んでいるのだ。値段の高さはネックを触ればわかる。ネックというのは、ギターの弦が張ってある、指で弦を押さえるところ全体の総称、という説明でいいだろうか。まあ、わからない人はネットで調べてくれ。そのギターはネックが握りやすく、とても指の移動がスムーズであった。そして何より音がいい。良い木材を使っているのだ。ボディで音を鳴らすアコースティックギターは、よりその良さが顕著に出る。とても作りが良い。自分の個人の所有しているギターは五千円くらいの安いやつであるから比べるまでもないし、父の少し高いやつは二十万位するらしく、これもとても良いのだが、学校のギターは五十万円くらいはするらしい。めちゃくちゃいいやつなのだ。しかし、それが誰も弾く人がいないからと、放置されているのである。もったいない。しかし、だからといって学校には弾く場所もない。音楽室は吹奏楽部が独占しているし、ましてや教室で見せびらかすように、これ見よがしに弾くわけにもいかない。持って帰って弾こうにも、破損でもしたらそれこそ責任が取れない。そこで先生から鍵を借りて、こっそり屋上で弾いていたのである。一人軽音楽部。僕はそれがとても気に入っていた。ギターは音楽準備室で保管されていた。とても状態がよく、僕はあまりにもその良さに感激していた。毎日ケースから出すたびに、惚れ惚れとしていた。
その日もこっそりと、ひっそりとギターを持ち出し、屋上に出て、ケースから取り出してチューニングをしていた。チューナーは自前の物である。チューニングが終わって、適当にコードを鳴らしてウォーミングアップをしていた、その時に、ふと入口を見た時、閉めたはずの扉が開いていて、そしてそこには女の子が居た。知らない女の子だったから、クラスは違うことが一瞬でわかったが、秘密がバレてしまったことも一瞬でわかり、まずいと、瞬間的に、刹那に思った。
別に隠していることではなかったが、しかし、おおっぴらに、みんなに知られて屋上を使っていたことがバレてはなにか問題になるかもしれない。先生から許可をもらって鍵を借りていたとはいえ、放課後であるとはいえ、普段は立入禁止のところ。そんなところで何をしているかと思うのが普通で、指を指したくなるのが普通だ。僕は急いでギターに覆いかぶさるようにして、そしてその女の子をじっと見た。相手も見返してきた。どうする。どうなる。
しばらくして、女の子は扉を閉めてこちらへやって来た。
「ギターを弾いていたの?」
「いや、これは、その……」
僕は言い訳をしようとした。なにか自分が悪いことをしていたかのように思えてしまったからである。
「ギターが弾けるんだ、すごいね」
「あ、ええ、と、……ありがとう」
「私、二組の桜田明美。二年生だよね?」
「あ、ああ。ええと、六組の岡島太一。あの、このことは」
「大丈夫。秘密にしておいてあげる。ねえ、だからさ、一つお願い聞いてよ」
「え? なに?」
「友達になってください」
「友達?」
「そう、友達」
僕には彼女の考えがわからなかった。彼女の意図がわからなかった。何を目論んでいるのか、企んでいるのか、どういうつもりなのか、その一言で全てが分からなくなった。友達になってほしい? そんな、急に? いや、急ではないのかもしれない。もしかしたらずっと前から僕のことを覗いて、ギターをしていた事を見ていたのかもしれない。それでいてどこか気に入って、友達になって欲しいと、少し前からそう言うつもりで、それでようやく今日言ったのかもしれない。いや、きっとそうだろう。そうに違いない。
「一日時間をくれないか。また明日、誰にも見つからないように、こっそりと来ることができるかい?」
「もちろん。わかった、じゃあ、また明日ね。岡島太一くん」
彼女は去った。扉を閉めたのを確認して少ししてから鍵を掛けた。まあ、多分彼女も鍵を持っているんだろうから、意味はないだろうけど。
「さて、どう思う? ナナ」
「どう思うって?」
「彼女のことだよ。友達になって欲しいって、どういうつもりだろう。どういう意図なんだろう」
「そのまんまの意味じゃないのかい? 友達になって欲しい。それだけ」
「そうかな」
「君は勘繰り過ぎなんだよ」
今現在、問題は二つある。一つはギターを持って屋上に来ていること、弾いていることを覗かれたことでだいぶ前から知られてしまっていた可能性があること。これは自分ひとりだけの秘密だと思っていたがゆえに、なかなか苦しい。非常に恥ずかしくて、恥ずかしくてたまらない。もう死んでしまいたくなる。うーっと体を丸めて唸って、羞恥心に襲われる自分を必死になだめた。もう一つはギターが続けられなくなる可能性があること。ことが公になれば、なぜ自分だけ特別扱いされているのだと糾弾され、この時間がなくなってしまう可能性がある。それは嫌だ。最悪ギターは許可貰って家に持ち帰りたい。最悪家で弾き続けられるように、先生や学校側と交渉する必要がある。家だと、あまり音出せないけど。ほら、騒音とか、近所とか、親とか。だから、学校のこの場所というのはかけがえのない、貴重で大切な場所だったのに。どうして脅かされるようなことに。
悩みは尽きない。今度は友達になって欲しいという、あの言葉だ。桜田明美と言ったか。あの少女は何なんだろう。なぜ屋上に。どうして僕なんかと友だちになりたいだなんて思ったのか。僕には『なないろ』と呼んでいる、愛称『ナナ』と呼んでいる友だちがいる。彼は男の子だ。年は同じ十四才。白髪のサラサラヘアーで、スタイリッシュな容姿でモデルのように美しい。昔から、幼い頃からずっと僕の傍にいて、ずっと僕の友達で、ずっと話を聞いてくれていた。だから友達なんていらない。僕には既に友達はいるのだ。だったら、改めて作る必要なんて無いじゃないか。そうだ。そうに違いない。
「君はリアルの友達が必要だと思うけどな」
「ナナまで僕のことを裏切るのか?」
「そうじゃないさ。僕はいつだって君のそばにいるし、君の味方だ。でも、それとこれとは話が違う」
「どういう意味?」
「成長だよ。人間同士の付き合いは自分自身を成長させる要因になるんだ。君はもっと他人を知るということをした方がいい」
「そんなの必要かな。僕には君と、それと、音楽がある」
「音楽はいいさ。とても良い。君の好きなアニメのキャラクターのセリフで言えば『心を潤してくれる、ヒトの生み出した文化の極み』ってところかな」
「それならなぜ」
「なおさらさ。音楽を生み出すのは人間だからね。人間を知らないと、音楽の本当の意味を理解したことにはならないんだよ。歌詞の意味でも、音の意味でも。だからいい機会だよ。一度僕からは卒業して、あの女の子と過ごす時間を増やすのは、決して悪いことではないと思うよ」
「そんな。ナナがいなくなるなんてのは、それこそそんなのは絶対に嫌だよ」
「大丈夫。いなくなるわけじゃない。卒業するだけさ」
「何が違うのさ」
「時が来ればわかるよ。今はそのための準備期間みたいなものなんだ。そう思ってくれていい。大丈夫、明日にでも、すぐにいなくなるわけじゃあない。今夜にでも呼んでくれればまた会える。ヒトは常に一人で生きる生き物だけど、君は一人ぼっちじゃない。それだけは忘れないで」
「うん。ありがとう、ナナ」
こうして僕は翌日を迎える。
それは屋上でギターを弾いていたことを見られてしまった日のことであった。
僕は自分の中学校に軽音楽部がなく、吹奏楽部しかないことを不満に思っていた。しかし、なぜだか学校には高いギターが数本並んでいるのだ。値段の高さはネックを触ればわかる。ネックというのは、ギターの弦が張ってある、指で弦を押さえるところ全体の総称、という説明でいいだろうか。まあ、わからない人はネットで調べてくれ。そのギターはネックが握りやすく、とても指の移動がスムーズであった。そして何より音がいい。良い木材を使っているのだ。ボディで音を鳴らすアコースティックギターは、よりその良さが顕著に出る。とても作りが良い。自分の個人の所有しているギターは五千円くらいの安いやつであるから比べるまでもないし、父の少し高いやつは二十万位するらしく、これもとても良いのだが、学校のギターは五十万円くらいはするらしい。めちゃくちゃいいやつなのだ。しかし、それが誰も弾く人がいないからと、放置されているのである。もったいない。しかし、だからといって学校には弾く場所もない。音楽室は吹奏楽部が独占しているし、ましてや教室で見せびらかすように、これ見よがしに弾くわけにもいかない。持って帰って弾こうにも、破損でもしたらそれこそ責任が取れない。そこで先生から鍵を借りて、こっそり屋上で弾いていたのである。一人軽音楽部。僕はそれがとても気に入っていた。ギターは音楽準備室で保管されていた。とても状態がよく、僕はあまりにもその良さに感激していた。毎日ケースから出すたびに、惚れ惚れとしていた。
その日もこっそりと、ひっそりとギターを持ち出し、屋上に出て、ケースから取り出してチューニングをしていた。チューナーは自前の物である。チューニングが終わって、適当にコードを鳴らしてウォーミングアップをしていた、その時に、ふと入口を見た時、閉めたはずの扉が開いていて、そしてそこには女の子が居た。知らない女の子だったから、クラスは違うことが一瞬でわかったが、秘密がバレてしまったことも一瞬でわかり、まずいと、瞬間的に、刹那に思った。
別に隠していることではなかったが、しかし、おおっぴらに、みんなに知られて屋上を使っていたことがバレてはなにか問題になるかもしれない。先生から許可をもらって鍵を借りていたとはいえ、放課後であるとはいえ、普段は立入禁止のところ。そんなところで何をしているかと思うのが普通で、指を指したくなるのが普通だ。僕は急いでギターに覆いかぶさるようにして、そしてその女の子をじっと見た。相手も見返してきた。どうする。どうなる。
しばらくして、女の子は扉を閉めてこちらへやって来た。
「ギターを弾いていたの?」
「いや、これは、その……」
僕は言い訳をしようとした。なにか自分が悪いことをしていたかのように思えてしまったからである。
「ギターが弾けるんだ、すごいね」
「あ、ええ、と、……ありがとう」
「私、二組の桜田明美。二年生だよね?」
「あ、ああ。ええと、六組の岡島太一。あの、このことは」
「大丈夫。秘密にしておいてあげる。ねえ、だからさ、一つお願い聞いてよ」
「え? なに?」
「友達になってください」
「友達?」
「そう、友達」
僕には彼女の考えがわからなかった。彼女の意図がわからなかった。何を目論んでいるのか、企んでいるのか、どういうつもりなのか、その一言で全てが分からなくなった。友達になってほしい? そんな、急に? いや、急ではないのかもしれない。もしかしたらずっと前から僕のことを覗いて、ギターをしていた事を見ていたのかもしれない。それでいてどこか気に入って、友達になって欲しいと、少し前からそう言うつもりで、それでようやく今日言ったのかもしれない。いや、きっとそうだろう。そうに違いない。
「一日時間をくれないか。また明日、誰にも見つからないように、こっそりと来ることができるかい?」
「もちろん。わかった、じゃあ、また明日ね。岡島太一くん」
彼女は去った。扉を閉めたのを確認して少ししてから鍵を掛けた。まあ、多分彼女も鍵を持っているんだろうから、意味はないだろうけど。
「さて、どう思う? ナナ」
「どう思うって?」
「彼女のことだよ。友達になって欲しいって、どういうつもりだろう。どういう意図なんだろう」
「そのまんまの意味じゃないのかい? 友達になって欲しい。それだけ」
「そうかな」
「君は勘繰り過ぎなんだよ」
今現在、問題は二つある。一つはギターを持って屋上に来ていること、弾いていることを覗かれたことでだいぶ前から知られてしまっていた可能性があること。これは自分ひとりだけの秘密だと思っていたがゆえに、なかなか苦しい。非常に恥ずかしくて、恥ずかしくてたまらない。もう死んでしまいたくなる。うーっと体を丸めて唸って、羞恥心に襲われる自分を必死になだめた。もう一つはギターが続けられなくなる可能性があること。ことが公になれば、なぜ自分だけ特別扱いされているのだと糾弾され、この時間がなくなってしまう可能性がある。それは嫌だ。最悪ギターは許可貰って家に持ち帰りたい。最悪家で弾き続けられるように、先生や学校側と交渉する必要がある。家だと、あまり音出せないけど。ほら、騒音とか、近所とか、親とか。だから、学校のこの場所というのはかけがえのない、貴重で大切な場所だったのに。どうして脅かされるようなことに。
悩みは尽きない。今度は友達になって欲しいという、あの言葉だ。桜田明美と言ったか。あの少女は何なんだろう。なぜ屋上に。どうして僕なんかと友だちになりたいだなんて思ったのか。僕には『なないろ』と呼んでいる、愛称『ナナ』と呼んでいる友だちがいる。彼は男の子だ。年は同じ十四才。白髪のサラサラヘアーで、スタイリッシュな容姿でモデルのように美しい。昔から、幼い頃からずっと僕の傍にいて、ずっと僕の友達で、ずっと話を聞いてくれていた。だから友達なんていらない。僕には既に友達はいるのだ。だったら、改めて作る必要なんて無いじゃないか。そうだ。そうに違いない。
「君はリアルの友達が必要だと思うけどな」
「ナナまで僕のことを裏切るのか?」
「そうじゃないさ。僕はいつだって君のそばにいるし、君の味方だ。でも、それとこれとは話が違う」
「どういう意味?」
「成長だよ。人間同士の付き合いは自分自身を成長させる要因になるんだ。君はもっと他人を知るということをした方がいい」
「そんなの必要かな。僕には君と、それと、音楽がある」
「音楽はいいさ。とても良い。君の好きなアニメのキャラクターのセリフで言えば『心を潤してくれる、ヒトの生み出した文化の極み』ってところかな」
「それならなぜ」
「なおさらさ。音楽を生み出すのは人間だからね。人間を知らないと、音楽の本当の意味を理解したことにはならないんだよ。歌詞の意味でも、音の意味でも。だからいい機会だよ。一度僕からは卒業して、あの女の子と過ごす時間を増やすのは、決して悪いことではないと思うよ」
「そんな。ナナがいなくなるなんてのは、それこそそんなのは絶対に嫌だよ」
「大丈夫。いなくなるわけじゃない。卒業するだけさ」
「何が違うのさ」
「時が来ればわかるよ。今はそのための準備期間みたいなものなんだ。そう思ってくれていい。大丈夫、明日にでも、すぐにいなくなるわけじゃあない。今夜にでも呼んでくれればまた会える。ヒトは常に一人で生きる生き物だけど、君は一人ぼっちじゃない。それだけは忘れないで」
「うん。ありがとう、ナナ」
こうして僕は翌日を迎える。