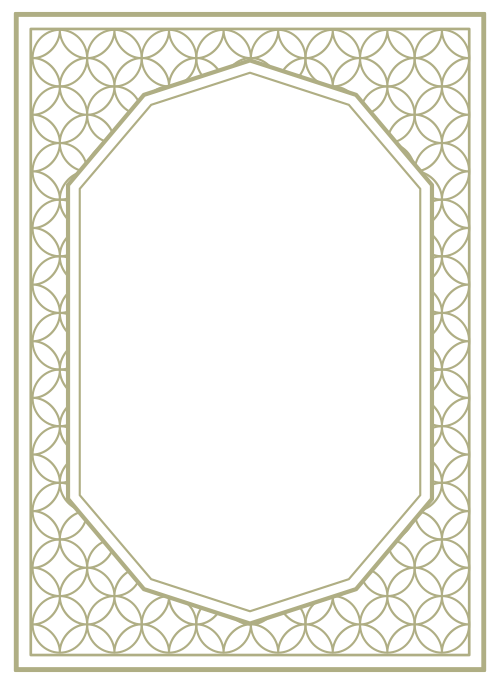最近、不穏な空気が自分の周りに漂っているなあ、とは少し前から感じていた。
原因もわかっていた。
ただ、勝手にすればいいと思っていたし、相手にする姿勢を見せなければそのうちどうにかなるとも思っていた。
でも、それは少し甘かったとあるときわかった。
「そのルートに入ってもスチルは出ないんだけど、台詞とかがすごく素敵で、手前でセーブして何回も見ちゃうの」
お昼休み。いつものメンバーでお弁当を食べながらおしゃべりしていた。
今日は、恵麻ちゃんが最近クリアした乙女ゲームについて熱く語っていた。創作をするほどではないけれど、プレイしたタイトル数でいえば恵麻ちゃんもオタクの部類に入ると思う。乙女ゲームはスマホでも携帯ゲームでもかなりの本数をプレイ済で、かなり凝り性だからバッドエンドを含むすべてのエンドを回収している。言ってみれば、ガチの乙女ゲーマーだ。本人は自覚がないみたいだけれど。
「そういうのってあるよね。スチルがないものでもシーン別再生機能があったらいいのにね」
「わかる! パッと開いてパッと見れたらいいよねー」
私とサナもそれなりにプレイするから、恵麻ちゃんとはこの手の話題でかなり盛り上がってしまう。
「それってお気に入りの本に付箋を貼っときたい感じ?」
そう言ったのは葉月で、彼女はかなりの読書好きだ。名作文学から最近流行りのライト文芸まで読む。試しにラノベを貸してみたら、いくつかハマって自分でも続きを集め始めたりしている。「本の虫って言ってみれば本オタクでしょ」というのが彼女の言い分で、だから私たちとも気が合う。
地味で無害な集団、と私はそんな自分たちのことを認識していた。
「たぶん続編が出ると思うんだけど、エンディングのあと、ヒロインと男の子たちがどんなふうに過ごしてるかなあって考えちゃうんだよね。最近、ファンディスクを出すことありきの本編なのか、ラストまで甘さ控えめなものが増えたんだよね。だから、ついつい妄想しちゃうし、ネットで上手な人の二次創作の小説読んじゃった」
「それは恵麻ちゃん、もう我々への仲間入りだよ。その妄想を漫画でも小説でもいいから形にするといいよー」
「そうそう。漫研に入ろう? 楽しいよ? 漫画を描けなくても、原案としてその妄想を提供してくれたら、私かサナが形にするよ」
「えー。どうしよっかな。楽しそうだとは思うんだけど」
そのときも、そんなふうに自分たちの好きなことについて楽しくおしゃべりしていた。
それなのに――。
「キモ。うるせーんだよ」
突然、悪意のある言葉をぶつけられて私たちは凍りついた。
その言葉を発したのは私たちの席の近くを通りかかった派手めの女子の集団で、周りを見回しても私たちに向けられた言葉だったのは明白だった。
「……別にいつもと同じ声量で話してたんだけどね」
「楓」
言い返すみたいな物言いになってしまった私を、葉月がたしなめた。つい口をついて出てしまった。
サナは平気そうな顔をしていたけれど、恵麻ちゃんは青ざめていた。
無理もない。恵麻ちゃんは私やサナと違ってオタクであると開き直って生きていないし、おまけに気が小さい。いい子なのに、気を許した人以外の前ではいつも所在なさそうに小さくなっているような子だ。
決して大声ではしゃいでいたわけでもないのにクラスの派手グループに威嚇されて、さぞ怖い思いをしたのだろう。
「みんな、ちゃんと教科書とか持って帰りなね。あと、できるなら上履きも毎日持ち帰ること」
お弁当箱を片しながら、葉月が静かに言った。それを聞いて、恵麻ちゃんの顔はさらに青くなった。
「脅すわけじゃないよ。ただ、ああいった人たちがエスカレートしたときにやりそうなことを前もって考えて自衛しとけば安心でしょ? ってこと」
「じゃあ、これからはトイレは四人一緒に行こう」
安心させるために葉月が微笑んで見せたから、私はそれに答えるために連れションの提案をした。それでやっと恵麻ちゃんは笑ったけれど、ざらりとした嫌な気持ちが残ったままお昼休みは終わってしまった。
そのあとの授業は、あまり頭に入らなかった。
(私のせいだよね)
そんな気持ちが、ずっとぐるぐると巡っていたから。
誰も私を責めなかったけれど、みんなそう思っていたんじゃないだろうか。
だって私たちは地味で、あんな派手な子たちからしたら無害だけれど同時に無益だ。構う価値もない。私たち自身もそういうふうに、なるべく彼女たちの視界に入らないように自分たちの世界で生きてきた。だから、虫の居所が悪いときに八つ当たりとかをされたとしても、積極的に悪意を向ける対象ではなかったはずだ。
これまでは――。
でも、これまでと違うことといったら……北大路のことだろう。
私にとって、俺様ナルシストで迷惑な存在だったとしても、やっぱり顔が良いとなるとファンもつく。
そのファンの子たちからしてみれば、最近私が北大路と話をしているというのは面白くなかったに違いない。だから、嫌な視線を向けられているのは感じていた。何か言われているのも気づいていた。でも、睨まれても陰口を言われても死にはしないんだからと、知らんぷりをしていたのだ。
だって、そうやって私のことを面白く思っていない人たちに、いちいち弁解していくわけにもいかない。「本当は、ああしてつきまとわれるのは、なかなか迷惑してるんですよ」と主張しても、この陰キャラめ生意気な、と思われるだけだろう。何を言っても、事態がよくなることはない。だから、ほとぼりが冷めるまで放っておくしかないと思っていたのだ。
でも、それが周りに及ぶのなら、もう黙っていられない。
恵麻ちゃんが怖がって好きなことの話をできなくなるのは嫌だし、あの人たちの視線に怯えてお通夜みたいな空気の中でお昼休みを過ごすのも嫌だ。
だから、私は行動に出ることにした。
「サナ、教室に忘れ物したから取ってくるね」
そう言って、私は頃合いを見計らって部室を出た。
今日の日直は本田さん。派手グループの一員だ。ホームルームの最中もビシビシと例の派手グループの悪意を感じていたから、たぶん今から行けば現場を押さえられるだろう。
私は今から、嫌がらせ現場に乗り込む。
私の考えすぎじゃなければ、昼休みの感じからすると彼女たちのイライラはピークに達していただろうから。しかも、自分たちの一人が日直の日なんて絶好の嫌がらせ日和だ。
私に精神攻撃するだけじゃ気が済まなくなって昼休みのあの行動なら、物理的な嫌がらせに移行するまでに時間はかからないだろう――そう推理していたけれど、果たしてそれはビンゴだった。
「何してるの?」
私は、まだ教室に残ってひとつの机を囲んで何かしている女子の集団に声をかけた。なぜなら、その机は私のものだったから。
「……お前、何撮ってんだよ」
「気にしないで。続けて続けて」
私は、スマホを構えて教室に入っていった。それに気づいた一人が威嚇してくるけれど、その顔もばっちり撮っておく。もちろん動画だ。
「それ、私の机だよね? それに、教科書も出てる。……何するつもりだったの?」
落書きをするか破るか。そのくらいしか嫌がらせにバリエーションはないけれど、わざわざ聞いてみた。葉月に教科書を持ち帰るように言われていたのに、このためにあえて置いて帰ったのはどうやら正解だったみたいだ。
……なんて冷静に分析していると装って、心臓はバクバクだ。でも、いじめられっ子に甘んじるわけにはいかないのだ。
「あんた、北大路くんと話なんかして生意気なんだよね」
そう言ったのは、このグループのリーダー格の女子・白川詩織だ。こいつの名前はすぐ覚えた。去年、体育の時間にわざとではなかったにしろ私にボールをぶつけ、そのとき痛みのあまりに自然と涙が出てしまったら、「泣くほどじゃないじゃん!」と文句をつけやがったのだ。謝るどころか文句を言ってくるなんてギルティ。絶対名前忘れない、と思っていたら今年は同じクラスになってしまった。
「生意気って何が?」
怖いから、あまり距離は詰めずに尋ねてみる。もう、この状況で何をどんなふうに聞いたって挑発っぽくなるのだから仕方ない。
私の手にあるスマホを警戒してか、白川以外はどうしようかと困惑した顔を浮かべている。主体性のないやつらめ。
「……なんでもいいけどさ」
何も言わない白川たちに焦れて、私は自分から本題に入ることにした。
あまり長くかかるとサナが心配するだろうし、白川たちと喧嘩をしにきたわけでもないのだから。
「北大路と話するからってムカつかれてるんだよね? でもね、あっちから話しかけてきたんだからね。あいつのこと好きなんでしょ? ならちゃんと見ててよ。話しかけてくるのっていつも向こうだから。それなのに、あいつと話すからってムカつかれて、睨まれたり今日の昼休みみたいに威嚇されるなんて理不尽よ。その上、教科書に落書き? 隠すつもりだったの? とにかく、そんな嫌がらせまでされるなんておかしい。自分たちも話したいなら話しかけたらいいでしょ?」
一気にそう、言いきった。
怖かったけど、頭の中でシミュレーションした通りに言ってやった。シミュレーションの中では胸ぐら掴まれたりビンタされたりなんてことがあったけれど、実際にはただ怖い顔で睨まれただけだった。
「……お前、あんま調子乗るなよ。嫌がらせ? 証拠ないじゃん? 睨んだ? 威嚇した? そんなの被害妄想じゃない?」
開き直ったのか、白川は馬鹿にしきった顔で言った。完全に私のことを舐めている。まぁ、一人で乗り込んできたオタクなんて怖くもなんともないだろうけれど。実際、私は逃げ足が速いだけで体育は得意じゃないし、筋肉もない。あきらかに中学時代に運動部に入ってましたよ感がある白川に飛びかかられでもしたら、あっという間に負けるに決まっている。何か、ひょろっとした私と違って肉感的な身体だし(notセクシー)。
「私の机を白川さんたちが囲むこの動画を見た人がどう思うかだよね。とにかく、今すぐ私の机から離れて。今後私のものがなくなったり、落書きされたりしたら全部白川さんたちのせいなんだなって思うから。あと、私の友達もね! もし何かあったらこの動画を先生に見せるから。内申に関わるよ? 二年のこんな時期に問題なんて起こしたくないでしょ? だから、もう何もしないで」
野良犬に狙われたときと同じように、決して目をそらさず、背中を向けたらダメだからジリジリと後ずさって私は出口を目指した。
その姿は間抜けだっただろうけれど、白川たちが白けたように私の机から離れるのを確認してホッとする。
もう、ここまでして今後何かしてくることはないだろうな。してきてもこの動画を本当に証拠として誰かに見せればいいわけだし――そんなふうに思いながら教室をでようとしたとき、低く唸るような白川の声が聞こえた。
「北大路くんが話しかけてくれるからって調子づくなよ、ブスが。地味ブス! お前らみたいなのは日の当たらないところでコソコソしてろ。キモいんだよ。漫画とかアニメとか、そんなもんに夢中のくせに。お前らみたいな女として終わってるブスは、せいぜいそういうブスのために作られた恋愛ゲームとやらでキャーキャー言ってれば? オタクのくせに」
それだけ言うと、白川は満足そうに片頬を歪めて笑い、もう何も言うことはないというように口を閉じた。そんな表情を浮かべたってことは、狙い通り私は傷ついた顔をしたんだろう。
でも、それが自分でわからないほど、体の奥がグラグラとしていた。
オタクで何が悪いって言うんだ。何も、誰にも迷惑なんてかけてないのに、何でこんなに馬鹿にされなくちゃいけないんだろう。それに、クリエイターの人たちが一生懸命作って世に送り出しているものまで馬鹿にされたみたいで、腹が立った。
「……ブスとかキモいとか言うけど、あんたたちだって二次元の美少女を前にしたら全員等しく駄立体なんだからなっ!」
後ずさりで体が完全に廊下に出ると、そう叫んで私は一気に走り出した。グラグラする。胃が熱い。
走りながら体が小刻みに震えているのを感じていた。でも、止まることができない。
「姫川!」
あまり前を見ずに走っていたから、ドンッと誰かにぶつかった。顔を上げなくても、誰とぶつかったのかわかってしまった。
「その……真田に気になる話を聞いて、それでもしかしてと思って来てみたんだけど……大丈夫か?」
北大路だ。へたり込んだ頭上から、心配げな声がする。でも、体の奥が熱くて、私は返事をすることができない。
この熱さは怒りか、悲しみか……わからないけれど、その奥から湧き上がるような熱さが、気がつくと口から零れ出していた。
「……もう、学校で話しかけないで」
北大路がヒュッと息を飲むのがわかったけれど、私はまた立ち上がって走り出した。
震えはさっきよりひどくなって、吐きそうなほど胃が熱くなっていたけれど、それでももう、走り続けるしかなかった。
原因もわかっていた。
ただ、勝手にすればいいと思っていたし、相手にする姿勢を見せなければそのうちどうにかなるとも思っていた。
でも、それは少し甘かったとあるときわかった。
「そのルートに入ってもスチルは出ないんだけど、台詞とかがすごく素敵で、手前でセーブして何回も見ちゃうの」
お昼休み。いつものメンバーでお弁当を食べながらおしゃべりしていた。
今日は、恵麻ちゃんが最近クリアした乙女ゲームについて熱く語っていた。創作をするほどではないけれど、プレイしたタイトル数でいえば恵麻ちゃんもオタクの部類に入ると思う。乙女ゲームはスマホでも携帯ゲームでもかなりの本数をプレイ済で、かなり凝り性だからバッドエンドを含むすべてのエンドを回収している。言ってみれば、ガチの乙女ゲーマーだ。本人は自覚がないみたいだけれど。
「そういうのってあるよね。スチルがないものでもシーン別再生機能があったらいいのにね」
「わかる! パッと開いてパッと見れたらいいよねー」
私とサナもそれなりにプレイするから、恵麻ちゃんとはこの手の話題でかなり盛り上がってしまう。
「それってお気に入りの本に付箋を貼っときたい感じ?」
そう言ったのは葉月で、彼女はかなりの読書好きだ。名作文学から最近流行りのライト文芸まで読む。試しにラノベを貸してみたら、いくつかハマって自分でも続きを集め始めたりしている。「本の虫って言ってみれば本オタクでしょ」というのが彼女の言い分で、だから私たちとも気が合う。
地味で無害な集団、と私はそんな自分たちのことを認識していた。
「たぶん続編が出ると思うんだけど、エンディングのあと、ヒロインと男の子たちがどんなふうに過ごしてるかなあって考えちゃうんだよね。最近、ファンディスクを出すことありきの本編なのか、ラストまで甘さ控えめなものが増えたんだよね。だから、ついつい妄想しちゃうし、ネットで上手な人の二次創作の小説読んじゃった」
「それは恵麻ちゃん、もう我々への仲間入りだよ。その妄想を漫画でも小説でもいいから形にするといいよー」
「そうそう。漫研に入ろう? 楽しいよ? 漫画を描けなくても、原案としてその妄想を提供してくれたら、私かサナが形にするよ」
「えー。どうしよっかな。楽しそうだとは思うんだけど」
そのときも、そんなふうに自分たちの好きなことについて楽しくおしゃべりしていた。
それなのに――。
「キモ。うるせーんだよ」
突然、悪意のある言葉をぶつけられて私たちは凍りついた。
その言葉を発したのは私たちの席の近くを通りかかった派手めの女子の集団で、周りを見回しても私たちに向けられた言葉だったのは明白だった。
「……別にいつもと同じ声量で話してたんだけどね」
「楓」
言い返すみたいな物言いになってしまった私を、葉月がたしなめた。つい口をついて出てしまった。
サナは平気そうな顔をしていたけれど、恵麻ちゃんは青ざめていた。
無理もない。恵麻ちゃんは私やサナと違ってオタクであると開き直って生きていないし、おまけに気が小さい。いい子なのに、気を許した人以外の前ではいつも所在なさそうに小さくなっているような子だ。
決して大声ではしゃいでいたわけでもないのにクラスの派手グループに威嚇されて、さぞ怖い思いをしたのだろう。
「みんな、ちゃんと教科書とか持って帰りなね。あと、できるなら上履きも毎日持ち帰ること」
お弁当箱を片しながら、葉月が静かに言った。それを聞いて、恵麻ちゃんの顔はさらに青くなった。
「脅すわけじゃないよ。ただ、ああいった人たちがエスカレートしたときにやりそうなことを前もって考えて自衛しとけば安心でしょ? ってこと」
「じゃあ、これからはトイレは四人一緒に行こう」
安心させるために葉月が微笑んで見せたから、私はそれに答えるために連れションの提案をした。それでやっと恵麻ちゃんは笑ったけれど、ざらりとした嫌な気持ちが残ったままお昼休みは終わってしまった。
そのあとの授業は、あまり頭に入らなかった。
(私のせいだよね)
そんな気持ちが、ずっとぐるぐると巡っていたから。
誰も私を責めなかったけれど、みんなそう思っていたんじゃないだろうか。
だって私たちは地味で、あんな派手な子たちからしたら無害だけれど同時に無益だ。構う価値もない。私たち自身もそういうふうに、なるべく彼女たちの視界に入らないように自分たちの世界で生きてきた。だから、虫の居所が悪いときに八つ当たりとかをされたとしても、積極的に悪意を向ける対象ではなかったはずだ。
これまでは――。
でも、これまでと違うことといったら……北大路のことだろう。
私にとって、俺様ナルシストで迷惑な存在だったとしても、やっぱり顔が良いとなるとファンもつく。
そのファンの子たちからしてみれば、最近私が北大路と話をしているというのは面白くなかったに違いない。だから、嫌な視線を向けられているのは感じていた。何か言われているのも気づいていた。でも、睨まれても陰口を言われても死にはしないんだからと、知らんぷりをしていたのだ。
だって、そうやって私のことを面白く思っていない人たちに、いちいち弁解していくわけにもいかない。「本当は、ああしてつきまとわれるのは、なかなか迷惑してるんですよ」と主張しても、この陰キャラめ生意気な、と思われるだけだろう。何を言っても、事態がよくなることはない。だから、ほとぼりが冷めるまで放っておくしかないと思っていたのだ。
でも、それが周りに及ぶのなら、もう黙っていられない。
恵麻ちゃんが怖がって好きなことの話をできなくなるのは嫌だし、あの人たちの視線に怯えてお通夜みたいな空気の中でお昼休みを過ごすのも嫌だ。
だから、私は行動に出ることにした。
「サナ、教室に忘れ物したから取ってくるね」
そう言って、私は頃合いを見計らって部室を出た。
今日の日直は本田さん。派手グループの一員だ。ホームルームの最中もビシビシと例の派手グループの悪意を感じていたから、たぶん今から行けば現場を押さえられるだろう。
私は今から、嫌がらせ現場に乗り込む。
私の考えすぎじゃなければ、昼休みの感じからすると彼女たちのイライラはピークに達していただろうから。しかも、自分たちの一人が日直の日なんて絶好の嫌がらせ日和だ。
私に精神攻撃するだけじゃ気が済まなくなって昼休みのあの行動なら、物理的な嫌がらせに移行するまでに時間はかからないだろう――そう推理していたけれど、果たしてそれはビンゴだった。
「何してるの?」
私は、まだ教室に残ってひとつの机を囲んで何かしている女子の集団に声をかけた。なぜなら、その机は私のものだったから。
「……お前、何撮ってんだよ」
「気にしないで。続けて続けて」
私は、スマホを構えて教室に入っていった。それに気づいた一人が威嚇してくるけれど、その顔もばっちり撮っておく。もちろん動画だ。
「それ、私の机だよね? それに、教科書も出てる。……何するつもりだったの?」
落書きをするか破るか。そのくらいしか嫌がらせにバリエーションはないけれど、わざわざ聞いてみた。葉月に教科書を持ち帰るように言われていたのに、このためにあえて置いて帰ったのはどうやら正解だったみたいだ。
……なんて冷静に分析していると装って、心臓はバクバクだ。でも、いじめられっ子に甘んじるわけにはいかないのだ。
「あんた、北大路くんと話なんかして生意気なんだよね」
そう言ったのは、このグループのリーダー格の女子・白川詩織だ。こいつの名前はすぐ覚えた。去年、体育の時間にわざとではなかったにしろ私にボールをぶつけ、そのとき痛みのあまりに自然と涙が出てしまったら、「泣くほどじゃないじゃん!」と文句をつけやがったのだ。謝るどころか文句を言ってくるなんてギルティ。絶対名前忘れない、と思っていたら今年は同じクラスになってしまった。
「生意気って何が?」
怖いから、あまり距離は詰めずに尋ねてみる。もう、この状況で何をどんなふうに聞いたって挑発っぽくなるのだから仕方ない。
私の手にあるスマホを警戒してか、白川以外はどうしようかと困惑した顔を浮かべている。主体性のないやつらめ。
「……なんでもいいけどさ」
何も言わない白川たちに焦れて、私は自分から本題に入ることにした。
あまり長くかかるとサナが心配するだろうし、白川たちと喧嘩をしにきたわけでもないのだから。
「北大路と話するからってムカつかれてるんだよね? でもね、あっちから話しかけてきたんだからね。あいつのこと好きなんでしょ? ならちゃんと見ててよ。話しかけてくるのっていつも向こうだから。それなのに、あいつと話すからってムカつかれて、睨まれたり今日の昼休みみたいに威嚇されるなんて理不尽よ。その上、教科書に落書き? 隠すつもりだったの? とにかく、そんな嫌がらせまでされるなんておかしい。自分たちも話したいなら話しかけたらいいでしょ?」
一気にそう、言いきった。
怖かったけど、頭の中でシミュレーションした通りに言ってやった。シミュレーションの中では胸ぐら掴まれたりビンタされたりなんてことがあったけれど、実際にはただ怖い顔で睨まれただけだった。
「……お前、あんま調子乗るなよ。嫌がらせ? 証拠ないじゃん? 睨んだ? 威嚇した? そんなの被害妄想じゃない?」
開き直ったのか、白川は馬鹿にしきった顔で言った。完全に私のことを舐めている。まぁ、一人で乗り込んできたオタクなんて怖くもなんともないだろうけれど。実際、私は逃げ足が速いだけで体育は得意じゃないし、筋肉もない。あきらかに中学時代に運動部に入ってましたよ感がある白川に飛びかかられでもしたら、あっという間に負けるに決まっている。何か、ひょろっとした私と違って肉感的な身体だし(notセクシー)。
「私の机を白川さんたちが囲むこの動画を見た人がどう思うかだよね。とにかく、今すぐ私の机から離れて。今後私のものがなくなったり、落書きされたりしたら全部白川さんたちのせいなんだなって思うから。あと、私の友達もね! もし何かあったらこの動画を先生に見せるから。内申に関わるよ? 二年のこんな時期に問題なんて起こしたくないでしょ? だから、もう何もしないで」
野良犬に狙われたときと同じように、決して目をそらさず、背中を向けたらダメだからジリジリと後ずさって私は出口を目指した。
その姿は間抜けだっただろうけれど、白川たちが白けたように私の机から離れるのを確認してホッとする。
もう、ここまでして今後何かしてくることはないだろうな。してきてもこの動画を本当に証拠として誰かに見せればいいわけだし――そんなふうに思いながら教室をでようとしたとき、低く唸るような白川の声が聞こえた。
「北大路くんが話しかけてくれるからって調子づくなよ、ブスが。地味ブス! お前らみたいなのは日の当たらないところでコソコソしてろ。キモいんだよ。漫画とかアニメとか、そんなもんに夢中のくせに。お前らみたいな女として終わってるブスは、せいぜいそういうブスのために作られた恋愛ゲームとやらでキャーキャー言ってれば? オタクのくせに」
それだけ言うと、白川は満足そうに片頬を歪めて笑い、もう何も言うことはないというように口を閉じた。そんな表情を浮かべたってことは、狙い通り私は傷ついた顔をしたんだろう。
でも、それが自分でわからないほど、体の奥がグラグラとしていた。
オタクで何が悪いって言うんだ。何も、誰にも迷惑なんてかけてないのに、何でこんなに馬鹿にされなくちゃいけないんだろう。それに、クリエイターの人たちが一生懸命作って世に送り出しているものまで馬鹿にされたみたいで、腹が立った。
「……ブスとかキモいとか言うけど、あんたたちだって二次元の美少女を前にしたら全員等しく駄立体なんだからなっ!」
後ずさりで体が完全に廊下に出ると、そう叫んで私は一気に走り出した。グラグラする。胃が熱い。
走りながら体が小刻みに震えているのを感じていた。でも、止まることができない。
「姫川!」
あまり前を見ずに走っていたから、ドンッと誰かにぶつかった。顔を上げなくても、誰とぶつかったのかわかってしまった。
「その……真田に気になる話を聞いて、それでもしかしてと思って来てみたんだけど……大丈夫か?」
北大路だ。へたり込んだ頭上から、心配げな声がする。でも、体の奥が熱くて、私は返事をすることができない。
この熱さは怒りか、悲しみか……わからないけれど、その奥から湧き上がるような熱さが、気がつくと口から零れ出していた。
「……もう、学校で話しかけないで」
北大路がヒュッと息を飲むのがわかったけれど、私はまた立ち上がって走り出した。
震えはさっきよりひどくなって、吐きそうなほど胃が熱くなっていたけれど、それでももう、走り続けるしかなかった。