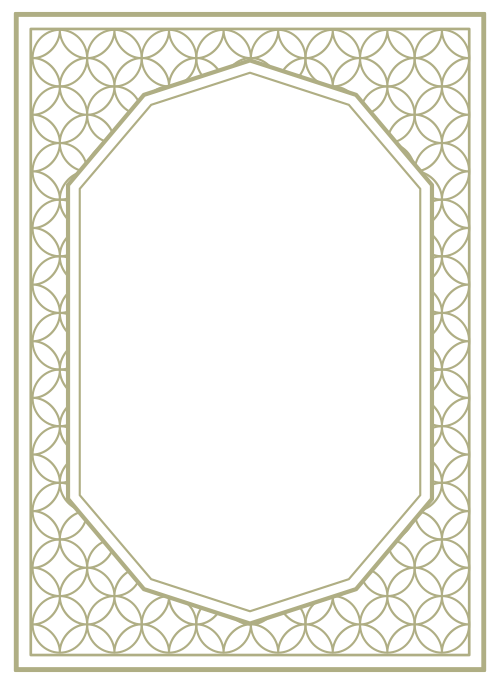BLショック発熱から復帰して登校してきても、北大路は私に声をかけてこなかった。もうあきらめてくれたのだろうか。
何にせよ、そのおかげで、休み時間はサナや他の趣味の合う子たちと平和におしゃべりして過ごすことができた。
回し読みしている漫画の続きを貸してもらったり、一緒にハマっているソーシャルゲームでなかなか私が出せないでいるキャラクターを出した子にゲーム内イベントを見せてもらったり。
ちらりと北大路のほうを見れば、昼休みの前半はどこかに行っていたし、戻ってきてからは自分の机でイヤホンをして、熱心に何か音楽を聴いている様子だった。まるで、昨日まで私にしつこく声をかけていたのが嘘みたいだ。
これが私の日常よね――そんなふうに思って胸を撫で下ろしていたのだ。
それなのに……
「姫川、喜べ! 今から俺とカラオケに行くぞ!」
放課後、部活に行くために教室を出ようとしたところで、北大路に足止めされた。
しかも、わけのわからないことを言っている。
「どいてよ。今から部活に行くんだから」
「大丈夫だ。部長さんにはもう二人が部活を休むことの許可を得てる」
「はぁ? いつの間に?」
「てか、あたしも?」
呆れる私とサナに、北大路は「ドヤァ」という顔をしてきた。用意周到だろうと言いたいらしい。
(それにしても何で許可を出してるんだ、部長。しかもこいつもわざわざ三年生の教室に行って話をしてきたのか。その行動力があるなら仲違いしたバンド仲間と仲直りして来いよ。それか別の楽曲提供者を探せ。もしくは自分で作れよ。)
言いたいことはたくさんあったけれど、疲れるのがわかっていたから私はもう何も言わなかった。それを肯定ととったのか、北大路は嬉しそうだ。
「お前の作った曲を探して聴いたんだ! ますますお前に曲を作ってもらいたくなった! お前、なかなかセンスあるな」
「そりゃどうも」
誰だ、情報漏らしたのは。捕まえてとっちめてやりたい――そう思うけれど、八つ当たりかもしれないと気づいてグッと堪えた。
こいつが私につきまとったりしなければ、そんな情報が漏れようが大したことではないのだから。
徹頭徹尾、悪いのはこいつだ。
「それで、姫川も俺の歌を聴けば、きっと俺に曲を作りたくなるだろうって気がついたんだ。嬉しいだろう? ただで俺の歌が聴けるんだから」
北大路は、またおかしなことを言っている。しかもこれを冗談ではなく真顔で言っているのだから質が悪い。他の女子たちなら、こんなことを言われればキャーキャー言って大喜びするのかもしれない。でも、私には二次元の素敵な王子様がいるのだ。そんじょそこらの異性に騒ぐなんて思われているなら心外だ。ムカつく。ムカつきすぎて顔面にパンチしてやりたい。
でも、私は大人だからそんなことはせず、そっと北大路の手に百円玉を握らせた。
「姫川? ……この百円はどういう意味だ?」
「『ただで歌を聴かせてやるから有り難がれ』って言うんだったら、お金あげるから帰ってもらおうと思って」
「なっ……!」
明確な拒絶をしたことでようやく理解できたのか、北大路はショックを受けた顔をしている。まぁ、これまでの人生で女子をカラオケに誘ってこんなふうに嫌がられることなんてきっとなかっただろうから、ショックを受けるのも仕方がない。でも、同情なんてしてやらない。三次元に興味のない人間もいるということを、そろそろしっかり知ったほうがいい。
「サナ、行こう」
「待って、メーちゃん」
私は北大路を放って部室へ向かおうとした。
でも、サナは歩き出した私の手を引いて、またあいつのところへ戻ってしまった。
「今日はせっかくだからキンヤくんとカラオケ行こうよ。キンヤくんも、歌を聴いた上でメーちゃんが断るんだったらあきらめるよね?」
「あ、ああ……それなら仕方ないな」
「よっしゃ! なら行こう!」
最初は何を言い出すのかと思ったけれど、サナの機転に救われた。喜びの雄叫びをついあげてしまったあと、私はこっそりサナに「グッジョブ」と囁いた。日頃からイケメンボイス(声優さんの)は聴き慣れているんだ。そこそこかっこよくてそこそこうまいくらいの歌声を聴かされたって、私の心は絶対に一ミリも動かない自信がある。歌声を聴かせて私の心を動かせないのなら、それが北大路の実力ってやつだ。今度こそしっかり断って、あきらめてもらおう。
何もわかっていないのは北大路だけで、満足そうな顔をして私とサナの後ろに続いていた。
それにしても……
北大路を連れて歩くのはすごく目立つ!
北大路が目立つのはもちろんだけれど、こいつの容姿と私たちの容姿のギャップも原因な気がする。
不良のような着崩し方やアレンジではないけれど、北大路は芋臭くならないよう適度に制服を着崩している。おまけにイケメン。それに長身でスタイルもいいから、制服映えする容姿なのだ。
かたや私とサナは、スカート丈こそ少しだけ気を使って膝が半分ほど見える位置まで上げてはいるものの、いわゆる“女子高生”な出で立ちをしているわけではない。アレンジもしていなければ、余計な付属品も一切つけていない。まあぶっちゃけ、ダサいのは自覚しているのだ。
そんなのがイケメンと並んで歩けば、嫌でも目を引くだろう。
昇降口にたどりつくまでの間だけでも、視線、視線、視線。
見られるって、かなりのストレスだなと感じた。
でも、今日このあとカラオケに行けば、北大路につきまとわれることもなくなる。だから、それまでの我慢だ。
そう思っていたのに……
「う、うまい……」
十八番《おはこ》だという人気バンドのヒット曲を高らかに歌い上げる北大路。
その歌唱力に私は圧倒された。
声質がわりと低く聞こえるため勘違いをしていたけれど、北大路が得意とするのはむしろ高音域だったのだ。
男っぽい歌声を期待していたのに、かなり少年っぽい。でも、甘さの中にかすれた切なさもあって、かなり色気のある声だ。
しかも、しゃくりやビブラートといった歌唱テクニックも駆使して歌うから、かなり聴きごたえがある。
悔しいけれど、認めざるを得ない。こいつはうまい、と。
きっと大したことない、下手であってほしい――そう思っていたから、諸手を挙げて絶賛することはできないけれど。
サナなんてとびきりのタンバリンテクニックとともに声援を送っている。聴衆になれるサナが羨ましい。私だって、歌っているのが北大路でなければ手拍子打って盛り上がりたい。
私の胸は震えていた。この震えを私は知っている。これは、素晴らしいものに出会ったときの震えだ。
とびきり魅力的な新人声優の声を初めて聴いた時のような、ここ数年で一番のヒット作になりそうな予感のするアニメの一話を見たときのような、そんなとびきりの瞬間にだけ感じるドキドキだ。
ドキドキして、目まで潤んでくる。
「どうだ姫川!」
歌い終えて北大路は、息継ぎをするより先に私にそう尋ねた。
「……うまかった」
胸の震えを悟られたくなくて、それだけを私は伝えた。でもそれは事実上の敗北宣言で、私の言葉を聞いた北大路は満面の笑みを浮かべた。まるで子供のような、無邪気な笑顔だ。
「やった! よかった! もし得意な曲《これ》でダメだったら奥の手を使うことになってたからな……」
北大路は嬉しそうに、そしてホッとしたように呟いていた。
「奥の手って、何よ」
「いや……練習もなしにいきなり歌うのは信条に反するんだが、部長さんが『この曲さえ歌えばメーさんを落とせる』という曲を教えてくれたんだ。それで休み時間はずっとそれを聴き込んで備えてたんだ」
「部長に? いつの間に?」
「昼休みだ。尋ねて行ったらわざわざお前の作った曲のことも教えてくれたし、あの人は親切だな」
「あの野郎……」
思わぬところに敵がいたらしい。
でも、部長が人の良さそうな顔で他意も悪意もなくこいつに情報提供している姿を想像すると、あまり怒る気にはなれないけれど。あの人は根っから温厚で、そして親切なのだ。
「それにしても、何であんたは誰かに曲を作ってもらうことにこだわるの?」
私は、ずっと気になっていたことを北大路に尋ねた。
ただ歌いたいだけなら、こうしてカラオケに来て歌えばいい。歌を聴いてほしいのなら、勝手に歌ってネットにでも投稿すればいい。
それなのに、北大路はずっと私に「俺に曲を作らせてやる」と作曲することを要求してきていたのはなぜなのだろう。それが私は不思議だったのだ。軽音部のバンドだって、何もみんながオリジナル曲をやっているわけではないし。
そんな私の問いに、北大路はふふんと不敵に笑った。
「だって、誰かと一緒にやるほうが楽しいだろう? 歌だって、なんだって」
そう言って北大路は笑った。
その言い分は理解できる。私だって、ひとりきりで漫画を読んだり書いたりするよりも、誰かと一緒にワイワイやるほうが楽しいから漫研に入っているのだ。
でも、俺様ナルシストの北大路がそんなことを思っているなんて意外で、何だか癪に障る。
「ねぇ、キンヤくん。部長に教えてもらった曲ってこれ?」
サナがそう言って、タッチパネル式の端末を指差した。そこに表示されていたのは、私が大好きなアニメのキャラクターが劇中で歌った曲だった。
「そうそう、それだ!」
「いや、待って!」
北大路が確認して頷くと、サナは私が止めるのも聞かずにその曲を予約してしまった。
誰も曲を入れていなかったから、その曲はすぐに始まった。
イントロなしで、合図のあとすぐに北大路は歌いはじめる。
私の大好きな曲を。
大好きだけど、ダメなのだ。私はこの曲を聴くと泣いてしまう。劇中、この曲を聴いてヒロインが涙するシーンがあるのだけれど、そのヒロインさながら私は泣く。ボロボロ泣く。何度聴いたって泣く。
元気がないとき、辛いとき、この曲を聴いて勇気をもらう。そして、泣く。
北大路の声は、しっとりとしたこのバラードを歌うのに非常に適した声をしていた。そして、ちょっとだけそのキャラクターを演じる声優さんの声に似ていた。
目を閉じれば、アニメのシーンが頭の中にばっちり浮かぶ。
あることがあって自信をなくしたヒロインに、私の推しキャラがこの歌を歌うのだ。励ますために、自分の思いはヒロインと共にあると伝えるために。それに応えるように、ヒロインも泣きながら歌声を重ねるというロマンティックなシーンなのだ。
こうして思い出すだけでも、涙が出てきてしまう。
「なぁ、姫川……俺に曲を作ってくれるか? 一緒に、音楽活動してくれるか?」
間奏中に、北大路はそんなことを言ってきた。無駄に良い声で、しかもマイクを通して。
悔しいけれど、大好きな歌と北大路の声に泣かされていた私は、もう抵抗する力なんて残っていない。
ジッと見つめるその瞳から逃れたくて、ハンカチで顔を隠して頷くしかできなかった。
これがいつもの俺様だったら、断ってやることもできたのに。
ちょっとしおらしいなんて、反則だ。
「よかったね、キンヤくん」
「ああ。それにしても、何で部長さんも真田も俺のことを“キンヤ”って呼ぶんだ? 俺の名前は涼介なんだけど」
「あだ名だよ。漫研はみんなあだ名で呼ばれるから」
「それはつまり、俺も仲間と認められたってことか?」
「そうだね」
どうやら意気投合したらしいサナと北大路は、友好の印にハイタッチを交わした。何だもう、サナまで取り込まれてしまった。
「姫川、これからよろしくな」
それはそれは嬉しそうに、北大路は私に微笑みかけてくる。
「はいはい」
だから私は素っ気なくそう返事をする。
悔しい。
何だか北大路に負けたみたいな気分だし、何よりも泣かされてしまったことが。
でも、ちょっとだけワクワクしていた。
これまで、ほぼひとりでやってきた音楽活動に、誰かが加わるということが。
作詞をして、メロディを決めて、電子の歌姫たちに歌わせていた。生み出すのも命を吹き込むのも、自分だけで完結する閉じた作業。出来上がったものをサナに聴いてもらうまで、あるいはネットにあげるまで、誰にも共有できない寂しい作業だ。
だから、自分の作った曲に誰かが生身の声を吹き込んでくれるというのは、考えるだけでワクワクしてしまう。それがたとえ、ちょっといけ好かない俺様ナルシストな北大路であったとしても。
これから、どんなことができるのだろうかーーそんなことを考えると、どうしたってワクワクしてしまう。
「誰かと一緒にやるほうが楽しいだろう?」
北大路のことは好きになれないけれど、この気持ちだけは共有できるから。
何にせよ、そのおかげで、休み時間はサナや他の趣味の合う子たちと平和におしゃべりして過ごすことができた。
回し読みしている漫画の続きを貸してもらったり、一緒にハマっているソーシャルゲームでなかなか私が出せないでいるキャラクターを出した子にゲーム内イベントを見せてもらったり。
ちらりと北大路のほうを見れば、昼休みの前半はどこかに行っていたし、戻ってきてからは自分の机でイヤホンをして、熱心に何か音楽を聴いている様子だった。まるで、昨日まで私にしつこく声をかけていたのが嘘みたいだ。
これが私の日常よね――そんなふうに思って胸を撫で下ろしていたのだ。
それなのに……
「姫川、喜べ! 今から俺とカラオケに行くぞ!」
放課後、部活に行くために教室を出ようとしたところで、北大路に足止めされた。
しかも、わけのわからないことを言っている。
「どいてよ。今から部活に行くんだから」
「大丈夫だ。部長さんにはもう二人が部活を休むことの許可を得てる」
「はぁ? いつの間に?」
「てか、あたしも?」
呆れる私とサナに、北大路は「ドヤァ」という顔をしてきた。用意周到だろうと言いたいらしい。
(それにしても何で許可を出してるんだ、部長。しかもこいつもわざわざ三年生の教室に行って話をしてきたのか。その行動力があるなら仲違いしたバンド仲間と仲直りして来いよ。それか別の楽曲提供者を探せ。もしくは自分で作れよ。)
言いたいことはたくさんあったけれど、疲れるのがわかっていたから私はもう何も言わなかった。それを肯定ととったのか、北大路は嬉しそうだ。
「お前の作った曲を探して聴いたんだ! ますますお前に曲を作ってもらいたくなった! お前、なかなかセンスあるな」
「そりゃどうも」
誰だ、情報漏らしたのは。捕まえてとっちめてやりたい――そう思うけれど、八つ当たりかもしれないと気づいてグッと堪えた。
こいつが私につきまとったりしなければ、そんな情報が漏れようが大したことではないのだから。
徹頭徹尾、悪いのはこいつだ。
「それで、姫川も俺の歌を聴けば、きっと俺に曲を作りたくなるだろうって気がついたんだ。嬉しいだろう? ただで俺の歌が聴けるんだから」
北大路は、またおかしなことを言っている。しかもこれを冗談ではなく真顔で言っているのだから質が悪い。他の女子たちなら、こんなことを言われればキャーキャー言って大喜びするのかもしれない。でも、私には二次元の素敵な王子様がいるのだ。そんじょそこらの異性に騒ぐなんて思われているなら心外だ。ムカつく。ムカつきすぎて顔面にパンチしてやりたい。
でも、私は大人だからそんなことはせず、そっと北大路の手に百円玉を握らせた。
「姫川? ……この百円はどういう意味だ?」
「『ただで歌を聴かせてやるから有り難がれ』って言うんだったら、お金あげるから帰ってもらおうと思って」
「なっ……!」
明確な拒絶をしたことでようやく理解できたのか、北大路はショックを受けた顔をしている。まぁ、これまでの人生で女子をカラオケに誘ってこんなふうに嫌がられることなんてきっとなかっただろうから、ショックを受けるのも仕方がない。でも、同情なんてしてやらない。三次元に興味のない人間もいるということを、そろそろしっかり知ったほうがいい。
「サナ、行こう」
「待って、メーちゃん」
私は北大路を放って部室へ向かおうとした。
でも、サナは歩き出した私の手を引いて、またあいつのところへ戻ってしまった。
「今日はせっかくだからキンヤくんとカラオケ行こうよ。キンヤくんも、歌を聴いた上でメーちゃんが断るんだったらあきらめるよね?」
「あ、ああ……それなら仕方ないな」
「よっしゃ! なら行こう!」
最初は何を言い出すのかと思ったけれど、サナの機転に救われた。喜びの雄叫びをついあげてしまったあと、私はこっそりサナに「グッジョブ」と囁いた。日頃からイケメンボイス(声優さんの)は聴き慣れているんだ。そこそこかっこよくてそこそこうまいくらいの歌声を聴かされたって、私の心は絶対に一ミリも動かない自信がある。歌声を聴かせて私の心を動かせないのなら、それが北大路の実力ってやつだ。今度こそしっかり断って、あきらめてもらおう。
何もわかっていないのは北大路だけで、満足そうな顔をして私とサナの後ろに続いていた。
それにしても……
北大路を連れて歩くのはすごく目立つ!
北大路が目立つのはもちろんだけれど、こいつの容姿と私たちの容姿のギャップも原因な気がする。
不良のような着崩し方やアレンジではないけれど、北大路は芋臭くならないよう適度に制服を着崩している。おまけにイケメン。それに長身でスタイルもいいから、制服映えする容姿なのだ。
かたや私とサナは、スカート丈こそ少しだけ気を使って膝が半分ほど見える位置まで上げてはいるものの、いわゆる“女子高生”な出で立ちをしているわけではない。アレンジもしていなければ、余計な付属品も一切つけていない。まあぶっちゃけ、ダサいのは自覚しているのだ。
そんなのがイケメンと並んで歩けば、嫌でも目を引くだろう。
昇降口にたどりつくまでの間だけでも、視線、視線、視線。
見られるって、かなりのストレスだなと感じた。
でも、今日このあとカラオケに行けば、北大路につきまとわれることもなくなる。だから、それまでの我慢だ。
そう思っていたのに……
「う、うまい……」
十八番《おはこ》だという人気バンドのヒット曲を高らかに歌い上げる北大路。
その歌唱力に私は圧倒された。
声質がわりと低く聞こえるため勘違いをしていたけれど、北大路が得意とするのはむしろ高音域だったのだ。
男っぽい歌声を期待していたのに、かなり少年っぽい。でも、甘さの中にかすれた切なさもあって、かなり色気のある声だ。
しかも、しゃくりやビブラートといった歌唱テクニックも駆使して歌うから、かなり聴きごたえがある。
悔しいけれど、認めざるを得ない。こいつはうまい、と。
きっと大したことない、下手であってほしい――そう思っていたから、諸手を挙げて絶賛することはできないけれど。
サナなんてとびきりのタンバリンテクニックとともに声援を送っている。聴衆になれるサナが羨ましい。私だって、歌っているのが北大路でなければ手拍子打って盛り上がりたい。
私の胸は震えていた。この震えを私は知っている。これは、素晴らしいものに出会ったときの震えだ。
とびきり魅力的な新人声優の声を初めて聴いた時のような、ここ数年で一番のヒット作になりそうな予感のするアニメの一話を見たときのような、そんなとびきりの瞬間にだけ感じるドキドキだ。
ドキドキして、目まで潤んでくる。
「どうだ姫川!」
歌い終えて北大路は、息継ぎをするより先に私にそう尋ねた。
「……うまかった」
胸の震えを悟られたくなくて、それだけを私は伝えた。でもそれは事実上の敗北宣言で、私の言葉を聞いた北大路は満面の笑みを浮かべた。まるで子供のような、無邪気な笑顔だ。
「やった! よかった! もし得意な曲《これ》でダメだったら奥の手を使うことになってたからな……」
北大路は嬉しそうに、そしてホッとしたように呟いていた。
「奥の手って、何よ」
「いや……練習もなしにいきなり歌うのは信条に反するんだが、部長さんが『この曲さえ歌えばメーさんを落とせる』という曲を教えてくれたんだ。それで休み時間はずっとそれを聴き込んで備えてたんだ」
「部長に? いつの間に?」
「昼休みだ。尋ねて行ったらわざわざお前の作った曲のことも教えてくれたし、あの人は親切だな」
「あの野郎……」
思わぬところに敵がいたらしい。
でも、部長が人の良さそうな顔で他意も悪意もなくこいつに情報提供している姿を想像すると、あまり怒る気にはなれないけれど。あの人は根っから温厚で、そして親切なのだ。
「それにしても、何であんたは誰かに曲を作ってもらうことにこだわるの?」
私は、ずっと気になっていたことを北大路に尋ねた。
ただ歌いたいだけなら、こうしてカラオケに来て歌えばいい。歌を聴いてほしいのなら、勝手に歌ってネットにでも投稿すればいい。
それなのに、北大路はずっと私に「俺に曲を作らせてやる」と作曲することを要求してきていたのはなぜなのだろう。それが私は不思議だったのだ。軽音部のバンドだって、何もみんながオリジナル曲をやっているわけではないし。
そんな私の問いに、北大路はふふんと不敵に笑った。
「だって、誰かと一緒にやるほうが楽しいだろう? 歌だって、なんだって」
そう言って北大路は笑った。
その言い分は理解できる。私だって、ひとりきりで漫画を読んだり書いたりするよりも、誰かと一緒にワイワイやるほうが楽しいから漫研に入っているのだ。
でも、俺様ナルシストの北大路がそんなことを思っているなんて意外で、何だか癪に障る。
「ねぇ、キンヤくん。部長に教えてもらった曲ってこれ?」
サナがそう言って、タッチパネル式の端末を指差した。そこに表示されていたのは、私が大好きなアニメのキャラクターが劇中で歌った曲だった。
「そうそう、それだ!」
「いや、待って!」
北大路が確認して頷くと、サナは私が止めるのも聞かずにその曲を予約してしまった。
誰も曲を入れていなかったから、その曲はすぐに始まった。
イントロなしで、合図のあとすぐに北大路は歌いはじめる。
私の大好きな曲を。
大好きだけど、ダメなのだ。私はこの曲を聴くと泣いてしまう。劇中、この曲を聴いてヒロインが涙するシーンがあるのだけれど、そのヒロインさながら私は泣く。ボロボロ泣く。何度聴いたって泣く。
元気がないとき、辛いとき、この曲を聴いて勇気をもらう。そして、泣く。
北大路の声は、しっとりとしたこのバラードを歌うのに非常に適した声をしていた。そして、ちょっとだけそのキャラクターを演じる声優さんの声に似ていた。
目を閉じれば、アニメのシーンが頭の中にばっちり浮かぶ。
あることがあって自信をなくしたヒロインに、私の推しキャラがこの歌を歌うのだ。励ますために、自分の思いはヒロインと共にあると伝えるために。それに応えるように、ヒロインも泣きながら歌声を重ねるというロマンティックなシーンなのだ。
こうして思い出すだけでも、涙が出てきてしまう。
「なぁ、姫川……俺に曲を作ってくれるか? 一緒に、音楽活動してくれるか?」
間奏中に、北大路はそんなことを言ってきた。無駄に良い声で、しかもマイクを通して。
悔しいけれど、大好きな歌と北大路の声に泣かされていた私は、もう抵抗する力なんて残っていない。
ジッと見つめるその瞳から逃れたくて、ハンカチで顔を隠して頷くしかできなかった。
これがいつもの俺様だったら、断ってやることもできたのに。
ちょっとしおらしいなんて、反則だ。
「よかったね、キンヤくん」
「ああ。それにしても、何で部長さんも真田も俺のことを“キンヤ”って呼ぶんだ? 俺の名前は涼介なんだけど」
「あだ名だよ。漫研はみんなあだ名で呼ばれるから」
「それはつまり、俺も仲間と認められたってことか?」
「そうだね」
どうやら意気投合したらしいサナと北大路は、友好の印にハイタッチを交わした。何だもう、サナまで取り込まれてしまった。
「姫川、これからよろしくな」
それはそれは嬉しそうに、北大路は私に微笑みかけてくる。
「はいはい」
だから私は素っ気なくそう返事をする。
悔しい。
何だか北大路に負けたみたいな気分だし、何よりも泣かされてしまったことが。
でも、ちょっとだけワクワクしていた。
これまで、ほぼひとりでやってきた音楽活動に、誰かが加わるということが。
作詞をして、メロディを決めて、電子の歌姫たちに歌わせていた。生み出すのも命を吹き込むのも、自分だけで完結する閉じた作業。出来上がったものをサナに聴いてもらうまで、あるいはネットにあげるまで、誰にも共有できない寂しい作業だ。
だから、自分の作った曲に誰かが生身の声を吹き込んでくれるというのは、考えるだけでワクワクしてしまう。それがたとえ、ちょっといけ好かない俺様ナルシストな北大路であったとしても。
これから、どんなことができるのだろうかーーそんなことを考えると、どうしたってワクワクしてしまう。
「誰かと一緒にやるほうが楽しいだろう?」
北大路のことは好きになれないけれど、この気持ちだけは共有できるから。