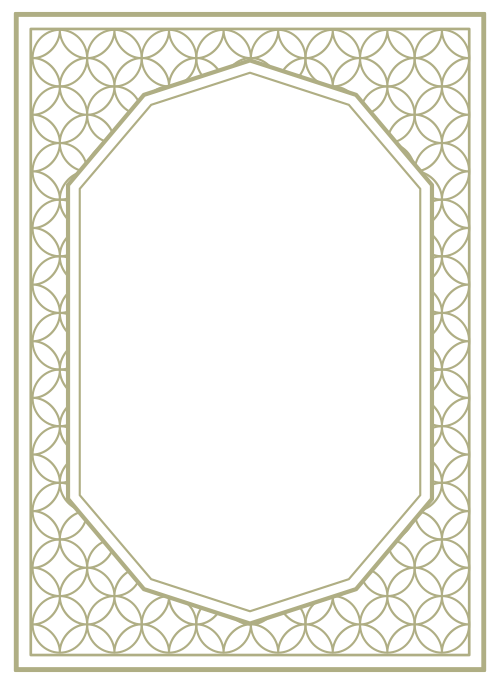にぎやかな人混みの中を、私は顔を熱くして歩いていた。
隣には北大路。いろんな意味で恥ずかしくて、顔から火が出てしまいそうだ。
あれから、北大路は平然と他二曲を歌いあげ、ステージ裏から客席にやってきた。公開告白なんて大胆なことをした人物のおでましだ。まるで海が割れるかのごとく人波が割れ、颯爽と私の前に現れやがった。
それから「姫川を借りていくぞ」などと申し出、逃すまいと両脇をガードしていたサナと本田さんに私は「どうぞどうぞ」とされてしまったのだ。そして逃走防止のためかガッチリ手を握られ、そのまま体育館の外に連れ出されてしまった。
「一緒に出店を回ろう。その前に、何か飲むか」
「う、うん」
異性と手をつないだのなんて、たぶん幼稚園のお遊戯会以来だ。だから、私は緊張してパニックになって、半分以上わけがわからなくなっている。
「自販機でいいか。たしか、飲み物は喫茶系の店をやってるクラスまで行かなきゃならないからな」
「うん」
ポケットから文化祭のプログラムを取り出して見ながら、北大路はピロティのほうに歩いていく。さすが俺様。エスコートもばっちりだ。そんなことより、身長差的にエスコートされているというより、連行される宇宙人のように見えていないかが心配だ。
「姫川は何が飲みたい?」
「え、えっと、冷たいの……リンゴジュース」
「わかった」
北大路は私をベンチに座らせると、自販機のほうに行ってしまった。空いていてよかった、座れるし人目がなくてよかった……なんてことを思っていたけれど、そんな場合じゃなかった。これじゃまるで、買いに行かせるのが当たり前みたいな態度だ。
「ご、ごめん! お金、払う」
「いいよ、別に。そんなことより、飲んで落ち着いてくれ」
「うん、ありがと……」
戻ってきた北大路に慌ててお金を渡そうとすると、グイグイとジュースを押しつけられて再び椅子に座らされてしまった。仕方なく紙パックにストローを刺し、喉を潤す。
隣に座る北大路をチラッと見ると、冷たいココアを飲んでいた。推しキャラがココアを飲んでいると錯覚しそうになる。でも、彼はコーヒー党だった。だから、やっぱり目の前にいるのは北大路だ。
「何か、適当に買ってくるから待っててくれ」
「う、うん」
喉が渇いていたのか、北大路はあっという間にココアを飲み干した。落ち着かない様子で、せかせか歩いていってしまった。
正直、私も気持ちの整理ができていなくて混乱していたから、ひとりになってホッとする。
信じられないことばかり起きている。現実じゃないみたいだ。
まず、公開告白だなんて漫画やアニメみたいなことが自分の身に起きたということが信じられない。現実にそんなことがあるとしても、そんなの一部のリア充のすることだと思っていた。でも、告白されたのはまさかのオタク女子だ。地味系陰キャラ代表だ。
しかも、相手はあの北大路。俺様ナルシストとはいえ、女子の多くが憧れるイケメンだ。仲良くなった自覚はあったけれど、一体いつ、何で私のことを好きになったというのだろう……やっぱり、これは壮大な夢なのかも。
「……いてて」
夢か現実か確かめるために、ベタだけど頬をつねってみた。痛かった。どうやら、これは現実らしい。
「ねえねえ、何してんのー?」
「コスプレじゃん。ナントカカントカってアニメの」
「ギャハハ。ナントカカントカじゃわかんねーよ」
ひとりで照れたり痛がったりしているうちに、いつの間にか周りを取り囲まれていた。他校の制服を着た、あきらかにウェイウェイしてる系の男子たちに。
「ぼっちなん?」
「オレたちと一緒に回ろうよ。てか、案内してよー」
「オレら怖くないよ? めっちゃイイヤツだってー」
何も言わない私に、ウェイたちはどんどん話しかけてくる。別に怯えているわけじゃないのに。ただ返す言葉に困っているだけだ。オタクを舐めるな。このコミュ力モンスターめ。
内心でそんな悪態をつきながら、私はハタと気がついた。文化祭で他校の男子や大学生に絡まれるというこのシチュエーション――めっちゃ少女漫画とかであるやつだ、と。
それなら、あとの展開もきっとお決まりなパターンだ。私はヒロイン属性足りていないけれど、見た目やスペック的にはバッチリヒーローなあいつなら、見事この状況を打破してくれるはずだ。
そんなことを考えていたら、北大路が食べ物を手に戻ってきた。ウェイたちの背後から現れた姿は、キラキラのエフェクトがかかって見える。
セオリー通りなら、「そいつ、俺の彼女だから」とか「俺の女に何か用?」なんてセリフでモブを追い払ってくれるはず――。
そう思っていたのに、北大路は手を振ってにこやかに現れた。
「うちのクラスの出し物に興味がありますか? 二年五組の、コスプレ写真館です」
イケメンスマイルを浮かべた北大路は、なぜかそう言ってクラスの出し物の宣伝をした。好戦的にナルシストらしく、上から目線に対応するかと思ったのに、かなり紳士的だ。
でも、元々イケメンな上に完璧なコスプレをしていてオーラ倍増中の北大路は、それでも謎の威圧感を放っていた。
「そ、そうッスか。行ってみまーす」
そう言って、ウェイたちはそそくさと退散した。力量差をきちんとわかる人たちでよかった。といっても、それは顔面偏差値の話で、向こうが喧嘩っ早かったらどうなっていたかわからない。「色男、金と力はなかれけり」と昔から言われているくらいだし。
「あ、あの……助けてくれてありがと」
「ひとりにさせて悪かったな。さ、食べよう」
恩に着せるわけでもなくさらりと流して、北大路はアメリカンドックと紙カップに入ったフライドポテトを差し出してきた。手に提げているビニール袋の中には、たこ焼きも入っている。
お腹が空いていたから、私はそれを素直に受け取った。ひと口かじったアメリカンドックはちょっとしんなりしていたけれど、まずくはなかった。
「あとで教室に帰って、俺たちも写真を撮ろうか。その、せっかくおそろいみたいな格好してるわけだし」
フライドポテトをもそもそと食べながら、北大路はそう提案する。言われて、私はコスプレをしていたことを思い出した。めちゃくちゃヒロインぶってた。だから、さっきみたいな少女漫画イベントが発生してしまったわけか。
「……は、恥ずかしいから、いい」
「そっか。まあ、俺も今の姫川をたくさんの人の目に触れさせたいわけじゃないからいいけどな」
「…………」
ただでさえ恥ずかしいのに、北大路はさらに私を追いつめるようなことを言う。殺す気か。今なら簡単に死ねそうな気がする。死因・羞恥、だ。
「でも、やっぱり写真は撮りたい。スマホでなら、撮ってもいいか?」
「え、う……いいけど」
キラッキラの笑顔で尋ねられると、頷かざるを得なかった。今は北大路が大好きな彼のコスプレをしているというのも問題だ。まるで彼に話しかけられているような気がしてしまう。
「じゃあ、撮るぞ」
北大路はスマホを構え、インカメラで私とのツーショットを撮った。画面の中に収まるには顔を寄せ合わなきゃならなくて、私の顔はさらに赤くなってしまう。
さすがナルシスト。自撮りには慣れているのか、角度を変え、手早く何枚か撮っていく。ニッコリ笑顔を浮かべると北大路と違い、私の表情は硬かった。画面の中には、やたらと愛想のいい推しキャラと無表情で顔を真っ赤にしているヒロインもどきがいる。
「姫川、可愛いな」
今しがた撮ったばかりの写真を確認して、北大路はさらりとそんなことを言う。「な?」なんて笑顔でこちらに画面を見せてくるのも、すごくズルい。
でも、北大路の横でカチコチになっている私は、いつも鏡の中で見る私とは違って、たしかにちょっと可愛かった。
「……ねえ、いつもちゃんとお化粧ってしてたほうがいい?」
「え?」
ふと疑問に思ったことを尋ねると、北大路はびっくりしたように目を見開いた。それから、じんわりと喜びがにじんでいくように笑顔になっていった。
「いや、メイクなしの姫川が好きだ。もちろん、今みたいにしてるのも好きだけど」
「……っ」
恥ずかしげもなくそんなセリフを口にされて、私はもう口をパクパクさせるしかなかった。北大路が赤くなる私を楽しげに見ているのが、無性に腹が立つ。
改めて「好きだ」と言われ、さっきの体育館での告白が夢でも聞き間違いでもないことを思い知らされた。ということは、私はその告白に、きちんと答えなければならないということだろう。
答えるって、どうしたらいいんだろう。これまでもこれからも、まさか自分の人生に告白イベントなんてものが起こるなんて思ってもみなかったから、こんなときどうしたらいいかわからない。
……乙女ゲームでなら、いくらでも経験したことがあるのに。二人の攻略キャラの好感度を同時進行で上げて、三角関係イベントに持ち込んだこともある。でも、いくらゲームの中で「私のためにケンカはやめてー!」なんて展開を経験しても、それは現実ではまったく何の役にも立たない。
「あのさ、北大路……さっきの、話なんだけど」
気の利いた切り出し方がわからなくて、そんな身も蓋もない言い方になってしまう。でも、北大路を見ると、すべてを受け止めるような笑顔を浮かべていた。
「俺は、姫川がこの人のことを好きだってことは、ちゃんとわかってるつもりだ」
北大路は、“この人”と言って自分のことを指差した。つまり、今コスプレをしている、例の彼のことを言っているのだろう。
「彼への想いが、生半可なものじゃないってこともわかってる。世界で一番好きだってことも……だから、二番でいい。……いや、三次元の中で一番、俺のことを好きになってほしいんだ!」
北大路は、ステージに立っていたときと同じくらい……あの時以上に真剣な様子で、改めて告白してきた。
よく見ると頬が少し赤いし、手も小刻みに震えている。北大路も緊張しているのだ、怖いのだということがわかると、恥ずかしがってばかりもいられないと気づいた。
俺様ナルシストでも、やっぱり告白は怖いのだ。
そんな当たり前のことがわかると、北大路のことが好きだという気持ちがジワジワと湧いてきて、胸がギューッと苦しくなる。
「彼のことは、もちろん大好きだよ。でも、一番じゃなくて殿堂入りしてるから……」
北大路の気持ちに答えようと話し始めたのに、自分でもよくわからなくなってきた。当然、北大路にも伝わっていなくて、やつは喜ぶべきなのか落ち込むべきなのかわからないという顔をしている。
「それは、つまり……?」
「つまり、今は世界で一番の座は空席だから……」
「俺のことが世界一好きってことか!?」
ガタッと立ち上がって、北大路は叫ぶ。そんなふうにはっきり言われると恥ずかしい。でも、間違いじゃないから、コクコクと頷くしかない。
「やった! 姫川も俺のことが好きだって! やったー!」
「や、やめて! 大きい声出すな! 恥ずかしい……」
「いいじゃないか!」
赤面する私をよそに、北大路ははしゃぎまくる。喜びのあまり、背中に羽が生えて飛んでいってしまいそうなほどだ。あとで戻ってきてくれていいから、私が落ち着くまで一旦どこかに飛んでいってくれないだろうか。
「なあ、俺のこと好きなら、姫川の部屋に俺の祭壇を作ってくれるか?」
はしゃぎまくる北大路は、調子に乗ってそんなことまで聞いてくる。
祭壇といえば、グッズを飾るということだ。写真にポスターに添い寝シーツ……そこまで考えて恥ずかしくて死んでしまいそうになった。
「……そんなの、ダメ。絶対に」
「何でだ?」
「……眠れなくなるでしょうが」
「……!」
今度は、北大路が悶絶する番だった。その反応を見て気がついたけれど、今の発言はまずかった。デレだ。無自覚にデレてしまった。
「ひ、姫川……今のは反則だろ……デレのインフレだ」
「は? ちょっと何言ってんのかわかんない」
「そんなふうにツンツンしても、逆効果だからな」
「ツンじゃないし」
何を言っても北大路は嬉しそうだ。ニヤニヤしている。ムカつくけれど、自分の発言で誰かが――好きな人が嬉しそうにしてくれるというのは、嫌な感じではない。
「姫川は、ツンツンしててもデレても、可愛いな」
「なっ……!」
北大路は私の手に自分の手を重ね、耳元でそっとそんなことを囁いた。いつもより、ちょっと低めの声で。これが噂の耳つぶか……!
そんなことをされてしまったから、私の心臓はありえないほど速く鼓動を刻み始めた。
でも、そうやって手を重ねられていると、北大路の鼓動も感じられる。やつの鼓動も、私に負けず劣らず速いテンポだ。
(これが、恋のビートってやつか……!)
軽くパニックに陥った私の頭に、ふいにそんなくだらないセリフがよぎる。くだらない。ものすごくダサい。
それなのに、頭から離れなくなってしまった。
「……何か、いい曲作れそうな気がしてきた」
「姫川もか。俺もだ。いい詞が書けそうだ」
照れながらの私の言葉に、北大路は真面目に返す。そのせいで恥ずかしさが倍増したから、私はやつの肩にポスンと頭をもたれさせてやった。
〈end〉
隣には北大路。いろんな意味で恥ずかしくて、顔から火が出てしまいそうだ。
あれから、北大路は平然と他二曲を歌いあげ、ステージ裏から客席にやってきた。公開告白なんて大胆なことをした人物のおでましだ。まるで海が割れるかのごとく人波が割れ、颯爽と私の前に現れやがった。
それから「姫川を借りていくぞ」などと申し出、逃すまいと両脇をガードしていたサナと本田さんに私は「どうぞどうぞ」とされてしまったのだ。そして逃走防止のためかガッチリ手を握られ、そのまま体育館の外に連れ出されてしまった。
「一緒に出店を回ろう。その前に、何か飲むか」
「う、うん」
異性と手をつないだのなんて、たぶん幼稚園のお遊戯会以来だ。だから、私は緊張してパニックになって、半分以上わけがわからなくなっている。
「自販機でいいか。たしか、飲み物は喫茶系の店をやってるクラスまで行かなきゃならないからな」
「うん」
ポケットから文化祭のプログラムを取り出して見ながら、北大路はピロティのほうに歩いていく。さすが俺様。エスコートもばっちりだ。そんなことより、身長差的にエスコートされているというより、連行される宇宙人のように見えていないかが心配だ。
「姫川は何が飲みたい?」
「え、えっと、冷たいの……リンゴジュース」
「わかった」
北大路は私をベンチに座らせると、自販機のほうに行ってしまった。空いていてよかった、座れるし人目がなくてよかった……なんてことを思っていたけれど、そんな場合じゃなかった。これじゃまるで、買いに行かせるのが当たり前みたいな態度だ。
「ご、ごめん! お金、払う」
「いいよ、別に。そんなことより、飲んで落ち着いてくれ」
「うん、ありがと……」
戻ってきた北大路に慌ててお金を渡そうとすると、グイグイとジュースを押しつけられて再び椅子に座らされてしまった。仕方なく紙パックにストローを刺し、喉を潤す。
隣に座る北大路をチラッと見ると、冷たいココアを飲んでいた。推しキャラがココアを飲んでいると錯覚しそうになる。でも、彼はコーヒー党だった。だから、やっぱり目の前にいるのは北大路だ。
「何か、適当に買ってくるから待っててくれ」
「う、うん」
喉が渇いていたのか、北大路はあっという間にココアを飲み干した。落ち着かない様子で、せかせか歩いていってしまった。
正直、私も気持ちの整理ができていなくて混乱していたから、ひとりになってホッとする。
信じられないことばかり起きている。現実じゃないみたいだ。
まず、公開告白だなんて漫画やアニメみたいなことが自分の身に起きたということが信じられない。現実にそんなことがあるとしても、そんなの一部のリア充のすることだと思っていた。でも、告白されたのはまさかのオタク女子だ。地味系陰キャラ代表だ。
しかも、相手はあの北大路。俺様ナルシストとはいえ、女子の多くが憧れるイケメンだ。仲良くなった自覚はあったけれど、一体いつ、何で私のことを好きになったというのだろう……やっぱり、これは壮大な夢なのかも。
「……いてて」
夢か現実か確かめるために、ベタだけど頬をつねってみた。痛かった。どうやら、これは現実らしい。
「ねえねえ、何してんのー?」
「コスプレじゃん。ナントカカントカってアニメの」
「ギャハハ。ナントカカントカじゃわかんねーよ」
ひとりで照れたり痛がったりしているうちに、いつの間にか周りを取り囲まれていた。他校の制服を着た、あきらかにウェイウェイしてる系の男子たちに。
「ぼっちなん?」
「オレたちと一緒に回ろうよ。てか、案内してよー」
「オレら怖くないよ? めっちゃイイヤツだってー」
何も言わない私に、ウェイたちはどんどん話しかけてくる。別に怯えているわけじゃないのに。ただ返す言葉に困っているだけだ。オタクを舐めるな。このコミュ力モンスターめ。
内心でそんな悪態をつきながら、私はハタと気がついた。文化祭で他校の男子や大学生に絡まれるというこのシチュエーション――めっちゃ少女漫画とかであるやつだ、と。
それなら、あとの展開もきっとお決まりなパターンだ。私はヒロイン属性足りていないけれど、見た目やスペック的にはバッチリヒーローなあいつなら、見事この状況を打破してくれるはずだ。
そんなことを考えていたら、北大路が食べ物を手に戻ってきた。ウェイたちの背後から現れた姿は、キラキラのエフェクトがかかって見える。
セオリー通りなら、「そいつ、俺の彼女だから」とか「俺の女に何か用?」なんてセリフでモブを追い払ってくれるはず――。
そう思っていたのに、北大路は手を振ってにこやかに現れた。
「うちのクラスの出し物に興味がありますか? 二年五組の、コスプレ写真館です」
イケメンスマイルを浮かべた北大路は、なぜかそう言ってクラスの出し物の宣伝をした。好戦的にナルシストらしく、上から目線に対応するかと思ったのに、かなり紳士的だ。
でも、元々イケメンな上に完璧なコスプレをしていてオーラ倍増中の北大路は、それでも謎の威圧感を放っていた。
「そ、そうッスか。行ってみまーす」
そう言って、ウェイたちはそそくさと退散した。力量差をきちんとわかる人たちでよかった。といっても、それは顔面偏差値の話で、向こうが喧嘩っ早かったらどうなっていたかわからない。「色男、金と力はなかれけり」と昔から言われているくらいだし。
「あ、あの……助けてくれてありがと」
「ひとりにさせて悪かったな。さ、食べよう」
恩に着せるわけでもなくさらりと流して、北大路はアメリカンドックと紙カップに入ったフライドポテトを差し出してきた。手に提げているビニール袋の中には、たこ焼きも入っている。
お腹が空いていたから、私はそれを素直に受け取った。ひと口かじったアメリカンドックはちょっとしんなりしていたけれど、まずくはなかった。
「あとで教室に帰って、俺たちも写真を撮ろうか。その、せっかくおそろいみたいな格好してるわけだし」
フライドポテトをもそもそと食べながら、北大路はそう提案する。言われて、私はコスプレをしていたことを思い出した。めちゃくちゃヒロインぶってた。だから、さっきみたいな少女漫画イベントが発生してしまったわけか。
「……は、恥ずかしいから、いい」
「そっか。まあ、俺も今の姫川をたくさんの人の目に触れさせたいわけじゃないからいいけどな」
「…………」
ただでさえ恥ずかしいのに、北大路はさらに私を追いつめるようなことを言う。殺す気か。今なら簡単に死ねそうな気がする。死因・羞恥、だ。
「でも、やっぱり写真は撮りたい。スマホでなら、撮ってもいいか?」
「え、う……いいけど」
キラッキラの笑顔で尋ねられると、頷かざるを得なかった。今は北大路が大好きな彼のコスプレをしているというのも問題だ。まるで彼に話しかけられているような気がしてしまう。
「じゃあ、撮るぞ」
北大路はスマホを構え、インカメラで私とのツーショットを撮った。画面の中に収まるには顔を寄せ合わなきゃならなくて、私の顔はさらに赤くなってしまう。
さすがナルシスト。自撮りには慣れているのか、角度を変え、手早く何枚か撮っていく。ニッコリ笑顔を浮かべると北大路と違い、私の表情は硬かった。画面の中には、やたらと愛想のいい推しキャラと無表情で顔を真っ赤にしているヒロインもどきがいる。
「姫川、可愛いな」
今しがた撮ったばかりの写真を確認して、北大路はさらりとそんなことを言う。「な?」なんて笑顔でこちらに画面を見せてくるのも、すごくズルい。
でも、北大路の横でカチコチになっている私は、いつも鏡の中で見る私とは違って、たしかにちょっと可愛かった。
「……ねえ、いつもちゃんとお化粧ってしてたほうがいい?」
「え?」
ふと疑問に思ったことを尋ねると、北大路はびっくりしたように目を見開いた。それから、じんわりと喜びがにじんでいくように笑顔になっていった。
「いや、メイクなしの姫川が好きだ。もちろん、今みたいにしてるのも好きだけど」
「……っ」
恥ずかしげもなくそんなセリフを口にされて、私はもう口をパクパクさせるしかなかった。北大路が赤くなる私を楽しげに見ているのが、無性に腹が立つ。
改めて「好きだ」と言われ、さっきの体育館での告白が夢でも聞き間違いでもないことを思い知らされた。ということは、私はその告白に、きちんと答えなければならないということだろう。
答えるって、どうしたらいいんだろう。これまでもこれからも、まさか自分の人生に告白イベントなんてものが起こるなんて思ってもみなかったから、こんなときどうしたらいいかわからない。
……乙女ゲームでなら、いくらでも経験したことがあるのに。二人の攻略キャラの好感度を同時進行で上げて、三角関係イベントに持ち込んだこともある。でも、いくらゲームの中で「私のためにケンカはやめてー!」なんて展開を経験しても、それは現実ではまったく何の役にも立たない。
「あのさ、北大路……さっきの、話なんだけど」
気の利いた切り出し方がわからなくて、そんな身も蓋もない言い方になってしまう。でも、北大路を見ると、すべてを受け止めるような笑顔を浮かべていた。
「俺は、姫川がこの人のことを好きだってことは、ちゃんとわかってるつもりだ」
北大路は、“この人”と言って自分のことを指差した。つまり、今コスプレをしている、例の彼のことを言っているのだろう。
「彼への想いが、生半可なものじゃないってこともわかってる。世界で一番好きだってことも……だから、二番でいい。……いや、三次元の中で一番、俺のことを好きになってほしいんだ!」
北大路は、ステージに立っていたときと同じくらい……あの時以上に真剣な様子で、改めて告白してきた。
よく見ると頬が少し赤いし、手も小刻みに震えている。北大路も緊張しているのだ、怖いのだということがわかると、恥ずかしがってばかりもいられないと気づいた。
俺様ナルシストでも、やっぱり告白は怖いのだ。
そんな当たり前のことがわかると、北大路のことが好きだという気持ちがジワジワと湧いてきて、胸がギューッと苦しくなる。
「彼のことは、もちろん大好きだよ。でも、一番じゃなくて殿堂入りしてるから……」
北大路の気持ちに答えようと話し始めたのに、自分でもよくわからなくなってきた。当然、北大路にも伝わっていなくて、やつは喜ぶべきなのか落ち込むべきなのかわからないという顔をしている。
「それは、つまり……?」
「つまり、今は世界で一番の座は空席だから……」
「俺のことが世界一好きってことか!?」
ガタッと立ち上がって、北大路は叫ぶ。そんなふうにはっきり言われると恥ずかしい。でも、間違いじゃないから、コクコクと頷くしかない。
「やった! 姫川も俺のことが好きだって! やったー!」
「や、やめて! 大きい声出すな! 恥ずかしい……」
「いいじゃないか!」
赤面する私をよそに、北大路ははしゃぎまくる。喜びのあまり、背中に羽が生えて飛んでいってしまいそうなほどだ。あとで戻ってきてくれていいから、私が落ち着くまで一旦どこかに飛んでいってくれないだろうか。
「なあ、俺のこと好きなら、姫川の部屋に俺の祭壇を作ってくれるか?」
はしゃぎまくる北大路は、調子に乗ってそんなことまで聞いてくる。
祭壇といえば、グッズを飾るということだ。写真にポスターに添い寝シーツ……そこまで考えて恥ずかしくて死んでしまいそうになった。
「……そんなの、ダメ。絶対に」
「何でだ?」
「……眠れなくなるでしょうが」
「……!」
今度は、北大路が悶絶する番だった。その反応を見て気がついたけれど、今の発言はまずかった。デレだ。無自覚にデレてしまった。
「ひ、姫川……今のは反則だろ……デレのインフレだ」
「は? ちょっと何言ってんのかわかんない」
「そんなふうにツンツンしても、逆効果だからな」
「ツンじゃないし」
何を言っても北大路は嬉しそうだ。ニヤニヤしている。ムカつくけれど、自分の発言で誰かが――好きな人が嬉しそうにしてくれるというのは、嫌な感じではない。
「姫川は、ツンツンしててもデレても、可愛いな」
「なっ……!」
北大路は私の手に自分の手を重ね、耳元でそっとそんなことを囁いた。いつもより、ちょっと低めの声で。これが噂の耳つぶか……!
そんなことをされてしまったから、私の心臓はありえないほど速く鼓動を刻み始めた。
でも、そうやって手を重ねられていると、北大路の鼓動も感じられる。やつの鼓動も、私に負けず劣らず速いテンポだ。
(これが、恋のビートってやつか……!)
軽くパニックに陥った私の頭に、ふいにそんなくだらないセリフがよぎる。くだらない。ものすごくダサい。
それなのに、頭から離れなくなってしまった。
「……何か、いい曲作れそうな気がしてきた」
「姫川もか。俺もだ。いい詞が書けそうだ」
照れながらの私の言葉に、北大路は真面目に返す。そのせいで恥ずかしさが倍増したから、私はやつの肩にポスンと頭をもたれさせてやった。
〈end〉