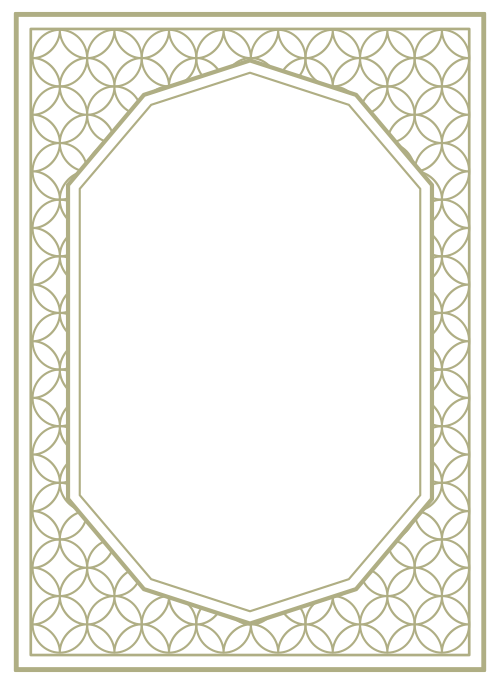いろいろあって、週末。
せっかくの休みだっていうのに気持ちが晴れなくて、ボーッと机に向かっていた。パソコンで大好きなアニメを流しているけれど、全く頭に入ってこない。元気にもならない。
あれ? 私、オタクだったよね?って気分になる。別にオタクであることにアイデンティティを見出しているわけではないけれど。
原因はわかっていた。
ものすごい自己嫌悪に苛まれているからだ。
昨日、部室に戻ってから顛末を聞かせたサナにも、「それはメーちゃんが悪いよ」と言われた。隠していようと思っていたのに、カバンを取りに戻ったら結局様子がおかしいのがバレてすべて話すことになってしまったのだ。
「キンヤくんは何も悪いことしてないじゃない」
そう言われて、私は自分が北大路に八つ当たりしてしまったのだと気がついた。
北大路が私に話しかけるから白川にあんなことを言われてしまった……なんて思ったけれど、別に北大路が悪いわけではない。
傷つけられた気持ちを、そのとき当たりやすかった北大路にぶつけただけだった。そんなの、北大路と話したいのに話しかけられない苛立ちを私にぶつけた白川と同じだ。めちゃくちゃダサいし、卑怯だ。
そのことに気がついたら、ギュッと胸の奥が重くなって苦しくなった。
大抵のことは一晩寝れば忘れてしまう質なのに、今朝は全く気持ちが晴れなかった。
白川たちの物理的な嫌がらせは未然に防ぐことができたし、釘を刺すことができたからこれ以上悪化はしないと思う。恵麻ちゃんや葉月に迷惑もかからないはず。それは、サナも安心していいと言ってくれた。
でも、北大路のことを考えると気が重い。
嫌いだったかもしれないけれど、あんなことを言って傷つけていい理由にはならない。
でも……嫌いだったというのも自分の中でよくわからなくなってしまっていた。
もう部室にいるのも気にならないし、一緒に曲作りだってした。それなのに、よく知る前と同じように嫌いだと言い切ってしまえるのだろうか。
「何で、メーちゃんはあんなにキンヤくんのこと嫌うの?」
昨日の帰り道、サナにそう尋ねられて、私は北大路を、というより地味の対極にあるような人種を嫌う理由を話した。
でも、全部話し終わったあとサナに「それもキンヤくんには関係ない事情じゃない」と言われてしまったし、話しながら自分でも感じていた。
要するに私は、北大路本人に理由がないことであいつを嫌い、北大路に関係のないことで八つ当たりをしてしまったのだ。
「……サイテー」
自分ひとりの部屋にその声は無駄に響いて、ズキンと胸に突き刺さった。
私は一体、何と戦っていたんだろう。
地味なことにコンプレックスなんてないし、オタクであることも別に恥じてなんていない。モブで上等だと思って生きている。
――自分たちを中心に世の中がまわっていると思っている連中に、踏みにじられさえしなければ。
でも、踏みにじられることを恐れて、攻撃的になりすぎていたのかもしれない。
今回の白川たちみたいに実際に攻撃されたのなら噛み付けばいいだけで、何もさせる前からひどい態度をとっていたのは良くなかった。
北大路の悪いところと言えば……俺様なところだけだ。あの俺様な態度が反射的にひどい態度をとらせていたと言えなくもないけれど。
月曜、学校で謝らなくちゃ。こういうのはメールじゃダメだから――そう思って不貞寝を決め込もうとしたとき、インターフォンが鳴らされた。
誰だ。土曜の昼間にピンポン鳴らすのはセールスか宗教の勧誘か。でも、町内会とかだったら困る。
お父さんもお母さんも土曜でも仕事に行っているし、兄ちゃんもバイトだ。出られるのは私しかいない。
しかも、かなり鳴らし続けている。
とりあえず、モニターで誰が来ているのかだけでも確認しよう。
「……おい、ヘアセットなら自分の鏡を見てやれよ」
急いでリビングに降りてモニターを覗いて、私は自分のこめかみに青筋が立つのを感じていた。タイムリーな人物ではあるけれど、やっぱりこうして見ると、そのナルシストな仕草がいちいい癇に障る。
「あのさ、ナルシストの押し売りならお断りなんで帰ってもらえますかー?」
「姫川ー!」
手櫛でしきりに前髪を整え続けながらインターフォンをピンポンピンポン鳴らす北大路にそう言ってやると、やつは嬉しそうにブンブンと手を振ってきた。何なんだ。家なんて教えるんじゃなかった。
「どうしたの? あがる?」
玄関のドアを開けると、北大路が背筋をしゃんとして待っていた。
「いや、一人で留守番中のところに上がり込むなんていう不誠実なことはしない」
何でそこ顔赤らめるの。不誠実なことってあんた、何するの。
「一人って何で知ってるの?」
「真田に聞いた。というより真田に、『土日は大抵留守番だから遊びに行っても大丈夫だよ』って教えてもらったから」
「あの子……」
「学校では話しかけるなって言われたから、こうして来てみたんだ。今からちょっと話せるか?」
「……うん」
私は返事をして、一歩外に出ようとして気がついた。この服装はいかん!
「ちょっと待ってて!」
玄関は暗いしドアは半分くらいしか開けてなかったから、たぶんあまり見えてなかったとは思うけれど、着古したスウェット地のワンピースに足元はつっかけだった!
これでそのまま外に出て、しかも北大路みたいな美形の横を歩くなんて、市中引き回しの刑にも等しいじゃないか! どんな羞恥プレイだ。
といっても、こんなときにサッと着られるような服を持ち合わせてはいないのが困りものだ。
オタク趣味ばかりにお金を注ぎ込んできたツケがこんなところでまわってくるなんて……。
仕方なく、サナと一緒に買いに行った一張羅を着ることにした。
「ごめん、お待たせ。さっきの格好はあまりに部屋着だったから着替えてきた」
急いで玄関に戻ると、北大路は別段気分を害した様子もなく待っていてくれた。私のみっともない言い訳を聞いても、別に笑ったりしなかった
でも、しげしげと眺められて落ち着かない。
「姫川の私服、いいな」
しばらく眺めて、そう簡潔に感想を述べた。まさかそんなコメントをされるとは思っていなかったから、瞬時に顔が赤くなる。
「馬子にも衣装だって言いたいの?」
「違う。本当によく似合ってる。それに髪もそうして下ろしていたほうがいい」
「……ありがとう」
真正面から褒められるとやっぱり照れてしまう。でも、初めてこだわって買った洋服だったから似合っていると言われて嬉しかった。
これは、サナと二人で「大好きな“彼”とデートに行くなら」をテーマに選んだ服。“彼”はもちろん二次元で、恥を忍んで店員さんに相談してコーディネートしてもらったのだ。店員さんはオタクに理解があるお姉さんで(というよりお姉さん自身もオタクだと言っていた)、何のキャラか話すとノリノリで彼のテーマカラーでトータルコーディネートを考えてくれた。オタ的にも女子的にも、非常にレベルの高いワードローブになった。
この前の同人イベントでサナと仲良く着たきり、それ以来着る機会がなかったから、今日こうして着ることができてよかった。
……北大路と歩くには、ちょっと気合が入りすぎている気がするけれど。
「このへん何もないけど、ぶらぶらする?」
「そうだな。じゃあ適当に案内してくれ」
「うん」
何のことを話題にしようとしているかは明白なのに、ぎこちなくて仕方がない。というより、言わなくてはいけないことがあるのは私なのにこうして北大路に訪ねて来させてしまったのだから、私から口を開くべきだ。
そう思っていたのに、先に言葉を発したのも北大路だった。
「姫川……すまなかった」
「え?」
「俺の配慮が足りず、嫌な思いをさせてしまって。俺も馬鹿じゃないから、女子の悪質さとかわかっていたつもりだったんだけど……俺が話しかけたところで姫川が嫌そうにしているのは誰が見てもわかるだろうと思っていたんだ」
「私こそ、あの人たちに嫌なこと言われたからって北大路に八つ当たりみたいなことして、ごめん……」
「また学校で話しかけていいなら、いいさ。本気で嫌なら、無理にとは言わないけどな」
俺様な発言がひとつもなくて、しかも素直に謝られてしまって、調子が狂いそうになる。
こういうとき、イケメンは狡い。何か、ものすごく悪いことをした気分にさせられる。
「……今まで、態度がきつくてごめん。確かにあんたのナルシスト発言にイラッとすることはあったけど、根本にあったのは北大路と直接関係のないことだったから」
これを話したらどう思われるのだろう――そう思うと少し躊躇われるけれど、思いきって話すことにした。
話さなければきっと前に進めないし、八つ当たりをされた北大路には聞く権利があると思ったから。
「たぶんやったほうは大したことじゃないと思ってるだろうけど、すごく嫌な思いをしたことがあってね……」
今でもまだ思い出すと体の奥が怒りで静かに熱くなる、中学時代の出来事。
数人の男子たちによって行われた“ゲーム”だった。内容はよくある、地味な女子をからかって遊ぶという、あれ。
「ある男子がね、熱心に休み時間とか放課後とか話しかけてくるようになって、二週間くらい経ってから告白されたの。男子たちの筋書きではそこで私が勘違いして舞い上がってOKしたところで『どっきりでしたー。間に受けてやんのー』みたいにして笑い者にしてやるつもりだったんだろうけど」
私は断ったのだ。そんなわかりきったことに付き合ってやる筋合いはないと思ったし、何より怖かったから。
だから、それはそれは丁重に断ったのだ。相手のプライドを傷つけないよう配慮して、そういったことに興味がないから付き合えませんと、あくまで向こうに落ち度などないというように。
ところが、それが逆に気に障ったらしい。
「その告白した男子含め、ゲームをやっていた数人に寄ってたかって文句言われたの。『地味ブスのくせに生意気だ。断る権限があると思ってるなんて思い上がりだ。調子に乗るな』だって。笑い者にするところまでが筋書きだったなら、そりゃ確かに盛り上がらないもんね」
結局、現場にたまたま先生が通りかかって男子たちがこっぴどく叱られたことで収束したし、形だけ謝罪はされた。でも、私の心に大きなしこりとして、その出来事は残った。チャラチャラした、自分たちをスクールカースト上位の人間だと決めつけて高みにいる気でいるやつらを嫌う理由になった。
それ以来、私は心に決めたのだ。いけ好かない派手な連中のオモチャになってたまるものか、と。好きで地味で生きているのだ。好きでモブをやっているのだ。それを邪魔されてなるものか、と。
「モブがモブであるために勝ち続けなきゃならない……って思ってちょっと攻撃的になりすぎてた。ごめんね」
ペコっと頭を下げると、北大路がふっと笑うのがわかった。
「何で笑ったの?」
「いや、そこ、何で名曲もじったのかと思って」
ツボに入ったらしく、北大路はしばらく笑い続けていた。この前の平山とのことでも笑っていたし、こいつの笑いのツボってやっぱりわからない。
「とりあえず、姫川が本気で俺を嫌いだったわけじゃなくてよかった」
そう言って北大路は、心底ホッとしたという顔をした。
「よく考えたら私、嫌うほど北大路のこと知らなかったし」
「じゃあ、これから知ってくれ。俺は顔が良い以外にもたくさん良いところがあるんだからな」
「……殴って良い?」
拳を作って見せると北大路が大げさに身構えるから、それを見て私は笑った。こいつのナルシスト発言は、もしかしたらこんなふうに人間関係を円滑にいかせるための潤滑剤なのかもしれないな、なんて思えるようになった。
「姫川は自分のことを地味だとかモブだとか言うけれど、自分を過小評価しすぎだと思うけどな」
公園にたどりついて、ベンチに座った。買ってくれたジュースを開けようとしていたら、真剣な顔をして北大路が言う。
「話したら面白いし、漫画は描けるし曲も作れる。これって立派な個性だし、すごいことだろ?」
「そうかな。描ける人も作曲できる人もいくらでもいるからさ」
「でも、できない人もいる中、できるんだ。それに良いものを作ってると思うよ。姫川はもっと自信持って、自分にも作品にも向き合っていけよ。『わかる人にわかればいい』っていう姿勢はもったいない。だから、曲ももっとガンガン宣伝していこう?」
「う、うん」
「せっかくこの俺が才能があると認めてやってるんだ。もっと欲張れよ」
「わかった」
キラキラの笑顔でものすごい熱意を持って言われたから、少々の俺様発言は気にならなかった。
今まで誰もこんなことを言ってくれた人がいないから照れるけれど、こんなにはっきりと自分を肯定したもらえると嬉しくなる。
「姫川、これからも俺と一緒に音楽やってくれるか?」
答えのわかりきった北大路の問いかけに、私はコクンと頷いた。
不思議と優しくしみこむ言葉を発する北大路を見て、私はわかった気がする。リア充にもいろいろな人種がいるし、人気者には人気者でいるための苦労も努力もきっとあるのだろう、と。
だから、もう接する前から嫌うのはやめようと思う。せめて、北大路のようにこちらに興味を持って接してくれる人間には、棘を出さずにいようと。
「なんだ。俺のあまりの美貌に呆然としてるのか?」
「……いろいろ台無しだから、黙れ」
この空気を読まないナルシスト発言には、容赦なくつっこみを入れようと思うけれど。
「……よかった、仲直りできて。もし仲直りできなかったら、もう姫川にそうやってつっこんでももらえなかったんだからな」
ふざけているのかと思いきや、北大路は真剣な顔をしてそんなことを言う。イケメンの真剣な顔なんて、反則だ。私がオタクじゃなくて、三次元に興味のある健全な女子なら、好きになってしまうところだった。
「……なに、あんた。私につっこみ入れられるのが好きなの? てか、ボケてる自覚あったんだ」
あぶないあぶないと思いながら鋭い視線を向ければ、北大路はニコニコしてこちらを見てくる。……こいつ、もしかしてМなんだろうか。
「つっこまれるのが嬉しいというか、姫川とこうして話ができるのが嬉しい。――姫川は、特別だから」
へへっと、照れたように北大路は笑う。かっこつけた笑顔でもドヤ顔でもないそんな顔をするなんて意外で、何だかびっくりしてしまう。
「……と、特別?」
「そう、特別だ。だって、こんなにいろんな話をしてくれる女子はいないし、姫川は面白いことをたくさん教えてくれるから」
「なんだ、そういうこと……まあ確かに、リア充の北大路にとってはオタクの私と話すのは異文化コミュニケーションだよね……」
どこかでちょっと変なことを期待してしまっていた私は、「あはは」と乾いた笑いでごまかした。
イケメンリア充がオタクな私に……なんてことは、あるはずがないんだ。あってたまるかって話だ。
でも、こうしてわざわざ会いに来てくれたことは嬉しい。仲直りしたいと思ってくれたことも。
(……そうは言っても、非リアオタクの心臓にこのキラキラした友情イベントはなかなか堪えるな)
動悸を訴える心臓をこっそり押えて、私は溜息をついた。
せっかくの休みだっていうのに気持ちが晴れなくて、ボーッと机に向かっていた。パソコンで大好きなアニメを流しているけれど、全く頭に入ってこない。元気にもならない。
あれ? 私、オタクだったよね?って気分になる。別にオタクであることにアイデンティティを見出しているわけではないけれど。
原因はわかっていた。
ものすごい自己嫌悪に苛まれているからだ。
昨日、部室に戻ってから顛末を聞かせたサナにも、「それはメーちゃんが悪いよ」と言われた。隠していようと思っていたのに、カバンを取りに戻ったら結局様子がおかしいのがバレてすべて話すことになってしまったのだ。
「キンヤくんは何も悪いことしてないじゃない」
そう言われて、私は自分が北大路に八つ当たりしてしまったのだと気がついた。
北大路が私に話しかけるから白川にあんなことを言われてしまった……なんて思ったけれど、別に北大路が悪いわけではない。
傷つけられた気持ちを、そのとき当たりやすかった北大路にぶつけただけだった。そんなの、北大路と話したいのに話しかけられない苛立ちを私にぶつけた白川と同じだ。めちゃくちゃダサいし、卑怯だ。
そのことに気がついたら、ギュッと胸の奥が重くなって苦しくなった。
大抵のことは一晩寝れば忘れてしまう質なのに、今朝は全く気持ちが晴れなかった。
白川たちの物理的な嫌がらせは未然に防ぐことができたし、釘を刺すことができたからこれ以上悪化はしないと思う。恵麻ちゃんや葉月に迷惑もかからないはず。それは、サナも安心していいと言ってくれた。
でも、北大路のことを考えると気が重い。
嫌いだったかもしれないけれど、あんなことを言って傷つけていい理由にはならない。
でも……嫌いだったというのも自分の中でよくわからなくなってしまっていた。
もう部室にいるのも気にならないし、一緒に曲作りだってした。それなのに、よく知る前と同じように嫌いだと言い切ってしまえるのだろうか。
「何で、メーちゃんはあんなにキンヤくんのこと嫌うの?」
昨日の帰り道、サナにそう尋ねられて、私は北大路を、というより地味の対極にあるような人種を嫌う理由を話した。
でも、全部話し終わったあとサナに「それもキンヤくんには関係ない事情じゃない」と言われてしまったし、話しながら自分でも感じていた。
要するに私は、北大路本人に理由がないことであいつを嫌い、北大路に関係のないことで八つ当たりをしてしまったのだ。
「……サイテー」
自分ひとりの部屋にその声は無駄に響いて、ズキンと胸に突き刺さった。
私は一体、何と戦っていたんだろう。
地味なことにコンプレックスなんてないし、オタクであることも別に恥じてなんていない。モブで上等だと思って生きている。
――自分たちを中心に世の中がまわっていると思っている連中に、踏みにじられさえしなければ。
でも、踏みにじられることを恐れて、攻撃的になりすぎていたのかもしれない。
今回の白川たちみたいに実際に攻撃されたのなら噛み付けばいいだけで、何もさせる前からひどい態度をとっていたのは良くなかった。
北大路の悪いところと言えば……俺様なところだけだ。あの俺様な態度が反射的にひどい態度をとらせていたと言えなくもないけれど。
月曜、学校で謝らなくちゃ。こういうのはメールじゃダメだから――そう思って不貞寝を決め込もうとしたとき、インターフォンが鳴らされた。
誰だ。土曜の昼間にピンポン鳴らすのはセールスか宗教の勧誘か。でも、町内会とかだったら困る。
お父さんもお母さんも土曜でも仕事に行っているし、兄ちゃんもバイトだ。出られるのは私しかいない。
しかも、かなり鳴らし続けている。
とりあえず、モニターで誰が来ているのかだけでも確認しよう。
「……おい、ヘアセットなら自分の鏡を見てやれよ」
急いでリビングに降りてモニターを覗いて、私は自分のこめかみに青筋が立つのを感じていた。タイムリーな人物ではあるけれど、やっぱりこうして見ると、そのナルシストな仕草がいちいい癇に障る。
「あのさ、ナルシストの押し売りならお断りなんで帰ってもらえますかー?」
「姫川ー!」
手櫛でしきりに前髪を整え続けながらインターフォンをピンポンピンポン鳴らす北大路にそう言ってやると、やつは嬉しそうにブンブンと手を振ってきた。何なんだ。家なんて教えるんじゃなかった。
「どうしたの? あがる?」
玄関のドアを開けると、北大路が背筋をしゃんとして待っていた。
「いや、一人で留守番中のところに上がり込むなんていう不誠実なことはしない」
何でそこ顔赤らめるの。不誠実なことってあんた、何するの。
「一人って何で知ってるの?」
「真田に聞いた。というより真田に、『土日は大抵留守番だから遊びに行っても大丈夫だよ』って教えてもらったから」
「あの子……」
「学校では話しかけるなって言われたから、こうして来てみたんだ。今からちょっと話せるか?」
「……うん」
私は返事をして、一歩外に出ようとして気がついた。この服装はいかん!
「ちょっと待ってて!」
玄関は暗いしドアは半分くらいしか開けてなかったから、たぶんあまり見えてなかったとは思うけれど、着古したスウェット地のワンピースに足元はつっかけだった!
これでそのまま外に出て、しかも北大路みたいな美形の横を歩くなんて、市中引き回しの刑にも等しいじゃないか! どんな羞恥プレイだ。
といっても、こんなときにサッと着られるような服を持ち合わせてはいないのが困りものだ。
オタク趣味ばかりにお金を注ぎ込んできたツケがこんなところでまわってくるなんて……。
仕方なく、サナと一緒に買いに行った一張羅を着ることにした。
「ごめん、お待たせ。さっきの格好はあまりに部屋着だったから着替えてきた」
急いで玄関に戻ると、北大路は別段気分を害した様子もなく待っていてくれた。私のみっともない言い訳を聞いても、別に笑ったりしなかった
でも、しげしげと眺められて落ち着かない。
「姫川の私服、いいな」
しばらく眺めて、そう簡潔に感想を述べた。まさかそんなコメントをされるとは思っていなかったから、瞬時に顔が赤くなる。
「馬子にも衣装だって言いたいの?」
「違う。本当によく似合ってる。それに髪もそうして下ろしていたほうがいい」
「……ありがとう」
真正面から褒められるとやっぱり照れてしまう。でも、初めてこだわって買った洋服だったから似合っていると言われて嬉しかった。
これは、サナと二人で「大好きな“彼”とデートに行くなら」をテーマに選んだ服。“彼”はもちろん二次元で、恥を忍んで店員さんに相談してコーディネートしてもらったのだ。店員さんはオタクに理解があるお姉さんで(というよりお姉さん自身もオタクだと言っていた)、何のキャラか話すとノリノリで彼のテーマカラーでトータルコーディネートを考えてくれた。オタ的にも女子的にも、非常にレベルの高いワードローブになった。
この前の同人イベントでサナと仲良く着たきり、それ以来着る機会がなかったから、今日こうして着ることができてよかった。
……北大路と歩くには、ちょっと気合が入りすぎている気がするけれど。
「このへん何もないけど、ぶらぶらする?」
「そうだな。じゃあ適当に案内してくれ」
「うん」
何のことを話題にしようとしているかは明白なのに、ぎこちなくて仕方がない。というより、言わなくてはいけないことがあるのは私なのにこうして北大路に訪ねて来させてしまったのだから、私から口を開くべきだ。
そう思っていたのに、先に言葉を発したのも北大路だった。
「姫川……すまなかった」
「え?」
「俺の配慮が足りず、嫌な思いをさせてしまって。俺も馬鹿じゃないから、女子の悪質さとかわかっていたつもりだったんだけど……俺が話しかけたところで姫川が嫌そうにしているのは誰が見てもわかるだろうと思っていたんだ」
「私こそ、あの人たちに嫌なこと言われたからって北大路に八つ当たりみたいなことして、ごめん……」
「また学校で話しかけていいなら、いいさ。本気で嫌なら、無理にとは言わないけどな」
俺様な発言がひとつもなくて、しかも素直に謝られてしまって、調子が狂いそうになる。
こういうとき、イケメンは狡い。何か、ものすごく悪いことをした気分にさせられる。
「……今まで、態度がきつくてごめん。確かにあんたのナルシスト発言にイラッとすることはあったけど、根本にあったのは北大路と直接関係のないことだったから」
これを話したらどう思われるのだろう――そう思うと少し躊躇われるけれど、思いきって話すことにした。
話さなければきっと前に進めないし、八つ当たりをされた北大路には聞く権利があると思ったから。
「たぶんやったほうは大したことじゃないと思ってるだろうけど、すごく嫌な思いをしたことがあってね……」
今でもまだ思い出すと体の奥が怒りで静かに熱くなる、中学時代の出来事。
数人の男子たちによって行われた“ゲーム”だった。内容はよくある、地味な女子をからかって遊ぶという、あれ。
「ある男子がね、熱心に休み時間とか放課後とか話しかけてくるようになって、二週間くらい経ってから告白されたの。男子たちの筋書きではそこで私が勘違いして舞い上がってOKしたところで『どっきりでしたー。間に受けてやんのー』みたいにして笑い者にしてやるつもりだったんだろうけど」
私は断ったのだ。そんなわかりきったことに付き合ってやる筋合いはないと思ったし、何より怖かったから。
だから、それはそれは丁重に断ったのだ。相手のプライドを傷つけないよう配慮して、そういったことに興味がないから付き合えませんと、あくまで向こうに落ち度などないというように。
ところが、それが逆に気に障ったらしい。
「その告白した男子含め、ゲームをやっていた数人に寄ってたかって文句言われたの。『地味ブスのくせに生意気だ。断る権限があると思ってるなんて思い上がりだ。調子に乗るな』だって。笑い者にするところまでが筋書きだったなら、そりゃ確かに盛り上がらないもんね」
結局、現場にたまたま先生が通りかかって男子たちがこっぴどく叱られたことで収束したし、形だけ謝罪はされた。でも、私の心に大きなしこりとして、その出来事は残った。チャラチャラした、自分たちをスクールカースト上位の人間だと決めつけて高みにいる気でいるやつらを嫌う理由になった。
それ以来、私は心に決めたのだ。いけ好かない派手な連中のオモチャになってたまるものか、と。好きで地味で生きているのだ。好きでモブをやっているのだ。それを邪魔されてなるものか、と。
「モブがモブであるために勝ち続けなきゃならない……って思ってちょっと攻撃的になりすぎてた。ごめんね」
ペコっと頭を下げると、北大路がふっと笑うのがわかった。
「何で笑ったの?」
「いや、そこ、何で名曲もじったのかと思って」
ツボに入ったらしく、北大路はしばらく笑い続けていた。この前の平山とのことでも笑っていたし、こいつの笑いのツボってやっぱりわからない。
「とりあえず、姫川が本気で俺を嫌いだったわけじゃなくてよかった」
そう言って北大路は、心底ホッとしたという顔をした。
「よく考えたら私、嫌うほど北大路のこと知らなかったし」
「じゃあ、これから知ってくれ。俺は顔が良い以外にもたくさん良いところがあるんだからな」
「……殴って良い?」
拳を作って見せると北大路が大げさに身構えるから、それを見て私は笑った。こいつのナルシスト発言は、もしかしたらこんなふうに人間関係を円滑にいかせるための潤滑剤なのかもしれないな、なんて思えるようになった。
「姫川は自分のことを地味だとかモブだとか言うけれど、自分を過小評価しすぎだと思うけどな」
公園にたどりついて、ベンチに座った。買ってくれたジュースを開けようとしていたら、真剣な顔をして北大路が言う。
「話したら面白いし、漫画は描けるし曲も作れる。これって立派な個性だし、すごいことだろ?」
「そうかな。描ける人も作曲できる人もいくらでもいるからさ」
「でも、できない人もいる中、できるんだ。それに良いものを作ってると思うよ。姫川はもっと自信持って、自分にも作品にも向き合っていけよ。『わかる人にわかればいい』っていう姿勢はもったいない。だから、曲ももっとガンガン宣伝していこう?」
「う、うん」
「せっかくこの俺が才能があると認めてやってるんだ。もっと欲張れよ」
「わかった」
キラキラの笑顔でものすごい熱意を持って言われたから、少々の俺様発言は気にならなかった。
今まで誰もこんなことを言ってくれた人がいないから照れるけれど、こんなにはっきりと自分を肯定したもらえると嬉しくなる。
「姫川、これからも俺と一緒に音楽やってくれるか?」
答えのわかりきった北大路の問いかけに、私はコクンと頷いた。
不思議と優しくしみこむ言葉を発する北大路を見て、私はわかった気がする。リア充にもいろいろな人種がいるし、人気者には人気者でいるための苦労も努力もきっとあるのだろう、と。
だから、もう接する前から嫌うのはやめようと思う。せめて、北大路のようにこちらに興味を持って接してくれる人間には、棘を出さずにいようと。
「なんだ。俺のあまりの美貌に呆然としてるのか?」
「……いろいろ台無しだから、黙れ」
この空気を読まないナルシスト発言には、容赦なくつっこみを入れようと思うけれど。
「……よかった、仲直りできて。もし仲直りできなかったら、もう姫川にそうやってつっこんでももらえなかったんだからな」
ふざけているのかと思いきや、北大路は真剣な顔をしてそんなことを言う。イケメンの真剣な顔なんて、反則だ。私がオタクじゃなくて、三次元に興味のある健全な女子なら、好きになってしまうところだった。
「……なに、あんた。私につっこみ入れられるのが好きなの? てか、ボケてる自覚あったんだ」
あぶないあぶないと思いながら鋭い視線を向ければ、北大路はニコニコしてこちらを見てくる。……こいつ、もしかしてМなんだろうか。
「つっこまれるのが嬉しいというか、姫川とこうして話ができるのが嬉しい。――姫川は、特別だから」
へへっと、照れたように北大路は笑う。かっこつけた笑顔でもドヤ顔でもないそんな顔をするなんて意外で、何だかびっくりしてしまう。
「……と、特別?」
「そう、特別だ。だって、こんなにいろんな話をしてくれる女子はいないし、姫川は面白いことをたくさん教えてくれるから」
「なんだ、そういうこと……まあ確かに、リア充の北大路にとってはオタクの私と話すのは異文化コミュニケーションだよね……」
どこかでちょっと変なことを期待してしまっていた私は、「あはは」と乾いた笑いでごまかした。
イケメンリア充がオタクな私に……なんてことは、あるはずがないんだ。あってたまるかって話だ。
でも、こうしてわざわざ会いに来てくれたことは嬉しい。仲直りしたいと思ってくれたことも。
(……そうは言っても、非リアオタクの心臓にこのキラキラした友情イベントはなかなか堪えるな)
動悸を訴える心臓をこっそり押えて、私は溜息をついた。