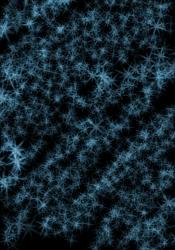***
青い空は柔らかな光に満ち、春の日差しに包まれた今日、私、駒田彩は一年前に卒業した山梨商業高校の正門の前にやってきた。
一年前の卒業からの時間が経ち、桜並木を歩くといくつものピンクの花びらが風に乗り優雅に舞い降りていくのが見える。
「君は相変わらずだね」
花びらに向かって私は声をかける。
桜は優しくてあたたかくて自由で、高校を卒業したあの頃と何も変わっていない。
身に着けてきたクラシックなフルスケルトン文字盤の腕時計を確認すると、時計の針は午後二時半を指していた。特に決めた時間や約束はなかったけれど、午前中に行くつもりでいたので、予定より遅くなってしまったと感じた。
正門にたどり着いた直前と比べて喉が渇くのは気候の暑さだけではなく、内面に秘めた緊張感のせいもあった。
黒色のロングストレートの髪を一つに束ね、白色のYシャツに、グレー色のテーラードジャケットとパンツ、黒色のパンプスといういつもの仕事着を封印して、新たな見た目に挑戦した。予約をした人気の美容院で昨日髪をショートにカットして、オレンジ色が混じった明るめの茶色に髪を染めて、ナチュラルなパーマをかけてもらった。
今日のコーディネートは、べージュ色のスプリングコートに、水玉のついたレースが入っているふわりとした白色のワンピース、こげ茶色のパンプス。らしくない姿だなんて分かってるけど、私がこれらを選んだ理由は、いつもの自分よりも高飛車にみせたかったから。そして今日一番重要なのは、今、両手で抱えている、ほのかな甘い香りがする三十本の白いチューリップの花束だったりする。
今年の卒業式は、明後日らしい。
私は卒業して以来一度も高校を訪れていない。でも、私に懐かしさなんてなかった。私はずっと鮮明に覚えていたから。
そして思う。
こんな形で学校を訪れたくなかった。
「駒田さん?」
私の胸がどくっと大きく鳴る。たまたま校舎から出てきた佐原和也先生は目を丸めて私の近くにやってきた。
佐原先生は優しい笑顔を浮かべ、黒色の爽やかなマッシュショートの髪をしていて、白色のYシャツとグレー色のテーラードジャケットとパンツを着ている。服装が普段の私とたまたま同じでちょっと笑みがこぼれた。童顔で細身の体形は一年前とほとんど変わっていない。今年で三十歳には見えなかった。
私が会いたかった人は閉ざされた正門の向こう側にいる。佐原先生は私を見つけると何の迷いもなく正門の鍵を開けて、門の内側にあるハンドルを握り、ゆっくりと門の下についているローラーをスライドさせた。ギギギと鈍く重い音が響いた後で佐原先生の真ん丸な目が私を見つめた。佐原先生の優しい目のセンサーを感知すると、私の心は自動的に点灯してぽっと心を明るく温かくしてくれる。だから心の中で落ち着いてと、自分に言い聞かせていた。
「久しぶりだね、佐原先生」
「驚きました。懐かしいですね。元気にしていましたか?」
「……うん」
高まる胸の高鳴りを佐原先生に気づかれないように静かに押さえつけて、私はにこやかに笑ってみせた。卒業して社会人になったので、佐原先生には敬語を使って話すつもりでいたのに、いざ佐原先生を目の当たりにすると、つい気が緩んで学生時代と同じタメ語で話してしまっていた。
「私のこと、覚えてたの?」
「顔を見たらすぐ分かります」
「見たら、すぐ?」
「駒田さんは……ガラスを割る問題児でしたから、いまだに忘れるはずありません」
私の話し方なんて気にせずに、佐原先生はからかうようにそう言って笑い、私もさらに口角を上げた。
「駒田さん、仕事は順調ですか?」
と尋ねられて、私はうなずいた。
「うん。卒業前に佐原先生に相談してよかった。素敵な職場に就けたよ」
「それは良かったですね」
「お兄ちゃんも私がちゃんと立ち直って就職できたことにほっとしてる」
佐原先生も優しくうなずいた。
「……駒田さん、雰囲気が大人っぽく変わりましたね。すごくきれいになりました」
私は嬉しいような寂しいような感情を抱きながら微笑んだ。
「今日は特別な日だから」
「特別な日、ですか?」
佐原先生が首をかしげる。私は一度うつむいてしまったが、すぐに顔をあげて微笑みながら花束を少しだけ押し付けるように差し出した。
「佐原先生。結婚、おめでとう」
先生は一瞬だけ驚いた表情を浮かべたが、すぐに子供みたいに明るく笑い、私の花束をそっと受け取った。
「えっ、え……僕に? 嬉しいです! ありがとうございます、駒田さん!」
「うん」
「すごい数の……チューリップですね」
佐原先生は柔らかな表情でじっと花束を見つめながら、そっとつぶやいた。
「そうでしょ? 春だからチューリップの花束にしたの」
「きれいですね。いい匂いもします。白いチューリップの花言葉って何でしたっけ?」
私は顔をあげた佐原先生にふわりと聞かれて無理に笑顔を作りながら、あからさまに首をかしげた。
「……何だったかな? 分からないな」
佐原先生は私のわざとらしい行動に一切疑問を持たなかった。
「駒田さんは僕の結婚のお祝いに……来てくれたのですか?」
「そう。学校のグループラインで知ったから……お祝いをしたくて」
「嬉しいです。丁寧にありがとうございます。一人で来てくれたのですか?」
「……うん」
佐原先生は私の話を深く受け入れるように優しく何度もうなずく。少しの沈黙の後、佐原先生は口を開いた。
「駒田さんは……校舎のガラスを割るような生徒だった、それがこんなに変わって。見た目も、そして中身も。僕は本当に嬉しいです」
「佐原先生、私は……変わってないよ」
そっと首を振ると、佐原先生はくすくすと笑った。
「今でも公共の場で椅子を振り回して暴れる人だって言うんですか?」
「もう……そうじゃないよ。そこは完全に改心した」
「大人になりましたね」
私は静かに口をつぐむ。佐原先生に褒められてもらうとじんわりと温かくて、誰よりも勇気をもらえる。だから思ってしまう。
言え、私。今、まっすぐに。でも……もうそれは言えないことだと知りすぎていた。
「佐原先生。私のあげた花束、大切にしてね」
静かに伝えると、佐原先生は迷わずに強くうなずいた。
「もちろんです」
童顔な顔に似合う中身はなんて素直で可愛いのだろう。それが今はとても切ない。
「うん……それじゃ」
私は会釈する。佐原先生はぴくっと反応して眉を下げる。
「え……もう帰るのですか? せっかくなら、校舎の中に入っていきませんか?」
「大丈夫。できれば学校には……入りたくなかった。優しい思い出に浸るから」
「え?」
「佐原先生がここにきてくれてよかった。それじゃ」
私は軽くお辞儀をして、佐原先生に背を向ける。
「駒田さん……?」
私は来た道をさっと引き返すために歩きだした。
「え、待ってください……!」
後ろで佐原先生の声がした。
勝手だって思われただろう。
でも、決めていた。
花束を渡して背を向けたら佐原先生に名前を呼ばれても振り向かない。
「駒田さん……!」
後ろから聞こえた声に反応して私は思う。
ねえ、佐原先生。
私を引き留める気が本気であるなら、門の内側で立ち止まらないでほしい。声をかけるだけじゃなくて私を追いかけて、腕を強く引っ張ってほしいよ。行かないで、もうどこへも行かずに側にいてと……言ってほしい。
でも、それは無理なんだ。
腕を掴んで強く引き留めてもらえるなんて甘い期待は……私の空想でしかない。
佐原先生は来月、私の知らない誰かと結婚する。だから佐原先生の足音は後ろからやって来ない。私を追いかけてこない。それは当たり前のこと、学校に来る前から分かっていたことだ。どんなに思いを寄せたって……私の想像通りにならないことなんて、私は知っているはずだ。
私はこの学校を卒業してから大人になった、仕事もばりばりこなせて人とのコミュニケーションも上手くなってとても強くなった……そう思っていた。なのにポロポロと涙があふれてくる。今日だけはせめて高飛車に見せようとしたのに、全然だめらしい。私は強がることができない。
佐原先生を振り切るために歩くスピードをあげると、さらに冷たい涙はこぼれ落ちる。
そう、変わっていない。
佐原先生が私を間違った道から正しく変えてくれた一年前と、気持ちは変わっていない。
佐原先生が好き。その気持ちだけで、ここまで生きてこられた。
欲を言おう。
私は、佐原先生の大切な人になりたかった。佐原先生の一番大切な人にしてほしかった。
だけどその思いはそっとしまう。
佐原先生が一番に選んだ大切な彼女のために、言わないでおく。でも……私と一緒に過ごした日々を佐原先生に忘れてほしくない。
気持ちに整理をつけたい。だからその為に私は今日ここに一人で、おめでとうとさよならの花束を置きにきた。
青い空は柔らかな光に満ち、春の日差しに包まれた今日、私、駒田彩は一年前に卒業した山梨商業高校の正門の前にやってきた。
一年前の卒業からの時間が経ち、桜並木を歩くといくつものピンクの花びらが風に乗り優雅に舞い降りていくのが見える。
「君は相変わらずだね」
花びらに向かって私は声をかける。
桜は優しくてあたたかくて自由で、高校を卒業したあの頃と何も変わっていない。
身に着けてきたクラシックなフルスケルトン文字盤の腕時計を確認すると、時計の針は午後二時半を指していた。特に決めた時間や約束はなかったけれど、午前中に行くつもりでいたので、予定より遅くなってしまったと感じた。
正門にたどり着いた直前と比べて喉が渇くのは気候の暑さだけではなく、内面に秘めた緊張感のせいもあった。
黒色のロングストレートの髪を一つに束ね、白色のYシャツに、グレー色のテーラードジャケットとパンツ、黒色のパンプスといういつもの仕事着を封印して、新たな見た目に挑戦した。予約をした人気の美容院で昨日髪をショートにカットして、オレンジ色が混じった明るめの茶色に髪を染めて、ナチュラルなパーマをかけてもらった。
今日のコーディネートは、べージュ色のスプリングコートに、水玉のついたレースが入っているふわりとした白色のワンピース、こげ茶色のパンプス。らしくない姿だなんて分かってるけど、私がこれらを選んだ理由は、いつもの自分よりも高飛車にみせたかったから。そして今日一番重要なのは、今、両手で抱えている、ほのかな甘い香りがする三十本の白いチューリップの花束だったりする。
今年の卒業式は、明後日らしい。
私は卒業して以来一度も高校を訪れていない。でも、私に懐かしさなんてなかった。私はずっと鮮明に覚えていたから。
そして思う。
こんな形で学校を訪れたくなかった。
「駒田さん?」
私の胸がどくっと大きく鳴る。たまたま校舎から出てきた佐原和也先生は目を丸めて私の近くにやってきた。
佐原先生は優しい笑顔を浮かべ、黒色の爽やかなマッシュショートの髪をしていて、白色のYシャツとグレー色のテーラードジャケットとパンツを着ている。服装が普段の私とたまたま同じでちょっと笑みがこぼれた。童顔で細身の体形は一年前とほとんど変わっていない。今年で三十歳には見えなかった。
私が会いたかった人は閉ざされた正門の向こう側にいる。佐原先生は私を見つけると何の迷いもなく正門の鍵を開けて、門の内側にあるハンドルを握り、ゆっくりと門の下についているローラーをスライドさせた。ギギギと鈍く重い音が響いた後で佐原先生の真ん丸な目が私を見つめた。佐原先生の優しい目のセンサーを感知すると、私の心は自動的に点灯してぽっと心を明るく温かくしてくれる。だから心の中で落ち着いてと、自分に言い聞かせていた。
「久しぶりだね、佐原先生」
「驚きました。懐かしいですね。元気にしていましたか?」
「……うん」
高まる胸の高鳴りを佐原先生に気づかれないように静かに押さえつけて、私はにこやかに笑ってみせた。卒業して社会人になったので、佐原先生には敬語を使って話すつもりでいたのに、いざ佐原先生を目の当たりにすると、つい気が緩んで学生時代と同じタメ語で話してしまっていた。
「私のこと、覚えてたの?」
「顔を見たらすぐ分かります」
「見たら、すぐ?」
「駒田さんは……ガラスを割る問題児でしたから、いまだに忘れるはずありません」
私の話し方なんて気にせずに、佐原先生はからかうようにそう言って笑い、私もさらに口角を上げた。
「駒田さん、仕事は順調ですか?」
と尋ねられて、私はうなずいた。
「うん。卒業前に佐原先生に相談してよかった。素敵な職場に就けたよ」
「それは良かったですね」
「お兄ちゃんも私がちゃんと立ち直って就職できたことにほっとしてる」
佐原先生も優しくうなずいた。
「……駒田さん、雰囲気が大人っぽく変わりましたね。すごくきれいになりました」
私は嬉しいような寂しいような感情を抱きながら微笑んだ。
「今日は特別な日だから」
「特別な日、ですか?」
佐原先生が首をかしげる。私は一度うつむいてしまったが、すぐに顔をあげて微笑みながら花束を少しだけ押し付けるように差し出した。
「佐原先生。結婚、おめでとう」
先生は一瞬だけ驚いた表情を浮かべたが、すぐに子供みたいに明るく笑い、私の花束をそっと受け取った。
「えっ、え……僕に? 嬉しいです! ありがとうございます、駒田さん!」
「うん」
「すごい数の……チューリップですね」
佐原先生は柔らかな表情でじっと花束を見つめながら、そっとつぶやいた。
「そうでしょ? 春だからチューリップの花束にしたの」
「きれいですね。いい匂いもします。白いチューリップの花言葉って何でしたっけ?」
私は顔をあげた佐原先生にふわりと聞かれて無理に笑顔を作りながら、あからさまに首をかしげた。
「……何だったかな? 分からないな」
佐原先生は私のわざとらしい行動に一切疑問を持たなかった。
「駒田さんは僕の結婚のお祝いに……来てくれたのですか?」
「そう。学校のグループラインで知ったから……お祝いをしたくて」
「嬉しいです。丁寧にありがとうございます。一人で来てくれたのですか?」
「……うん」
佐原先生は私の話を深く受け入れるように優しく何度もうなずく。少しの沈黙の後、佐原先生は口を開いた。
「駒田さんは……校舎のガラスを割るような生徒だった、それがこんなに変わって。見た目も、そして中身も。僕は本当に嬉しいです」
「佐原先生、私は……変わってないよ」
そっと首を振ると、佐原先生はくすくすと笑った。
「今でも公共の場で椅子を振り回して暴れる人だって言うんですか?」
「もう……そうじゃないよ。そこは完全に改心した」
「大人になりましたね」
私は静かに口をつぐむ。佐原先生に褒められてもらうとじんわりと温かくて、誰よりも勇気をもらえる。だから思ってしまう。
言え、私。今、まっすぐに。でも……もうそれは言えないことだと知りすぎていた。
「佐原先生。私のあげた花束、大切にしてね」
静かに伝えると、佐原先生は迷わずに強くうなずいた。
「もちろんです」
童顔な顔に似合う中身はなんて素直で可愛いのだろう。それが今はとても切ない。
「うん……それじゃ」
私は会釈する。佐原先生はぴくっと反応して眉を下げる。
「え……もう帰るのですか? せっかくなら、校舎の中に入っていきませんか?」
「大丈夫。できれば学校には……入りたくなかった。優しい思い出に浸るから」
「え?」
「佐原先生がここにきてくれてよかった。それじゃ」
私は軽くお辞儀をして、佐原先生に背を向ける。
「駒田さん……?」
私は来た道をさっと引き返すために歩きだした。
「え、待ってください……!」
後ろで佐原先生の声がした。
勝手だって思われただろう。
でも、決めていた。
花束を渡して背を向けたら佐原先生に名前を呼ばれても振り向かない。
「駒田さん……!」
後ろから聞こえた声に反応して私は思う。
ねえ、佐原先生。
私を引き留める気が本気であるなら、門の内側で立ち止まらないでほしい。声をかけるだけじゃなくて私を追いかけて、腕を強く引っ張ってほしいよ。行かないで、もうどこへも行かずに側にいてと……言ってほしい。
でも、それは無理なんだ。
腕を掴んで強く引き留めてもらえるなんて甘い期待は……私の空想でしかない。
佐原先生は来月、私の知らない誰かと結婚する。だから佐原先生の足音は後ろからやって来ない。私を追いかけてこない。それは当たり前のこと、学校に来る前から分かっていたことだ。どんなに思いを寄せたって……私の想像通りにならないことなんて、私は知っているはずだ。
私はこの学校を卒業してから大人になった、仕事もばりばりこなせて人とのコミュニケーションも上手くなってとても強くなった……そう思っていた。なのにポロポロと涙があふれてくる。今日だけはせめて高飛車に見せようとしたのに、全然だめらしい。私は強がることができない。
佐原先生を振り切るために歩くスピードをあげると、さらに冷たい涙はこぼれ落ちる。
そう、変わっていない。
佐原先生が私を間違った道から正しく変えてくれた一年前と、気持ちは変わっていない。
佐原先生が好き。その気持ちだけで、ここまで生きてこられた。
欲を言おう。
私は、佐原先生の大切な人になりたかった。佐原先生の一番大切な人にしてほしかった。
だけどその思いはそっとしまう。
佐原先生が一番に選んだ大切な彼女のために、言わないでおく。でも……私と一緒に過ごした日々を佐原先生に忘れてほしくない。
気持ちに整理をつけたい。だからその為に私は今日ここに一人で、おめでとうとさよならの花束を置きにきた。