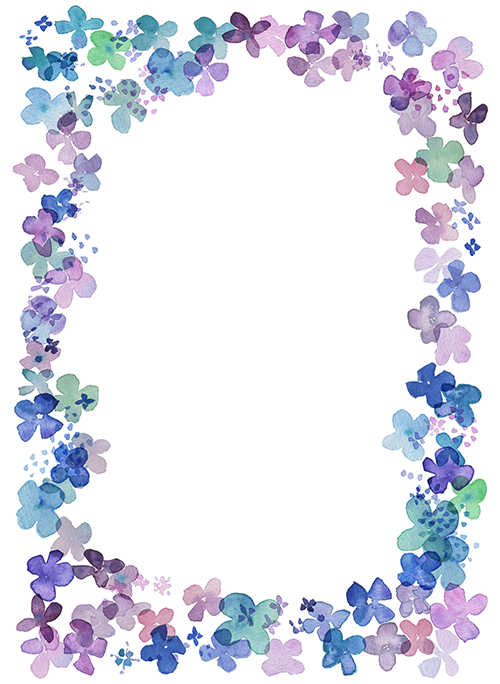あの日から近づけなかった場所に来た。部活を抜け出して傾きかけた陽を追いかけるように歩いた。幸い学校から十五分も掛からないところなので疲れることも無い。しかし、とても長く感じてしまったのは取り留めなく色々なことを思い出していたからだ。
「ここって……海だよね」
「うん」
君が不思議そうに尋ねた。何処にも行かないでね、と彼のシャツの袖をきゅっと握りしめると分かったよというように彼も私のセーラー服を握り返す。踏み出す度に力が抜けてしまう砂浜を踏みしめて波打ち際まで進んだ。
海水に触れてしまいそうなほどの距離まで歩くと、私は腰が抜けてしまいそのまま尻餅をついた。
「おい、大丈夫か?」
「いいから、そのまま聞いて」
私の鋭い声が君の伸ばしかけた腕を制す。後ろで息を呑む音が漣にかき消されるほど小さく聞こえた。深呼吸を一度、私は真っすぐ前を向きながら話し始める。
「一昨年の夏、弟を殺した」
その言葉を口にすれば、切れかけのビデオテープのようにぎこちなく、しかし鮮明に記憶が蘇った。弟の無邪気な笑顔と、君が見せる笑った顔が重なってすぐに泡のように弾けた。
「あの時私は受験生で、弟は小学生で。夏休みのほとんどを姉の夏期講習やら高校見学やらの予定で埋められてフラストレーションが溜まっていたんだろうね。ある日、弟が海に行きたいって言ったんだ」
あの日のことは鮮明に覚えている。父に止められたのにも関わらず、弟はどうしても海に行きたいと聞かなくて。じゃあ私が連れて行くよと提案したのだ。私もこの機会を逃せばもうこの夏は何処にも行けない。せっかくの中学最後の夏の思い出が勉強だけになってしまうのは嫌だったので、弟のその言葉は好都合だった。その日は天気が悪くなることが分かっていた。それでもどうしても、少しでもいいから弟の付き添いで海に行きたかった。今思えばなんて子供じみた判断をしたんだろうと思う。弟が泣きながら懇願すると、父は折れたようで「少しだけなら」と許してくれた。
「海についたとき、『なんだ、天気予報大間違いじゃん』なんて言ってしまう程の炎天下だった。だから私たちは夢中になって泳いでたんだ。けどね、段々と雲行きが怪しくなって……弟、気づけば波が高くなって陸地に戻れなくなっちゃったの」
彼は焦って何度も私を呼んだ。私は必死の形相で弟の元まで泳いで、もう大丈夫だよって頭を撫でて抱きしめてやった。合流できてよかった、これで助かる、その時は疑うことなくそう思っていた。
「それから私たちは何とかして砂浜に戻ろうと泳いだ。けどね、……な、波が邪魔して……っ手遅れで……」
突然大きな波が私たちを襲って、咄嗟に繋いでいた手を離した。そのあとすぐに私の手前で大きく波打つ白波。
体が放り出された時、私は弟を探した。波が邪魔してよく見えない。でも視界が逆さまになった瞬間、状況を理解してしまった。
『お姉ちゃん……っ』
弟の背後に迫りくる高波、大きな影が彼を飲み込んだ。それでも一度だって後ろを振り返らず、私の行方を心配そうに見つめる瞳。
それが最後に視界に焼きつけられた景色だった。
瞬きをすればもうそこは青かった。口から漏れる息が全て白い泡に変わる。上下も分からないまま水中を暫く彷徨った。暗い方に引っ張られそうになりながら、本能は浮上を目指す。腕が重い、足が動かない。それでも必死に水を藻掻く。酸素が足りなくて呼吸をしようとすると肺に海水が入り込んだ。激痛のあまり呻き声をあげる、その度にまた海水が肺を侵食した。
ああ、もう駄目かもしれない。
けれどもしここで死んでも構わなかった。あの大波の中、弟が助からないことを悟っていたからだ。
ごめんね、こんなお姉ちゃんで。私が連れてきたからこんな風になっちゃったよね。こんな天気になるんだったら初めから「駄目だよ」って言えば良かったね。責任取るよ、一人で死なせない。
神様約束だよ、このまま私を死なせて。
記憶はそこで途切れた。
私はそのまま意識を失って、気が付けば白い天井と眩い光が私を包み込んでいた。
なんだ、死ねなかったんだ。助かっちゃったんだ。
朦朧とする意識の中、母だけが忙しなく書類にサインを施しているのが分かる。私は霞む視界の中、目を凝らしてその文字を読もうとする。
黒い枠に弟の名前と太字の死亡届の文字が見えた瞬間、私は言葉に出来ない程の絶望感に襲われた。
「私は、あの日初めて死にたいって思った。優しくてどんな駄作もキラキラした瞳で見てくれる弟を、私が手を離したせいで助けられなかった。……悔やんでも、死にたくても、動けなくて。その日を境に私は青が怖くなった」
全て投げ出して消えたらどんなに楽なんだろう。
何も感じないまま死ねたらどれだけ幸せだろう。
死んだらどんな世界が待っているのだろう。弟に謝ることはできるのだろうか。
出来るんだったら喜んで死にたい。そして彼だけは生まれ変わって幸せに生きてほしい。
どれだけ死について考えても私は臆病者だから行動には移せない。
しかしこれだけは言える、私みたいな奴がのうのうと生きててはいけない。生き残ったならせめて弟に恥じないように生きようと勉強に勤しんだ。彼が褒めてくれた絵も頑張ろうと思った。
けれど、成績は全く伸びず定員割れの今の高校に入ることになった。
絵画コンクールだって、何度も応募しても落選の通知しかこなかった。
「私は誰かに認められる資格がないの。これから先、どれだけ絵が下手になっても、今の腫れもの扱いが悪化しようが、情けを掛けてもらう資格もない。弟を裏切って生きてしまったから。生きているのに、何も成せやしないただの落ちぶれ者だから。どう?それでも五十嵐は一緒にいてくれる?」
ふっと顔をあげると私の嫌いな青海原が視界を埋め尽くす。空も海も青い、目の前にあるだけで過呼吸になってしまう。酸素が足りなくなって座っているのにも関わらず今にも倒れそうだった。夕陽が目に染みるとずっと抑えていた涙が溢れ、我慢できずに嗚咽する。こんなみっともない姿、見せるつもりなんて無かったのに君と会えばいつも泣いている気がする。
水面に反射する君の顔は目に光がなく、絶望に満ちていた。
しょうがない、この反応が当たり前なんだから。
引いたでしょ、こんな重い人間だったんだって。
言いかけた言葉が声にならなかったのは君が抱きしめたからだ。
「辛かったんだな、みゃーこ」
掠れた声が鼓膜を揺らした。辛かったんだな、たったそれだけの言葉で涙で視界が歪むのはどうしてなんだろう。なんでそんなに優しく私のことを呼ぶんだろう。
「い……がらしぃ」
感情は一度溢れだしたら止まらない。自分では制御できない滅茶苦茶な情緒を君にぶつける。私の涙が制服を濡らしてしまっても、大丈夫だよと右手は背中に回したまま、優しい手つきで頭を撫でてくれた。
「みゃーこの世界の青は、こんなにも苦しかったんだね」
何か下手な励ましやアドバイスをくれるわけじゃない、ただぎゅっと力強く抱きしめてくれるだけ。そういうところだ、君の優しさは。どれだけ時間が経ったのだろう、呼吸が落ち着いた頃には、微かに赤みが差していた空は一面茜色に染まっていた。
私が恐る恐る君を見上げると、彼は申し訳なさそうに告白する。
「ごめんみゃーこ、俺一つ嘘ついてた。実は怪我したんだ」
怪我
君の表彰されていた姿が脳裏で再生される。それは選手生命を脅かす不穏なワードだった。嫌な予感は的中したようで困ったように笑う君に胸が痛くなる。
「膝やっちゃってさ、もう高校の間はバスケやっちゃ駄目って医者から言われてたんだ。みゃーこに会う前にバスケの練習してきたってあれ嘘。本当はずっと一人体育館の隅でリハビリしてた」
「え……」
「大事な場面で俺が怪我したせいで先輩は最後の大会、県大会に行けなかったんだ。俺、どうしてもバスケ部に居ずらくてさ。文化祭の日、本当はチームのメンバーで回ろうって約束してたけれどドタキャンした。最後の大会を台無しにしたメンバーがいても、しらけるだけだろ?そのまま帰ろうと思ったんだけど、偶然美術室からすすり泣く声が聞こえてきたんだよ。『これ幽霊じゃね?』って好奇心が勝って寄ってみた」
『何で泣いてるの?』
たった今ここで君が言ったかように、過去の五十嵐の空耳がした。当時の私は五十嵐が苦手だった。人が泣いてるときに普通話しかけてこないだろ、と心の中では早く帰って欲しいと願っていた記憶がある。
「実際は幽霊なんかじゃなくて一人で泣いてるみゃーこだった。最初は吃驚したよ、けどみゃーこの反応がいちいち面白くてさつい意地悪したくなっちゃって、案内人に任命したんだ」
案内を依頼された時も正直面倒くさいと思った。
だって、普通こんな校舎の隅で展示されているちっぽけな展示に解説なんていらないだろう。各々がゆっくりと自分なりの解釈で見ればいいじゃん。どうして不幸なことが立て続けに起こるんだろうと自分の境遇を嘆いていた。提案したのは五十嵐なくせに反応薄かったし。
私が思っていたことが伝わったようで苦笑いを浮かべる君。
「正直言うと最初の方の作品はあんまし記憶にない。どれも個性よりもどれだけ本物を忠実に再現できるかとか、色の綺麗さだけを求めてて、ありきたりだなぁって思った。けど最後の作品だけは違ったんだ」
息が止まった。その瞬間、まるで魔法がかかったかのように微動だにできなくなる。
右頬が夕陽で染まる君と重なるのは、あの時の泣きそうな顔だった。
「ただの体育館なのに、全部がオレンジ色に染まってんだよ。白い柱も、舞台の深紅のカーテンも、フローリングの床も、空気も。他のメンバーの練習が終わった後、一人で体育館に残ってリハビリしている時の景色そっくりだった。俺、劣等感からリハビリするのがあんまり好きじゃなくて、ずっとひとりぼっちで残ってるあの時間が苦しかったんだ。
けど、俺が見ていた景色はみゃーこが描くことで、夕陽が差し込んで全部が煌めいていて、こんなにも綺麗だったんだって知った」
『じゃあ、君は天才だ』
あの日、君がくれた言葉を忘れはしない。天才だ、なんて言われたことは初めてだった。けれど、私は天才なんかじゃない。何なら凡人にすらなれないと思い込んで折角貰った言葉を蔑ろにした。
君はそれでも私の作品を好きだと言い続けてくれた。誰も認めてくれない私の絵を、君だけはしっかり受け止めてくれた。
みゃーこ、何度もそう呼ぶ声は相変わらず優しい。
「俺がみゃーこの作業を見るのが好きなのは、みゃーこが前に進む気持ちを教えてくれるからだよ」
君は頬を緩ませ、目を細める。
「あれだけの過去があったら絵を描くことが嫌いになってもおかしくない。それでも描きつづけられるのは、誰にも負けることのないみゃーこの想いの強さだ」
「……そんなことない、私は弱いよ。それに私は何の面白みのない絵しか描けない」
「みゃーこはよく自分の絵のことをつまらない絵だって言う。誰にも評価されない絵だって。けれど、みゃーこの絵はちゃんと俺に届いた。だから、つまらない絵なんかじゃない。誰かの心を震わせられる絵だ。誰かの心を掴める絵だ。誰かを泣かせることのできる絵だ。
他の人から厳しい言葉を言われたって無視しておけばいい、馬鹿にされたって鼻で笑っておけばいい。みゃーこの世界はみゃーこのものなんだから、誰かがそれを汚したり酷評したりする権利はないんだよ」
あたたかい指が目の縁をなぞる。零れる雫を受け止めてくれようとしているが、大粒の涙は乾いた砂浜を濡らした。波の音が小さくなる。海が穏やかになるのに反比例するように、私の泣き声は大きく夏の空に響いた。
「誰にも評価されないんだったら俺が死ぬまで証明するよ。苦しみながらもみゃーこが重ねてきた色はみゃーこの生きた証そのものなんだって。つまらなくなんかない、沢山の想いが積み重ねられた絵はどの作品よりも綺麗なんだって」
優しくされればされるほど、胸の奥の軋む音がボリュームを上げる。
けれど私が今後どれだけ作品を作り上げたって、そこに青が重なることはない。そんな絵を誰かと比べて、これが私の人生なんだと言うのは気が引けた。
しかし、私がそうやって考えるのはお見通しだったようだ。底なしに明るい声が私の俯いていた顔を上げさせる。
「けど、俺がどれだけ言ったって君は卑屈になるだろ?だからさ、とっておきのおまじないしてあげるよ」
おまじない?私が首を傾げると君はこちらに向けて手を差し出してくる。私は反射的に自分の右手を重ねると、君は急に走り出した。転ばないように私も濡れた砂を蹴る。
向かう先は海だった。
「え!ちょ、いがらし?!馬鹿なの?……やめっ!」
「息止めて!」
次の瞬間、私の顔に水飛沫がかかる。胃が浮くような感覚のあと、コポコポと何かが耳を塞ぐ音が聞こえた。ゆっくり目を開けるとそこはあの日みた景色と一緒だった。下は真っ暗で今にも吸い込まれてしまいそうな程深い。怖い、助けて死んじゃう。体がゆっくりと、しかし確実に下へ下へと引きずり込まれていくのが分かる。セーラー服の赤いスカーフが水中を揺蕩う様子が視界の端に映った。突然、私の歪めた顔に、何かが触れた。それはもう一度、私の閉ざされた瞼を撫でる。私はゆっくりと瞼を持ち上げた。
目の前にいたのは君だった。
おかしなくらい穏やかな顔をしている君は私の腕をゆっくりと引く。段々と距離が縮まり、君の腕が背中に回された。恐怖心はいつの間にか消えて、私はただ呆然と君の一挙手一投足に見とれる。君の背後は明るい青だった。光の差し込む美しい海の中、五十嵐は馬鹿みたいに笑っていた。
君の口から零れた二酸化炭素が小さな真珠のように連なって浮上していく。
君が私を光の方へ導いてくれる。その手は離さないとばかりに力強く、繋がっていた。
「……っはぁはぁ」
「うげっ……はぁ、くるし」
白波を立てて浮上した私たちは息を忘れていた。必死になって酸素を貪る。海水が喉に入ったのか、咳き込みながらも声をあげて笑う君の肩を私は思い切り叩いた。
「くるし、じゃないわ……ばか……あほ」
「痛った!どこにあるんだよそんな馬鹿力。ほら呼吸整えて」
「五十嵐のくせにっ……なんで息切れてないの……はぁ」
滑る砂を蹴り、何とか波打ち際まで辿り着く。そこで力尽きたのは君も同じようで仰向けに倒れこんだ。夕陽が地平線に滲んでいくのが見える。遠くの空からは一際明るい水色の光が見えた。
「大丈夫だったろ」
静寂を破る声。何が、という感じだが、ふと横を盗み見ると満足そうな表情を浮かべている五十嵐がいた。
「俺は死なないし、みゃーこも死なない。絶対に死なせない。どれだけ沈んだって必ず明るい方に連れてく。掴んだ手は離さない。だからどうか怖がらないで。きっとみゃーこの弟くんも自分のことで大好きなお姉ちゃんが苦しむなんて望んでないよ」
もう一度重ね合わせる二つの掌。私が握ると更に強い力で握り返された。
弟は私のことを許してくれるのだろうか。
その時、水色の星が頷くかのように強く光る。驚いて目を見開いてしまった。……じゃあこれがひとまず弟が許してくれた合図だとしよう。これがもし勘違いだとしても、天国で会った時に許していなかったら私が地獄に落ちればいいだけだ。
「どうだった、今の海。やっぱり怖かった?」
「……ううん。綺麗だった。最初は怖かったのに、もう死んじゃうかと思ったのに、五十嵐がいつもみたいに笑うから。この人は必ず私を引っ張ってくれる、絶対大丈夫だって思えた」
青い視界の中見せた君の笑顔は、私のトラウマを払拭したのだ。
安心させるような表情に私は水中だと言うのに泣きそうになっていた。
自分と相手が共鳴したり、相手を見た瞬間胃の裏から焼けるように熱くなるその感覚。聴覚も触覚も何もなくなって、ただ視覚だけが研ぎ澄まされるその瞬間。
これも運命だと言えるのだろうか。
「五十嵐の世界の青はこんなにも美しいんだね」
君は一瞬驚いたような表情をしたあと、また屈託のない笑顔で「だろ!」と答えた。
先ほどからどうしたのもか、五十嵐が色々な表情を見せる度に心臓がぎゅうっと絞られたように痛む。冷え性なはずなのに、足の先から中指の先端からじわりと熱が滲んでくる。
流石に高校生なので、この気持ちの正体を知っていた。
どうやら、私は君のことが好きになってしまったらしい。
「いがらし」
「ん、どうした?」
言いかけた言葉をぐっと飲みこんだ。今はまだ、伝える時ではない。いつかまた私の絵が君の運命となったら、その時にちゃんと言おう。言葉に出来ない程のありったけの想いを告げよう。
だから、それまではどうか今までのような関係であってほしい。私が前に進んでいく姿を、笑いながら見届けて。
「私、やっぱりコンクール用の絵を描き直そうと思う」
帰ったら赤く染めたキャンバスをもう一度白く塗りつぶそう、そう思った。
悩んで重ねあげた今までの私も大切だけれど、新しい自分が描く絵で挑戦してみたい。
気づいたのだ。人の評価を気にするような絵じゃなくても、誰か一人に届けばそれでいい。そして、願わくばその相手は君がいい。
我儘だろうか、そんな願いは。
「そっか、俺楽しみにしてるわ」
嬉しそうな口元がそう形作る。君にそう言ってもらえると、私は何でもできる気がした。
「早く帰ろ、風邪ひいちゃうよ」
「そうだな。あ~髪べとべとする~!!早く風呂入りてぇ」
「知ってる?馬鹿は風邪引かないから、そんなに早くお風呂入りたかったら学校のプールで髪洗ってくれば?」
「るせえよ!馬鹿は風邪引かないってそんなの迷信……あれ、確かに俺風邪引いた経験……?」
「……つまり、純度百パーセントの馬鹿ということで間違いない」
「おいこら待て、言ったな?」
私の言葉に君は猛牛のごとく追いかけまわしてくる。しかしムキになればなるほど砂浜に足が縺れるようで、その場で激しく転倒した。その姿があまりにもおかしくて、間抜けで、私は声をあげて笑ってしまう。君も痛ったぁと顔をしかめた後、つられて笑った。
今日で怖がりな自分とは卒業だ。これから私は君が教えてくれたこの鮮やかな世界を、歩んでいく。
明日の放課後、私はあの新品のチューブを手に取って筆に含ませるのだ。きっと隣では五十嵐が輝く瞳で私を見ていてくれるだろう。
何も恐れるものはない。ただ描こう、私の世界に広がる私だけの青を。