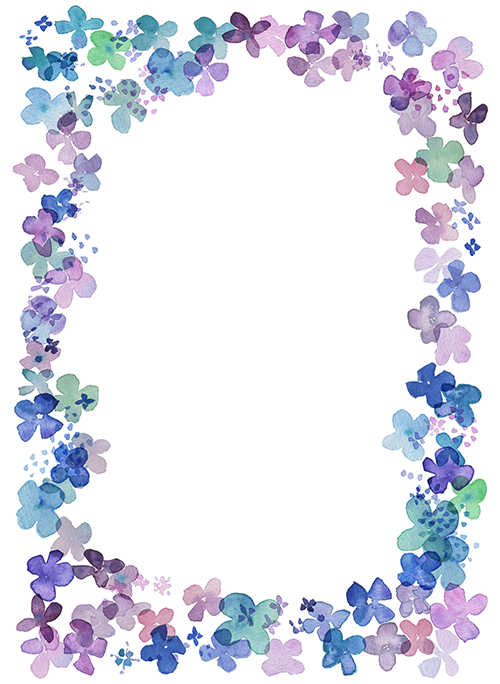青は嫌いだ。
美術部員のくせに何を言っているのだと自分でも思う。青が無くちゃ緑も紫も作り出せない。三原色が青を抜いてしまえば表現の幅がぐんと減る。そんなの良く分かっている。
けれど、どうしても怖いのだ。
鮮やかな青は私のトラウマを連想させる。思い出すと息が苦しくて窒息してしまいそうな程の二酸化炭素が肺を圧迫する。そのうち何も考えられなくなって、何で生きているんだろうという気持ちになるから、嫌だった。
目の前に広がるのは暖色で統一されたキャンバス。今日は少し大きな作品にチャレンジしようと思っている。街の丘から見える景色と広がる夕陽。青を一切使わずに描き上げるとなるとどれも同じような色ばかりで単調になってしまう。
黄色、橙、唐茶色
何度も何度も迷う筆。歪な配色。
悩みながら重なる色は自分自身のことのように思えた。
使おうとした茜色が丁度パレットから消えていたので、使い古した百均のプラスチックケースから赤色を取り出そうとする。しかし、見たくもないのに何故か一番最初に目に飛び込んできたのは、まだ表面にハリがあるターコイズのラベルのチューブだった。
「っは……」
怖い
ケースに取り残された手がまるで別の生き物のように震える。軽いケースは簡単に持ち上がり、手の振動と連動してガタガタと音を立てた。浅くなる息にますます恐怖心が掻き立てられたその時。
「みゃーこ」
聞き覚えのある声と同時に震える手のひらに長い指が重ねられた。
「……五十嵐」
「うわ、手え冷たっ⁈みゃーこって冷え性?」
場違いな程に明るい声色が美術室に響く。君の大きな声はこの部屋だけに留まらず廊下の奥まで突き抜けてしまいそうだ。
私のことをみゃーこと呼ぶこの男は少し変わっていた。
こいつはバスケ部のくせに練習が終われば必ず美術室に遊びに来る。そして対して進みもしていない絵の進捗状況を確認してくるのだ。私がいくら怒ってもヘラヘラ笑ってまた次の日には何事もなかったようにやって来た。
私が呆れたようにため息を吐くと、君は反対に嬉しそうに笑う。
みゃーこのファンだから許してよ!、それが君の口癖だった。
「また新しく描いてるのか?」
「そ、今度のコンクールに提出する用のやつ」
「相変わらず夕日がきれーだなぁ。これは全国金賞間違いなし!」
「五十嵐が思ってるほど、全国はそんなに甘くないよ」
「みゃーこの絵は一番だから」
そう言ってにっこりと笑うと、どこかから椅子を持ってきて私の横に座り始めた。特に何もすることなくじっとしているので、放っておくことにする。油のツンとした匂いが充満する蒸し暑い真夏の教室。こんな環境で作業しなければいけないことが前までは憂鬱だったけれど、君の瞳が光を反射させ、煌めきを纏いながら工程を見ていてくれるからまだ頑張ろうと筆を動かせた。
手元に熱い視線を感じるが居心地は悪くはない。寧ろ手の震えが収まらなかったあの瞬間、誰かが居てくれなければどうにかなっていたので来てくれて良かった。
君がいてくれてよかったと思うのは二回目だった。
一度目は初めて出会った日。
去年の文化祭、私は運悪く美術部の展示紹介の待機係になった。この係になってしまったらその日は一日美術室の入口で待機、つまり貴重な文化祭二日間のうち一日を強制的に潰されるのだ。くじ引きの結果、私が引いたのはアタリという名のハズレの赤色のくじだった。
「どうせ皆クラスの出し物の方に行くんだよ、チュロスとかお化け屋敷とかメイド喫茶とか……こんな油絵と水彩だらけの展示なんて見に来るはず無いのに」
ぽつりと不満が漏れる。
皆は楽しんでいる中、一人薄暗い美術室で待機させられている私。まだ六月の半ばだというのにその年の夏はとても暑かった。座っているだけなのに汗が滲んでくる。新築の一棟、二棟と違いここ南校舎は創設当初からずっと工事されていないのでエアコンはない。少しでもこの蒸し暑い空気を入れ替えようと窓を開けているのに、入ってくるのは疎らな蝉の鳴き声だけだった。
上の階からは楽しそうな歓声が聞こえてくる。
私も楽しみたかった。こんなところで一人で過ごしたくなかった。美術部のメンバーで一人でも仲がいい人がいれば、午前と午後で交代してもらえたのだろうか。交代してもらえたらその後一緒に校内を回って遊んだりしたのだろうか。
「いや、そんなわけないか」
美術部での自分の立場なんて分かっていた。
色が使いこなせない宝の持ち腐れ。
美術の世界では才能のありなしも命取りだ。幾ら絵を描くことが好きだったってある程度の画力がなければ何もできない。だからこそ、高い技術を持っている人は己の力を使いこなせなければ恨まれる。
私は青が使えない。つまり、青色のない世界で描いていかなくてはいけない。
色の鮮やかさと画力がセットとなって初めて評価されていた私は、あるトラウマの縛りによってその片方を失った。
皆が喉から手が出る程欲しいものをもっている私は、私が喉から手が出る程欲しい青色を持っていない。
中学最後に描いた絵は最優秀賞にまで選ばれて美術館に期間限定で展示された。沢山の人に見てもらえて、沢山の人が評価をしてくれた。しかし今は中学の時には取れていた市の佳作ですら全く取れない。
それが何を意味しているか、どれだけの期待を掛けてくれていた人が落胆し私に幻滅したか。
分かっていながらそれでも絵を描き続けている私はきっと馬鹿なのだろう。
唇を噛みしめる、けれど涙腺は耐えきれなかったようで緩んでしまったらもう戻れなかった。ポロポロと溢れる涙は止めを知らない。
ああ、一人で泣いたって誰も慰めてくれないのに何で。
誰か来てしまったらまずいので慌てて制服の袖で目元を擦る。それでも尚、雫は濃紺のスカートに更に濃いシミを作った。
「何で泣いてるの?」
「……え」
頭上から声がした。ゆっくり頭をあげるとそこには不思議そうにこちらを見下ろす少年の顔があった。詰襟のボタンを二つ開けた金髪の頭。間違いなく高校生活を楽しんでいるあっち側の人だ。私はもう一度袖に涙を染み込ませて彼を睨みつける。
「嗤いに来たんですか?」
「えっ!?何でそうなる?」
「どうせ惨めだなぁって思ったんでしょ。貴方みたいな陽キャ野郎には分かんないだろうね」
つい突き放すような言い方をしてしまった。完全に八つ当たりだ。冷静になれたのは彼が目を丸くした後だった。傷つけただろうか。視線を何処にしたらいいのか分からなくなって俯いていると、突然息が漏れた音が聞こえる。
「っはは……!」
その音は段々と大きくなり静かな廊下に響き渡った。一体何を考えているんだ、私の皮肉に気づかない程にこの人は頭の中がお花畑なのか。思っていることが顔に出てしまっていたのか、彼は私の怪訝そうな表情を見てまたツボにハマってしまったらしい。しゃがみ込んだままお腹を抱えて楽しそうな声をあげていた君が私を見上げたのは暫くした後だった。
「や、ごめん。あんなに『私今とっても不幸です』って顔で泣いてたのに、こんなに早口になるなんて思わなくて」
「失礼な言い方ね」
全く想像していなかった言葉に謝罪の気持ちを忘れてしまった。私が依然ツンとした態度を取っても「君本当に面白いね。表情がコロコロ変わって、見ていて楽しい気分になるよ」なんて言葉が返ってくる。
本当に何なんだ、こいつ。
次第によく分からなくなってきた。彼のことも、今の感情も。感傷に浸っている最中にノコノコやって来た彼のことが憎いはずなのに、行ってしまわないでと思う。このままくだらない会話を続けてほしいとも思う。
おかしいのは彼ではなくて、私なのかもしれない。
今の私は長い時間の待機で、どうかしてしまっている。
ぼうっとしながら君を見上げると、意外にも真剣な顔で入り口の説明書きに目を通していた。そういうのちゃんと読むタイプなのね。大体の人が読み飛ばしてすぐに展示に入ってしまうのに、不真面目そうな君だけは真面目に読んでいる。ちぐはぐな状況に思わず失笑してしまった。
読み終わった彼は何故かキラキラした表情で私を見つめてくる。
「案内してよ!展示の」
「なんで」
「何のためにそこ座ってるんだよ。案内するためじゃないの?まさかイジメ?」
「いや、違うけど……きっとつまらないと思うよ。うちの美術部、顧問が真面目だから油絵と水彩しかないし……アニメのイラストとかの展示が見たかったら漫研の方、」
「違うー!!俺は美術部の絵画が見たいんだよ、漫研には行かねえ」
「……なんで?」
「君、何でか知らないけど俺に偏見持ちすぎ!!俺ってそんなに美術興味なさそう?」
「うん」
「ひでえ」
君はいちいちオーバーリアクションだ。子犬のように潤ませた瞳が、穴が開くほどの視線を送ってくる。一応仕事だから仕方がないか。私は椅子から立ち上がると彼と一緒に展示を回ることにした。
これは先輩の絵で、これはグリザイユ画法ってのを使っていて、これは永遠をモチーフにしている作品で
色彩感覚は失ってしまったけれど知識だけは腐るほどあったので、沢山喋った。君は「ほーん」や「ふーん」と、理解しているのかしていないのか分からない反応だった。
「これって……」
最後の作品の前で足音が消える。君は今までとは違う表情を見せた。口を閉じることすら忘れて、食い入るようにキャンバスを見つめる。瞬きを我慢するように彼の長い睫毛が震えた。それほど真剣に、目に焼き付けるように、ただ目の前の作品を見ていた。
「この作品、好きなの?」
私が問いかけても届いていないようだ。
私はこの状況の名前を知っている。
自分と作品が共鳴したり、絵を見た瞬間胃の裏から焼けるように熱くなるその感覚。聴覚も触覚も何もなくなって、ただ視覚だけが研ぎ澄まされるその瞬間。
私はそれを運命と呼んでいた。
ぱちっと瞼が一度上下してようやく自我が戻ってきたみたいだ。錆びたロボットのような動作で振り返る。
「この作品は体育館?」
「そうだよ、ただの夕方の体育館」
「じゃあなんでこんなにも泣きそうになるんだろうな」
よく見れば窓から差し込む夕陽と重なる君の目の縁は淡い紅に染まっていた。私は今初めて君の瞳とちゃんと目を合わせた気がする。映りこむ橙とこげ茶色は触れてしまったら最後、壊れてしまいそうなほど繊細で澄んでいた。
「これ、君が描いたの?」
「うん」
「じゃあ、君は天才だ」
君の真っ直ぐなその言葉を私は素直に受け取れなかった。だって私は天才なんかじゃない。
ぐちゃぐちゃな表情を隠すように君より先に出口に向かった。しかし、後ろから伸びてくる掌で早歩きする私の肩が引き戻される。やめてよ、こんな顔見られたくない。私が困ったように見上げると君は眉尻を下げ、安心させるような微笑みを浮かべる。
「君、じゃ寂しいから名前教えてよ」
「……都島呉羽。都に島に呉服の呉と羽で、都島呉羽」
「都島サン?なんかどっかで聞いたことあるような」
「同級生だからね」
「え、まじ?ずっと歳下だと思ってた、ってなんで俺が同級生だって知ってんだよ」
「五十嵐でしょ。でっかいバスケの大会で最優秀賞とったとか何とかいう」
ずっと何処かが見たことのある顔だと思ったら今思い出した。彼は先週の朝会で表彰されていた、どうやらバスケの優秀な選手らしい。私はスポーツについては詳しくないが、遠くの舞台で校長先生から貰うトロフィーの数々はどれも一つ一つがとても重たそうに見えた。
「都島サン……は長いからみゃーこでいい?」
「なんでみゃーこなの。それじゃあ猫の名前じゃん」
「都島の都でみゃーこ!いいでしょ、俺ってネーミングセンスあるからさぁ」
「調子に乗るな」
気を抜けばすぐに軽口を叩く君。私は小さくため息を吐く半面、心の中ではこの五十嵐という変な男と話している時間が、高校に入ってから一番楽しい時間だったと気づいた。否、そんなこと口が裂けても彼には言ってやらないが。
喉の奥で痞えていた蟠りがすっと溶けて消えていく。
涙はいつの間にか引いていた。
リノリウムの廊下を私より三歩先に進み、「俺そろそろ行くわ」と言った五十嵐に一言ぶつけてやる。
君に負けないくらいの大声を出してみたかった。
「きっ、来てくれてありがとうございました!」
君の
驚いた表情を一瞬で崩し破顔する姿と、大きな手のひらが今でも忘れられなかった。
「みゃーこ、大丈夫?」
ふっと現実に引き戻される。私は首を振って目の前の作品と彼の姿を交互に見比べた。彼には私が放心状態になっているように見えたらしい。いつも私がぼうっとしている時は大抵スランプになっているので心配してくれたようだ。今にも手から滑り落ちそうになっている筆に気づき持ち直すと再び作品に向き合った。
「ごめん、ちょっと昔のこと思い出してて」
「どんなこと?」
「初めて五十嵐が美術室に来た時、居てくれて良かったなぁって」
自分でも驚くほど素直な言葉が零れた。彼も意表を突かれたような顔で私を見つめる。
「マジで大丈夫?熱ない?明日雪でも降るんじゃね」
「そうやって冗談言っときながら、ちょっと顔赤くするの辞めて」
「やー、だって仕方ないじゃん」
仕方なくないでしょ、と突っ込んでまた作品に目を向けようとすると、不意に冷たい人差し指が私の頬に触れた。そのまま無理やり五十嵐と顔を突き合わせる形にさせられる。折角の作業を中断された私は不満が伝わるように口角を下げた。
それでも五十嵐は構わず、先ほどとは全く違う真剣な眼差しを私に向ける。
「ねぇ、なんで今日は目え合わせてくれないの」
「えっ」
「いつもはどんなに作業が忙しくても、俺が話してるときはちゃんと目を合わせて聞いてくれるだろ。なのに今日はキャンバスばっかり。おまけにいつもは言わないようなこと言うわ、意識飛んでるわで、気づいてないとでも思った?」
図星だ。私は反射的にびくっと肩を震わせる。けれど、今日はどうしても君に向き合う気にはなれなかった。それを君に気づかれているのは想定外だったが、薄々察しているんだろうなぁとは私も感じ取っていた。
でも、貫き通さなきゃ。自分をいつもの強気なみゃーこの仮面で偽らなきゃいけない。
君に心配は掛けたくない。君にはただここでくだらない話をこれからもずっとしてもらいたいのだ。明日も、その先も、卒業してしまうまで他愛無い会話をして君に笑っていてもらいたいのだ。
その為には、この関係にヒビを入れてしまってはいけない。弱い自分を見せて幻滅してほしくない。
「何のこと?それよりほんとに邪魔しないでくれない?コンクールただでさえ提出ギリギリになりそうなのに、完成しなかったらどうするの。顧問に五十嵐が邪魔してきましたとでも、」
「惚けるくらいだったらその涙拭いたらどう?」
意思と体は時々結びつかなくなってしまう。
強い自分でありたいと思えば思う程、目頭からは熱いものが溢れた。駄目だなぁ私。絵も描けなければ、嘘も吐けない。何も出来やしない。私はせり上がる嗚咽を堪えて声を絞り出した。
「でも、きっと五十嵐の中の私のイメージが崩れちゃう。言いたいことが全部ぐちゃぐちゃで、頭と言葉が支離滅裂になっちゃって、何も伝わらない。五十嵐幻滅する」
そうやって言っておきながら君が誰かに対して失望しない人だってことは分かっていた。きっと口にしないだけで気づいているだろう、私が青に触れられないことを。それでも君は私の絵を評価してくれた。他の人が描けなくなった私から離れて行く中、君は、いつも同じような色遣いでつまらない絵を、みゃーこだけの世界だと言ってくれる。
そんな君に私は甘えていた。向き合うことを忘れて、何でも受け止めてくれる五十嵐がいればそれでいいと諦めていた。
そしていつか彼が私のことを認めてくれなくなる日が来たら突き放せばいいと考えていた。我ながらなんて自分勝手で酷い奴なんだろうと思う。
「みゃーこさ、なんでいつも唇噛みしめてるの」
思わず呆けた声が出た。咄嗟に唇に触れると指先に血が付きその表面はガサガサになっている。
「そうやって一人で我慢して、一人で気持ち抑え込んで。それの何がいいの?何が偉いの?そんなことされても俺、全然嬉しくないんだけど」
君の初めて見せる怒りの表情に硬直してしまう。でも、と言いかけてその息は喉に詰まる。何か言いたいのに何も言えない。
「雰囲気壊したくないからとか、自分の辛いこと話して受け止めてもらえないかもとか、それもうテレビに映るコメディアンじゃん。テレビに写っているタレントがそうやって視聴者の気分を害さないように気を使うのは分かるよ。けど違う。みゃーこはみゃーこでただの人間なんだよ。自分のしんどい気持ち吐き出さなきゃ生きていけないんだよ。そんな当たり前のことを憚れるくらいに俺のことが信じられない?俺のこと怖い?」
そんな訳ない。
五十嵐は私の人生を狂わせてしまう程の大きな歯車だ。自信も幸せも無かった私の生活が、君といるだけで心が安らぐようになった。描くことが怖かった絵が、毎日会話を重ねるように色を塗り重ねられるようになった。もう今となっては替えは見つからない大切な存在だ。
添えられた指が私の目尻の雫をそっと拭う。その手つきは酷く優しく、それでいてあたたかかった。
この手を離してはいけない、そんな直感が働く。いつまでも立ち止まってはいられない、逃げようったってそうはいかない。じゃあ私は君が差し伸べてくれた手を掴みとって今、進むべきなんだ。強いみゃーこじゃなくて、脆い呉羽を君にさらけ出すべきなんだ。
信じたい、君にもっともっと沢山のことを知ってほしい。
「……ごめん、五十嵐。さっきの言葉忘れてもらっていい?」
付いてきてほしい場所があるの。
君から言葉が発せられることはなかった。代わりに返ってきたのは瞬きと頷きだけだった。