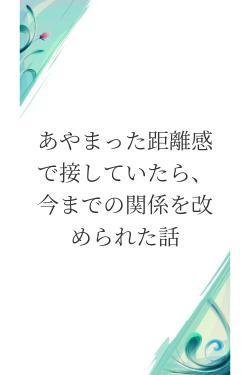その男は、急に現れた。
「今日から入部しました。
廣中です、バレーは初心者です」
一つ上の、高校二年生。
経験者の俺とは違う、初心者。
つまり、ノーマークで大丈夫って事だ。
一ヶ月後に、大きい試合がある。レギュラーに選ばれたくて、現在、必死に足掻いている俺。
最近は順調だから、このままいけば、きっとレギュラーに選ばれる。あのコートの上で、俺は戦えるんだ――と。
そう思っていた。
バレー初心者の廣中が、メキメキと頭角を現してくる、その時までは――
「廣中、お前は背も高いし、パワーもある。バレーのセンスがあるよ」
「え、本当ですか!?
やった、嬉しいです!」
三年の先輩から、思わぬ言葉をかけてもらった廣中先輩。頬は緩みまくって、デレデレ顔。
素直に喜んじゃってさ。
さっきの言葉を、廣中先輩は素直に受け止めてる。「きっとお世辞だろ」って、普通は、そう思わねぇ?
「気に入らないな……」
俺と違って、素直すぎるところも。俺と違って、バレーのセンスがあるところも。
廣中先輩の全部が、俺にとって、とてつもなく気に入らなくなってきた。
ぽひゅん
「あ……」
その時、ボールが手から滑り落ちる。テンテンと情けない音を立てて、ボールは床を転がった。
しまった……。
現在、部活中。
この大事な時期に、考え事をするなんて。
「おーい、木口〜。
これくらいのボールはとれよ。お前に期待してんだから、頼むぞー?」
「はは……、すみません」
三年の先輩に言われ、思わず、頭をかく仕草をする。ボリボリと、頭皮をかく音が、俺に反響する。
そんな中――
『廣中の”次に”お前に期待してんだから。頼むぞ』
あちらこちらで、ボールがバウンドする音。それに混じり、俺が勝手に作り出した副音声が、脳内に響き渡る。
先輩は、一言だって、そんな事を言っちゃいないのに。
「……はぁ」
――期待してんだから
せっかく、先輩が言ってくれてるのに。
なんで俺は、素直に受け取れないのか。
俺みたいな奴を、ひねくれ者って言うんだよな。
そんなの、自分が一番、よく分かってる。俺は素直じゃない、って。
イヤっていうほど、分かってるんだ。
「……っ」
ギュッと拳を握り締めた、その時。
――やった、嬉しいです!
廣中先輩の素直な受け答えが、記憶から蘇る。
「……はぁ」
俺も、あんな風に言ってみれば……
何か変わるのかな。
◇
「と、いうわけで。
以上のメンバーで、次の大会に出場する。皆、よろしく頼むな!」
「はい!!」
「……っす」
部員が、大きな声で返事をする中。俺は、一文字を呟くのが、やっとだった。
レギュラーに選ばれなかった――
それは、今までの頑張りを認めてもらえなかったような。そんな虚無感の塊を、胸に抱くようなものだ。
「や~ヒヤヒヤしたなあ」
「明日からはレギュラーメンバーで練習だってよ」
「ひゃー、大会まで体がもつかねぇ」
「おーい一年、片付け急げ~」
「……っす」
先輩たちが、俺を通り過ぎていく。
片付け……、あぁそうだ。
ネットを外さなきゃいけないんだった。
だけど――体が動かない。
足に重りをつけてんのか?ってくらい、体がズッシリ重い。頭は寝てんのか?ってほど、思考を停止している。
「俺、どうしちゃったんだ……」
はぁ――と。
重たいため息をこぼす。
すると、その時。
お椀型にした誰かの手が、俺の口に近づいてくる。そして、パカッと。お椀をひっくり返したように、俺の口に蓋をした。
「……は?」
お椀の中だと、くぐもった声になる。
クソ、話しずらい。
「おい、どけよ」
お椀の手を、パシッと叩き落とす。
ってか、誰だよ。
無遠慮に、俺の口を塞いでるのは。
ギロッと、怒りを含んだ目で見あげる。
すると映りこむ、その姿。
「や、元気?」
「……」
それは俺の宿敵――廣中先輩だった。
俺からレギュラーの座を奪った、張本人。
「ため息は出さない方がいいって、何かで聞いたから。だから、木口くんの口に、戻しておいたよ」
「……ため息?
あぁ、さっきの……」
ってか、戻すって。
手をお椀型にしてたのは、俺が出したため息を、キャッチアンドリリースするためだったのか。
あほくさ。
「子供っぽいんすね。廣中先輩」
「あ〜下に弟がいるからかもね。
年が離れててね、可愛いんだよ!」
締まりのない顔で、デレデレ笑う廣中先輩。心底どーでもいい情報を出されたわけだが、何か返事をした方がいいのか? 一応、先輩なわけだし……。
「そういえば、大会がもうそろそろだね」
「っ!!」
前言撤回。
やっぱり俺は、この先輩を、敬わないことにした。
「レギュラーに……入ってましたね」
「うん、びっくりしたよ!」
「……俺もですよ」
経験者の俺を追い抜いて、初心者のあんたが、レギュラー入りするなんてな。
思いもしなかったよ。
どんなサプライズだよ。
そんな下克上いらねーよ。
そこは先輩らしく、次世代を担う後輩にボジションを譲れよ。
あぁ、もう――イライラする。
内心で毒づく俺に、全く気付いていない廣中先輩。目をキラキラさせて、今後の目標とやらを語り始めた。
「選ばれたからには、チームの役に立ちたい。大会まで残りわずかだけど、一緒に練習を頑張ろうね!」
「……」
誰がやるか。
と心では、そうぼやいて。高い位置にある小さな窓から、空を見上げる。
だけど――
「あ、二階にまでボールが上がってるね。
俺、とってくるよ」
「……」
視界の隅に、アイツの頭。
これ以上は、悪い意味で目に毒だ――
俺は急いで、顔を下げた。
◇
ガラッ
「あれ? 木口くん!」
「……」
体育館にて、シューズの紐を結んだ瞬間。イヤな奴と遭遇してしまう。
もちろん、言う間でもなく――
廣中先輩だ。
「朝早くにどうしたの? 今日は朝練の日じゃないけど」
「忘れ物っす」
ウソ。
本当は、こっそり朝練しにきたんだよ。
なのに、なんでアンタがココにいるんだよ。まだ朝の6時だぞ?
すると廣中先輩は、俺を指さした。
いや、正確には――
ニコニコしながら「俺が着ているもの」を指さしていた。
「ふ~ん、忘れ物ねぇ。
わざわざジャージに着替えて?」
「……」
廣中先輩は、鈍そうに思えて、案外に鋭いところがある。
気づかないフリをして出て行けばいいものを――なんて毒づきながら、何と言い訳をしようか悩む俺。
すると――
ヒュッ
パシッ
俺に向かって、勢いよくボールが飛んできた。なんなく受け取った俺は、コレを投げてきた張本人を、キツく睨む。
すると、その人――未だボールを投げたままのフォームで止まっている廣中先輩は、腕の隙間から、チロリと顔を覗かせた。そして俺を見て笑ったかと思えば、とんでもない提案をしてきやがる。
「二人きりで練習しようか」
「……絶対イヤ」
あ、やべ。
色んなことに、イライラしすぎたからか。つい本音が出ちまった。
すると、そのイライラを漏れなくキャッチしたらしい廣中先輩は、眉を下げ、困ったように笑った。
「木口くんってさ、俺のこと嫌いだよね?」
「……」
こういうのは、ムシに限る。
「本音を言わないと、今度から君のことを、きぐっちゃんって呼ぶつもりだよ」
「嫌いっす。その呼ばれ方も、先輩の事も」
あ、しまった――
と思った時は、もう遅かった。本人を前に「嫌い」だと、ストレートに言ってしまった。しかも、相手は先輩。
俺……シメられるかも?
だけど、心配は無用だった。さっきまで困ったように笑っていた廣中先輩が、ハジける笑みを浮かべたからだ。
「そっか。俺のことが嫌いか!」
「……あの」
「ん?」
ん?、じゃねーだろ。「嫌い」って言われて、なんで嬉しそうなんだよ。
「廣中先輩の、そういうとこ……イライラします」
「え、嫌いな理由まで話す感じ?」
「先に聞いてきたのは、先輩っすよ」
「え〜」
慌てる廣中先輩と、終始しかめっ面で答える俺。これじゃ、どっちが先輩で、どっちが後輩か分かったもんじゃない。
「本音でぶつかり合えば、もっと仲良くなれると思ったのになぁ」
「……」
ほんと、何も分かってない。先輩なら、後輩の扱い方くらい、心得ておけよ。
「俺は先輩の、そういう素直なところが嫌いなんすよ」
「えぇ……!」
あまりのショックからか、廣中先輩はクルリと向きを変えた。その背中に「しょんぼり」と文字が浮かんでいる。
「今、俺は沈んだ”フリ”をしてるよ」
「は?」
「木口くんに声を掛けて貰えれば、元気になるかもしれないなぁ」
「それ……」
つまり、慰めろってか?
でも、フリなんだろ?
本当に沈んでるわけじゃ、ないんだろ?
高校二年生が、何やってんだか。
白けた目で、俺よりも大きい先輩を見る。
「そういう子供っぽいところも嫌いっす」
「わ~ストレートすぎて凹んじゃうなぁ」
嫌ってる相手を、どうして鼓舞しないといけないんだ。
冗談じゃない。
凹みたいのは、こっちなんだ。
俺からレギュラーを奪いやがって。
本当、どこまでも大人げない先輩だ。
「じゃあ、俺はこれで」
やめだ。もうボールを触る気もしねぇよ。今日は厄日だ――そう思って、回れ右をする。
すると、キュッと。床にこすれたシューズが、音を立てる。それと同時に――
「俺ね」と。渦中の先輩が、唐突に身の上話を始めた。
「小さい弟がいるって、そう言ったでしょ?今はもう年長さんだから、そうでもないんだけど……。昔は病弱でさぁ。よく保育園を休んでたんだ」
「……は?」
いや、知らねーよ。アンタの身内の話なんて、聞きたくねーっての。
だけど、俺が顔をしかめたのを、見て見ぬ振りした廣中先輩。
「弟はかわいいよ」――と。
俺に言っているようで、自分に言い聞かせているような……そんな口調で話す。
「可愛いんだけど、両親は共働き。
そんな両親が頼れるのは、俺だけ。
だから――
弟が小さい頃はさ。
放課後、自分の時間なんてなかったよ。
まっすぐ家に帰って、弟の世話。
まぁ、それもそれで……今となっちゃ、いい思い出なんだけどね」
「……」
あぁ、そうか。だから先輩は、変な時期に入部してきたのか。初心者だった理由は、今までクラブや部活に、入る時間がなかったって事か。
……ってか、なんでバレーに入ったんだよ。何もした事がなかったんなら、別にバレー以外でも良かっただろ。
「今、”なんでバレー部に来たんだ”って思ったでしょ」
「っ!」
くそ、やっぱ廣中先輩。
妙に、勘が鋭い……!
だけど、俺が廣中先輩を嫌っているのはバレてることだし。ここは素直に、嫌味の一つでも言っておくか。
「レギュラーを奪われた身からしたら、そう思うのが当然じゃないすか?」
「ふふ、言うねぇ。バレーを選んだのはね、家のテレビで試合を見たからなんだ。
高く飛んで、ボールを打って、仲間とハイタッチをする――それはどんなに気持ちがいいんだろうって、考えるだけで楽しかった」
その時。
廣中先輩は、開いている体育館の窓から、外を見た。回顧するように、目を細めながら――
「弟の看病をして、家に引きこもる日が続いた時。こうやって、窓の外をよく見ていた。こんな事、たぶん思っちゃいけないんだけど……」
――いいなぁ。俺も外に出て、皆と遊びたい。自由になりたい
「ダメなお兄ちゃんだよね。病気の弟を前に、そんな事を思うなんてさ」
「……」
うすうす、思っていたことがある。
廣中先輩は、部活の時、妙に張り切っていた。元気ありまくりの、熱血タイプ――それが、廣中先輩へのイメージだ。
だけど、そうか。
どうして、そのイメージがついたのか。
やっと、溜飲が下がった。
「ようは先輩、はしゃいでたんですね」
「え、はしゃぐ?」
「放課後、好きな部活を出来るのが嬉しかった。そういう事ですよね?」
「そ……」
そうなのかな――と呟いた先輩の顔。
それは、照れくさそうな顔。
そして、なんだか幸せそうな顔。
「そっかぁ、俺……嬉しいんだね」
「……」
「なんで、そんな渋い顔をしてるの?」
「……ウザ」
えー! ひどいー!
なんて声を、今度は俺が、背中で聞く。
「やっぱ気に食わねぇわ、この先輩」
「ん? 今なにか言った?」
いえ、何も――と返事をして、体育館の扉を目指す。その時、俺は冷や汗をかいていた。
だって――
「大会頑張ってくださいって、思わず言いそうになっちまった」
あの先輩を見ていると、俺まで「素直」に染まっていくような気がして……。そんな「そこはかとない不安」に蓋をするように。
俺は急いで、体育館のドアを閉めた。
◇
それからというもの。俺は、気づけば廣中先輩を、目で追うようになっていた。
すると、思わぬ事に気づいてしまう。
「熱中症、じゃないと思うけど、ちょっと休んだ方が良さそうだね。誰か、氷嚢を持ってきて。
あてる場所は、出来るだけ血管の太いところ。首の後ろとか、足首とかも良いよ」
「え、タンコブ? 頭は大事だからね。保健室に行こう。病院にも行くかもしれないから、荷物も持って行ってね」
気づいたこと――それは、廣中先輩の「面倒見の良さ」だ。
弟がいるだけあって、男子部員を束ねるのは、お茶の子さいさい。それに、弟の看病をよくしていたせいか、怪我や病気にも知識がある。そのため、マネージャー不在のバレー部に、廣中先輩は重宝された。
「うん。もう大丈夫そうだね」
「廣中、サンキュ~」
「鼻血はビックリするよね」
だけど……
重宝されすぎて、先輩がコートに入っていようがいまいが。お構いなしに、ヘルプの招集がかかる。
「悪いな、廣中。お前もレギュラーの選手だってのに」
「良いんですよ、困ってる時はお互い様です」
「なんだよ、ソレ……」
しばらく収まっていた俺のイライラが、再び、沸々と湧きあがって来た。
なにが「困ってる時はお互い様」だ。じゃあ、アンタが弟の看病で困っていた時、誰かが助けてくれたのかよ。
今だって「コートに入っていたい」っていうアンタの願いを、ここにいる誰が叶えてくれんだよ。
「廣中~」
「あ、はい!」
自分の願いとは裏腹な現実を前にしても、それでもニコニコ笑う廣中先輩がムカつく。何でもありませんって顔をして、たまに窓から外を見ているのがムカつく。
なぁ、廣中先輩。
今、先輩の目に写っているのは……体育館じゃないだろ? 病気の弟と一緒に過ごした部屋の窓――そこから見える景色が写ってるよな?
それなのに、どうしてニコニコ笑ってられるんだ。
――いいなぁ。俺も外に出て、皆と遊びたい。自由になりたい
あの時、俺に話してくれた先輩の本音は、どこに行ったんだよ。
「や~廣中。お前、本当にいい腕してるよ」
「本当ですか? 嬉しいな」
「ほんとほんと。選手じゃなくて、マネになってもらいたいくらいだ!」
「いやぁ……はは、参ったな……」
その時。
部員の膝をテーピングしていた、廣中先輩の手が止まる。ピタリと。
まるで、自由を奪われたかのように――
「俺は、マネじゃなくて……」
口を動かして、必死に何かを言おうとする先輩。その脳内は、きっと今、ミキサーでグチャグチャにされているだろうと、簡単に想像がつく。
それくらい……さっきの一言は、先輩にとって破壊力がありすぎるものだ。
だけど――悪い事は続く。
「廣中、いるかー?」
「……先生?」
この場に登場した、廣中先輩のクラスの担任。体育館では見かけない顔に、俺も部員も、何事かと動きが止まる。
そんな中、担任の声が響いた。
「さっき親御さんから電話があった。弟さんが熱が出たから、部活をきりあげて早く帰ってきてほしい、との事だ」
「!」
「スマホが通じないって、嘆いてたぞ。今度からは、いつでも連絡とれるようにな。
じゃ、そういう事だから。早く帰ってやれよ?」
「……はい」
この時。
廣中先輩の手から、ボールが滑り落ちる。このボールを持って、コートに入ろうとしていた足。それは――既に体育館の出口へと、向きを変えていた。
「廣中、弟がいたんだな!」
「熱なんて大変じゃねーか、早く帰ってやれよ?」
「こっちの事は、心配すんな!」
「お前ナシでも、何とか回して見せるからな!」
「……はい、すみません」
頭を下げる、廣中先輩。
だけど――なかなか顔を上げない。ふと先輩の手を見ると、ギュッと、拳が握られている。手が白くなるほど、固く……。
その拳の中に、先輩は何をしまい込んだのか。俺は、そんな事が気になった。
だから――
ドカッ
「う、わ!?」
「わー! 木口! 何やってんだ!」
「先輩に堂々と飛び蹴りすんなよ!!」
いつまでも顔を上げない先輩に、華麗な一発を食らわせてやる。すると、大きな体は、いとも簡単に吹っ飛んだ。
ガシャン
一度、前転をした先輩。久しぶりに見せた顔には、汗だか涙だか分からない雫がついている。それがまた――
俺はなぜだか、気に入らない。
「先輩、住所を教えてください」
「へ? 住所?」
「先輩の住所っす」
「俺の住所……、あ!」
その時。廣中先輩は俺の目論見に気付いたのか、口をへの字にした。
先輩の家庭の事情を、俺だけが知っている。そんな俺が「住所を教えて」なんて言うんだ。俺が何をしたいのか――
どうやら検討がついたらしい。
「ダメ、教えられない」
「そうだ。あと鍵もください」
「聞いてる!?」
チッ、いちいち反論すんのも面倒だ。
あ、そうだ。部室にある先輩のカバンを、根こそぎ持っていきゃ話は早いな。
俺はシューズを脱いで、ものの一分で二人分の荷物を、部室から持って来た。
だけど先輩はやっぱり、俺を止めたいらしい。ガシッ、と。俺の腕を、強く握る。
「行かせないよ。これは、俺がやるべき事だから」
「……」
うそこけ。
本当は、バレーがしたいですってツラ浮かべやがって。本当はコートにいたいですって、いつも思ってるくせに。
「先輩」
「え……」
俺は、先輩の手を握る。そして、優しくマッサージをするように、ムニムニと肌を揉みこんだ。
「ちょ、木口くん……!」
他の部員も「これから何が始まるのか」と、手で顔を覆っていた。だけど、その中の誰よりも顔を赤くしていたのは――廣中先輩だった。まったく、失礼なことだ。俺が何をすると思ってんのか。
「先輩、まだまだっすね」
「へ?」
「手のマメっすよ。
こんなツルツルの手でレギュラーとか。
――バレーなめんな」
「!」
キッと睨んだ俺にびくついて、小さくなる先輩。その顔は、今にも泣きそうだ。
「俺を押しのけて、先輩はレギュラー入りしたんだ。大会の日に自分がコートに立つのがどういう事か――死ぬ気で毎日練習して、俺を納得させてみろ」
「……っ!」
グッと、下唇を噛む廣中先輩。俺はわざとらしくため息をはき、部長を見た。
「部長――廣中先輩を、コートから出さんでください。この人がやるべき事は、部員の手当じゃありません。バレー。それだけです。マネが必要なら、募集かけてみましょうよ。じゃないと――
この人、前に進めませんよ?」
「ッ!」
廣中先輩が、俺を見る。
潤ませたその瞳の中に、過去の先輩が写っている気がした。それを早く拭けと言わんばかりに、俺は先輩にタオルを投げる。
「じゃあ、そういう事で。
部長、俺は早退しますから」
「わ、わかった……」
部長を見た後。
もう一度、廣中先輩を見る。
「コートにい続ける事が、先輩にできる“自分への手当”だ。だから――
そんな腑抜けた顔してる間は、絶対にコートから出るな。目障りだ」
「え……」
「なぁ、廣中先輩。
いつもバカ正直なのに、ここ一番って時に猫被ってどうすんだよ。見ててイラつくんだ。どうしようもなく、腹が立って仕方ない。
なんで、もっと自分に素直にならないんだよ」
「!」
俺は、先輩が持っていた氷嚢を、乱暴に奪う。
「さてと――熱がある時は、とりあえず水分だろ? あと、血管の太いとこに氷嚢をあて、体温を下げる。他に、何かあるか?」
「よく知ってたね、そんな事……」
「だって、」
俺は後輩だからな。
先輩であるアンタの背中を、今までずっと見て来た。目で見て技術を盗む――それが「後輩の役目」ってもんなんだよ。
「先輩が応急手当をしている姿を見て、看病に関しては、少し知識がついたつもりだ。だけど……所詮は、にわか知識だ。困ったことがあれば、すぐ電話させてもらうからな」
「わ、わかった。
あの……、木口くん!」
ヨイショと荷物を背負った俺に、先輩が声を掛ける。その手には、スポーツドリンクが握られていた。
「これ……、弟に飲ませてあげてほしい。弟は、熱を出した時、これしか飲まないから……」
「いーけど……。
コレ、部費で買ったもんじゃね?」
「あとで必ず返すよ。たまには俺も、素直にワガママを言わないとね。
あ、それと――」
「――……うざ」
耳の辺りで、先輩の弾んだ声を聞いた後は、いつも通り。
「ひどーい!」と嘆く先輩の声も背負って、俺は体育館を飛び出した。手の中には、先輩の家の住所と電話番号が書かれたメモ。そして、家の鍵。
「案外ちかいな。
部活で鍛えた俺の俊足、見とけよ!」
足を必死に動かす間、最後に見た先輩の顔を思い出す。
――ありがとう、木口くん
そう言いながら、先輩は、俺にメモと鍵を渡した。
その時。震える手と潤った瞳を、先輩が必死に隠そうとしているのが分かった。
「はぁ。何やってんだ、俺……」
先輩みたいになりたくないと、そう思っていたのに。蓋を開ければ、俺は、先輩よりも素直になっていた。言いたい事を言って、やりたい事をやっていた。
最悪だ……。明日から、どういう顔で部活に行けばいいんだよ。
ってかさ。
俺って、廣中先輩の家に初めて行くよな?
そこに、まだ会ったことない病気の弟がいるんだよな?
「……ヤバくね?」
脳裏に浮かぶのは、最悪のシナリオ。
――ドロボー! おまわりさーん!!
俺、通報されるんじゃね……?
大丈夫なのかよ、マジで……。
「あ~! もう、めんどうくせぇ!」
素直になんて、なるんじゃなかった。やっぱり俺は、ひねくれてるくらいがちょうどいい。
だけど、ちょっとだけ……。
――あ、それと。木口くん、ありがとう
――今だけ恩を売ってやるよ。お返しは、レギュラーの座。それだけだ
――ふふ。下剋上、楽しみにしてるね!
――……うざ
素直になるのは、ちょっとだけ気持ちが良かった、なんて。そんな事を思いながら、短い呼吸を繰り返す。
その時、体育館にあった高い窓を思い出し、顔を上げた。すると、そこには――
窓の形に収まらない果てしない空が、どこまでも広がっていた。
【完】