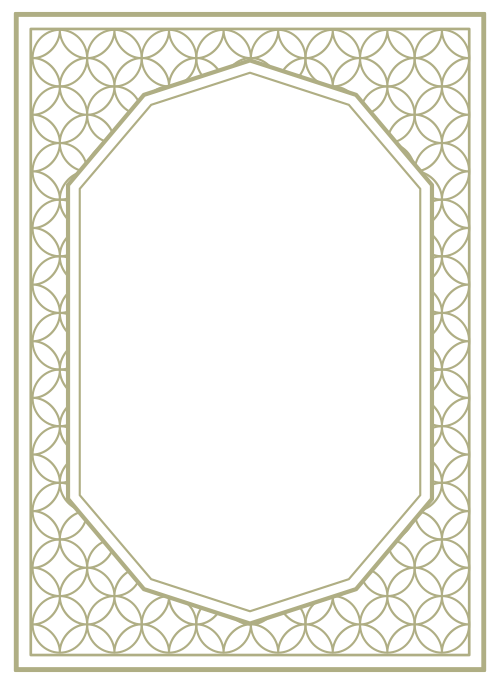「えっ!?」
村人同様、千代も驚いて見ると、扉の中からよろよろと出てきたのは水凪だった。……着物が焼け、ぼろぼろになって、袖から出る腕にはうろこが走り、うつろで大きな目が空(くう)を見る。
千代は水凪に駆け寄り、雨を降らせてくれるよう頼もうとした。すると水凪が何かぶつぶつと言っているのが分かった。
「水凪様……?」
「水凪様! ようお戻りくださった! 郷に雨を降らせてください!」
村人が口々に雨を、雨を、と言うも、水凪はそれを聞いていないようだった。ぶつぶつと独り言を繰り返している。
「おのれ、龍神め……。あの宝珠は我には強すぎる……。もっと力の弱い……」
そこで水凪の目がぎょろりと千代を見据えた。その恐ろしさに、ひっと思わず声が出てしまった。
「我の統べる沼が干からびてしまう……。娘、……その宝珠を寄越せ……!」
水凪はそう言って、あの時と同じように千代の首飾りを奪おうとした。すると。
今度も勾玉が光を放って水凪の手を拒絶した。バチっと音をさせて弾かれた水凪が後ろに吹き飛ばされて土煙が立つ。その土煙が消えた後に其処に居たのは、黒く薄汚れた水色の肌をした人の背丈ほどの蛟(みずち)だった。
「なんやと!?」
「龍神様じゃないぞ!」
「水凪殿、騙したのか!」
なんていうことだろう。神様だと思って接してきたのは、郷の沼に住むという蛟の妖怪だった。道理で水凪から沼の匂いがする筈だ。淀んだ沼の水は、それは気持ちが悪いだろう。
蛟を前に村人たちが責め立てる。蛟が、があ、と口を開いたその時、真っ青な天から蛟目掛けてパシン、と稲妻が落ちた。蛟はその勢いでその場に頽(くずお)れてしまった。
「ひっ! 龍神様がお怒りだ!」
「千代、早よ神様にお祈りしてくれ!」
「お怒りが俺らに向いてまう!」
「早く泉に入った罰当たり者を括ってしまえ!」
ひとりの村人の案に、他の村人がそうだそうだと賛同する。祈りをささげることには勿論賛同するが、それに千臣を巻き込みたくない。しかしこういう時、小さな村の中の異端児はたやすく吊るし上げられる。千代が止めてと叫ぶ中、千臣は後ろ手に縄を巻かれ、渇きの大桜に後ろ手のまま括り付けられると、神様に命を捧げろと村人に脅されていた。
こんなに恐ろしい村人たちを見たことがないと、千代は思った。いつも笑って千代を見守ってくれていた村人たちが、千代の大切な人を非道に扱い、命まで差し出せと迫っている。千代は泣いて村人たちに頭を下げた。
村人同様、千代も驚いて見ると、扉の中からよろよろと出てきたのは水凪だった。……着物が焼け、ぼろぼろになって、袖から出る腕にはうろこが走り、うつろで大きな目が空(くう)を見る。
千代は水凪に駆け寄り、雨を降らせてくれるよう頼もうとした。すると水凪が何かぶつぶつと言っているのが分かった。
「水凪様……?」
「水凪様! ようお戻りくださった! 郷に雨を降らせてください!」
村人が口々に雨を、雨を、と言うも、水凪はそれを聞いていないようだった。ぶつぶつと独り言を繰り返している。
「おのれ、龍神め……。あの宝珠は我には強すぎる……。もっと力の弱い……」
そこで水凪の目がぎょろりと千代を見据えた。その恐ろしさに、ひっと思わず声が出てしまった。
「我の統べる沼が干からびてしまう……。娘、……その宝珠を寄越せ……!」
水凪はそう言って、あの時と同じように千代の首飾りを奪おうとした。すると。
今度も勾玉が光を放って水凪の手を拒絶した。バチっと音をさせて弾かれた水凪が後ろに吹き飛ばされて土煙が立つ。その土煙が消えた後に其処に居たのは、黒く薄汚れた水色の肌をした人の背丈ほどの蛟(みずち)だった。
「なんやと!?」
「龍神様じゃないぞ!」
「水凪殿、騙したのか!」
なんていうことだろう。神様だと思って接してきたのは、郷の沼に住むという蛟の妖怪だった。道理で水凪から沼の匂いがする筈だ。淀んだ沼の水は、それは気持ちが悪いだろう。
蛟を前に村人たちが責め立てる。蛟が、があ、と口を開いたその時、真っ青な天から蛟目掛けてパシン、と稲妻が落ちた。蛟はその勢いでその場に頽(くずお)れてしまった。
「ひっ! 龍神様がお怒りだ!」
「千代、早よ神様にお祈りしてくれ!」
「お怒りが俺らに向いてまう!」
「早く泉に入った罰当たり者を括ってしまえ!」
ひとりの村人の案に、他の村人がそうだそうだと賛同する。祈りをささげることには勿論賛同するが、それに千臣を巻き込みたくない。しかしこういう時、小さな村の中の異端児はたやすく吊るし上げられる。千代が止めてと叫ぶ中、千臣は後ろ手に縄を巻かれ、渇きの大桜に後ろ手のまま括り付けられると、神様に命を捧げろと村人に脅されていた。
こんなに恐ろしい村人たちを見たことがないと、千代は思った。いつも笑って千代を見守ってくれていた村人たちが、千代の大切な人を非道に扱い、命まで差し出せと迫っている。千代は泣いて村人たちに頭を下げた。