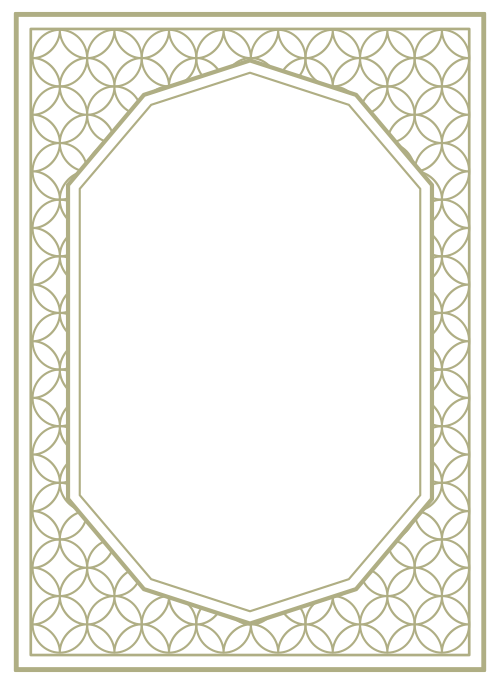さらりと心地よい風が流れたのに、それを感じることも出来ないくらいに、一気に体の熱が上がる。しかし、急に近寄った体温に対して千代が驚いたのに、千臣はなにも気にした様子はなく重ねた手から枝を握り、それを動かした。どきんどきんと心臓が鼓動に任せて喉の奥からせり出しそうで、ぐっと歯を食いしばることで、それを防ぐ。
「『す』や『む』のような、下から上へ円を描くときは指先の力を少し抜いて書くと良い。力を入れ過ぎたままだと枝を突き刺してしまう」
耳なじみの良い低い声が、鼓膜の傍で響いている。心臓が煩く騒ぐ中、懸命に言葉の意味を拾った。耳が熱を持った千代の指を少し持ち上げるようにして、千臣が『す』の円を下から上へ、描く。そのまま下にさらりと払って、『す』が完成した。心臓は大きく拍動を続けていたけど、今まで力を籠めすぎていたせいで枝先が地面に刺さってしまい、土を跳ね上げることになっていたので、文字を書くのに体の使い方があるのだと知って千代は素直に驚いた。
「こんな微妙な加減で書かなあかんのですね……。難しいです」
熱を持つ頬を否定するかのように、千代は冷静に感動した。
「まだ地面に書くのだから、やさしい方だぞ。筆を使ったら、もっと微妙な加減で書かねばならない」
「ふふ。筆なんて、高貴な人の持ち物や。農民が使うものやないですよ」
「まあ、そうだな。例えが悪かったか」
千臣の言葉に千代は微笑んだ。千臣も笑って、場が和む。日が傾いてきて、そろそろ地面に書いた文字も見えにくい。
「今日はこれくらいにするか。農作業の後だというのに、よく頑張るな、千代は」
「せやって、楽しいんです、文字を書くのが。こんなに楽しいことを教えて下さる千臣さんに感謝せなあきませんね」
千代の謝意にも、千臣は微笑むばかりだ。
「千代が楽しいならそれでいい」
「ふふ。ありがとうございます。じゃあ、夕餉にしましょうか。私、支度してきます」
千代はそう言って離れを辞した。緩く跳ねる心臓の動悸を心地よく感じながら、水無月の風に当たって、千代は頬の熱を冷ました。
「『す』や『む』のような、下から上へ円を描くときは指先の力を少し抜いて書くと良い。力を入れ過ぎたままだと枝を突き刺してしまう」
耳なじみの良い低い声が、鼓膜の傍で響いている。心臓が煩く騒ぐ中、懸命に言葉の意味を拾った。耳が熱を持った千代の指を少し持ち上げるようにして、千臣が『す』の円を下から上へ、描く。そのまま下にさらりと払って、『す』が完成した。心臓は大きく拍動を続けていたけど、今まで力を籠めすぎていたせいで枝先が地面に刺さってしまい、土を跳ね上げることになっていたので、文字を書くのに体の使い方があるのだと知って千代は素直に驚いた。
「こんな微妙な加減で書かなあかんのですね……。難しいです」
熱を持つ頬を否定するかのように、千代は冷静に感動した。
「まだ地面に書くのだから、やさしい方だぞ。筆を使ったら、もっと微妙な加減で書かねばならない」
「ふふ。筆なんて、高貴な人の持ち物や。農民が使うものやないですよ」
「まあ、そうだな。例えが悪かったか」
千臣の言葉に千代は微笑んだ。千臣も笑って、場が和む。日が傾いてきて、そろそろ地面に書いた文字も見えにくい。
「今日はこれくらいにするか。農作業の後だというのに、よく頑張るな、千代は」
「せやって、楽しいんです、文字を書くのが。こんなに楽しいことを教えて下さる千臣さんに感謝せなあきませんね」
千代の謝意にも、千臣は微笑むばかりだ。
「千代が楽しいならそれでいい」
「ふふ。ありがとうございます。じゃあ、夕餉にしましょうか。私、支度してきます」
千代はそう言って離れを辞した。緩く跳ねる心臓の動悸を心地よく感じながら、水無月の風に当たって、千代は頬の熱を冷ました。