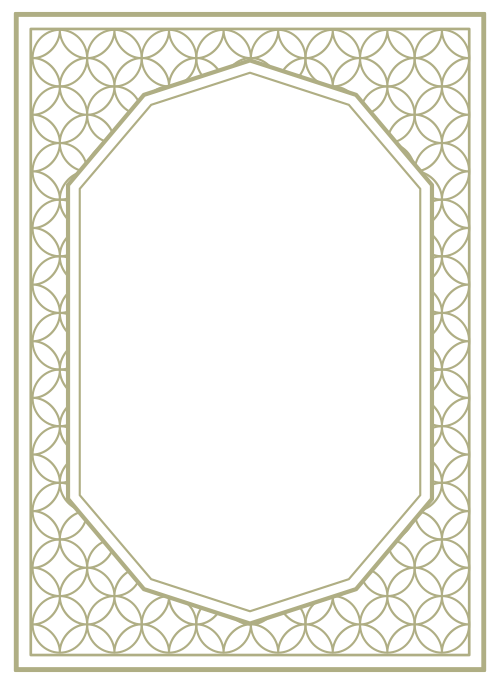自分は水凪と郷を繋ぐためだけに居るのだと思っていた。その為なら、何でもやらなければならないとも。それなのに千臣はそこから目を逸らさせてくれる。
待つ。待つ間、自分の為に時間を使う。それは千代にとって、とてつもない贅沢だった。
自分の為に、時間を使う。
思えば、子供の頃から郷の為、神さまの為に努めてきた。自分のことなんて、考えたこともなかった。千臣の提案が、夜の星空のようにきらきらと心に映り、どくんどくんと心臓の鼓動を速めた。
人生を自分の為に生きることは出来ないけれど。つかの間の自由だったら許されるだろうか。
「そ……、……う、です、……ね……」
千臣に応えることで、その自由が自らの中に帰るようだった。心臓が弾みはじめ、高揚してくるのが分かる。
いっとき、人生の自由を生きる。それは千代に甘美な陶酔感を与えた。
「で……、では、いろは歌を空(そら)で書けるようになりたいです。そしたら、千臣さんのお名前を書くことが出来るようになりますし」
「はは。俺の名を書いてどうする」
「文字の形が上手くなったか、見て頂けます」
千代の答えに、なるほど、と千臣は頷いた。
「では、毎回見てやろう」
「ありがとうございます」
約束をしてから千代は、毎日農作業の後に、歌いながら地面にいろは歌を書き記した。初めて知った文字だというのに、歌と共に書くと、自然と身に染みるように覚えて行けるのが嬉しかった。最初のうちは体の使い方が分からなくて、それを千臣がやさしく指導してくれた。
「肩の力は抜いた方が良い。力むと枝先までうまく操れない」
そう言って千臣は千代の背後から背を包むようにして立ち、腕を添わせるようにして千代が枝を握る荒れた手を、綺麗で大きな手で覆った。
「!」
待つ。待つ間、自分の為に時間を使う。それは千代にとって、とてつもない贅沢だった。
自分の為に、時間を使う。
思えば、子供の頃から郷の為、神さまの為に努めてきた。自分のことなんて、考えたこともなかった。千臣の提案が、夜の星空のようにきらきらと心に映り、どくんどくんと心臓の鼓動を速めた。
人生を自分の為に生きることは出来ないけれど。つかの間の自由だったら許されるだろうか。
「そ……、……う、です、……ね……」
千臣に応えることで、その自由が自らの中に帰るようだった。心臓が弾みはじめ、高揚してくるのが分かる。
いっとき、人生の自由を生きる。それは千代に甘美な陶酔感を与えた。
「で……、では、いろは歌を空(そら)で書けるようになりたいです。そしたら、千臣さんのお名前を書くことが出来るようになりますし」
「はは。俺の名を書いてどうする」
「文字の形が上手くなったか、見て頂けます」
千代の答えに、なるほど、と千臣は頷いた。
「では、毎回見てやろう」
「ありがとうございます」
約束をしてから千代は、毎日農作業の後に、歌いながら地面にいろは歌を書き記した。初めて知った文字だというのに、歌と共に書くと、自然と身に染みるように覚えて行けるのが嬉しかった。最初のうちは体の使い方が分からなくて、それを千臣がやさしく指導してくれた。
「肩の力は抜いた方が良い。力むと枝先までうまく操れない」
そう言って千臣は千代の背後から背を包むようにして立ち、腕を添わせるようにして千代が枝を握る荒れた手を、綺麗で大きな手で覆った。
「!」