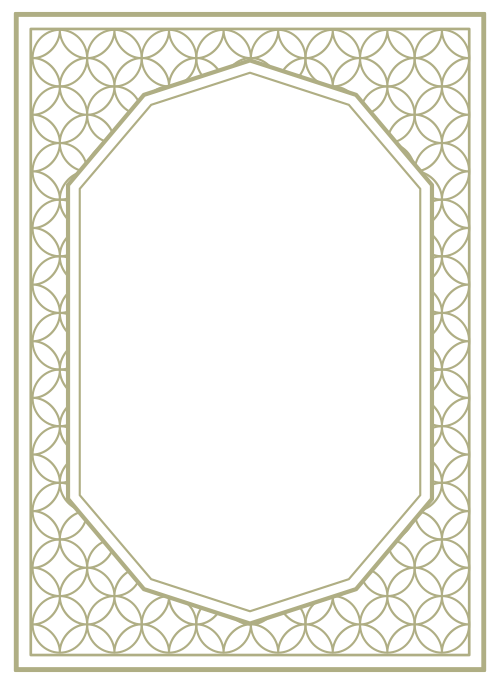聞き終わった千臣は腕を組んだ。
「ふむ」
「意味も分からず歌うてるんですけど……。なんか分かりますか?」
千代の問いに、千臣は頷いた。
「俺は分かるが、千代が分からなければ意味がない。まず、歌を文字に書き起こした方が良い」
文字? 文字だって? 文字なんてもの、殿上人ならともかく、こんな片田舎の農村の人間で知ってる人なんていないことを、千臣は知らないのだろうか。千臣が当たり前に知っていることを知らないという事実を恥ずかしく思いながらも、千代は口を継いだ。
「文字? でも私、文字は読めへんし、書いたこともあらへんです……。郷の人だって誰一人として文字は知らへんし、おばあさまやって知らへんですよ……?」
恥ずかしさから俯き、荒れた指先をもじもじと動かした。
「では、これから覚えるのはどうだ。俺が居る間は看病の礼として教えてやれる。紙や筆がなくても、地面に書けばいい。覚える気さえあれば、俺は教えてやる」
新しいことを、覚える。
それは千代にとって描けなかった未来を指し示した明るい光のようなものだった。無知ゆえに怯えて暮らしてきたという指摘が本当なら、文字を覚えることで今まで知らなかったことを知ることが出来るようになるかもしれない。千代の胸は踊り、目は輝いた。知りたい。知らなかったことを、知りたい。
どうにも抗えないその欲求に、千代は素直に屈した。
「教えて……、ください……っ。頑張ります……っ」
千代の表情に、千臣はやわらかく微笑んだ。
「目が生きたな。千代は本来、そういう人間なのだろうな、羨ましい」
言葉の最後にやや視線を俯け、ぽそりと呟かれたそれを、千代は聞き取れなかった。
「千臣さん? 何て言わはりました?」
「いや、何でもない。では、先ず水凪殿の承諾を得てくることからだな。水凪殿は随分君に執心しているようだから、もしかすると反対されるかもしれない」
ふふ、とからかうように笑う千臣にはどこにも憂いた様子はない。聞き間違いだったかなにかなのだろうと見当をつけて、千代は千臣に必ず承諾を得てくる、と約束した。