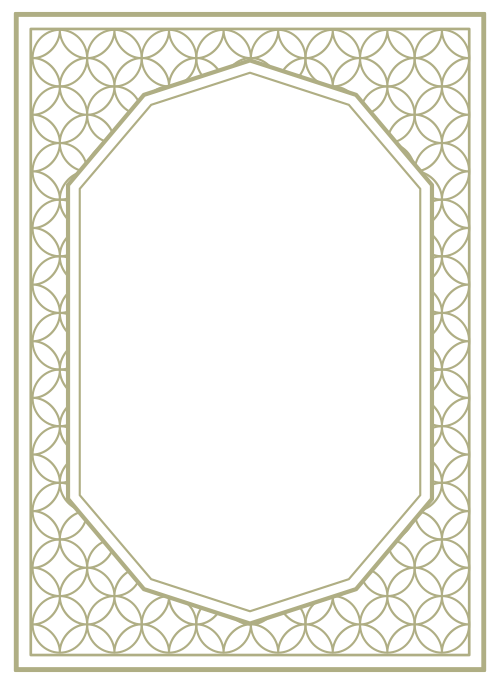夜。神社に戻ると、水凪が出て来たままになっていた本殿の扉が少し開いていたので、締めようと手を掛けると、中からうすぼんやりとした光が漏れていることに気付いた。壁の板木の間から零れる月明かりかと思ったが、そうでもない。隙間から本殿の中を覗いてみると、ご神体を祀ってある棚の戸が少し開いて傾いていた。驚いて中に入ると、棚の下に転がっている水晶の珠があった。蒼白くぼんやりと光っている。……きっと、これがご神体だ。恐れ多くて千代は袖の先で水晶を隠すと、棚に水晶を戻そうとして持ち上げた。すると。
ふぅと流れた清涼な空気とともに脳裏に浮かび上がった、人型の影。鋭利な刃物を透明な水に隠した、そんな気配。水凪が怒ったら、こんな空気になるのかといった雰囲気だ。
本殿の中が緊張感に満ちていたことを、千代は知った。きっと人間が宝珠を触ったからだ。急いで宝珠を棚に仕舞うと、本殿を出る。ぎい、と音をさせて戸を後ろ手に占めると、穏やかな空気が千代を包んだ。……月の光だ。
今日はめでたい日だった。何といっても、神様が郷に降りてきてくださったのだ。それも、千代に乗り移らずに。奉職式の後に夢に見た、幼い頃に千代に向かって『迎えに来る』と言ったのは、水凪だったのかと気づく。今までは『迎え』という言葉が恐怖の源となっていたが、こんな風にお迎えできるのなら、万々歳だ。嫁というのはまだ少し自覚するのに時間が掛かるが、この日の為に日々お務めに励んできたのだ。
(……私は、村の為に、神様をお迎えする身。それ以上でも、それ以下でもない……)
その夜、千代は清涼な空気に包まれて眠った。