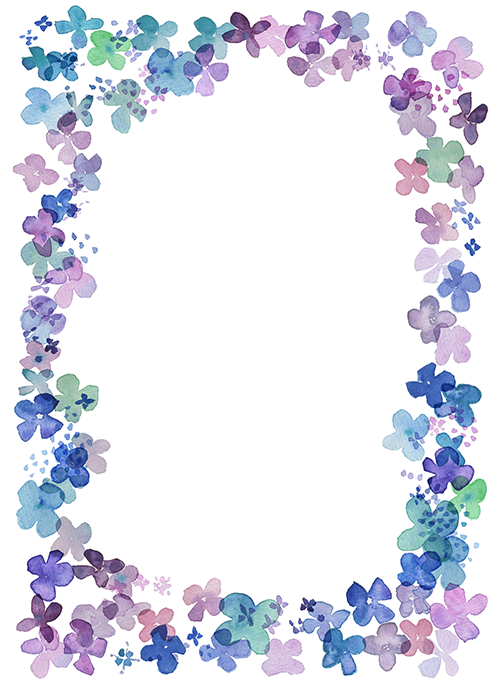激しい動悸で目覚める。息が苦しかった、胸が痛かった。忘れてしまわぬように額を流れる大粒の汗を拭うこともせず、夢日記に記憶の欠片を綴る。筆を置いてから、鐘を鳴らしたときのような甲高い音が耳元でずっと反響していたことに気づいた。不快感に思わず眉をひそめると、耳鳴りが段々と潮の音に変わった。
朝焼けの海を見に行こう、突然そんなことが頭に浮かぶ。海に行ったって、君はいるはずがないのに。居ても君かどうかなんて分かるはずもないのに。君の幻影をまたもう一度見たかっただけだ。幼いだろうか、恋焦がれる相手への想いを募らせたこの行動は。でも僕はもう少しだけ、少しだけでいいから夢見心地のままいたいだけなんだ。
「住の江まで出してくれないか、牛車を」
使いの者たちは驚いたようにひそめき合った後、「承知しました」と恭しく首を垂れた。
牛車は僕と数人を乗せて海へと向かう旅路を進む。牛が歩を進める度に、車体が大きく揺れた。いつもなら書物を読んだり、眠りについたりするのだが、今日だけは何もやる気になれない。ただ簾をじっと見つめながら、頭の中で今も焼き付いて離れない微笑む少女に尋ねる。
「君は誰なんだ」
「どうして僕の夢に出てきたんだ」
「一度でいい、必ず覚えているから名前を教えてくれ」
返事をしないのに消えることのない記憶の中の少女に、僕は唸ってしまう。ふと特有の香りが鼻孔をくすぐった。鼻の奥を刺激するような香り。牛の足音もザッザッザと土を蹴る音から、何か細かいものを踏む音へと変化している。そろそろかと外に顔を覗かせると、使いの者が簾を掲げてくれた。砂浜にそっと足を踏み入れる。まだ日の当たっていない砂は僕の冷たく足を包み込んだ。
「ここが、住の江……。噂に聞いていたからまさかとは思ったが……。本当に夢の中の景色に酷似しているではないか」
一面に広がる海。遠くに小さな島が浮かぶ。朝焼けの雲も似ている。
ただ一つ、君がいない。
その事実が胸を軋ませる。波打ち際に視線を移す。そこには足跡なんかなく、無数の白い泡が波の動きに合わせ引いたり近づいたりを繰り返すだけ。艶やかな黒髪をたなびかせる少女はいない。
僕は手を海の方へ向ける。空を切った手には、当たり前だが服の裾を掴んだ感覚も、人のぬくもりに触れた感覚もない。
突然、視界に白いものが映って「誰だ!」と声を荒げながら振り返る。岩に蔦をまいた花だった。僕は気落ちしつつも、それを手に取る。純白の花弁は君の頬みたいだ。
「夕顔……だろうか」
いつかの書物で目にしたことがある。今は蕾のように萎んでしまっているが、申の刻近くなると大きな花弁をいっぱいに広げるらしい。僕は申し訳ないと思いつつ、一つそれを拝借するときゅっと祈るように握りしめた。
お願いだ、もう一度出てきてくれ。
君の顔が見れていないと言うのに、夢にすら出てきてくれなければこの想いはどうしたらいいのだ。
胸の苦しさ全てを花に込める。持ち帰るのもなんだかなと思い、悩んだ挙句蕾は海に流すことにした。水面に浮かぶ姿は何かの手向けのように見えた。