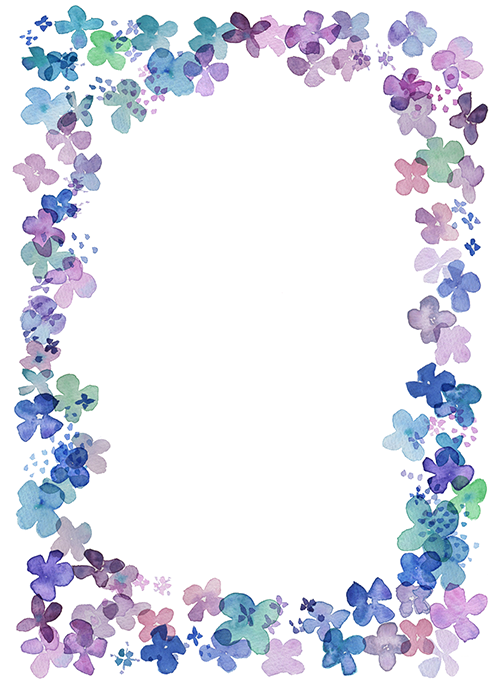夢を見た。
目の前の人物は、霞がかった視界の中そこにいた。
夜明け色の群青に染まる海と白いあぶく、波打ち際に立つ誰かが微笑む。海鳥の鳴き声がひどく鮮明に耳に焼き付く。必死で伸ばしたはずの掌は少女に届くことなく、虚空を空ぶった。
どうか、君であってくれ。
その白い首筋も、姿勢のよい立ち姿も、微笑むとえくぼができるのも、君であってくれ。
君の顔を見たことはない。交わしたのは歌だけ。故に微笑む少女が誰なのか、僕にはわからない。
必死に願った。君であることをただ願う。夢の中に出てきたら結ばれるのだ。僕と君は運命だと言えるのだ。
少女は小さく笑った。僕は少女の次の動作が分かってしまった。手を伸ばしても届かないと知った僕は何もできない。僕は泣きそうな顔になる。どうしてそんな顔をするんだ。僕のことを知らないかもしれないのに。
どうしてそんなに愛おしそうに微笑むんだ。
「君は、―――なのか?」
僕はただ一言、問う。少女は一筋涙を流すと、海面へと華奢な体が傾けた。海へと身投げたのだと瞬間的に理解した僕は「嫌だ」と叫んだ。君の名前を呼ぶ声がこだまして鼓膜を揺らした。
伸ばした腕はまた、空ぶった。
目の前の人物は、霞がかった視界の中そこにいた。
夜明け色の群青に染まる海と白いあぶく、波打ち際に立つ誰かが微笑む。海鳥の鳴き声がひどく鮮明に耳に焼き付く。必死で伸ばしたはずの掌は少女に届くことなく、虚空を空ぶった。
どうか、君であってくれ。
その白い首筋も、姿勢のよい立ち姿も、微笑むとえくぼができるのも、君であってくれ。
君の顔を見たことはない。交わしたのは歌だけ。故に微笑む少女が誰なのか、僕にはわからない。
必死に願った。君であることをただ願う。夢の中に出てきたら結ばれるのだ。僕と君は運命だと言えるのだ。
少女は小さく笑った。僕は少女の次の動作が分かってしまった。手を伸ばしても届かないと知った僕は何もできない。僕は泣きそうな顔になる。どうしてそんな顔をするんだ。僕のことを知らないかもしれないのに。
どうしてそんなに愛おしそうに微笑むんだ。
「君は、―――なのか?」
僕はただ一言、問う。少女は一筋涙を流すと、海面へと華奢な体が傾けた。海へと身投げたのだと瞬間的に理解した僕は「嫌だ」と叫んだ。君の名前を呼ぶ声がこだまして鼓膜を揺らした。
伸ばした腕はまた、空ぶった。