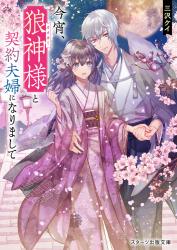◆ 第六章 後宮の闇を解く
器の中にお湯が注がれる。丸い茶葉がゆっくりと広がり、中から飛び出した可愛らしい花がまるで咲いているように見えた。
「うわあ、すごい! 可愛いわ」
蓮妃が興奮気味に器の中を見つめ、すんと鼻から息を吸い込む。
「それに、とてもいい香り」
「お気に召していただけて嬉しく思います。実家から取り寄せたものなのです。おふたりをご招待した甲斐があります」
今日の茶話会の主宰である蘭妃はにっこりと微笑んだ。
(皇都にはいろんなお茶があるのね)
玲燕もまた、初めて見るその飲み物を興味深げに見つめる。工芸茶というらしいが、田舎である東明では飲んだことはおろか、存在すら知られていなかったように思う。
「今日は、暖かいですね」
玲燕は外を眺める。
まだまだ冷え込む日が多いが、着実に春は近づいてきている。
「もうすぐ梅が咲くかしら?」
蓮妃も外を見る。
「実家にいる頃は梅の季節になると、いつも両親と梅園を見に行ったの。たくさんの梅の花が咲いていてとても綺麗なのよ」
器の中にお湯が注がれる。丸い茶葉がゆっくりと広がり、中から飛び出した可愛らしい花がまるで咲いているように見えた。
「うわあ、すごい! 可愛いわ」
蓮妃が興奮気味に器の中を見つめ、すんと鼻から息を吸い込む。
「それに、とてもいい香り」
「お気に召していただけて嬉しく思います。実家から取り寄せたものなのです。おふたりをご招待した甲斐があります」
今日の茶話会の主宰である蘭妃はにっこりと微笑んだ。
(皇都にはいろんなお茶があるのね)
玲燕もまた、初めて見るその飲み物を興味深げに見つめる。工芸茶というらしいが、田舎である東明では飲んだことはおろか、存在すら知られていなかったように思う。
「今日は、暖かいですね」
玲燕は外を眺める。
まだまだ冷え込む日が多いが、着実に春は近づいてきている。
「もうすぐ梅が咲くかしら?」
蓮妃も外を見る。
「実家にいる頃は梅の季節になると、いつも両親と梅園を見に行ったの。たくさんの梅の花が咲いていてとても綺麗なのよ」