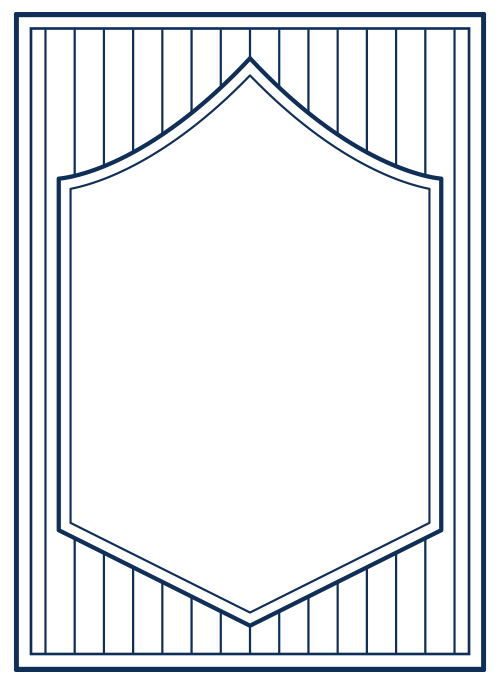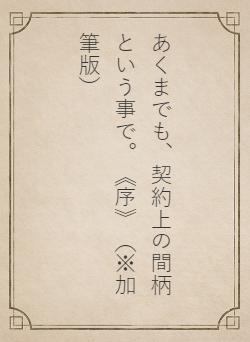時間は現在に戻る。
「お勤めの帰りに君を見付けたと言いましたけど。要するに、悪縁を切るお仕事の帰りでしてね」
「そうだったのですか」
彼女は「ここからが本題なんですが」と口調を改めた。
「先代から譲渡された神通力を縁切りに使用している訳ですが、私としてはやはり『切る』と明確にイメージ…意識できる媒介があった方が助かるんです。ですが切るにしても…例えば鋏だとかは身近ですが、神通力の媒介にするには、どうも物足りない。悪縁を『絶つ』に相応しい物があればいいと思っていた所なんです」
彼女は彼を見据えた。
「勿論、君さえ良ければですけれど。私の神器に、この神社の御神刀になってはもらえませんか?」
「ご、御神刀!?」
そもそもが名も無き志士の刀であった彼としては、あまりにもと言えばあまりにもな展開だ。だが彼女はやはり何の事も無さそうに「ええ」と返す。
「君は私に仕えると言ってくれました。そして私は、仕事の相棒と言える神器が欲しい。君は動乱の幕末を駆け抜けた刀です。つまりは実戦経験があるという事。十分に強みになるでしょう。私は仕事をし易くなって、君は刀として活躍できる。こういうのを現代では『win-winの関係』と言います。悪い話ではないと思いますけどね」
どうも彼女、彼が人斬りに使われていたと承知の上で、むしろその事実すらも買って勧誘してくれているらしい。人神になった経緯といい、これまでの言動といい、彼女は相当図太い人物らしい。
「まあでも、あくまでも『君さえ良ければ』の話です。勿論ですが、強制はしませんし、命令ではありません。最初にも言った通り、元々の持ち主を探したいならそうすればいいですし…んーまあ冥界にまでは入れない身なれど、付き合える所まではきちんと付き合いますから」
同時に彼は気付いていた。彼女は頭ごなしにものを言ってくる訳ではなく、ひたすら相手の目線に合わせて『頼む』姿勢を一貫していると。
彼は「いえ」とゆっくりと首を横に振った。
「武士に二言はありませぬ。再び形を与えて下さり、お役目まで頂けるのです。この身がある限り、貴方様にお仕え致します」
彼は静かに、本体である刀を片手に持った。
「――忠義を」
空いている片手で柄を持ち、刀の鍔を打ち合わせる。澄んだ音が響いた。『金打』である。
「ありがとうございます。助かりますよ」
彼女は安堵したように眉を下げた。
「今まであえて訊かないでいましたけど。君のお名前を教えてもらっても構いませんか?それとも、もしも名前が無いなら、私が名前を付けましょうか?」
「主様から直々に、名を頂けるのですか!?」
彼は目を輝かせた。
「わたくしは無名の刀工に打たれた身。また、前の持ち主と共に在った時も、名を付けられた事はありませんでした。主様の刀としての名を頂けるのは、この上ない名誉でございます!」
「そうですか。では『掬水』なんてどうかなと思うんですけどね」
彼女は手近な筆記用具を引き寄せて『掬水』と書いてみせた。
「『塵芥の中から物理的に掬い上げた』というのもありますけど。君の本体の刀身は水のように潤みがあって美しいですからね」
さりげなく刀剣としての美を称賛され、彼は頬が熱くなるのを感じた。
そんな彼の様子を知ってか知らずか、彼女は「何より」とマイペースに続ける。
「この名前なら、共に人間社会で活動する上で違和感もありませんしね」
「共に活動…ですか?」
「これから相棒になるんです。一緒に現代社会に出て仕事をするんですから、上手く人間に紛れる事ができる名前の方がいいでしょう。まああまり刀ぽくはない名前ですが、これで如何です?」
「――いえ。素晴らしい名です」
彼は畳に両手をつき、深々と頭を垂れた。
「ありがとうございます。頂いた名にかけて、誠心誠意お仕え致します」
「それについてなんですけど。私の相棒となる上で、幾つか絶対に守って欲しい事があります」
「は。絶対に…ですか?」
掬水の緊張を汲み取ったのか、彼女は「いやまあ難しい事ではないんですが」と手を横に振る。
「まず一つ。ここで一緒に住む上でも仕事の上でも『これこれをああして欲しいこうして欲しい』とか要望なり希望なりがあったら、きちんと言って欲しいんです。君はもう意志も感情も持っている身ですからね。何かして欲しい事や欲しい物があれば尊重したいです。んーまあ、主従関係が前提にあるから抵抗はあるかもしれませんけど、言ってもらえると私も助かります」
「は、はい」
確かに、主たる彼女に意見するのはどうかという考えは根底にある。でも同時に、主は自分を思いやってくれているのだとわかったので、掬水は頷いた。
「もう一つ。君の二心を疑ったりしている訳ではなく、私の時代で当たり前になっている『職業選択の自由』から来る考えなんですが。何処かもっといい条件で神器なり神使なりにしてくれる所があったら、そこに行っていいです。また、どうしても前の持ち主に会いたくなったら、それも言って下さい」
「主様、それは」
彼女は「決して二心を疑ったりしている訳ではありませんよ」と言い聞かせるように繰り返した。
「これからきちんとイコマさんとニコマさんと宮司さん達に君を紹介した上で細かい取り決めをしますが、労働条件は考えられる限り良いものにするつもりです。でも世の中にはもっといい条件の神社があるかもしれませんし、君が何処かの神様に引き抜きに遭うかもしれません」
彼女は「現代では『ヘッドハンディング』と言うんですけど」と付け足した。
「君が意志も人格も持つ以上、選ぶ自由はありますから、『ここがいい』と思う所があれば、そこへ行って構いません。また、どうしても前の持ち主に会いたくなる時もあるかもしれません。まあ要は里帰りみたいなものだと私は捉えていますから、それもきちんと相談してくれればいい話なので、君の自由にして下さい。一つ目の話と重複する所がありますが、これも君の自由を尊重したいんです」
「主様…」
武士の心を持つ身としては、主を気安く鞍替えするなど考えられないのだが、しかしこれも主が自分を一人前に扱い尊重してくれているからだとわかる。掬水は躊躇いつつもどうにか頷いた。
「更に一つ。一番重要な事です。私が悪い事や間違った事をして、諫めても止まらないようだったら、私を殺しなさい」
掬水は、ひゅっと息を呑んでいた。
「私は神通力を渡されただけの只の人間です。その気になりさえすれば、どんな悪い事でもできるでしょう。イコマさんとニコマさんにも、私を諫めてくれるよう言ってはいますが、本性が刀である掬水君に頼むのは、また別の大切な意味を持つと思います」
彼女は小さく溜め息をついたようだった。
「掬水君が私の相棒にして側近となる以上、私を最も諫める事ができるのは掬水君です。なので、これは約束と言うより命令です。私が悪事に走って止まらなかったら、掬水君の手で私の首を落としなさい」
掬水は圧倒されていた。彼女は肝が据わっているだけではなく、恐ろしく冷徹な一面も持っている事に。そして理解していた。掬水が成すべき事の大切さを。
掬水は、静かに頭を下げた。
「必ずや、仰せの通りに致します」
だがすぐに顔を上げた。
「しかし、そのようにお考えの主様が、道を違えるとは思えませんが」
「そうですか?うーん。まあ、君達に愛想を尽かされないように、精々頑張りますよ」
彼女が何処までも大真面目なのはわかっているのだが、掬水は思わず笑ってしまった。
こうして、掬水と名付けられた刀の化身は、何とも数奇な経緯で、一風変わった神の神器となったのである。
「お勤めの帰りに君を見付けたと言いましたけど。要するに、悪縁を切るお仕事の帰りでしてね」
「そうだったのですか」
彼女は「ここからが本題なんですが」と口調を改めた。
「先代から譲渡された神通力を縁切りに使用している訳ですが、私としてはやはり『切る』と明確にイメージ…意識できる媒介があった方が助かるんです。ですが切るにしても…例えば鋏だとかは身近ですが、神通力の媒介にするには、どうも物足りない。悪縁を『絶つ』に相応しい物があればいいと思っていた所なんです」
彼女は彼を見据えた。
「勿論、君さえ良ければですけれど。私の神器に、この神社の御神刀になってはもらえませんか?」
「ご、御神刀!?」
そもそもが名も無き志士の刀であった彼としては、あまりにもと言えばあまりにもな展開だ。だが彼女はやはり何の事も無さそうに「ええ」と返す。
「君は私に仕えると言ってくれました。そして私は、仕事の相棒と言える神器が欲しい。君は動乱の幕末を駆け抜けた刀です。つまりは実戦経験があるという事。十分に強みになるでしょう。私は仕事をし易くなって、君は刀として活躍できる。こういうのを現代では『win-winの関係』と言います。悪い話ではないと思いますけどね」
どうも彼女、彼が人斬りに使われていたと承知の上で、むしろその事実すらも買って勧誘してくれているらしい。人神になった経緯といい、これまでの言動といい、彼女は相当図太い人物らしい。
「まあでも、あくまでも『君さえ良ければ』の話です。勿論ですが、強制はしませんし、命令ではありません。最初にも言った通り、元々の持ち主を探したいならそうすればいいですし…んーまあ冥界にまでは入れない身なれど、付き合える所まではきちんと付き合いますから」
同時に彼は気付いていた。彼女は頭ごなしにものを言ってくる訳ではなく、ひたすら相手の目線に合わせて『頼む』姿勢を一貫していると。
彼は「いえ」とゆっくりと首を横に振った。
「武士に二言はありませぬ。再び形を与えて下さり、お役目まで頂けるのです。この身がある限り、貴方様にお仕え致します」
彼は静かに、本体である刀を片手に持った。
「――忠義を」
空いている片手で柄を持ち、刀の鍔を打ち合わせる。澄んだ音が響いた。『金打』である。
「ありがとうございます。助かりますよ」
彼女は安堵したように眉を下げた。
「今まであえて訊かないでいましたけど。君のお名前を教えてもらっても構いませんか?それとも、もしも名前が無いなら、私が名前を付けましょうか?」
「主様から直々に、名を頂けるのですか!?」
彼は目を輝かせた。
「わたくしは無名の刀工に打たれた身。また、前の持ち主と共に在った時も、名を付けられた事はありませんでした。主様の刀としての名を頂けるのは、この上ない名誉でございます!」
「そうですか。では『掬水』なんてどうかなと思うんですけどね」
彼女は手近な筆記用具を引き寄せて『掬水』と書いてみせた。
「『塵芥の中から物理的に掬い上げた』というのもありますけど。君の本体の刀身は水のように潤みがあって美しいですからね」
さりげなく刀剣としての美を称賛され、彼は頬が熱くなるのを感じた。
そんな彼の様子を知ってか知らずか、彼女は「何より」とマイペースに続ける。
「この名前なら、共に人間社会で活動する上で違和感もありませんしね」
「共に活動…ですか?」
「これから相棒になるんです。一緒に現代社会に出て仕事をするんですから、上手く人間に紛れる事ができる名前の方がいいでしょう。まああまり刀ぽくはない名前ですが、これで如何です?」
「――いえ。素晴らしい名です」
彼は畳に両手をつき、深々と頭を垂れた。
「ありがとうございます。頂いた名にかけて、誠心誠意お仕え致します」
「それについてなんですけど。私の相棒となる上で、幾つか絶対に守って欲しい事があります」
「は。絶対に…ですか?」
掬水の緊張を汲み取ったのか、彼女は「いやまあ難しい事ではないんですが」と手を横に振る。
「まず一つ。ここで一緒に住む上でも仕事の上でも『これこれをああして欲しいこうして欲しい』とか要望なり希望なりがあったら、きちんと言って欲しいんです。君はもう意志も感情も持っている身ですからね。何かして欲しい事や欲しい物があれば尊重したいです。んーまあ、主従関係が前提にあるから抵抗はあるかもしれませんけど、言ってもらえると私も助かります」
「は、はい」
確かに、主たる彼女に意見するのはどうかという考えは根底にある。でも同時に、主は自分を思いやってくれているのだとわかったので、掬水は頷いた。
「もう一つ。君の二心を疑ったりしている訳ではなく、私の時代で当たり前になっている『職業選択の自由』から来る考えなんですが。何処かもっといい条件で神器なり神使なりにしてくれる所があったら、そこに行っていいです。また、どうしても前の持ち主に会いたくなったら、それも言って下さい」
「主様、それは」
彼女は「決して二心を疑ったりしている訳ではありませんよ」と言い聞かせるように繰り返した。
「これからきちんとイコマさんとニコマさんと宮司さん達に君を紹介した上で細かい取り決めをしますが、労働条件は考えられる限り良いものにするつもりです。でも世の中にはもっといい条件の神社があるかもしれませんし、君が何処かの神様に引き抜きに遭うかもしれません」
彼女は「現代では『ヘッドハンディング』と言うんですけど」と付け足した。
「君が意志も人格も持つ以上、選ぶ自由はありますから、『ここがいい』と思う所があれば、そこへ行って構いません。また、どうしても前の持ち主に会いたくなる時もあるかもしれません。まあ要は里帰りみたいなものだと私は捉えていますから、それもきちんと相談してくれればいい話なので、君の自由にして下さい。一つ目の話と重複する所がありますが、これも君の自由を尊重したいんです」
「主様…」
武士の心を持つ身としては、主を気安く鞍替えするなど考えられないのだが、しかしこれも主が自分を一人前に扱い尊重してくれているからだとわかる。掬水は躊躇いつつもどうにか頷いた。
「更に一つ。一番重要な事です。私が悪い事や間違った事をして、諫めても止まらないようだったら、私を殺しなさい」
掬水は、ひゅっと息を呑んでいた。
「私は神通力を渡されただけの只の人間です。その気になりさえすれば、どんな悪い事でもできるでしょう。イコマさんとニコマさんにも、私を諫めてくれるよう言ってはいますが、本性が刀である掬水君に頼むのは、また別の大切な意味を持つと思います」
彼女は小さく溜め息をついたようだった。
「掬水君が私の相棒にして側近となる以上、私を最も諫める事ができるのは掬水君です。なので、これは約束と言うより命令です。私が悪事に走って止まらなかったら、掬水君の手で私の首を落としなさい」
掬水は圧倒されていた。彼女は肝が据わっているだけではなく、恐ろしく冷徹な一面も持っている事に。そして理解していた。掬水が成すべき事の大切さを。
掬水は、静かに頭を下げた。
「必ずや、仰せの通りに致します」
だがすぐに顔を上げた。
「しかし、そのようにお考えの主様が、道を違えるとは思えませんが」
「そうですか?うーん。まあ、君達に愛想を尽かされないように、精々頑張りますよ」
彼女が何処までも大真面目なのはわかっているのだが、掬水は思わず笑ってしまった。
こうして、掬水と名付けられた刀の化身は、何とも数奇な経緯で、一風変わった神の神器となったのである。